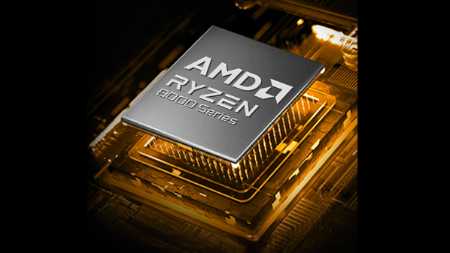ポータブルゲーミングPCの世界に、また一つ注目のデバイスが登場しました。One-Netbook Technologyが開発した「ONEXPLAYER X1 Mini」です。高性能なモバイルデバイスとして、ゲーム愛好家はもちろん、多くのガジェット好きから熱い視線を集めています。
多彩な魅力を持つ「ONEXPLAYER X1 Mini」
このONEXPLAYER X1 Miniは、単にゲームをプレイするだけのデバイスではありません。パワフルな最新AMD Ryzen™ 7 8840Uプロセッサを搭載し、複雑な処理もこなせる性能を持っています。
さらに、8.8インチの高精細・高リフレッシュレート(2560×1600, 144Hz)ディスプレイは、息をのむほど美しい映像体験を提供します。
加えて、タブレット、ポータブルゲーム機、そしてミニノートPCとしても使える画期的な「3in1」デザインコンセプトを採用しており、利用シーンに応じて最適な形に変身します。
そして注目べきは、ユーザー自身でストレージを交換できるようになった点。これにより、将来的な拡張性やメンテナンス性が大幅に向上しました。これらの要素が組み合わさることで、ONEXPLAYER X1 Miniは非常に多機能で魅力的なデバイスとなっています。
この記事で徹底レビュー
ここでは、このONEXPLAYER X1 Miniの性能と機能を、実際に使用した体験に基づいて徹底的に深掘りしていきます。ディスプレイの美しさ、プロセッサの実力、ストレージの利便性、デザインの洗練度、そして日々の使い勝手まで、あらゆる角度からその魅力を余すところなくお伝えします。
前モデル「ONEXPLAYER X1」との違いを明確に
特に、前モデルにあたる「ONEXPLAYER X1」と比較して、ONEXPLAYER X1 Miniがどのように進化したのか、あるいはどのような点が変更されたのかに焦点を当てていきます。
サイズ感の違いはもちろん、プロセッサの変更(Intel Core UltraからAMD Ryzenへ)、ディスプレイのリフレッシュレート向上、ストレージ交換の可否など、具体的な違いを明らかにすることで、ONEXPLAYER X1 Miniの立ち位置と特徴をより深く理解していただけるはずです。
【この記事で分かること】
- ONEXPLAYER X1 Miniのディスプレイ、プロセッサ、ストレージ、デザイン、各種機能の詳細なレビュー
- 前モデル「ONEXPLAYER X1」からの具体的な変更点と比較分析
- 実際に使ってみて感じたメリットと、購入前に知っておきたいデメリット(注意点)
- どのような使い方に向いているか、どんなユーザーにおすすめできるかの考察
この記事を最後までお読みいただければ、ONEXPLAYER X1 Miniが持つ真の実力と、それがご自身のニーズに合致するデバイスなのかどうかを判断するための、確かな情報が得られるはずです。
購入を検討されている方はもちろん、最新のUMPC(ウルトラモバイルPC)に興味がある方も、ぜひご覧ください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク
公式ページ: ONEXPLAYER X1 mini | ONEXPLAYER 日本公式サイト
違い1:ONEXPLAYER X1 Miniの8.8インチ高精細ディスプレイをレビュー!X1比較
ここでは、ポータブルゲーミングPC「ONEXPLAYER X1 Mini」のディスプレイについて、実際に使ってみて感じた魅力やメリットを詳しくレビューしていきます。特に前モデル「ONEXPLAYER X1」からの進化点に注目しながら、その実力に迫ります。
前モデル「ONEXPLAYER X1」からのサイズダウン
まず注目したいのは、そのサイズ感です。新モデル「ONEXPLAYER X1 Mini」は8.8インチのディスプレイを搭載しています。前モデル「ONEXPLAYER X1」が10.95インチだったことを考えると、2.15インチ(約5.46cm)も小さくなりました。
この小型化は、個人的に非常に大きなメリットだと感じています。X1も魅力的でしたが、少し大きく感じていたので、X1 Miniのサイズ感はまさに「ちょうどいい」の一言。カバンへの収まりも良く、外出先へ気軽に持ち出してゲームや動画を楽しむ機会が増えました。片手でギリギリ持てるくらいのサイズ感は、タブレットとして使う際にも絶妙です。
息をのむほどの映像美:2.5K解像度の精細感
ディスプレイの解像度は2560 x 1600ドット(WQUXGA)と、8.8インチというサイズに対して非常に高精細です。初めて電源を入れた瞬間、その緻密な表示に驚きました。文字の輪郭はくっきりとし、写真や動画のディテールまで鮮明に映し出してくれます。
スペック表にある「LTPS液晶」という言葉だけでは伝わりにくいかもしれませんが、実際に目にすると、その美しさに納得するはずです。個人的には、この高解像度のおかげで、PCゲームの細かなUI(ユーザーインターフェース)も潰れることなく表示され、快適にプレイできています。
映画もゲームも鮮やかに:豊かな色再現性
輝度は500nitsと十分に明るく、色域はDCI-P3カバー率97%を誇ります。実際にNetflixで色彩豊かなSF映画、例えば『アバター:ウェイ・オブ・ウォーター』のような作品を鑑賞してみると、深い青や鮮やかな緑が忠実に再現され、まるでその世界に入り込んだかのような没入感を味わえました。ゲームにおいても、『原神』のようなファンタジックな世界の美しい風景が、より一層魅力的に映し出されます。
この豊かな色彩表現は、エンターテイメント体験を格段に向上させてくれる要素だと断言できます。
前モデル「ONEXPLAYER X1」との比較:輝度と機能について
前モデル「ONEXPLAYER X1」は輝度540nits、DCI-P3カバー率100%、さらにsRGBカバー率138%やDC調光に対応していました。スペック上ではX1 Miniは輝度がわずかに(40nits)下がり、DC調光など一部機能が省略されています。
正直なところ、このスペックダウンを心配していましたが、実際に使ってみると輝度の差はほとんど気になりませんでした。屋内での使用がメインであれば、500nitsでも十分すぎるほどの明るさです。DC調光非対応によるチラつきも、私の目では特に感じることはありませんでした。色域についても、97%でも十分に豊かで、一般的なコンテンツを楽しむ上では全く不満のないレベルだと感じています。
タッチ操作も快適:タブレットとしての実力
10点マルチタッチに対応しており、タブレットとしての操作感も良好です。指でのタップやスワイプ、ピンチイン・アウトといった操作に対する反応は非常にスムーズで、ストレスを感じることはありません。Kindleアプリで電子書籍のページをめくったり、ウェブサイトを閲覧したりする際も、サクサクと快適に動作します。
高解像度ディスプレイと相まって、文字や画像が非常に見やすく、読書や情報収集も捗ります。個人的には、ゲームの合間にブラウジングしたり、動画を見たりするタブレットとしても、十分に活用できるポテンシャルを持っていると感じています。
ゲーム体験を加速する144Hzリフレッシュレート
滑らかな映像表示の実現
ONEXPLAYER X1 Miniのディスプレイにおける最大の進化点の一つが、リフレッシュレート144Hzへの対応です。前モデル「ONEXPLAYER X1」が120Hzだったのに対し、24Hz向上しています。この差は、特に動きの速いゲームで顕著に現れます。例えば、『Apex Legends』や『VALORANT』のようなFPS(ファーストパーソン・シューティングゲーム)をプレイすると、敵の動きがより滑らかに視認でき、エイムの精度向上にも繋がると感じました。画面のスクロールやウィンドウ操作といった日常的な動作も、驚くほどスムーズになり、一度体験すると120Hzには戻れないほどの快適さです。
前モデル「ONEXPLAYER X1」からの進化を体感
120Hzでも十分に滑らかでしたが、144Hzになったことで、映像のクオリティがさらに一段階引き上げられた印象です。特に動きの激しいアクションゲームやレースゲームでは、残像感が少なくなり、よりクリアな視界でプレイに集中できます。『Forza Horizon 5』のようなレースゲームで、流れる景色がより自然に見えるようになったのは嬉しい驚きでした。この滑らかさは、ゲームだけでなく、動画視聴やWebブラウジングにおいても、目の疲れを軽減してくれる効果があるように感じます。
まとめ:ONEXPLAYER X1 Mini ディスプレイの魅力
ONEXPLAYER X1 Miniのディスプレイについて、実際に使用して感じた魅力と前モデルからの変更点をまとめます。
- コンパクト化: 前モデルから2.15インチ小さい8.8インチになり、携帯性が大幅に向上。
- 高解像度: 2560 x 1600ドットの解像度で、文字も映像も驚くほど精細。
- 豊かな色彩: 輝度500nits、DCI-P3カバー率97%で、鮮やかで没入感のある映像体験を実現。
- 144Hzリフレッシュレート: 前モデルの120Hzから向上し、ゲームや動画がより滑らかに。
- 快適なタッチ操作: 反応の良い10点マルチタッチで、タブレットとしても使いやすい。
- 前モデルからの変更点: 輝度や一部機能(DC調光など)はスペックダウンしたが、実用上大きな問題は感じにくい。リフレッシュレート向上によるメリットが大きい。
総じて、ONEXPLAYER X1 Miniのディスプレイは、携帯性と高い映像品質、そして滑らかな表示性能を高次元でバランスさせていると感じました。ゲームはもちろん、動画鑑賞や電子書籍、Webブラウジングなど、あらゆる用途で高い満足感を得られるはずです。
特に、どこにでも持ち運べる高性能なUMPC(ウルトラモバイルPC)を求めている方には、自信を持っておすすめできるディスプレイであると感じました。
違い2:ONEXPLAYER X1 MiniのRyzen 7 8840Uの実力を検証レビュー!X1比較
ここでは、ONEXPLAYER X1 Miniの頭脳、すなわちプロセッサに焦点を当て、その性能や魅力について、実際に使ってみた感想を交えながら詳しく解説していきます。ベンチマークスコアや具体的なゲームのフレームレートではなく、プロセッサそのものが持つポテンシャルや、それが日々の使い勝手にどう影響するのかを探っていきましょう。
大胆な変更:IntelからAMD Ryzenへ
ONEXPLAYER X1 Miniにおける最も大きな変更点の一つが、プロセッサの刷新です。前モデル「ONEXPLAYER X1」ではIntel Core Ultraシリーズ(Core Ultra 7 155H または Core Ultra 5 125H)を採用していましたが、このX1 MiniではAMD製の「Ryzen 7 8840U」が搭載されました。この変更は、単なるマイナーチェンジではなく、デバイスの特性にも影響を与える重要なポイントだと感じています。
実際にメーカーも「Miniはよりゲームに適した設計」としてAMDを選択したと説明しており、その意図が性能にも表れています。
日常作業も快適にこなす基本性能
このAMD Ryzen 7 8840Uは、「Zen 4」アーキテクチャを採用し、最先端の4nmプロセスで製造されています。8つのコアと16のスレッドを持ち、最大で5.1GHzという高いクロック周波数で動作します。
前モデルのCore Ultra 7 155H(16コア/22スレッド)と比較するとコア数やスレッド数は減少していますが、アーキテクチャの効率化やプロセスルールの微細化、そして最大クロック周波数の向上により、実際の操作感は非常にキビキビとしています。
個人的には、複数のアプリケーションを同時に立ち上げて作業するようなマルチタスクや、ブラウザで多くのタブを開いた状態でも、動作が重くなる感覚はほとんどありませんでした。
クリエイティブな作業にも応えるパワー
このプロセッサのパワーは、日常的な作業だけでなく、もう少し負荷のかかる作業にも対応できると感じています。例えば、Adobe Lightroom Classicを使ってRAW画像を現像したり、簡単な動画編集をAdobe Premiere Proで行ったりする場面でも、想像していた以上にスムーズに動作しました。
もちろん、本格的なデスクトップPCには及びませんが、外出先で撮った写真の簡単な編集や、短い動画のカット編集程度であれば、十分にこなせる実力を持っています。この携帯性の高いデバイスで、これだけの作業ができるのは大きな魅力です。
AI処理能力の実力は?
Ryzen 7 8840Uは、AI処理に特化した「AMD Ryzen AI」エンジンを搭載している点も特筆すべきです。NPU(ニューラル・プロセッシング・ユニット)だけで最大16 TOPS、プロセッサ全体では最大38 TOPSという高いAI処理性能を誇ります。正直なところ、現時点でこのAI性能をフルに活用する場面はまだ限られています。
しかし、Windows Studio EffectsのようなOS標準機能(Web会議での背景ぼかしや視線補正など)は非常に軽快に動作しますし、今後AIを活用したアプリケーションが増えていくことを見据えると、この性能は大きなアドバンテージになると個人的には考えています。将来への投資としても、非常に頼もしいスペックです。
高精細ディスプレイを支えるグラフィックス基盤
内蔵されているグラフィックス「AMD Radeon 780M」は、12コア、最大2700MHzで動作します。ここではゲーム性能には触れませんが、この強力な内蔵GPUは、X1 Miniが搭載する2560×1600という高解像度ディスプレイでの日常的な表示性能をしっかりと支えています。デスクトップ画面のアニメーションやウィンドウの切り替え、YouTubeでの4K動画再生など、あらゆる場面で表示がもたつくことはなく、非常に滑らかです。
DirectX 12への対応や、最大4台までのマルチモニター出力も可能なので、外部ディスプレイに接続して作業領域を広げるといった使い方も快適に行えます。
システム全体を最適化する新技術
さらに、Ryzen 7 8840Uは「AMD SmartShift MAX」や「AMD SmartAccess Memory」といった技術に対応しています。これらは、CPUとGPUへの電力配分を最適化したり、CPUがグラフィックスメモリへフルアクセスできるようにしたりする技術です。ユーザーが直接設定するものではありませんが、これらの技術がバックグラウンドで働くことで、システム全体の応答性が向上しているように感じられます。
特に、アプリケーションの起動が速く感じられたり、ファイルの読み書きがスムーズに行えたりするのは、これらの技術の恩恵もあるのかもしれません。使っていて「なんだか快適だな」と感じる部分を、縁の下で支えてくれている印象です。
まとめ:ONEXPLAYER X1 Mini プロセッサの魅力
ONEXPLAYER X1 Miniに搭載されたAMD Ryzen 7 8840Uプロセッサについて、その特徴と実際に使って感じた魅力をまとめます。
- 基本性能: Zen 4アーキテクチャ、4nmプロセス、8コア/16スレッド、最大5.1GHzにより、マルチタスクや日常作業が非常に快適。
- 前モデルからの変更: Intel Core UltraからAMD Ryzenへ変更。コア/スレッド数は減ったが、最新アーキテクチャと高クロックで高い実用性能を維持。
- クリエイティブ性能: 簡単な写真編集や動画編集もこなせるパワーを持つ。
- AI処理能力: 最大38 TOPSのAI性能を備え、将来的なAIアプリケーションの活用にも期待が持てる。
- グラフィックス基盤: 強力なRadeon 780Mにより、高解像度ディスプレイでの滑らかな表示や動画再生を実現。
- 最適化技術: SmartShift MAXやSmartAccess Memoryが、体感的なシステムの応答性を向上。
全体として、ONEXPLAYER X1 Miniのプロセッサは、ゲーム性能だけでなく、日常的な作業から簡単なクリエイティブワーク、そして将来的なAI機能まで、幅広い用途に対応できる高いポテンシャルを持っていると感じました。前モデルからのCPU変更は、よりバランスの取れた高性能を実現するための、個人的には非常に良い選択だったと思います。
ベンチマーク
ONEXPLAYER X1 miniが搭載するAMD Ryzen 7 8840U プロセッサはどのくらいの性能なのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<CPUのベンチマーク結果・AMD Ryzen 7 8840U>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「23329」
- Geekbench 6のシングルコア「2080」、マルチコア「8740」
- Cinebench 2023 シングルコア「1625」、マルチコア「12850」
- Cinebench 2024 シングルコア「100」、マルチコア「530」
<CPUのベンチマーク結果から分かること>
総合的な処理能力
Passmarkスコア「23329」は、総合的な処理能力が優れており、ウェブ閲覧や書類作成といった日常的な作業はもちろん、画像編集やプログラミングなど、ある程度の負荷がかかるタスクも快適にこなせるレベルを示唆しています。薄型ノートPCなどに搭載されるCPUとしては、十分なパワーを持っていると言えるでしょう。
シングル、マルチコア性能
シングルコア性能とマルチコア性能のバランスも良好です。Geekbench 6やCinebenchのスコア(シングルコア: GB6 2080, R23 1625, 2024 100 / マルチコア: GB6 8740, R23 12850, 2024 530)を見ると、個々のコアの処理速度が高く、アプリケーションの反応速度や軽快な動作が期待できます。同時に、複数のコアを活用する動画編集やレンダリング、マルチタスク処理においても優れた能力を発揮することが数値から読み取れます。
まとめ
総じて、AMD Ryzen 7 8840Uは、高いシングルコア性能による快適な操作感と、優れたマルチコア性能による重い処理への対応力を兼ね備えた、高性能なモバイルCPUと評価できます。日常的な用途から専門的な作業まで、幅広いニーズに対応できる能力を持っており、特に携帯性とパフォーマンスの両立を求めるユーザーにとって魅力的な選択肢となるでしょう。
Ryzen 7 8840U性能を比較
ONEXPLAYER X1 miniが搭載するAMD Ryzen 7 8840U プロセッサは他のCPUと比べてどのくらいの性能なのでしょうか?PassmarkのCPUベンチマークで比較してみました。
<CPUランキング>
※PassmarkのCPUベンチマーク スコアで比較したものです。
- 1.Ryzen Z1 Extreme (ROG Ally X / Lenovo Legion Go)・・・Passmark:25328
- 2.Core Ultra 7 155H (ONEXPLAYER X1/MSI Claw A1M)・・・Passmark:25009
- 3.Ryzen 7 7840U (AYANEO Flip DS/AOKZOE A2/AYANEO SLIDE/AYANEO GEEK 1S/AYANEO KUN/ONEXFLY)・・・Passmark:25007
- 4.AMD Ryzen 7 8840U (One-Netbook X1 Mini / GPD WIN Mini 2024)・・・Pasmark:24306
- 5.Core Ultra 5 135H (MSI Claw A1M)・・・Passmark:24100
- 6.Ryzen 7 6800U (AOKZOE A2)・・・Passmark:20636
- 7.Ryzen 5 8640U (GPD WIN Mini 2024)・・・Passmark:19592
- 8.Ryzen 7 4800U (AYANEO NEXT LITE)・・・Passmark:16709
- 9.AMD Ryzen 5 4500U (AYANEO NEXT LITE)・・・Passmark:10938
- 10.AMD APU 3.5GHz (Steam Deck OLED)・・・Passmark:8683
<比較から分かること>
AMD Ryzen 7 8840U(スコア: 24306)は、携帯デバイス向けCPUとして非常に高性能な部類に入ることがわかります。Ryzen Z1 Extreme(25328)やCore Ultra 7 155H(25009)、Ryzen 7 7840U(25007)といった最上位クラスのCPUにはわずかにスコアで劣りますが、その差は小さく、依然としてトップレベルの性能グループに位置しています。
一方で、Core Ultra 5 135H(24100)や同世代のRyzen 5 8640U(19592)、旧世代のRyzen 7 6800U(20636)やSteam DeckのAPU(8683)などと比較すると、Ryzen 7 8840Uは明確に高いスコアを示しています。このことから、Ryzen 7 8840Uは優れた処理能力を持ち、携帯ゲーミングPCや高性能小型ノートPCにおいて、快適な動作と高いパフォーマンスを提供できるCPUであると評価できます。
グラフィック性能
AMD Ryzen 7 8840Uが内蔵するRadeon 780M グラフィックスはどのくらいの性能なのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<GPUのベンチマーク結果・Radeon 780Mグラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで「5370」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「2600」
- Time Spy グラフィックスコアで「2907」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「20145」
- 3DMark Wild Life「12050」
ベンチマーク結果からAMDのRadeon GPUの中では最も高いスコアでグラフィックスコアが高く、NVIDAのグラフィックボード「GTX 1650」に近い性能であることが分かります。
また、インテルのCore Ultra 9 185Hが内蔵するインテル Arc グラフィックスも同じくらいのスコアになっています。
他のCPUが内蔵するGPUと比較すると、以下のようになります。
- 1.Radeon 780M・・・3DMark Fire Strike:8000 前後
- 2.Intel Arc graphics・・・3DMark Fire Strike:8000 前後
- 3.Radeon 760M・・・3DMark Fire Strike:7800 前後
- 4.Radeon 680M・・・3DMark Fire Strike:6000 前後
- 5.8 RDNA 2 CU (Steam Deck OLED)・・・3DMark Fire Strike:5000
ゲーム性能
AMD Ryzen 7 8840Uプロセッサーと内蔵GPUのRadeon 780Mは、その強力な統合グラフィックス性能により、多くのPCゲームを快適にプレイできる能力を持っています。以下に、人気タイトルを含む各種ゲームにおける動作の目安を、ゲームの説明と合わせて示します。
【人気ゲームタイトルのFPS】
原神 (Genshin Impact)
広大なオープンワールドを探索する、美しいグラフィックとキャラクターが特徴のアクションRPGです。1080p中設定程度で50-60 FPSでの動作が可能で、フィールド探索や戦闘を滑らかで快適に楽しめます。グラフィック設定を調整することで、安定したフレームレートを維持しやすくなります。
ELDEN RING (エルデンリング)
フロム・ソフトウェア開発のダークファンタジー・アクションRPGで、歯ごたえのある戦闘と広大な探索要素が人気です。1080p低設定でFSRを併用すると40-50 FPS程度で動作します。探索や通常の戦闘は概ねスムーズですが、負荷の高い場面ではフレームレートがやや低下することもあり、設定次第でプレイアビリティを確保できます。
Cyberpunk 2077 (サイバーパンク2077)
未来都市ナイトシティを舞台にしたオープンワールド・アクションRPGで、緻密に描かれた世界観が特徴です。この要求スペックの高いタイトルも、1080p低設定でFSRを有効にすることで63 FPS程度のフレームレートで動作し、アップスケーリング技術により比較的滑らかなゲーム体験を得ることが可能です。
Grand Theft Auto V (GTA 5)
広大な架空の都市を舞台にした自由度の高いクライムアクションゲームで、長年人気を博しています。1080p中設定程度で71 FPS前後という高いフレームレートで動作し、ドライビングや銃撃戦などあらゆる場面で非常に滑らかで応答性の良いプレイが可能です。
Red Dead Redemption 2
西部開拓時代末期を舞台にしたオープンワールド・アクションアドベンチャーで、美麗なグラフィックと重厚なストーリーが評価されています。1080p低設定でFSRなどをバランス設定で用いることで60 FPSでのプレイが可能となり、広大な自然の探索やストーリー進行を美しい映像とともにスムーズに楽しめます。
The Witcher 3: Wild Hunt
ダークファンタジー世界を舞台にしたオープンワールドRPGの金字塔で、魅力的なキャラクターとストーリーが特徴です。1080p低~中設定で53 FPS程度で動作し、広大な世界の探索や戦闘をストレスなく楽しむことができるパフォーマンスです。次世代機向けアップデート後のバージョンでも設定次第で快適に遊べます。
Baldur’s Gate 3
ダンジョンズ&ドラゴンズの世界観をベースにしたターン制RPGで、非常に高い自由度と重厚な物語が評価されています。1080p低設定でFSRを併用すると39 FPS程度となります。ターン制バトルが主体のためゲームプレイ自体は十分可能ですが、特に都市部などではやや重さを感じる可能性があります。
Forza Horizon 5
メキシコを舞台にしたオープンワールド・レーシングゲームで、美しい景色の中を自由にドライブできます。1080p低~中設定で65 FPSでのプレイが可能で、高速で流れる景色も滑らかに描画され、爽快なドライビング体験を存分に味わえます。
God of War
北欧神話を舞台にしたアクションアドベンチャーゲームで、重厚なストーリーと迫力ある戦闘が魅力です。1080p低設定でFSRを併用すると65 FPSでのプレイが可能となり、激しい戦闘シーンも滑らかに表現され、映画のような体験をスムーズに楽しめます。
Ghost of Tsushima DIRECTOR’S CUT
対馬を舞台にしたオープンワールド時代劇アクションアドベンチャーで、美しい日本の風景と武士の戦いを描きます。1080p低設定でFSRを併用することで65 FPSでのプレイが可能となり、広大なフィールドの探索や流れるような剣戟アクションを高いフレームレートで快適に楽しめます。
Final Fantasy VII Rebirth (※参考: Remake Intergrade)
不朽の名作RPG「Final Fantasy VII」のリメイクプロジェクト第2作です(データは第1作Intergradeのもの)。1080p低設定(パフォーマンスモード相当)で60 FPSでのプレイが可能で、美麗なグラフィックで描かれるキャラクターや戦闘を滑らかに楽しむことができます。Rebirthも同程度の設定での動作が見込めます。
Hogwarts Legacy
「ハリー・ポッター」の世界を舞台にしたオープンワールド・アクションRPGで、魔法学校での生活や冒険を楽しめます。1080p低設定でFSRを併用すると40-50 FPS程度で動作し、広大なホグワーツ城や周辺地域の探索、魔法を使った戦闘など、ゲームの主要な要素をプレイ可能なレベルで楽しめます。
【バトルロイヤルゲームタイトルのFPS】
Apex Legends
3人1組で戦う人気のチームベース・バトルロイヤルFPSで、スピーディーな戦闘とキャラクターごとのアビリティが特徴です。1080p低設定で80-100 FPS程度での動作が可能で、高速な操作や激しい銃撃戦においても非常に滑らかで応答性が高く、競技性の高い環境でも有利に戦えます。
Fortnite
建築要素が特徴的なバトルロイヤルTPS/FPSで、多様なゲームモードと頻繁なアップデートが人気です。1080p解像度の「パフォーマンスモード」または低設定で70-90 FPS程度でのプレイが可能で、建築や戦闘といった本作のコア要素をスムーズに楽しむことができます。
Call of Duty: Modern Warfare III / Warzone
世界的に人気の高いミリタリーFPSシリーズ(Warzoneは同シリーズのバトルロイヤル)です。1080p低設定でFSRを併用すると57 FPS程度での動作が可能で、動きの速いマルチプレイヤー対戦やWarzoneにおいても概ねスムーズなプレイが可能ですが、場面によるフレームレート変動の可能性はあります。
VALORANT
5対5で戦うチームベースのタクティカルFPSで、キャラクター固有のアビリティと精密な射撃が求められます。比較的軽量なタイトルであり、1080p低~中設定で150 FPSを超える非常に高いフレームレートで動作し、高リフレッシュレートモニターの性能を活かした極めて滑らかなプレイが可能です。
NARAKA: BLADEPOINT
近接戦闘とパルクール要素を特徴とするバトルロイヤルアクションゲームです。1080p低設定で60 FPSでのプレイが可能で、スピーディーな近接戦闘や立体的な移動を滑らかな映像で楽しむことができます。
【その他のゲームタイトルのFPS】
Fallout 4
核戦争後の荒廃した世界を舞台にした自由度の高いオープンワールドRPGです。1080p中設定程度で60 FPSでのプレイが可能で、広大な世界の探索や戦闘を快適に行うことができます。MOD導入時はパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
Overwatch 2
5対5で戦うチーム対戦型アクションシューティング(FPS)で、個性的なヒーローとスピーディーなゲーム展開が特徴です。1080p低設定でFSRをバランス設定などで有効にすることで70-80 FPS程度でのプレイが可能となり、チームでの連携やアビリティを駆使した戦闘を滑らかな描画で快適に楽しめます。
まとめ
AMD Ryzen 7 8840UとRadeon 780Mの組み合わせは、多くの人気PCゲームを1080p解像度において、設定次第で快適にプレイできる実力を持っていることが確認できます。特にeスポーツタイトルや少し前のAAAタイトルでは高いフレームレートも期待でき、最新の重いタイトルもFSRなどを活用すれば十分にプレイ可能です。
違い3:ONEXPLAYER X1 Miniの高速ストレージをレビュー!X1比較
ここでは、ONEXPLAYER X1 Miniのデータ保存領域であるストレージに注目し、そのスペックや特徴、そして何よりも大きな魅力となった「交換可能性」について、実際に触れて感じたことを詳しくレビューしていきます。
高速規格 PCIe 4.0 x4 を採用
ONEXPLAYER X1 Miniは、ストレージとして高速なNVMeプロトコルに対応したM.2 SSDを採用しています。接続インターフェースはPCIe 4.0 x4であり、これは現行のポータブルデバイスとしては非常に高速な部類に入ります。この高速な接続のおかげで、OSやアプリケーションの起動、ゲームのロード時間、大容量ファイルの読み書きなどが非常にスムーズに行われます。
実際に『Cyberpunk 2077』のような広大なオープンワールドゲームをプレイする際も、ロード時間のストレスがかなり軽減されていると感じました。また、動画編集のために数十GB単位の素材ファイルをコピーする際も、待たされる感覚が少なく快適です。
選択可能な容量と小型化された規格
ストレージ容量は、512GB、1TB、2TBのモデルから選択可能です。前モデル「ONEXPLAYER X1」では最大4TBまでのラインナップがありましたが、X1 Miniでは最大2TBとなっています。少し残念に思うかもしれませんが、個人的には2TBあれば、AAA級のゲームタイトルを複数インストールしたり、大量の写真や動画データを保存したりするにも十分な容量だと感じています。
また、採用されているSSDの物理的な規格が、前モデルの「M.2 2280」から、より小型な「M.2 2230」または「M.2 2242」に変更されました。この小型化は、X1 Mini全体のコンパクト化にも貢献しているのかもしれませんね。2230/2242規格のSSDは、最近のポータブルゲーミングPCで採用例が増えており、入手性も以前よりは改善してきています。
最大の進化点:ユーザー自身によるストレージ交換が可能に!
そして、このONEXPLAYER X1 Miniのストレージにおける最大の、そして最も画期的な進化点が、ユーザー自身でSSDを交換できるようになったことです。前モデル「ONEXPLAYER X1」ではストレージの交換は基本的に想定されておらず、メーカー保証外の行為となっていました。しかし、X1 Miniでは、このストレージ交換が公式にサポートされているのです。これは本当に素晴らしい変更点だと、個人的には感動すら覚えています。
交換作業も驚くほど簡単です。本体背面にあるキックスタンドを開くと、その裏側にSSDスロットを覆う小さなパネルがあります。このパネルを固定しているネジを1本外すだけで、簡単にM.2 SSDスロットにアクセスできるのです。わざわざ本体の裏蓋全体を開ける必要がないため、非常に手軽で、PCの分解に慣れていない方でも比較的安全に作業できるでしょう。
ただし、注意点もあります。標準搭載されているSSDにはWindows OSのシステムデータが含まれているため、新しいSSDに交換しただけでは起動しません。メーカー公式サイトからリカバリー用のデータをダウンロードし、USBメモリなどを使ってOSの再インストール(リカバリー作業)を行う必要があります。この一手間はかかりますが、手順自体はそれほど難しいものではありません。
ストレージ交換がもたらす大きなメリット
このストレージ交換が可能になったことによるメリットは計り知れません。まず、購入時のコストを抑えたい場合、最も容量の少ない512GBモデルを選び、後から市場価格が下がったタイミングで、より大容量の1TBや2TBのM.2 2230/2242 SSDを購入して自分で換装するという選択肢が生まれます。これは非常に経済的です。
また、「購入時は1TBで十分だと思ったけれど、思った以上にゲームが増えて容量が足りなくなってきた…」といった将来的な容量不足の不安からも解放されます。最大2TBまでのSSDに交換できるため、長くデバイスを愛用していく上で非常に心強い仕様です。さらに、万が一SSDが故障してしまった場合でも、自分で交換部品を用意して修理できる可能性が出てくるという点も、自作PCユーザーなどにとっては見逃せないポイントでしょう。
この「自由度の高さ」こそ、X1 Miniのストレージが持つ最大の魅力だと私は考えます。
まとめ:ONEXPLAYER X1 Mini ストレージの魅力
ONEXPLAYER X1 Miniのストレージについて、その特徴と魅力をまとめます。
- 高速性能: PCIe 4.0 x4接続のM.2 NVMe SSDにより、OSやアプリ、ゲームの高速な読み書きを実現。
- 容量選択肢: 512GB、1TB、2TBから選択可能。
- 規格変更: 前モデルのM.2 2280から、小型なM.2 2230/2242規格に変更。
- 最大の魅力:交換可能: ユーザー自身で簡単にSSDの交換が可能になった(最大2TBまで)。前モデルでは不可能だった画期的な仕様。
- 交換の容易さ: キックスタンド裏のパネルを外すだけでアクセス可能。ただしOSリカバリー作業は必要。
- 交換のメリット: 初期コストの抑制、将来的な容量増設への対応、自己修理の可能性など、自由度が大幅に向上。
高速なパフォーマンスに加え、ユーザー自身による交換という大きなアドバンテージを得たONEXPLAYER X1 Miniのストレージは、デバイスとしての価値をさらに高めています。特に、コストパフォーマンスを重視する方や、将来的な拡張性、カスタマイズ性を求めるユーザーにとって、非常に魅力的な選択肢となると感じています。
違い4:ONEXPLAYER X1 Miniのデザインをレビュー!X1比較
ここでは、ONEXPLAYER X1 Miniを手にしたときにまず感じるであろう、その「見た目」や「触り心地」、つまりデザインについて、実際に使ってみた感想や前モデルとの違いを交えながら詳しくレビューしていきます。
持ち運びたくなる絶妙なサイズ感と軽さ
ONEXPLAYER X1 Miniの大きな魅力の一つは、そのコンパクトさと軽さにあります。本体サイズは幅約210.6mm、奥行き約129.2mm、そして重量は約710g。
前モデル「ONEXPLAYER X1」が幅約252mm、奥行き約163mm、重量約789gだったことと比較すると、一回り小さく、そして約79gも軽くなっています。この差は実際に手に取ってみると明らかで、カバンへの収まりが良いだけでなく、持ち運び時の負担がかなり軽減されました。
通勤時にカバンに入れて持ち運んでも、以前ほど重さを意識しなくなったのは嬉しい変化です。個人的には、このサイズと重量のバランスが、ポータブルゲーミングPCとして非常に優れていると感じています。
性能と携帯性のバランス?厚みについて
一方で、本体の厚みは約20mmあり、前モデル「ONEXPLAYER X1」の約13mmと比較すると増加しています。タブレットとして見ると少し厚めに感じるかもしれませんが、高性能なCPUや冷却機構を内蔵していることを考えれば、これは十分に納得できる範囲だと個人的には思います。
また、冷却性能を高めるための設計(例えば、フィン素材やヒートパイプ数、ファンの性能など)が施されているようなので、この厚みは安定したパフォーマンスを維持するために必要なものなのでしょう。他の高性能UMPC、例えばSteam Deckなどと比較しても、極端に厚いというわけではありません。
シンプルで機能的な外観と心地よい質感
本体のデザインは、過度な装飾がなくシンプルにまとめられており、個人的には非常に好印象です。マットでしっとりとした手触りの塗装は、滑りにくくグリップ感を高めてくれるだけでなく、安っぽさを感じさせません。ただ、人によっては指紋が少し目立つと感じるかもしれません。背面には斜めのラインがデザインアクセントとして入っており、排熱用の吸気口もそのデザインにうまく溶け込んでいます。
コントローラーを装着した際の一体感も高く、デザイン的な破綻がない点も評価できます。
使い勝手を考慮したボタン・インターフェース配置
操作ボタン類は、本体上部に指紋センサーを兼ねた電源ボタン、音量調整ボタン、そして専用ユーティリティ「OneXConsole」を呼び出すTurboボタンが配置されています。インターフェースは上部にUSB Type-C(USB4)、USB Type-A(3.2)、3.5mmイヤホンジャックがあり、底面にはUSB Type-C(USB4)、OCuLinkポート、microSDカードスロットが配置されています。
前モデルは左右側面にもポートがありましたが、X1 Miniでは上下に集約されました。個人的には、底面のポート(特にUSB4やOCuLink)は、ケーブルを接続したまま机に置くと干渉してしまうことがあるため、上部か側面に配置されている方が使いやすいと感じる場面もありました。しかし、これも本体設計上の理由があるのかもしれません。
格段に進化したキックスタンドの利便性
デザイン面での大きな改善点として、キックスタンドが本体に内蔵されたことが挙げられます。前モデル「ONEXPLAYER X1」では別売りのブラケット(カバー兼スタンド)を取り付ける必要がありましたが、X1 Miniでは本体だけで自立させることができます。
このキックスタンドは金属製でしっかりとした作りになっており、無段階で角度調整が可能。最大135度まで開くため、机の上に置いて動画を見たり、コントローラーを外してテーブルモードでゲームをプレイしたりする際に、非常に安定して見やすい角度に設置できます。
個人的にこの内蔵キックスタンドは、利便性を大きく向上させる素晴らしい改善点だと感じています。さらに、このキックスタンドの裏には、簡単にSSDへアクセスできるパネルが隠されているという機能的な側面も併せ持っています。
まとめ:ONEXPLAYER X1 Mini デザインの魅力
ONEXPLAYER X1 Miniのデザインについて、その特徴と魅力をまとめます。
- コンパクト&軽量: 前モデルより大幅に小型・軽量化(約710g)され、携帯性が格段に向上。
- 質感: マットでしっとりとした塗装で、グリップ感と高級感を両立。
- シンプルな外観: 過度な装飾がなく、機能的で洗練されたデザイン。コントローラー装着時の一体感も高い。
- ボタン・ポート配置: 操作ボタンや主要なインターフェースを上下に配置。底面ポートの配置は好みが分かれる可能性も。
- 内蔵キックスタンド: 安定感のある金属製キックスタンドを内蔵し、利便性が大幅に向上。角度調整も自由自在。
- 前モデルとの比較: 小型軽量化、キックスタンド内蔵が大きな改善点。一方で厚みは増加。
ONEXPLAYER X1 Miniは、前モデルからデザインコンセプトを受け継ぎつつ、携帯性や利便性を着実に向上させた、非常にバランスの取れたデザインに仕上がっていると感じました。特に、どこへでも気軽に持ち運べて、様々なスタイルで使いたいと考えるユーザーにとって、このデザインは大きな魅力となると感じています。
前モデルから引き継いだONEXPLAYER X1 miniのメリット まとめ
ここでは、ONEXPLAYER X1 Miniが備える、日々の使い勝手や快適なゲームプレイを支える様々な機能的な魅力について、実際に使ってみて感じたメリットを中心に詳しくご紹介していきます。単なるスペックの羅列ではなく、これらの機能がどのように役立つのか、その実用性に迫ります。
快適な操作とプレイ環境を実現する要素
手になじみ、カスタマイズも可能な専用コントローラー
ONEXPLAYER X1 Miniには、X1シリーズ共通の専用コントローラーが用意されています(※別売りオプションの場合あり)。タブレット本体の左右に装着すればポータブルゲーミングPCとして、また別売りのコネクターを使えばワイヤレスコントローラーとしても利用可能です。実際に手に取ってみると、人間工学に基づいたエルゴノミクスデザイン、特にS字カーブを描くグリップ部分は手のひらにしっくりと馴染み、長時間のプレイでも疲れにくいと感じました。
さらに、背面に2つのカスタムキーが搭載されており、専用アプリ「OneXConsole」からボタンマッピングやマクロ設定、連射機能(ターボ)の割り当てが可能です。自分のプレイスタイルに合わせて細かくカスタマイズできるのは非常に便利で、より快適なゲーム体験を実現してくれます。操作感も良好で、特にアナログスティックやボタンの反応も良く、ストレスなくプレイに集中できました。
ゲームも動画も臨場感アップ:Harman認定 高音質スピーカー
内蔵されているデュアルスピーカーは、オーディオブランドとして名高いHarman社の認定を受け、「Harman AudioEFX」オーディオ技術に対応しています。正直、ポータブルデバイスの内蔵スピーカーにはあまり期待していなかったのですが、X1 Miniのスピーカーは良い意味で裏切られました。
ゲームの効果音やBGMはもちろん、映画や音楽を再生した際も、クリアで迫力のあるサウンドを楽しむことができます。特に低音域もしっかりと表現されており、内蔵スピーカーだけでも十分に没入感のある体験が可能です。外出先でイヤホンなしでゲームや動画を楽しみたい時にも、この高音質スピーカーは大きなアドバンテージになります。
高いパフォーマンスと持続性を両立
余裕の処理能力を支える大容量・高速メモリ
ONEXPLAYER X1 Miniは、最大64GBという大容量のLPDDR5Xメモリを搭載可能です(モデルにより16GB/32GB/64GB)。メモリクロックも7500MHzと非常に高速です。この大容量かつ高速なメモリは、PC全体の快適な動作に大きく貢献しています。例えば、複数のアプリケーションを同時に起動したり、ブラウザで大量のタブを開いたりといったマルチタスクもスムーズにこなせます。
ゲームをプレイしながら攻略情報をWebで検索したり、録画ソフトを裏で動かしたりといった使い方でも、メモリ不足による動作の遅延を感じることはほとんどありませんでした。
外出先でも安心:大容量バッテリーと100W PD急速充電
バッテリー容量は65.02Wh (16890mAh)と、ポータブルデバイスとしては比較的大容量です。公式の駆動時間目安としては、TDP(消費電力のような指標)15W設定でのゲームプレイで約2.5時間、TDP 5W設定なら約6時間、オフラインでの動画再生なら約11時間とされています。実際のプレイ環境にもよりますが、TDP設定を調整すれば、外出先でも十分にゲームを楽しむことができました。
さらに嬉しいのが、100WのPD(Power Delivery)急速充電に対応している点です。付属の充電器(または対応充電器)を使えば、わずか30分でバッテリー残量を50%まで回復させることができます。バッテリーが少なくなっても、短時間の充電でかなり回復できるので、外出先でのバッテリー切れの不安が大幅に軽減されます。これは本当に心強い機能です。
高負荷時も安定動作:考え抜かれた冷却システム
高性能なプロセッサを安定して動作させるためには、強力な冷却システムが不可欠です。X1 Miniには、油圧ベアリングを採用した高効率ファン、表面積の広いアルミニウム製フィン、そして2本のヒートパイプを組み合わせた最新の冷却システムが搭載されています。
本体背面や上部には効率的に排熱を行うための通気孔が設けられており、高負荷なゲームを長時間プレイしても、極端なパフォーマンス低下(サーマルスロットリング)を起こしにくい設計になっています。
実際に使っていても、本体はそれなりに熱を持ちますが、動作が不安定になることはありませんでした。ファンの音も、負荷に応じて回転数が変化しますが、個人的には耳障りな高音ではなく、許容範囲内だと感じました。
高い拡張性と便利な接続性
デスクトップ級のパワーを:OCuLinkポート搭載
本体にはOCuLinkポートが搭載されています。これは、最大63Gbps(理論値)という非常に高速なデータ転送が可能なインターフェースで、主に外付けGPUボックス(eGPU)を接続するために使用されます。別売りの「ONEXGPU」のようなeGPUデバイスを接続すれば、内蔵GPU(Radeon 780M)を遥かに凌ぐグラフィック性能を発揮させることが可能です。
これにより、自宅ではデスクトップPCに匹敵するような環境で最新のAAA級ゲームを高画質設定で楽しむ、といった使い方も可能になります。将来的なパワーアップの選択肢があるのは、大きな魅力と言えるでしょう。
豊富なインターフェース:USB4とUSB-A
接続ポート類も充実しています。高速データ転送(最大40Gbps)、映像出力(最大4K)、そして100W PD充電に対応したフル機能のUSB4 Type-Cポートが2基搭載されています。これにより、充電しながら外部ディスプレイに映像を出力したり、高速な外付けSSDを接続したりと、様々な使い方が可能です。
加えて、従来の周辺機器との互換性を確保するためのUSB 3.2 Type-Aポートも1基搭載されています。マウスやキーボード、USBメモリなど、まだまだUSB-A接続の機器は多いため、変換アダプタなしで直接接続できるのは非常に便利です。個人的にも、愛用しているマウスをそのまま使えるのは助かりました。
スマートで便利な機能群
素早く安全にログイン:顔認証&指紋認証
セキュリティと利便性を両立する生体認証に対応している点も、X1 Miniの魅力です。ディスプレイ上部(横持ち時)にはWindows Hello対応のAIカメラが搭載されており、顔認証でのログインが可能です。
さらに、本体上部の電源ボタンには指紋認証センサーも内蔵されています。マスクをしている時や暗い場所では指紋認証、それ以外では顔認証といったように、状況に応じて使い分けられるのが非常に便利です。パスワードやPINコードを入力する手間なく、素早く安全にログインできるため、ストレスなく使い始められます。
設定もゲーム管理もこれ一つ:「OneXConsole」アプリ
ONEXPLAYERシリーズ共通の管理用アプリ「OneXConsole」がプリインストールされています。このアプリを使えば、TDP(消費電力)の設定、ファンの回転数制御、CPU/GPUの動作状況モニタリング、コントローラーのRGBライト設定、背面カスタムキーの割り当てなど、デバイスの様々な設定を簡単に行うことができます。ゲームごとに最適な設定を素早く呼び出せるのは非常に便利です。
また、異なるプラットフォーム(Steam、Epic Gamesなど)のゲームを一元管理できるランチャー機能や、デバイス間でセーブデータを同期できる「ゲームクラウドアーカイブ転送」機能(対応デバイス間)も搭載しており、UMPCをより快適に使うための機能が詰まっています。
まとめ:ONEXPLAYER X1 Mini を支える多彩な機能
ONEXPLAYER X1 Miniが備える、使い勝手を高める様々な機能についてまとめます。
- 専用コントローラー: 装着・分離可能で、カスタマイズ性も高く快適な操作感を提供(別売りオプションの場合あり)。
- 高音質スピーカー: Harman認定スピーカーにより、内蔵ながら臨場感のあるサウンドを実現。
- 大容量・高速メモリ: 最大64GBのLPDDR5Xメモリで、マルチタスクもスムーズ。
- バッテリーと充電: 65.02Whの大容量バッテリーと100W PD急速充電で、外出先でも安心。
- 冷却システム: 高負荷時でも安定したパフォーマンスを維持する効率的な冷却設計。
- OCuLinkポート: 外付けGPU接続による大幅なグラフィック性能向上の可能性。
- 豊富なUSBポート: 高速・多機能なUSB4 Type-C x2と汎用性の高いUSB-A x1を搭載。
- 生体認証: 顔認証と指紋認証の両対応で、素早く安全なログインが可能。
- 専用アプリ「OneXConsole」: TDP設定やゲーム管理などを簡単に行える統合ユーティリティ。
これらの多彩な機能が組み合わさることで、ONEXPLAYER X1 Miniは単なる高性能なポータブルゲーミングPCにとどまらず、日常的な利用からクリエイティブな作業まで、幅広いシーンで快適に使えるデバイスとなっていると感じました。
「ONEXPLAYER X1 mini」のデメリット
ここでは、多くの魅力を持つONEXPLAYER X1 Miniについて、素晴らしい点だけでなく、実際に使ってみて感じた「ここは少し気になる」「購入前に知っておいた方が良い」と感じた点、つまりデメリットや注意点について正直にレビューしていきます。どんな製品にも長所と短所があります。購入後のミスマッチを防ぐためにも、ぜひ参考にしてください。
サイズと重量のトレードオフ:携帯性と存在感
携帯性は向上したが、依然として「ずっしり」感
ONEXPLAYER X1 Miniは、前モデル「ONEXPLAYER X1」と比較して大幅に小型・軽量化(約710g)されました。これにより携帯性が向上したのは間違いなくメリットです。しかし、約710gという重量は、一般的なタブレットやNintendo Switch(有機ELモデル、Joy-Con取り付け時で約420g)などと比較すると、依然として「ずっしり」とした重さを感じさせます。
実際に手に持って長時間ゲームをプレイすると、腕や手首に負担を感じることがありました。特に寝転がってプレイするようなスタイルには、あまり向いていないかもしれません。もちろん、膝の上に乗せたり、机に置いたりしてプレイする分には問題ありませんが、「どこでも気軽に手持ちで長時間」というイメージを持っていると、少しギャップを感じる可能性があります。
前モデルより増した「厚み」の印象
重量だけでなく、本体の厚みが約20mmある点も、人によっては気になるかもしれません。前モデル「ONEXPLAYER X1」が約13mmだったことを考えると、7mmほど厚くなっています。高性能な冷却機構を搭載するためには必要な厚みなのかもしれませんが、タブレットとして手に持った際には、その厚みがやや無骨に感じられることもありました。スリムさを重視する方にとっては、少し気になるポイントかもしれません。
インターフェース配置のクセ:底面ポートの使い勝手
机上での利用やキーボード接続時に注意
ONEXPLAYER X1 Miniは豊富なインターフェースを備えていますが、その配置には少しクセがあります。特に本体底面にUSB4 Type-Cポート、OCuLinkポート、そしてmicroSDカードスロットが集中している点は、利用シーンによっては不便さを感じることがありました。
例えば、本体をキックスタンドで立てて机の上で使いたい場合、底面のUSB Type-Cポートから充電ケーブルや外部機器を接続すると、ケーブルが邪魔になったり、安定して置けなかったりすることがあります。また、別売りの専用キーボードを接続すると、これらの底面ポートがキーボードで隠れてしまい、アクセスできなくなります。
キーボードを接続したままmicroSDカードを抜き差ししたり、OCuLinkでeGPUを接続したりといった使い方は基本的にできません。個人的には、もう少しポート配置に工夫があれば、さらに使い勝手が向上したのではないかと感じています。
パフォーマンスと価格のバランス:高価格帯という現実
高性能ゆえの価格設定
ONEXPLAYER X1 Miniは、最新のAMD Ryzen 7 8840Uプロセッサ、高速・大容量メモリ、高精細・高リフレッシュレートディスプレイなど、非常に高性能なパーツで構成されています。そのため、本体価格も比較的高価な設定となっています。最も安価な構成でも15万円近く(※価格は変動する可能性があります)、メモリやストレージ容量を増やすと20万円を超える価格帯になります。
もちろん、その価格に見合うだけのパフォーマンスや機能を持っていることは事実ですが、気軽に購入できる価格帯とは言えません。他のポータブルゲーミングPCや、同価格帯のノートPCなどと比較検討し、本当に自分のニーズに合っているか、この価格を出す価値があるかを慎重に判断する必要があるでしょう。
フル活用にはアクセサリー費用も
以前のレビューでも触れましたが、このデバイスの「3in1」コンセプトを最大限に活かすためには、別売りの専用コントローラーや専用キーボードが必要になる場合が多いです。これらを揃えるとさらに数万円の追加コストがかかるため、トータルでの予算をしっかりと見積もっておくことが重要です。
細かいけれど気になるかもしれない点
SSD規格の選択肢(M.2 2230/2242)
ストレージ交換が可能になった点は大きなメリットですが、採用されているSSDの規格が「M.2 2230」または「M.2 2242」という小型タイプである点には注意が必要です。一般的なノートPCやデスクトップPCで広く使われている「M.2 2280」規格と比較すると、まだ製品の選択肢が少なく、同じ容量でも価格が割高になる傾向があります。将来的に自分でSSDを換装しようと考えている場合は、この点を留意しておくと良いでしょう。
まとめ:購入前に考慮すべき注意点
ONEXPLAYER X1 Miniは多くの魅力を持つ一方で、以下のような注意点やデメリットも存在します。
- 重量と厚み: 約710gの重量は長時間の手持ちには不向きな場合があり、約20mmの厚みはタブレットとしては厚く感じる可能性がある。
- ポート配置: 底面に主要なポートが集中しているため、使用状況によってはケーブルの取り回しやアクセスに不便が生じる。
- 価格: 高性能な分、本体価格が高価であり、気軽に購入できる価格帯ではない。
- 追加コスト: デバイスの機能をフル活用するには、別売りのアクセサリー(コントローラー、キーボード等)が必要になる場合が多く、総額が高くなる。
- SSD規格: 交換可能なSSDは小型のM.2 2230/2242規格であり、2280規格より選択肢や価格面で注意が必要な場合がある。
これらの点を理解し、自身の使い方や予算、許容できる範囲などを考慮した上で、ONEXPLAYER X1 Miniが自分にとって最適なデバイスかどうかを判断することが大切です。
ONEXPLAYER X1 miniのスペック
- ディスプレイ 8.8インチ、解像度 2560 x 1600ドットのLPTS
※WQXGA/16:10/輝度500nits/DCI-3 97%/sRGB 138%/DC調光/10点マルチタッチ - リフレッシュレート 144 Hz
- プロセッサ AMD Ryzen 7 8840U
※4nm/8コア/16スレッド/最大5.1GHz/Zen 4 - GPU AMD Radeon 780M (12コア,2700 MHz, RDNA 3)
- NPU AMD Ryzen AI (最大 16 TOPS)
- RAM(メモリ) 16GB/32GB/64GB LPDDR5X-7500 MHz
- ストレージ 512GB/1TB/2TB (M.2 2230/2242 PCle 4.0×4)
- 拡張ストレージ M.2 2230/2242 PCle 4.0×4で最大2TBまで、microSD 4.0カードで最大2TBまで
- バッテリー 65.02 Wh (16890mAh)
- 駆動時間 15Wゲームプレイで約2.5時間、5Wゲームプレイで約6時間、オフラインビデオ再生で約11時間
- 充電 100WのPD急速充電(GaN急速充電アダプター:30分で50%まで回復)
- カメラ フロントAIカメラ
- ワイヤレス通信 Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2
- インターフェース USB4 Type-C (フル機能) x2、USB 3.2 Type-A x1、microSDカードスロット 4.0 (300MN/s,最大2TB)x1、3.5mm オーディオ x1、OCuLink (PCle 4.0×4) x1
- スピーカー Harman AudioEFX (x2)、HARMAN社認定、8Ω/1W
- タッチペン 4096段階の筆圧検知 タッチペン(別売)
- コントローラー ホールトリガー、L1/R1ボタン、ALPS社製ジョイスティック、十字キー、重さ約125g
- モーター 従来のバイブレーションモーター
- ジャイロ 6軸ジャイロセンサー(3軸ジャイロセンサー+3軸加速センサー)
- 冷却システム 速度:4700RPM、ベアリング:油圧ベアリング、フィン素材:アルミニウム、放熱面積:26000 mm2、ヒートパイプの数:2
- 生体認証 指紋認証(電源ボタンに指紋センサー搭載)、顔認証
- オプション 専用カバーキーボード、専用コントローラー、専用コントローラーコネクター、専用液晶保護フィルム、専用ケース
- アプリ OneXConsole (管理用コンソール)
- OS Windows 11
- サイズ 210.6 x 129.2 x 20 mm
- 重量 約 710 g
- カラー ブラック
ONEXPLAYER X1 miniの評価
6つの基準で「ONEXPLAYER X1 mini」を5段階で評価してみました。
- スペック:★★★★★
- デザイン:★★★★
- 通信:★★★★
- 機能:★★★★
- 使いやすさ:★★★★★
- 価格:★★
「ONEXPLAYER X1 mini」はこんな人におすすめ!
ポータブルゲーミングPCとしてだけでなく、8.8インチのタブレットとしても使いたい人に最適です。
10.95インチだった前モデル「ONEXPLAYER X1」よりも小型化したことで携帯性がぐんとアップ。単体での重さは約 789 gと、一般的なノートPCと比べてもかなり軽量です。
また、小型サイズながらもAMD Ryzen 7 8840U プロセッサ搭載でパワフルに動作するのも魅力的です。前モデルが搭載するCore Ultra 7 155Hよりはやや性能が劣るものの、ほとんどのPCゲームが60 FPS以上で動作するのは非常に大きなメリットです。
ゲーミング性能では専用のX1コントローラーで快適に操作できるほか、OCuLink ポートや本格的な冷却システムも搭載されており、完成度は高いといえます。
そのほか、ストレージの交換にも対応するようになったのが非常に便利です。内蔵ストレージは512GB/1TB/2TB (M.2 2230/2242 PCle 4.0×4)から選べますが、少ない容量を選んでも、後から容量を増やて便利です。
「ONEXPLAYER X1 mini」はAndroidタブレットにはない仕様で、大容量ストレージのWindowsタブレットとして使いたい人に最適です。
ONEXPLAYER X1 miniの価格・購入先
One-Netbookストア
16GB+512GBで139,800円、16GB+1TBで146,110円、
32GB+1TBで160,360円、32GB+2TBで177,460円、
64GB+2TBで216,600円、
で販売されています。
One-Netbookストアで「One-Netbook X1 Mini」をチェックする
ECサイト
- Amazonで200,600円(税込)、
- AliExpressで131,051円、
で販売されています。
Amazonで「ONEXPLAYER X1 mini」をチェックする
楽天市場で「ONEXPLAYER X1 mini」をチェックする
ヤフーショッピングで「ONEXPLAYER X1 mini」をチェックする
AliExpressで「One-Netbook X1 Mini」をチェックする
米国 Amazon.comで「One-Netbook X1 Mini」をチェックする
※AliExpressでの購入方法・支払い方法はこちらのページで紹介しています。
AliExpressで激安ガジェットをお得に購入する方法を徹底 解説

おすすめの類似製品を紹介
「ONEXPLAYER X1 mini」に似たポータブルゲーミングPCも販売されています。
OneXPlayer G1
OneXPlayer社から発売されるノートPC兼ポータブルゲーミングPCです(2025年5月発売予定)。
AMD Ryzen™ AI 9 HX 370/AMD Ryzen™ 7 8840Uプロセッサ、32GB/64GBのLPDDR5Xメモリ、8.8インチのLTPS液晶(2560×1600解像度)、1TB/2TB/4TBのPCIe 4.0×4 SSDストレージ、51.975Whバッテリー、2MPのWindows Hello対応カメラ、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、脱着式でRGBバックライト付きの物理キーボード、ホール効果ジョイスティック&リニアトリガーを備えたゲームコントローラー部、144Hzリフレッシュレート、Harmanチューニングのデュアルスピーカー、Oculinkポートに対応。
65WのGaN急速充電(バイパス充電対応)や、電源ボタン一体型の指紋認証センサー、2つのUSB4 Type-Cポート、USB 3.2 Type-Aポート、microSDカードスロット 4.0、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2にも対応しています。
価格は、Amazonで163,000円(税込)、楽天市場で163,000円(税込・送料無料)、AliExpressで139,395円、です。
関連記事:ONEXPLAYER G1徹底解剖レビュー!X1 miniとの違いを比較検証
ZOTAC ZONE
ZOTACから発売された7インチの携帯ゲーム機(ハンドヘルドゲーム機、ポータブルゲーミングPC)です。
Windows 11 Home、AMD Ryzen 7 8840U、16GB LPDDR5X、フルHDのAMOLED(有機EL)液晶、512GB M.2 NVMe ストレージ、48.5Wh バッテリー、1MPのWebカメラ、6軸ジャイロセンサー、カードリーダー(UHS-II microSD)搭載で、
リフレッシュレート 120Hz、RGBライト(背面)、ホール効果のトリガー・アナログスティック、65W PD 急速充電、ステレオスピーカー、冷却システム、触覚フィードバック、ドッキングステーション(別売)、USB4 x2、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.2 にも対応しています。
価格は、799 ドル(※日本円で約11,684円)、です。
関連記事:「ZOTAC ZONE」とROG Ally、Steam Deckの違いを解説
ROG Ally X
ASUSから発売されたRyzen Z1 Extreme搭載の7型ポータブルゲーミングPCです。フルHDのIPS タッチスクリーン、1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)、80WHrsバッテリー搭載で、デュアル ステレオスピーカー、指紋認証、AURA SYNC、USB4 Gen2、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、Amazonで139,800円、ASUS公式オンラインストアで139,800円 (税込)です。
関連記事:「ROG Ally X」に買い替えは必要か? 変更点を詳細に調べてみた
Steam Deck OLED
米国 Valve から発売された7.4インチのポータブルゲーミングPCです。Steam OS 3.0、Zen2ベースのAMD APUと16 GB LPDDR5 メモリ、HD画質のHDR OLED(有機EL)タッチスクリーン、512GB/1TB NVMe SSD、50 Whバッテリー、トラックパッド搭載で、
リフレッシュレート 90 Hz、HDハプティクス、大型の冷却ファン、DSP内蔵ステレオスピーカー、デュアルアレイマイク、microSDカードでのストレージ拡張、45W急速充電、6軸ジャイロセンサー、Steam Deck ドッキングステーション(別売)、USB3 Gen2 Type-C (DP映像出力/PD充電/データ転送)x1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応しています。
価格は、KOMODO公式サイトで84,800円~です。
関連記事:「Steam Deck OLED」実は超快適? 人気ポータブルゲーミングPCと徹底 比較!
MSI Claw A1M
MSIから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです。フルHD液晶、Core Ultra 7、16GBメモリ、NVMe Gen4 SSD、53 WHrバッテリ、Thunderbolt 4、2W スピーカー搭載で、ハイパーフロー冷却、Wi-Fi 7に対応しています。
価格は、Amazonで95,396円 (税込・CoreUltra5モデル)、楽天市場で93,630円円(送料無料・Core Ultra 5モデル)、ヤフーショッピングで85,420円、米国 Amazon.comで$569.00です。
関連記事:「MSI Claw A1M」は爆速でコスパもいい? 新世代のポータブルゲーミングPCと比較
「Lenovo Legion Go」
レノボから発売された8.8型のポータブルゲーミングPCです。WQXGA液晶、Ryzen Z1 Extremeプロセッサ、49.2Whrバッテリ、512GB M.2 SSD、着脱式のコントローラー搭載で、Wi-Fi 6Eにも対応しています。
価格は、Amazonで110,880円(税込)、楽天市場で108,760円(送料無料)、ヤフーショッピングで114,000円(送料無料)、レノボ公式サイトで134,860円~、米国 Amazon.comで$884.99です。
関連記事:「Lenovo Legion Go」が革新を起こす?最新 ポータブルゲーミングPCと徹底 比較!
その他のおすすめゲーム製品は?
その他のおすすめゲーム製品は以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
ポータブルゲーミングPCはどれを選ぶべきか? 最新の全機種と選び方を紹介
最新のポータブルゲーミングPCをまとめて紹介しています。
AYANEOのポータブルゲーミングPCがやはり最強か? 全機種 まとめ
AYANEOのポータブルゲーミングPCをまとめて紹介します。
GPDの超小型PC(UMPC)やタブレットをまとめています。