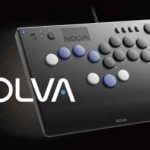2023年11月17日に発売されたValve「Steam Deck OLED」は、携帯ゲーミングPCの世界に衝撃を与えた前モデルを大幅に改良し、”最強の携帯ゲーム機”の座を確固たるものにしようとしています。
このレビューでは、最大のライバルである「ROG Ally X」と性能、画質、操作性、そして最も重要な「ゲーム体験」において、どちらが本当に買いなのかを徹底的に比較・検証しました。
【先に結論からお伝えしましょう】
Steam Deck OLED の長所(Pros):
- 圧倒的な画質を誇るHDR対応OLEDディスプレイ
- SteamOSによる「ゲーム機」のような快適なUIと完璧なスリープ機能
- ROG Ally Xにはない独自のトラックパッドと4つの背面ボタン
- ROG Ally X(約678g)より軽量(約640g)で疲れにくいデザイン
- EmuDeckなどによる高いカスタマイズ性
Steam Deck OLED の短所(Cons):
- ROG Ally X (Zen 4/RDNA 3)に圧倒的に劣る純粋な処理性能 (Zen 2/RDNA 2)
- 「Xbox Game Pass」などSteam以外のゲームがネイティブで動かない
- ROG Ally X (80Whr)に劣るバッテリー容量 (50Whr)
- 内蔵SSDの換装(交換)が非常に難しい
- USB-Cポートが1基しかなく拡張性が低い
総合評価:
Steam Deck OLEDは、純粋な「パフォーマンス」を追求するならROG Ally Xに軍配が上がりますが、「ゲーム体験の質」と「ストレスのない快適さ」を最重要視するユーザーにとって、唯一無二の最高の選択肢です。
<この記事で分かること>
- ソフトウェア比較: SteamOSとWindows 11の決定的な違い
- できるゲーム: Xbox Game Passが動くか、EmuDeckの導入方法
- 性能比較: ベンチマークスコアで見るROG Ally Xとの圧倒的な性能差(グラフィック性能比較)
- 実機ゲーム性能: 『サイバーパンク2077』などAAAタイトルの実測FPS(フレームレート)
- ディスプレイ比較: OLED (HDR/90Hz) vs Ally X (液晶/120Hz/フルHD)
- 操作性比較: トラックパッドの有無と背面ボタンの数の違い
- デザイン比較: 重量はどっちが軽い?ポートの拡張性(USB-C)
- メモリ/ストレージ: 16GB vs 24GB、SSD換装(交換)の難易度
- バッテリー比較: 50Whr vs 80Whr、冷却性能とファンの静音性
- メリット・デメリット: 両機種を徹底比較した上での長所と短所
- 価格とスペック: 国内での購入先・ライバル機種との価格比較
この記事を最後まで読むことで、「Steam Deck OLED」が本当に「買い」なのか、それとも高性能な「ROG Ally X」を選ぶべきなのかが、はっきりと分かるはずです。購入に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク
公式ページ:Steam Deck OLED登場
KOMODO Steam Deck Store – Steam Deck is here!
ソフトウェアと「できるゲーム」:”最強のゲーム機” SteamOS vs “万能PC” ROG Ally X
ここでは、Steam Deck OLEDがどのようなゲームをプレイできるのか、その核となるOS「SteamOS」の強みと限界、そしてライバル機「ROG Ally X」との決定的な違いについて書いていきます。この2機種は、性能の数字以上にソフトウェア体験が全く異なるため、購入前に最も理解すべきポイントです。
“ゲーム機”としてのSteamOSと完璧なスリープ機能
Steam Deck OLEDの最大の魅力は、OSにValveがゲーム専用に開発した「SteamOS 3」(Arch Linuxベース)を搭載している点です。これにより、ROG Ally XのWindows 11のようなPC特有の煩雑さ(突然のアップデート、ドライバ更新、マウス操作の要求など)から解放されます。電源を入れればすぐにゲームライブラリが表示され、操作はすべてコントローラーで完結します。まさに家庭用ゲーム機のようなストレスフリーな体験です。
この「ゲーム機体験」を象徴するのが、完璧な「高速一時停止/再開」機能です。ゲームのプレイ中、いつでも電源ボタンを押すだけで瞬時にスリープに入り、もう一度押せば数秒でゲームの続きから再開できます。OLEDモデルではこの復帰時間が旧LCDモデルより約30%も短縮されており、このシームレスな体験は、スリープが不安定なWindows機では決して味わえない喜びです。
Steamゲームと「Proton」互換レイヤー
Steam Deck OLEDは、基本的に「Steamライブラリで遊ぶこと」に特化しています。SteamストアにあるWindows専用ゲームをSteamOSで動かすために、「Proton」という強力な互換レイヤーが動作しています。Valve社の継続的な努力により対応タイトルは非常に多く、「確認済み」と「プレイ可能」を合わせた動作ゲーム総数は13,000タイトルを超えています。ストアページにはDeckでの動作互換性を示すアイコン(緑の「確認済み」や黄色の「プレイ可能」)があり、購入前に快適に遊べるか判断できます。
もし公式で「非対応」となっていても、諦めるのは早いです。「ProtonDB」という有志のデータベースサイトがあり、そこに対応状況や「起動させるための設定方法」が報告されています。さらに、デスクトップモードから「ProtonUp-Qt」というツールを使えば、有志が開発した「Custom Proton」を導入できます。これにより、『ペルソナ5S』や『グランディア HDリマスター』など、公式Protonでは動作しない一部のゲームがプレイ可能になるケースもありました。
エミュレーターと無限のカスタマイズ性
SteamOS(Linux)の強みは、そのカスタマイズ性の高さにもあります。特に「EmuDeck」というツールは革命的でした。これを導入するだけで、PS2やPSPといった往年の名機のエミュレーター群を一括でインストール・設定でき、Steam Deck OLEDを「最強のポータブル・レトロゲーム機」に変貌させることができます。
さらに「Decky Loader」というプラグインローダーも必須です。これを導入すると、ゲームライブラリにProtonDBの評価バッジを表示させたり、AirPodsの接続を管理する「MagicPods」プラグインを追加したりと、自分好みに機能を拡張できます。こうした「育てる」楽しみは、メーカー製ソフト(Armoury Crate SE)で体験が完結しているROG Ally Xにはない、Steam Deckならではの魅力です。
Steam以外のゲームと「ROG Ally X」との決定的な壁
SteamOSのシンプルさは強みであると同時に、最大の弱点でもあります。それは「Steam以外のゲームへの対応力」です。ROG Ally XがWindows 11を搭載し、「Xbox Game Pass」や「Epic Games Store」のゲームをネイティブでインストールして遊べるのに対し、Steam Deck OLEDでこれらを遊ぶのは非常に困難です。
「Xbox Cloud Gaming」や「GeForce NOW」といったクラウドゲーミングサービス(ストリーミング)も、デスクトップモードでブラウザ(Edgeなど)を設定すれば利用可能ですが、ネイティブ動作ではありません。Epic Gamesのゲームを動かすにも専門知識が必要です。ROG Ally XがWindows機としてこれらをネイティブアプリや標準ブラウザでシームレスに利用できるのとは対照的です。
ROG Ally Xのように「PCで動くゲームは全部動く」という万能性を期待すると、確実に失敗します。Steam Deck OLEDは、あくまで「Steamのゲームを手軽に遊ぶためのマシン」だと割り切る必要があります。
PCとしての一面:Linuxデスクトップモード
Steam Deck OLEDはゲーム機のように使えますが、「PCとして」の側面も持っています。電源メニューから「デスクトップに切り替え」を選ぶと、見た目がPCのようになる「デスクトップモード」に移行します。ここがROG Ally Xとの根本的な違いです。ROG Ally Xのデスクトップは私たちが使い慣れた「Windows 11」ですが、Steam Deck OLEDのデスクトップは「KDE Plasma」というLinuxのUIです。
Windowsとは操作感やアプリの導入方法(「Discover」アプリなど)が全く異なるため、PCとしての汎用性や操作の習熟度ではROG Ally Xに軍配が上がります。しかし、このデスクトップモードを使いこなすことで、Steam Deck OLEDの真価が発揮されます。
まとめ:ソフトウェアと「できるゲーム」
- SteamOS搭載:最大の魅力は「ゲーム機」のようなストレスフリーな操作感と、OLEDモデルでさらに高速化した完璧なスリープ機能です。
- Proton互換レイヤー:Steam上の多くのWindowsゲームが動作します。対応タイトル総数は13,000を超えており、「ProtonDB」や「Custom Proton」を活用すれば、非対応ゲームも動かせる可能性があります。
- デスクトップモード:Linux (KDE Plasma) のデスクトップ は、Windows (ROG Ally X) と操作感が異なりますが、カスタマイズの基盤となります。
- カスタマイズ性:「EmuDeck」によるレトロゲーム環境の構築 や、「Decky Loader」によるプラグイン導入 など、無限の拡張性を秘めています。
- 弱点とROG Ally Xとの違い:「Xbox Game Pass」のネイティブ動作や「Epic Games」の利用は困難です。ストリーミングサービスもブラウザ経由での設定が必要で、Windows機(ROG Ally X)のシームレスさには及びません。
パフォーマンスとゲーム性能
ここではSteam Deck OLEDのパフォーマンス(ベンチマークグラフィック性能比較)とゲーム性能について紹介します。
APU(プロセッサー)とROG Ally X(Ryzen Z1 Extreme)との違い
Steam Deck OLEDのAPU(プロセッサー)は、旧LCDモデルの7nmプロセスから、より電力効率の高い6nmプロセスにアップデートされました。これは純粋な性能向上というよりも、バッテリー持続時間を延ばすための改良です。アーキテクチャ自体は旧モデルと同じで、CPUは「Zen 2」(4コア/8スレッド、最大3.5GHz)、GPUは「RDNA 2」(8 CU、最大1.6GHz)を搭載しています。
TDP(消費電力)は4~15Wの範囲で動作します。この構成は、最大のライバルであるROG Ally Xとは根本的に異なります。ROG Ally Xは、はるかに世代が新しく強力な「Zen 4」アーキテクチャのCPU(8コア/16スレッド)と、「RDNA 3」アーキテクチャのGPU(12 CU)を搭載しています。そのため、純粋な処理性能(TFLOPS)では、ROG Ally XがDeck OLEDを圧倒しています。
ベンチマーク
Steam Deck OLEDが搭載するAMDカスタムAPU(Zen 2アーキテクチャの4コア8スレッド)の性能はどのくらいなのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
Steam Deck OLED AMDカスタムAPUのベンチマーク
<CPUのベンチマーク結果>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「8683」
- Geekbench 6のシングルコア「1331」、マルチコア「4352」
- Cinebench R23 シングルコア「977」、マルチコア「4436」
- Cinebench 2024 シングルコア「65」、マルチコア「300」
<GPUのベンチマーク結果>
- Fire Strike グラフィックスコアで「4313」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「1706」
- Time Spy グラフィックスコアで「1700」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「11500」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「10256」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
<ゲームのベンチマーク・フレームレート>
- ファイナルファンタジーXIV: 黄金のレガシーのベンチマークでHD解像度で設定で「5835」
- 「Cyberpunk 2077」のフレームレートで解像度 1280 x 720ドット、品質「Steam Deck」で「46.77」fps
- 「ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON」のフレームレートで解像度 1280 x 720ドット、画質は「低」設定で「37」fps
- BIOHAZARD RE:4で約52~55fps程度
- F1 23で60fps
- The Last of Us Part 1で平均35fps以上
- Hogwarts Legacyで平均60fps
<ベンチマーク結果から分かること>
ベンチマークの結果から分かるのは、Steam Deck OLEDが「720p/800p解像度でPCゲームを快適に遊ぶ」ことに特化している点です。CPUスコア(Cinebench R23 マルチ: 4436)は、旧世代のモバイルCPU(Ryzen 5 3550Hなど)と同等です。GPUスコア(Time Spy: 1700)も、最新のAAAタイトルをフルHD(1080p)の高設定で動かすには力不足です。
しかし、Steam Deckの真価はSteamOSの最適化にあります。実際のゲームベンチマークでは、『Cyberpunk 2077』を720p・Steam Deck設定で平均46fps、『ARMORED CORE VI』を720p・低設定で平均37fps前後で動作させる能力があります。
これは、60fpsには届かないものの、携帯機としてAAAタイトルを十分プレイ可能なラインを維持していることを示しています。
ROG Ally Xと比較
Steam Deck OLEDが搭載するAMDカスタムAPUのCPU・GPU性能は、ROG Ally X(Ryzen Z1 Extreme)と比較すると、どのくらい違うのでしょうか?ベンチマークで比較してみました。
ROG Ally X(Ryzen Z1 Extreme)のベンチマーク
<CPUのベンチマーク結果>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「25466」
- Geekbench 6のシングルコア「2211」、マルチコア「9669」
- Cinebench 2023 シングルコア「1753」、マルチコア「13801」
- Cinebench 2024 シングルコア「115」、マルチコア「820」
<GPUのベンチマーク結果>
- Fire Strike グラフィックスコアで「8042」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「4223」
- Time Spy グラフィックスコアで「3435」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「29319」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「16859」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
CPU性能の比較
- マルチコア性能: ROG Ally XがSteam Deck OLEDの約2.2倍~3.1倍のスコア。
- Cinebench R23 (Multi): ROG Ally X (13801) vs Deck OLED (4436) [約3.1倍差]
- Passmark CPU: ROG Ally X (25466) vs Deck OLED (8683) [約2.9倍差]
- Geekbench 6 (Multi): ROG Ally X (9669) vs Deck OLED (4352) [約2.2倍差]
- シングルコア性能: ROG Ally XがSteam Deck OLEDの約1.7倍のスコア。
- Cinebench R23 (Single): ROG Ally X (1753) vs Deck OLED (977)
GPU(グラフィック)性能の比較
- 総合性能: ROG Ally XがSteam Deck OLEDの約1.8倍~2.5倍のスコア。
- Time Spy (DirectX 12): ROG Ally X (3435) vs Deck OLED (1700) [約2倍差]
- Fire Strike (DirectX 11): ROG Ally X (8042) vs Deck OLED (4313) [約1.86倍差]
- Night Raid (DX12, 低負荷): ROG Ally X (29319) vs Deck OLED (11500) [約2.5倍差]
<比較から分かること>
ベンチマークスコアの比較から分かるのは、ROG Ally XがSteam Deck OLEDを圧倒的なパフォーマンスで上回っているという事実です。これは単なる僅差ではなく、アーキテクチャの世代が根本的に違うこと(Zen 2/RDNA 2 vs Zen 4/RDNA 3)を明確に示しています。
CPU性能では、特にマルチコア性能でその差が顕著です。Cinebench R23のマルチコアスコアで比較すると、ROG Ally X(13801)はSteam Deck OLED(4436)の約3.1倍という圧倒的なスコアを記録しています。Geekbench 6(約2.2倍)、Passmark(約2.9倍)でも同様に、ROG Ally Xの8コア16スレッド(Zen 4)は、Deck OLEDの4コア8スレッド(Zen 2)をまったく寄せ付けません。
GPU性能(グラフィック性能)においても、その差は決定的です。DirectX 12の性能を測るTime Spyスコアで、ROG Ally X(3435)はSteam Deck OLED(1700)の約2倍。DirectX 11を測るFire Strike(8042 vs 4313)でも約1.86倍のスコア差があります。
この結果が意味するのは、ROG Ally XはSteam Deck OLEDよりもはるかに重い処理に耐えられるということです。Steam Deck OLEDが720p/800pという解像度で「快適に遊ぶ」ことを目指しているのに対し、ROG Ally Xは1080p(フルHD)という高解像度で「高フレームレートを狙う」ことが可能な、まったく異なるパフォーマンス・クラスのデバイスであると言えます。
AMDカスタムAPU Zen 2性能を比較
Steam Deck OLEDが搭載するAMDカスタムAPU(Zen 2アーキテクチャの4コア8スレッド)の性能を、他のCPU、GPUと比較してみました。
【Cinebench R23でCPU性能を比較】
- Ryzen Z1 Extreme (ROG Ally X)・・・13801
- AMD Ryzen AI Z2 Extreme (ROG XBOX ALLY X)・・・13212
- AMD Ryzen Z2 Go (Lenovo Legion Go S)・・・5802
- Ryzen Z2 A (ROG XBOX ALLY)・・・4541
- AMDカスタム APU Zen 2(Steam Deck OLED)・・・4436
【Time Spyでグラフィック性能を比較】
- AMD Ryzen AI Z2 Extreme (ROG XBOX ALLY X)・・4009
- Ryzen Z1 Extreme (ROG Ally X)・・・3435
- AMD Ryzen Z2 Go (Lenovo Legion Go S)・・・2179
- Ryzen Z2 A (ROG XBOX ALLY)・・・1929
- AMDカスタム APU Zen 2(Steam Deck OLED)・・・1700
<CPU性能、グラフィック性能の比較からわかること>
【CPU性能】最新のRyzen Z1 Extremeと比較するとスコアは約3分の1に留まり、世代とコア数の差による演算性能の開きは顕著です。しかし、次世代エントリーモデルのRyzen Z2 Aとはほぼ同等の数値を記録しています。このことから、Zen 2アーキテクチャの当該APUは、最新のハイエンド性能には及ばないものの、普及帯の携帯機として必要な基礎的な処理能力は維持していることがわかります。
【グラフィック性能】上位モデルのスコアと比較すると半分以下の性能であり、高解像度や高設定でのゲームプレイは厳しい位置付けにあります。比較対象の中で最も低い数値ですが、Ryzen Z2 Aとの差は約1割程度と比較的近いです。最新の重量級タイトルでは力不足が否めませんが、解像度を抑えた環境であれば、次世代エントリー機に近い水準で動作させられる可能性があることを示しています。
ゲーム性能:Steam Deck OLEDはどこまで動く?実機レビュー
ここではSteam Deck OLEDのゲーム性能について、具体的なタイトルを動かしてみて、どれだけ快適に遊べたかをフレームレート(FPS)を交えてレビューしていきます。
原神 (Genshin Impact)
美しいテイワットの世界をOLEDの鮮やかな画面で冒険するのは、まさに感動的な体験でした。解像度1280×800、グラフィック設定を「中」程度に調整したところ、フィールド探索や街中での移動は非常に滑らかで、おおむね45フレームから60フレーム/秒(fps)を維持してくれます。もちろん、複数の敵と元素爆発が飛び交う派手な戦闘シーンではフレームレートに変動がありますが、プレイの快適さが大きく損なわれることはありません。手のひらの上で、これだけ美しい『原神』が動くのは素直に嬉しい驚きです。
Apex Legends
次に、スピーディーな展開が求められる『Apex Legends』です。競技性を重視し、1280×800解像度でグラフィック設定を「低」から「中」の競技向けにカスタムしたところ、60fpsをターゲットにしっかり動作してくれました。 遮蔽物の少ない開けた場所や屋内での戦闘では50fpsから60fpsを維持し、OLEDの応答速度(< 0.1ms)のおかげで敵の視認も非常にクリアです。降下時や最終盤の混戦では一時的に揺らぐものの、携帯機でここまで本格的な撃ち合いができるとは思いませんでした。
サイバーパンク2077 (Cyberpunk 2077)
最も気になる重量級タイトル、『サイバーパンク2077』です。解像度1280×720、専用のグラフィックプリセット「Steam Deck」に設定してベンチマークを計測したところ、平均46.77fpsという驚きの結果が出ました。ナイトシティのドライブ中は40fps台を維持し、激しい銃撃戦でも30fps台後半をキープしてくれます。OLEDのHDR機能で見るネオン街の輝きは息をのむ美しさで、60fpsは出なくとも、この世界を手のひらで体験できる満足感は非常に高かったです。
Forza Horizon 5
息をのむほど美しいメキシコの風景を、OLEDの鮮やかなディスプレイで堪能できました。1280×800解像度で、グラフィック設定を「中」から「低」でバランス調整したところ、ほとんどの場面で50fpsから60fpsをキープしてくれました。雨の中のレースや多数の車が密集する場面でも大きなカクつきはなく、携帯機とは思えない滑らかなドライブ体験に夢中になれました。
ストリートファイター6 (Street Fighter 6)
対戦格闘ゲームの命は、安定したフレームレートです。1280×800解像度で、グラフィック設定を「低」、あるいはSteam Deck専用プリセットを選択したところ、期待通り、対戦中はほぼ常時安定した60fpsを叩き出してくれました。技の入力が遅れたり、コンボが途切れるようなストレスは一切ありません。OLEDの鮮明な画面で相手の動きもはっきり見え、オンライン対戦も遅延なく楽しめます。「ワールドツアー」モードも快適で、まさに携帯できる最強の対戦台です。
ディアブロ IV (Diablo IV)
ハクスラの快適さも十分でした。1280×800解像度、グラフィック設定「中」で、FSR(アップスケーリング技術)をバランス良く効かせることで、概ね40fpsから60fpsの範囲で動作します。通常のダンジョン探索では滑らかに動作し、おびただしい数の悪魔が画面を埋め尽くす大規模な戦闘では40fps近くまで落ち込むこともありますが、ゲームプレイは安定しています。OLEDの完璧な黒がダンジョンの陰鬱な雰囲気を際立たせ、没入感は抜群でした。
まとめ:ゲーム性能
Steam Deck OLEDに搭載されたAMDカスタムAPUは、携帯型ゲーミングPCとして、非常にバランスの取れた優れたゲーム性能を有しています。ベンチマークスコア自体はROG Ally Xに劣るものの、SteamOSの最適化により、720p/800pというネイティブ解像度において多くのゲームを快適に動作させることに特化しています。
今回取り上げた『サイバーパンク2077』(平均46.77fps)や『ARMORED CORE VI』(平均37fps)といった重量級のAAAタイトルでも、専用の設定プリセットや低~中設定を活用することで、携帯機として十分プレイ可能なフレームレートを維持します。さらに、『ストリートファイター6』や『Forza Horizon 5』のような最適化されたタイトルでは、安定した60fps動作も実現しており、滑らかなゲーム体験が可能です。このパフォーマンスが、OLEDディスプレイの圧倒的な画質と応答速度と組み合わさることで、携帯機とは思えないほど没入感の高いゲーム体験を実現しています。
デザインと外観:Steam Deck OLEDの携帯性と拡張性
ここでは、Steam Deck OLEDの物理的なデザイン、特にその重量と持ちやすさ(携帯性)、そして接続ポート(拡張性)について書いていきます。旧型のSteam Deck LCDモデルや、直接のライバルとなるROG Ally Xと比較しながら、実際に手に持った感覚や使用感を詳しくレビューします。
軽さと持ちやすさの進化
Steam Deck OLEDを箱から取り出して最初に感じたのは、旧LCDモデルと比較した際の「明らかな軽さ」です。スペック上では旧LCDモデル(約669g)からOLEDモデル(約640g)へと約30gの軽量化ですが、実測では60g以上軽くなっており、この差は体感としてもしっかりと認識できました。数字以上に軽く感じるのは、絶妙な重量バランスと握りやすいグリップのおかげだと感じます。
直接のライバルであるROG Ally Xの重量が約678gであることを考えると、Steam Deck OLEDの約640gという重量は携帯性において明確なアドバンテージとなります。ROG Ally Xも人間工学に基づいたデザインで持ちやすいのですが、長時間プレイすると約38gの差がじわじわと効いてきます。個人的には、さまざまな携帯ゲーミングPCを試した中でも、Deckの「持ってて疲れにくい」感覚はトップクラスだと感じました。
また、旧LCDモデルからの細かなデザイン変更も好印象です。最も分かりやすいのは電源ボタンで、旧型では他と同じ黒色で押し間違いやすかったのが、OLEDモデルでは鮮やかなオレンジ色に変更され、一目で識別できるようになりました。さらに、アナログスティックの根本が黒に統一され、ゲームプレイ中に視界の端で白がチラつくことがなくなり、よりゲームに没入できるようになっています。
接続ポートと拡張性
拡張性に関しては、Steam Deck OLEDは非常にシンプルです。本体上部にUSB-C 3.2 Gen 2ポートが1基、3.5mmヘッドフォンジャック、そして底面にUHS-I対応のmicroSDカードスロットが1基あるだけです。このシンプルさは「ゲーム機」としての手軽さに貢献していますが、PCとしての拡張性は高くありません。
この点は、ROG Ally Xと比較すると明確な弱点となります。ROG Ally XはUSB-Cポートを2基搭載し、うち1基は高速なUSB4に対応しています。これにより、ROG Ally Xは本体を充電しながら、もう一方のポートでドックなしに直接モバイルモニターや他の周辺機器に接続できます。Steam Deck OLEDで同じことをするには、別途ドッキングステーションを用意する必要があり、手軽さの面で一歩劣ります。
とはいえ、microSDカードによるストレージ拡張は非常に便利です。最近のAAAタイトルは容量が大きいため、本体SSDがいっぱいになっても、カードを追加するだけでライブラリを増やせるのは大きなメリットです。
まとめ:デザインと外観
- 軽量化:旧LCDモデル比で約30g軽量化され(約640g)、体感できるレベルで持ちやすさが向上しています。
- ROG Ally Xとの比較:ROG Ally X(約678g)よりも約38g軽量で、グリップの良さも相まって長時間のプレイでも疲れにくいです。
- デザインの改善:電源ボタンがオレンジ色になるなど、旧LCDモデルから識別性やデザイン性が向上しました。
- 拡張性:ポート類はUSB-C x1とシンプルです。USB-C x2(USB4対応)を搭載するROG Ally Xと比べると、ドックなしでの拡張性は劣ります。
ディスプレイ:Steam Deck OLEDの画質とROG Ally Xとの比較
ここでは、Steam Deck OLEDのディスプレイについて書いていきます。旧LCDモデルからの劇的な進化点、そしてROG Ally XのフルHD液晶ディスプレイとの違いを、実際のゲーム体験を交えながら詳しくレビューします。
旧LCDモデルからの劇的な進化点
Steam Deck OLEDの最大の進化点は、間違いなくディスプレイです。旧LCDモデルの7.0インチ液晶 から、ベゼルが細くなり7.4インチ のHDR対応OLEDスクリーンへと変更されました。旧LCDモデルでは斜めから見ると白っぽく黒つぶれしがちだった画面が、OLEDではどの角度から見ても鮮明です。
注目すべきは、1,000,000:1を超えるコントラスト比と、110% P3の広色域です。『Cult of the Lamb』のような色彩豊かなゲームでは、色が目に飛び込んでくるように鮮やかです。また、OLEDはピクセル自体が消灯するため「本物の黒」を表現できます。『サイバーパンク2077』 や『Resident Evil 4』のような暗いシーンが多いゲームでは、旧LCDモデルとは比較にならない没入感が得られました。
ROG Ally Xとの画質比較
一方、ライバルのROG Ally Xと比較すると、仕様が全く異なります。ROG Ally Xは1920×1080ドットのフルHD解像度と120Hzのリフレッシュレートを誇る液晶ディスプレイを搭載しています。対してOLEDモデルは1280 x 800の解像度と最大90Hzのリフレッシュレートです。
正直、OLEDモデルの解像度がフルHDでない点には、少し残念な気持ちもありました。しかし、Ally XのディスプレイはTFT液晶であり、輝度も500 nitsです。OLEDモデルはSDR時でも600 nit、HDRでは1,000 nitのピーク輝度を持ち、コントラストと色の表現力でAlly Xを圧倒します。7インチクラスの画面では解像度の差よりもOLEDの画質がもたらす感動の方が大きく、応答速度も0.1ms未満と非常に高速で、残像感は一切ありません。
1TBモデルのアンチグレアガラス
1TBモデルには、プレミアムアンチグレアエッチングガラスが採用されています。これにより、屋外や明るい場所での光の反射は抑えられますが、一方で照明が強く当たる場所では、画面が少し白っぽく見えてしまうこともありました。512GBモデルは光沢(グレア)仕上げのOLEDです。
まとめ:ディスプレイ
- OLED採用:旧LCDモデルと比較し、画質、コントラスト、黒の表現が劇的に向上しました。
- 画面サイズ:7.0インチから7.4インチに大型化しました。
- 対ROG Ally X:Ally Xは解像度(1080p)とリフレッシュレート(120Hz)で勝りますが、OLEDモデルは画質、コントラスト、HDR輝度(1000 nit)で圧倒します。
- リフレッシュレート:旧LCDの60Hzから最大90Hzに向上しました。
- 応答速度:0.1ms未満と非常に高速で、残像がありません。
操作性:Steam Deck OLED 独自の入力方式と進化したレスポンス
ここでは、Steam Deck OLEDの「操作性」について書いていきます。携帯ゲーム機として最も重要な「コントローラーのレイアウト」と「入力の感触」に焦点を当て、ROG Ally Xや旧LCDモデルとの決定的な違いをレビューします。
独自のレイアウトとトラックパッド
Steam Deck OLEDの操作系を語る上で、まず触れるべきはその独特なレイアウトです。アナログスティックが左右対称に上部に配置され、十字キーとABXYボタンがその下にあります。これは、ROG Ally Xが採用する「Xboxコントローラー」に準拠した左右非対称のスティック配置とは根本的に思想が異なります。
Deckのこの配置は、両手の親指の一番押しやすい位置に2つの「トラックパッド」を搭載するために最適化された結果です。これがROG Ally Xにはない最大の武器であり、マウス操作が前提のRTSやシミュレーションゲーム、またはFPSのインベントリ管理など、スティックでは操作しづらいPCゲームを遊ぶ際に絶大な威力を発揮します。
旧モデルから進化したボタンとスティック
OLEDモデルは、旧LCDモデルのユーザーフィードバックを元に、操作系が細かくブラッシュアップされています。アナログスティックは素材と形状が見直され、グリップ力と防塵性が向上しました。また、ショルダーボタン(L1/R1)のスイッチ機構も応答性が良くなり、十字キーも対角入力の感触が調整されています。
これは、ROG Ally Xが旧型(無印Ally)から十字キーを格闘ゲーム向けの8方向入力に再設計し、スティックの耐久性を向上させたのと同様のアプローチです。また、OLEDモデルで最も感動したのがハプティクス(振動)の進化です。旧LCDモデルの微弱なものから、しっかりとした手応えのあるフィードバックへと劇的に進化しており、トラックパッドの操作感やキーボード入力の感触が格段に向上しました。
豊富な入力系統(背面ボタン・ジャイロ・タッチ)
入力の多さもDeckの強みです。本体背面には、薬指と小指で自然に押せる4つの「背面グリップボタン」が搭載されています。ROG Ally Xも背面ボタンを搭載していますが、こちらは2つ(マクロボタン)です。割り当てられる機能の数ではDeckが勝っており、より複雑な操作を親指をスティックから離さずに実行できます。
さらに、6軸IMUによるジャイロ機能も搭載しており、これをエイム操作に割り当てることで、スティック操作だけでは難しい精密な射撃が可能になります。操作性において見逃せないのが、タッチスクリーンの応答性です。OLEDモデルはタッチスクリーンのポーリングレート(操作を検知する頻度)を180Hzにアップデートしました。これにより、タッチ操作の遅延が少なく、非常に正確で滑らかな反応が得られます。
まとめ:操作性
- 独自のレイアウト:ROG Ally Xの非対称配置と異なり、トラックパッドを最優先した左右対称のスティック配置を採用しています。
- トラックパッド:ROG Ally Xにはない最大の強み。マウス操作が必要なPCゲームで絶大な威力を発揮し、OLEDモデルでハプティクス(振動)が大幅に改善されました。
- 背面ボタン:ROG Ally Xの2ボタンに対し、Steam Deck OLEDは4つの背面グリップボタンを搭載し、より多くの機能を割り当て可能です。
- 入力の改善:旧LCDモデルからスティック、十字キー、ショルダーボタンが全て改良されています。
- タッチスクリーン:180Hzのポーリングレートにより、タッチ応答性が非常に高速かつ正確です。
メモリとストレージ:Steam Deck OLED の快適性と換装の難易度
ここでは、Steam Deck OLEDのメモリ(RAM)とストレージについて書いていきます。特に、ROG Ally Xと比較した際のメモリ容量の違いと、ユーザーの関心が非常に高いストレージ換装(交換)の難易度について、詳しくレビューします。
メモリ(RAM):16GBへの高速化
まずメモリ(RAM)ですが、Steam Deck OLEDは16GBのLPDDR5メモリ(6400 MT/s)を搭載しています。これは、旧LCDモデルの5500 MT/sから高速化されており、遅延の改善や電力管理の強化に貢献しています。SteamOSでのゲームプレイにおいて、16GBという容量は十分快適に動作します。
しかし、ライバルのROG Ally Xはこれを上回る24GBのLPDDR5Xメモリ(7500 MT/s)を搭載しています。この8GBの容量差とさらなる高速化は、Windows 11というPC用OSを搭載するAlly Xにおいて、ゲームをしながらブラウザやDiscordなどのアプリを同時に起動する際の安定性に大きく貢献します。
ストレージ:換装の難易度とmicroSD
次にストレージです。OLEDモデルは512GBまたは1TBの高速NVMe SSDを搭載しています。しかし、最近のAAAタイトルは1本で100GBを超えることも珍しくなく、ストレージ換装(内蔵SSDの交換)のニーズは非常に高いです。ここで、ROG Ally Xとの大きな差が生まれます。ROG Ally Xは、一般的なPCで広く使われている「M.2 2280」という標準サイズのSSDを採用しており、換装が比較的容易に行えます。
一方、Steam Deck OLEDのストレージ換装は、公式が「技術を習得した専門家向け」と明言している通り、かなりの難易度を伴います。旧LCDモデルより内部へのアクセスは改善されたものの、分解には専用の工具(Torxドライバー)が必要で、内部コンポーネントも密集しています。換装作業は保証の対象外となるリスクもあり、標準規格のSSDを使えるROG Ally Xの手軽さと比べると、非常にハードルが高いと言わざるを得ません。
もちろん、Steam Deck OLEDにも簡単な拡張方法が用意されています。それが高速microSDカードスロットです。UHS-I規格に対応しており、ここに『ペルソナ3 リロード』や『パルワールド』などをインストールして遊びましたが、内蔵SSDと比べてロード時間に極端な差は感じませんでした。分解のリスクを負いたくない場合、microSDカードでの運用が現実的かつ最も安全な選択肢となります。
まとめ:メモリとストレージ
- メモリ:16GB (6400 MT/s) を搭載。ROG Ally Xの24GB (7500 MT/s) と比べると、容量・速度ともに控えめです。
- ストレージ換装(難易度):標準のM.2 2280を採用し換装が容易なROG Ally X に対し、Deck OLEDは専門知識が必要で難易度が非常に高いです。
- microSDスロット:UHS-I対応のスロットを搭載しており、分解リスクなしで手軽に容量を拡張できます。
バッテリーと冷却:Steam Deck OLED の持続時間と快適性
ここでは、Steam Deck OLEDのバッテリー持続時間と充電性能、そして長時間のプレイを支える冷却性能と発熱について書いていきます。旧LCDモデルからの劇的な進化、そしてROG Ally Xとの容量・設計思想の違いをレビューします。
旧LCDモデルを圧倒するバッテリー持続時間
Steam Deck OLEDの最も大きな進化点は、バッテリー持続時間です。旧LCDモデルの40Whrから50Whrへと、物理的な容量が25%も増加しました。これに加えて、注目すべきはAPU(プロセッサー)が旧型の7nmプロセスから、より効率的な6nmプロセスにアップデートされたことです。ディスプレイ自体の消費電力もOLEDになったことで削減され、これらが組み合わさることで、公式のアナウンス通り、プレイ時間が旧LCDモデル比で30~50%向上したとされています。
実際に使ってみると、この差は歴然でした。旧LCDモデルでは『ELDEN RING』のようなAAAタイトルをプレイすると1時間少々でバッテリーが切れてしまい、モバイルバッテリーが必須でしたが、OLEDモデルでは同じゲームでも1時間半以上は遊べる感覚です。動きの少ないパズルゲームでは、旧モデルが残り8時間と表示される場面で、OLEDモデルは13時間以上と表示されることもあり、バッテリー残量を気にするストレスが大幅に減りました。
冷却性能の進化と快適性
このバッテリー持続時間の向上には、冷却性能の改善も寄与しています。Steam Deck OLEDはファンが大型化され、排熱モジュールの性能も向上しました。これにより、旧LCDモデルよりも低い温度で動作するため、ファンの回転数が抑えられ、結果として消費電力の削減にもつながっています。
実際に高負荷なゲームをプレイしても、旧モデルほど本体が熱くならず、ファンの音も比較的静かに感じられます。長時間持っていても快適性が損なわれないのは、大きな進歩です。
ROG Ally Xとの容量・冷却比較
しかし、絶対的なバッテリー容量で比較すると、ROG Ally Xには及びません。Steam Deck OLEDが50Whrであるのに対し、ROG Ally Xはそれを遥かに凌駕する80Whrという大容量バッテリーを搭載しています。これは旧型ROG Allyの40Whrから2倍になったもので、「Steam Deck OLEDよりも1.5倍長く持つ」と評価されています。
冷却設計においても、ROG Ally Xは「デュアルファン」、「3番目の通気孔」、「エアフロー24%増加」といった強力な冷却システムを搭載しています。これにより、タッチパネルの温度を最大6℃低下させ、グリップ部分が熱くならないと評価されており、冷却に対するアプローチはOLEDモデル以上に強力です。OLEDモデルも電力効率と冷却のバランスは素晴らしいですが、純粋なバッテリー容量と冷却機構の物量ではAlly Xに軍配が上がります。
充電速度とポートの比較
OLEDモデルは充電速度も改善されています。バッテリーの化学的特性が見直され、バッテリー残量が20%の状態からでも、約45分で80%まで急速充電できることを確認しました。旧LCDモデルよりも明らかに早く回復します。付属のACアダプタは45Wで、ケーブルが旧型の1.5mから2.5mに長くなったのも、地味ながら非常に嬉しい改善点です。
一方で、ROG Ally Xはより強力な65WのACアダプタを標準で付属しています。最大の違いはポート数です。Steam Deck OLEDはUSB-Cポートが1基しかないため、充電しながらモニター出力や有線コントローラーを使いたい場合は、「公式ドッキングステーション」やサードパーティ製のハブが必須です。
その点、ROG Ally XはUSB-Cポートを2基(うち1基はUSB4対応)搭載しているため、1つのポートで充電しながら、もう1つのポートで周辺機器を接続するという、ドック不要の運用が可能です。さらにASUSは、充電器とハブを一体化させた「ROG Gaming Charger Dock」などのオプション品も展開しており、拡張性ではAlly Xが明確に有利です。
まとめ:バッテリーと冷却
- バッテリー容量:旧LCDモデルの40Whrから50Whrに25%増加しました。
- 実プレイ時間:6nm APUとOLEDディスプレイの効率化により、旧LCDモデル比で30~50%の持続時間向上を体感できます。
- 冷却性能:ファンが大型化し、排熱モジュールが改善されたことで、旧モデルより低温で動作します。
- ROG Ally Xとの比較:Ally Xは80Whrバッテリー と、より強力なデュアルファン冷却システムを搭載しています。
- 充電速度:急速充電が高速化し、約45分で20%から80%まで充電可能です。
- 充電と拡張性:Deck OLEDは45WアダプタとUSB-C x1ですが、Ally Xは65WアダプタとUSB-C x2を搭載し、充電しながらの周辺機器接続が容易です。
検証してわかったSteam Deck OLEDのメリット・デメリット
ここでは、Steam Deck OLEDを長期間使用して感じたメリット(利点)とデメリット(欠点)について書いていきます。旧LCDモデルからの進化点だけでなく、最大のライバルであるROG Ally Xとの比較も交えながら、購入を検討している人が知りたいポイントを正直にレビューします。
メリット(長所、利点)
メリット1: “ゲーム機”としての圧倒的な使いやすさ
Steam Deck OLEDの最大の強みは、Windows機であるROG Ally Xとの根本的な思想の違いにあります。SteamOSはゲーム専用に設計されており、電源ONからゲーム開始までが非常にシームレスです。注目すべきは「高速一時停止/再開」機能で、OLEDモデルでは旧LCDモデルより復帰が約30%高速化しています。ROG Ally XのWindowsスリープとは比較にならない安定感で、まさに家庭用ゲーム機のようにストレスなく遊べます。
メリット2: 魂を揺さぶるHDR OLEDディスプレイ
ディスプレイ品質は、ROG Ally Xの液晶(1920×1080 TFT) に対する絶対的な優位点です。7.4インチに拡大されたHDR OLEDは、1,000,000:1を超えるコントラスト比と1,000 nitsのピーク輝度(HDR時)を誇ります。『サイバーパンク2077』のような暗いシーンが多いゲームでは、黒が本当に「黒」として沈み込み、色彩の鮮やかさも旧LCDモデルとは比べ物になりません。解像度(1280×800)は低いですが、それを補って余りある画質体験です。
メリット3: 独自の入力系統(トラックパッドと背面ボタン)
Steam Deck OLEDは、ROG Ally Xにはない独自の入力系統を持っています。左右に搭載された「デュアルトラックパッド」は、マウス操作が前提のPCゲームを遊ぶ際に絶大な威力を発揮します。さらに、背面ボタンが4つ搭載されており、2つしかないROG Ally X よりも多くの操作を割り当てることができます。OLEDモデルではこれらの感触やハプティクス(振動)の精度も向上しています。
メリット4: 軽量化された快適なエルゴノミクス
旧LCDモデル(約669g)から約30g軽量化され、約640gとなりました。ROG Ally Xが約678gであることと比較してもOLEDモデルは軽量です。この軽さと、元々定評のあった握りやすいグリップ形状のおかげで、見た目の大きさ以上に疲れにくく、長時間のプレイでも快適でした。
メリット5: 高いカスタマイズ性(EmuDeckなど)
SteamOSはLinuxベースであるため、デスクトップモードを活用したカスタマイズ性が非常に高いです。特に「EmuDeck」を導入すれば、本機をPS2やPSPなども遊べる「最強のポータブル・レトロゲーム機」に変貌させることができます。また「Decky Loader」などのプラグインで、Windows機(Ally X)にはない細かな機能拡張を「育てる」楽しみもあります。
デメリット(短所、欠点)
デメリット1: 純粋なゲーム性能の差(対 ROG Ally X)
最大の弱点は、ROG Ally Xとの純粋な処理性能の差です。Deck OLEDのAPUが「Zen 2 / RDNA 2」ベース(6nm) であるのに対し、Ally Xは「Zen 4 / RDNA 3」ベースのRyzen Z1 Extremeを搭載しています。メモリもDeckの16GB LPDDR5-6400 に対し、Ally Xは24GB LPDDR5X-7500と、世代・容量・速度すべてで劣っています。
デメリット2: 対応ゲームの制約(Game Passが動かない)
Deck OLEDはSteamOS(Proton)で動作するため、Steam以外のゲーム、特に「Xbox Game Pass」や「Epic Games Store」のゲームをネイティブで遊ぶことができません。一方、Windows 11を搭載するROG Ally Xは、これらのプラットフォームのゲームをPCと全く同じようにインストールして遊べます。これは購入を決める上で決定的な違いとなります。
デメリット3: バッテリー容量の絶対差
OLEDモデルは旧型から50Whrに増量され、持続時間も大幅に改善しました。しかし、ROG Ally Xはそれを遥かに上回る80Whrという大容量バッテリーを搭載しています。実際のゲームプレイ時間においても、Ally Xの方がDeck OLEDより長く動作する場面が多く、携帯機としてのスタミナでは見劣りします。
デメリット4: ストレージ換装(SSD交換)の難易度
内蔵SSDの交換は、両者で難易度が大きく異なります。ROG Ally Xは一般的な「M.2 2280」サイズを採用しており、比較的容易に換装が可能です。一方、Deck OLEDは公式が「専門家向け」 と警告する通り、分解の難易度が高く、換装は上級者向けの行為となります。
デメリット5: ポート数の少なさと解像度
Deck OLEDはUSB-Cポートが1基しかありません。そのため、充電しながらモニターや有線コントローラーを使うにはドックが必須です。対してROG Ally XはUSB-Cポートを2基(うち1基は高速なUSB4)搭載し、ドックなしでも拡張性が高いです。また、Deckの解像度は1280×800であり、Ally Xの1920×1080(フルHD)に比べると、画面の精細さでは劣ります。
デメリット6: 日本国内での修理サポート
Steam Deckは海外(Valve)では公式の有償修理サービスがありますが、日本での販売代理店であるKomodoの顧客は、その修理サービスを利用できないという報告があります。1年保証が切れた後のサポート体制については、ASUS JAPANが国内でサポートを行うROG Ally Xに比べて不安が残ります。
Steam Deck OLEDのスペック(仕様)
- ディスプレイ: 7.4インチ、解像度1280 x 800ドットのHDR OLED タッチスクリーン ※16:10/輝度600ニト(SDR)/最大輝度1,000ニト(HDR)/色域110% P3/コントラスト比:> 1,000,000 : 1
- レスポンスタイム: < 0.1 ms
- リフレッシュレート: 最大90Hz
- プロセッサ: AMD APU ※6nm/4コア/8スレッド/最大3.5GHz
- CPU: Zen 2 4c/8t、2.4~3.5GHz(最大448 GFlops FP32)
- GPU: 8 RDNA 2 CU、1.6GHz(最大1.6 TFlops FP32)
- APU: power 4~15ワット
- RAM(メモリ): 16 GB LPDDR5 オンボード(6400 MT/sクアッド32ビットチャンネル)
- ストレージ: 512GB/1TB NVMe SSD
- 外部ストレージ: microSDカードで拡張可能
- バッテリー: 50Whr
- 駆動時間: 3~12時間のゲームプレイ(コンテンツによって異なります)
- 充電: 45W急速充電 (45W USB Type-C PD3.0電源)
- ワイヤレス通信: Wi-Fi 6E (2.4GHz、5GHz/6GHz 2 x 2 MIMO)、Bluetooth 5.3 ((コントローラ、アクセサリ、オーディオに対応))
- インターフェース: USB3 Gen2 Type-C (DP映像出力/PD充電/データ転送)x1、microSDカードリーダー(UHS-I) x1、3.5mmヘッドホンジャック x1
- センサー: ジャイロ 6軸IMU、デュアル環境光センサーALS
- オーディオ: DSP内蔵ステレオスピーカー、デュアルアレイマイク
- 操作: A B X Yボタン、十字キー、L&Rアナログトリガー、L&Rバンパー、表示&メニューボタン、割り当て可能な4個のグリップボタン
- サムスティック: 静電容量方式フルサイズアナログスティック(2本)
- 振動効果: HDハプティクス
- トラックパッド: 32.5mmハプティクスフィードバック付き角型トラックパッド(2個)
- 冷却システム: 大型化したファン、温度を低減
- OS: Steam OS 3.0 (Archベース)※デスクトップ KDE Plasma ※Windows 11 OSを導入可能
- サイズ: 298 x 117 x 49 mm
- 重量: 約640 g
- カラー: ブラック
- オプション: Steam Deck ドッキングステーション ※外部ディスプレイ、有線ネットワーク、USB周辺機器、電源への接続、充電(USB-C)
Steam Deck OLEDの評価
7つの評価基準で「Steam Deck OLED」を5段階で評価してみました。
画面の見やすさ:★★★★★ (5点)
解像度はFHDではありませんが、HDR対応有機ELディスプレイの画質は圧巻です。完璧な黒の表現と鮮やかな色彩、応答速度の速さは、液晶のROG Ally Xを凌駕します。
パフォーマンス:★★★☆☆ (3点)
SteamOSの最適化で多くのゲームが快適に動きますが、APUは旧世代(Zen 2)です。ROG Ally Xが搭載する最新世代のAPU(Zen 4)と比べると、純粋な処理性能では明確に劣ります。
操作性: ★★★★★ (5点)
左右のトラックパッドと4つの背面ボタンは、ROG Ally Xにはない独自の強みです。マウス操作や複雑な操作をコントローラーだけで完結でき、OLEDモデルで各ボタンの感触も改善されています。
機能性:★★★★☆ (4点)
Wi-Fi 6E対応は素晴らしいですが、USB-Cポートが1基しかない点は拡張性で劣ります。また、SteamOSは「Xbox Game Pass」などに公式対応しておらず、Windows機のAlly Xほどの万能性はありません。
デザイン:★★★★☆ (4点)
旧LCDモデルから約30g軽量化され、約640gとなりました。電源ボタンの配色変更など細部も洗練されており、重量バランスが良く長時間のプレイでも疲れにくいです。
使いやすさ:★★★★★★ (5点)
SteamOSによるゲーム機のようなUIと、完璧な「高速一時停止/再開」機能が最大の魅力です。Windows機(ROG Ally X)で感じるようなOS起因のストレスが一切ありません。
価格:★★★★☆ (4点)
ROG Ally X(約14万円)と比較し、OLEDディスプレイを搭載しながら8万円台から購入できる価格設定は非常に魅力的です。ただし、国内での修理サポート体制には不安が残ります。
総評:★★★★★ (5点)
“ゲーム体験”に特化した最強の携帯ゲーム機
Steam Deck OLEDは、初代Steam Deckが持っていた革新性をさらに磨き上げ、「携帯ゲーミングPCの完成形」に近づいた一台です。
まず明確にすべきは、純粋な処理性能(パフォーマンス)です。最新のZen 4 APU と24GBの高速メモリ を搭載するROG Ally Xと比較すれば、Deck OLEDのAPU(Zen 2) は見劣りします。しかし、Deck OLEDはその性能差を補って余りある、圧倒的な「ゲーム体験の質」で勝負するデバイスです。
「見る」体験の革命:HDR OLEDディスプレイ
最大の進化点は、間違いなく7.4インチに拡大されたHDR対応OLED(有機EL)ディスプレイです。これは、ROG Ally Xの高性能なフルHD液晶に対する絶対的な優位点です。
1,000,000:1を超えるコントラスト比と1,000 nitsのピーク輝度(HDR時)が実現する「本物の黒」は、液晶では決して味わえません。『サイバーパンク2077』のような暗いシーンではその美しさに息をのみ、旧LCDモデルとは比較にならない鮮やかな色彩は、あらゆるゲームを新たなレベルに引き上げます。
「遊ぶ」快適性の追求
このOLEDモデルは、「遊ぶ」快適性も徹底的に追求されています。50Whrへのバッテリー増量と6nm APUへの効率化により、バッテリー持続時間は旧LCDモデルから劇的に向上しました。(※ただし、80Whrバッテリーを搭載するROG Ally Xの絶対的なスタミナには及びません)
そして何より、SteamOSによる「ゲーム機」としての使いやすさが完璧です。特にOLEDモデルでさらに高速化した「高速一時停止/再開」機能は、スリープが不安定なWindows機(Ally X)では決して真似できない、ストレスフリーな体験を提供します。
結論:パフォーマンスと体験、どちらを選ぶか
Steam Deck OLEDには、ROG Ally Xと比較した弱点も確かに存在します。純粋な性能差、Windows機ではない故の「Xbox Game Pass」非対応、USB-Cポートが1基しかない拡張性の低さです。
しかし、8万円台からという価格設定は、これらの改良点を踏まえれば驚異的なコストパフォーマンスです。
結論として、もし「最高の性能とGame Passを含む万能性」を求めるならROG Ally Xが適しています。ですが、「Steamライブラリのゲームを、最高の画質と、一切のストレスがない”ゲーム機”としての体験」で遊びたいのであれば、Steam Deck OLEDは価格以上の価値がある、唯一無二の最高の選択肢です。
Valve Steam Deck OLED 512GB ハンドヘルドゲームコンソール、7.4インチ、90Hz、SteamOS 3.0、1280 x 800、キャリングケース、MTCアクセサリー付き
Steam Deck OLEDの価格・購入先
※価格は2025/12/12に調査したものです。価格は変動します。
KOMODO Steam Deck ストア
現在、すべて売り切れ中です。
KOMODO Steam Deck ストアで「Steam Deck OLED」をチェックする
ECサイト
- Amazonで146,200円、
- 楽天市場で98,600円(送料無料)、
- ヤフーショッピングで99,000円、
で販売されています。
Amazonで「Steam Deck OLED」をチェックする
楽天市場で「Steam Deck OLED」をチェックする
ヤフーショッピングで「Steam Deck OLED」をチェックする
米国 Amazon.comで「Steam Deck OLED」をチェックする
おすすめのライバル機種と価格を比較
「Steam Deck OLED」に似た性能をもつポータブルゲーミングPCも販売されています。価格の比較もできるので、ぜひ参考にしてみてください。
ROG XBOX ALLY / Ally X
ASUS (ROG) から発売された7.0インチのポータブルゲーミングPCです(2025年10月16日に発売・型番:RC73YA-Z2A16G512/RC73XA-Z2E24G1T)。
7.0型ワイドTFTカラー液晶 (1,920×1,080, 120Hz, FreeSync Premium対応)、AMD Ryzen™ Z2 A (Ally) / AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme (Ally X)、LPDDR5X 16GB (Ally) / 24GB (Ally X) メモリ、SSD 512GB (Ally) / 1TB (Ally X) (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 2280)、60Wh (Ally) / 80Wh (Ally X) バッテリー、Windows 11 Home 64ビットを搭載しています。
また、Xboxアプリ、UI「Xboxフルスクリーンエクスペリエンス」、Xboxボタン(Game Bar)、「Xbox Play Anywhere」、ASUSの管理コンソール「Armoury Crate Special Edition (ACSE)」、AMD Ryzen™ AI (NPU※Ally Xのみ)、モニター出力、内蔵SSDの交換(換装)に対応。
ステレオスピーカー (Dolby Atmos / Hi-Res Audio対応)、アレイマイク、HD振動機能 (Ally Xはインパルストリガー対応)、ROGインテリジェントクーリング (デュアルファン)、ジョイスティック×2(RGBライティング)、マクロボタン×2、バンパー/トリガー、指紋認証センサ (電源ボタン一体型)、USB Type-Cポート (Ally XはUSB4対応)、microSDカードスロット、Wi-Fi 6E、Bluetooth® 5.4にも対応しています。
価格は、Amazonで89,800円(ROG XBOX ALLY / Ally Xは139,800円)、楽天市場で88,650円(料無料)、ヤフーショッピングで86,520円、です。
関連記事:ROG XBOX ALLY/Ally X評価レビュー!期待以上の性能・機能か?
Amazonで「ROG XBOX ALLY」をチェックする
ROG Ally X
ASUSから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2024年7月 発売)。
AMD Ryzen Z1 Extreme、24GB LPDDR5-7500、フルHDののIPS タッチスクリーン、1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)、80WHrsバッテリー、6軸ジャイロセンサー、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、デュアル ステレオスピーカー、Dolby Atmos、アレイマイク、AIノイズキャンセリング、HDハプティクス、Microsoft Pluton セキュリティ、指紋認証、AURA SYNC、Gorilla Glass DXC、USB4 Gen2 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、Amazonで129,832円、楽天市場で127,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで127,800円、です。
関連記事:ROG Ally Xは買うべきか?できるゲームとグラフィック性能をレビュー
Amazonで「ROG Ally X」をチェックする
Lenovo Legion Go S
レノボから発売された8.0インチのポータブルゲーミングPCです(2025年12月12日に発売)。
AMD Ryzen™ Z2 Go プロセッサー、16GB LPDDR5X-7500MHzメモリ、8.0型 WUXGA (1920×1200) IPS液晶、512GB SSD (PCIe Gen4 NVMe/M.2 2242)ストレージ、55.5Whr バッテリー、Windows 11 Home 64bit (日本語版)、を搭載しています。
また、統合ソフト「Legion Space」(ランチャー・設定管理)、リフレッシュレート最大120Hz、VRR(可変リフレッシュレート)、冷却システム「Legion ColdFront」、急速充電「Super Rapid Charge」、ホール効果ジョイスティック(RGBライト付き)、調整可能トリガー、「トラックパッド」、大型ピボットDパッド」に対応。
2つのUSB4 (Type-C)ポート、外部モニター出力、外部GPU接続、前面配置ステレオスピーカー (2W x 2)、デュアルアレイマイク、トラックパッド、microSDカードスロット(最大2TBまで)、オーディオジャック、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3にも対応しています。
価格は、レノボ公式サイトで99,880円、楽天市場で109,860円(送料無料)、ヤフーショッピングで99,880円、米国 Amazon.comで$649.99、です。
関連記事:Lenovo Legion Go S徹底レビュー!10万円以下の実力は本物か?
Amazonで「Lenovo Legion Go S」をチェックする
MSI Claw 8 AI+ A2VM
MSI から発売された8インチのポータブルゲーミングPCです(2025年2月20日 発売)。
インテル Core Ultra 7 258V、32GB LPDDR5Xメモリ、WUXGA液晶(解像度1920 x 1200)、1TB M.2 NVMe SSDストレージ、80Whr バッテリー、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、ハイパーフロー強冷クーラー、RGBバックライト、ホールエフェクトスティック、2Wステレオ2スピーカー、ハイレゾオーディオ認証、フィンガータッチ、リニアトリガーボタン、背面マクロボタン、指紋認証リーダー、MSI Center(管理ソフト)、Thunderbolt 4 Type-C x2、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応しています。
価格は、Amazonで189,800円、楽天市場で159,800円(新品/中古モデルは136,580円)、ヤフーショッピングで159,800円、です。
関連記事:MSI Claw 8 AI+ A2VMレビュー!Core Ultra 7とAIで激変?
Amazonで「MSI Claw 8 AI+ A2VM」をチェックする
OneXFly F1 Pro
One-Netbook から発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2024年11月下旬に発売)。
AMD Ryzen AI 9 HX 370(Ryzen AI 9 HX 365 / Ryzen 7 8840U)、32GB/64GB LPDDR5Xメモリ、1TB/2TB/4TB M.2 2280 NVMe SSD (PCle 4.0)ストレージ、48.5Wh バッテリーを搭載しています。
また、HAMAN社認証 Indfx デュアル ステレオスピーカー、RGBライト、RGBホールジョイスティック、リニアトリガーボタン、カスタマイズキー、冷却システム、ゲーム一括管理コンソール「OneXconsole」、専用ゲームランチャー「GAME CENTER」、USB4 Type-C x2、USB 3.0 Type-A x1、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、Amazonで140,600円(税込)、楽天市場で148,000円(送料無料)、ヤフーショッピングで137,800円(送料無料)、です。
関連記事:【OneXFly F1 Pro レビュー】最新AI搭載でROG Ally超え?
Amazonで「OneXFly F1 Pro」をチェックする
GPD WIN Mini 2025
GPD から発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2025年3月上旬に発売)。
AMD Ryzen AI 9 HX 370 / AMD Ryzen 7 8840U、16GB/32GB LPDDR5xメモリ、1TB/2TB M.2 NVMe 2280 SSDストレージ、44.24Wh バッテリー(最大14時間駆動、利用状況による)、Windows 11 Home (64bit)、microSDカードスロット (最大読込160MB/s、最大書込120MB/s) x1を搭載しています。
また、冷却システム、デュアルスピーカー(独立アンプ内蔵)、DTS:X Ultra対応オーディオ、バックライト付QWERTYキーボード(シザースイッチ)、ホール効果ジョイスティック、L4/R4カスタムキー、タッチパッド (PTP)、アクティブ冷却、デュアルリニアモーターによる振動効果、
6軸ジャイロスコープ、3軸重力センサー、PD急速充電、USB4 (40Gbps) x1、USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、USB Type-A x1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応しています。
価格は、Amazonで228,000円(税込)、楽天市場で126,580円(送料無料・中古品)、ヤフーショッピングで168,000円(中古)、です。
関連記事:GPD WIN Mini 2025レビュー!AI性能で2024年型を凌駕?
Amazonで「GPD WIN Mini 2025」をチェックする
その他のおすすめゲーム製品は?
その他のおすすめゲーム製品は以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
ポータブルゲーミングPCはどれを選ぶべきか? 最新の全機種と選び方を紹介
最新のポータブルゲーミングPCをまとめて紹介しています。
AYANEOのポータブルゲーミングPCがやはり最強か? 全機種 まとめ
AYANEOのポータブルゲーミングPCをまとめて紹介します。
GPD WIN シリーズ・XP ゲーム機の全機種 ラインナップを比較
GPDの超小型PC(UMPC)やタブレットをまとめています。