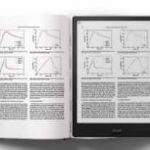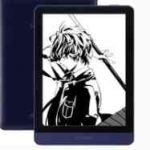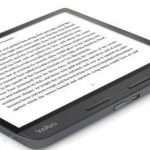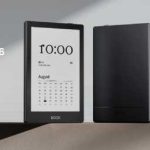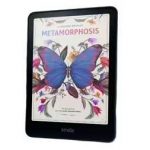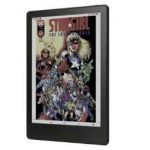2025年4月に発売された「Bigme HiBreak Pro」は、SIMスロットを搭載し、通話もできる革新的なE Inkスマートフォンとして注目されています。
このレビューでは、前モデル「Bigme HiBreak」から何が進化したのか、ライバル機「BOOX Palma 2」との違いは何なのか、その実力や使い勝手を徹底比較・検証しました。
【先に結論からお伝えしましょう】
Bigme HiBreak Pro の長所(Pros):
- 5G通信と音声通話に対応し、メイン機として運用可能
- Antutu約59万点の高性能処理でサクサク動作
- フロントカメラ搭載でビデオ通話や自撮りが可能
- 4500mAh大容量バッテリーと18W急速充電
- 基本無料で使えるAI機能(BigmeGPT 4.0)を内蔵
- モノクロモデルのほかにカラーモデル「HiBreak Pro Color」を用意
Bigme HiBreak Pro の短所(Cons):
- microSDカードスロットが廃止され、物理的な容量拡張が不可
- 筆圧対応のスタイラスペン(手書き入力)には非対応(※タッチペンは利用可)
- 重量が約182gと、競合機より少し重い
- 防水・防塵性能には非対応
- スピーカーの低音は控えめ
総合評価:
Bigme HiBreak Proは、「読む」快適さと「スマホ」の実用性を高い次元で融合させた、最強のE Inkデバイスです。Wi-Fi専用のBOOX Palma 2とは異なり、単体で通話やGPSナビが利用できるため、荷物を減らしたいミニマリストや、目に優しい画面で穏やかな日常を過ごしたいユーザーにとって最適な選択肢です。SDカードや筆圧ペンに非対応という弱点はありますが、それを補って余りある性能と視認性の良さは、E Inkスマホの新しい基準と言えます。
<この記事で分かること>
- デザイン: 6.13インチへのサイズアップ、重量(182g)比較、フラットな背面カメラ、マットな質感、指紋認証付き電源ボタン、SDカードスロット廃止の影響、専用ケースなどの付属品
- ディスプレイと操作性: E Ink Carta 1200 (300PPI)、Color版 (Kaleido 3) との違い、暖色フロントライト調整、xRapidリフレッシュ技術、残像(ゴースト)除去、ブルーライトカット、屋外での視認性
- 通信性能: 5G対応、SIMフリー、物理Dual SIM(eSIM非対応)、楽天モバイルでの動作、VoLTE通話、テザリング、NFC(Google Wallet)、IR(赤外線)ポート、GPSナビゲーション、Wi-Fi接続、Bluetooth 5.2(接続安定性)、技適、日本
- パフォーマンス: Antutuベンチマーク (V10)、Dimensity 1080 vs Helio P35 vs Snapdragon 750G、CPU・GPU性能比較、メモリ (8GB RAM)、ストレージ (256GB)、発熱
- アプリの動作感: Webブラウジングのスクロール遅延、OneNoteでの入力応答性、Kindleのページめくり速度、動画再生 (Extremeモード)、画像編集
- カメラ性能: 20MPリアカメラ、5MPフロントカメラ、ビデオ通話 (Zoom/Meet)、ドキュメントスキャン (OCR機能)、4K動画撮影、E Inkプレビューの挙動、手ぶれ補正 (OIS) 非対応
- オーディオ: ステレオスピーカーの音質、マイク性能(録音・文字起こし)、テキスト読み上げ (TTS)、Bluetoothコーデック (LDAC対応)、イヤホンジャック非搭載
- バッテリー: 4500mAh容量、PCMark駆動時間テスト、18W急速充電、実際の持続時間、ワイヤレス充電非対応、スタンバイ消費
- AI機能: 無料のBigmeGPT 4.0、スマートチャット(日本語対応)、クリエイティブライティング、インテリジェントな描画
- OSとソフトウェア: Android 14搭載、Google Playストア、Bigme独自UI、xReaderアプリ (翻訳・ハイライト・注釈)、ファームウェアアップデート、日本語キーボード
- スペック: HiBreak Proの詳細仕様、前モデル・BOOX Palma 2とのスペック比較
- 評価: 5段階評価(星の数)、詳細な総評、比較 BOOX Palma 2、最適なユーザー層
- 価格: Amazon、楽天、公式ストア、中古、他社ライバル機種との価格比較
この記事を最後まで読むことで、「Bigme HiBreak Pro」を購入するべきかどうかがはっきりと分かるはず。購入に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク / AliExpress リンク
公式ページ:HiBreak Pro – Bigme Official Store
デザイン:Bigme HiBreak Proの質感と操作性
ここでは、Bigme HiBreak Proのデザイン、サイズ感、インターフェースの配置について、前モデルや競合機との比較を交えながら詳しく見ていきます。
質感と形状:フラットなカメラとマットな手触り
箱から取り出して最初に手に取った瞬間、良い意味で「道具」としての実用性を感じました。筐体はプラスチック製ですが、背面はマットな仕上げ(レザー風のテクスチャという情報もありますが、実際にはさらっとした指紋のつきにくい加工)が施されており、安っぽさは感じません。最近のハイエンドスマホのようなガラスの冷たさはありませんが、その分、滑りにくく手に馴染む感覚があります。
個人的に感動したのは、背面カメラのデザインです。最近のスマホはカメラユニットが大きく出っ張っているのが常ですが、HiBreak Proはカメラレンズが背面と完全にフラットになっています。机に置いてもガタガタせず、スッキリとした一枚板のような形状は、ポケットへの収まりも非常に良いです。指紋汚れも目立ちにくく、ケースなしでも気兼ねなく使えるタフな印象を受けました。
サイズと重量:前モデルやライバル機との比較
サイズ感については、前モデルからの変化が顕著です。前作「Bigme HiBreak」が5.84インチのコンパクトサイズだったのに対し、Pro版は6.13インチへと大型化しました。実際に並べてみると、画面の見やすさは向上しましたが、横幅が約76.8mmから約80.9mmへと広がっており、片手でのホールド感は少し人を選ぶかもしれません。
重量は約182gで、前モデルやライバル機である「BOOX Palma 2」(約170g)と比較すると、手に持った瞬間に「少しずっしりくるな」と感じました。Palma 2はWi-Fi専用機でバッテリーも3950mAhと控えめですが、HiBreak Proは5G通信モジュールと4500mAhの大容量バッテリーを積んでいるため、この重さは機能とのトレードオフと言えるでしょう。カラーはブラックとホワイトの2色展開で、私はホワイトを選びましたが、E Inkの紙のような表示と相まって非常に清潔感があります。
ボタン配置とインターフェース:SDカードスロットの廃止
ボタンやポートの配置は非常に機能的です。右側面には音量ボタンと、指紋認証センサーを兼ねた電源ボタンがあります。指紋認証の反応はスムーズで、スリープ解除がストレスなく行えました。左側面にはSIMスロットと、カスタマイズ可能なファンクションボタンが2つ(※HiBreakは1つのみ)配置されています。ここに「画面リフレッシュ」などを割り当てられるのはE Ink端末ならではの利点です。
底面にはUSB Type-Cポート(充電・データ転送用)とスピーカーが配置されています。ただし、ここで注意が必要な大きな変更点があります。前モデルのHiBreakや、競合のBOOX Palma 2にはmicroSDカードスロットが搭載されていますが、このHiBreak ProではSDカードスロットが廃止されています。内蔵ストレージが256GBあるとはいえ、大量の自炊書籍データを外部メモリに入れて持ち運びたいユーザーにとっては、明確なデメリットと感じるかもしれません。
耐久性と付属ケース
耐久性に関しては、ガラスを多用した一般的なスマホよりも安心感があります。プラスチック筐体は衝撃に対してある程度の柔軟性があるため、落としても背面がバキバキに割れる心配は少なそうです。ただし、防水・防塵性能(IP等級)についての公式な記載は見当たらず、水回りでの使用には注意が必要です。
嬉しいことに、製品には専用のケースが最初から付属しています。サードパーティ製のアクセサリーが少ないこの手のニッチなデバイスにとって、純正ケースの同梱は非常に助かります。装着してもボタンの押し心地を損なわず、本体をしっかり保護してくれます。
付属品
パッケージ内容はシンプルですが必要十分です。本体に加え、前述の保護ケース、USB Type-Cケーブル、SIMピン、マニュアルが同梱されています。充電アダプターは付属していないため、手持ちのものを使用する必要があります。画面には最初からアンチグレアタイプの保護フィルムが貼られているように見え、購入後すぐに使い始められる配慮を感じました。
まとめ:デザイン
- 第一印象:プラスチック製だがマットな仕上げで指紋が目立ちにくく、実用的な「道具」としての良さを感じる。
- 形状:背面カメラが完全なフラットで出っ張りがなく、机に置いても安定する点が非常に優秀。
- サイズ比較:前モデル(5.84インチ)から6.13インチへ大型化。BOOX Palma 2と同等の画面サイズだが、幅が広く少し大きい。
- 重量:約182gと、前モデルやBOOX Palma 2(約170g)よりも重くなっており、手に持つと密度の高さを感じる。
- ボタン配置:右側面の電源ボタンに指紋認証を搭載。左側面には便利なカスタムボタンを2つ装備している。
- ポートと拡張性:底面にUSB Type-Cを配置。最大の注意点はmicroSDカードスロットが廃止されたこと(前モデルやPalma 2は対応)。
- 付属品:専用ケースが標準付属しており、別途購入の手間が省ける点は高評価。
- 耐久性:防水性能(IP等級)の記載はないため、水濡れには注意が必要。
ディスプレイ:Bigme HiBreak Proの進化と「紙」に迫る視認性
ここでは、Bigme HiBreak Proのディスプレイ性能と、それに伴う操作性の変化について、前モデルや競合機種と比較しながら詳しくレビューしていきます。
ディスプレイの第一印象と質感
画面を点灯させた瞬間、6.13インチというサイズ感と、E Ink Carta 1200がもたらす「紙」のような質感に目を奪われました。表面はマットなアンチグレア処理が施されており、蛍光灯の下でも反射がほとんどなく、まるで印刷された文字を見ているかのような自然な発色です。
カラーモデル「HiBreak Pro Color」(Kaleido 3搭載機)の場合、液晶のような派手な鮮やかさはありませんが、パステルカラー調の柔らかい色合いが目に優しく、雑誌の表紙やグラフの色分けを確認するには十分な視認性を確保しています。黒の締まりも良く、文字が背景からくっきりと浮き上がって見えるため、長時間の読書でも没入感が途切れることはありませんでした。
サイズ・解像度の比較と進化
前モデルのHiBreakが5.84インチ(275PPI/720×1440)だったのに対し、本機は6.13インチ(300PPI/824×1648)へと大型化かつ高精細化しました。実際に並べてみると、わずかなサイズアップですが、Webブラウジング時の情報量は確実に増えています。
解像度300PPIは競合のBOOX Palma 2と同等で、前モデルで感じた細かい漢字のジャギー(ギザギザ)が解消され、印刷物レベルの滑らかさを実現しています。アスペクト比は2:1の縦長形状で、片手でのホールド感を維持しつつ、SNSのタイムラインや縦書きの小説を快適に閲覧できる絶妙なバランスだと感じました。
また、ラインナップされているカラー版(HiBreak Pro Color)についても触れておきましょう。こちらは最新のE Ink Kaleido 3技術を採用しており、モノクロ表示時は300PPIの高精細さを維持しつつ、カラー表示でも150PPIを実現しています。前モデルのカラー版が約92PPIだったことを考えると、色の粒状感が大幅に改善されており、雑誌やWebサイトの色付き図表もより自然に判別できるようになりました。モノクロ版の「圧倒的な白と黒の美しさ」を取るか、カラー版の「情報量の多さ」を取るか、用途に合わせて選べるのも本シリーズの進化点です。
フロントライト:待望の「暖色」対応で夜読書が快適に
最も感動したのはフロントライトの進化です。前モデルのHiBreak(特に初期のレビューや一部モデル)では寒色ライトのみで、暖色(アンバー)への切り替えができない点が弱点とされていました。しかし、HiBreak Proでは36段階の寒色・暖色調整が可能になりました。
夜、ベッドで読書をする際、BOOX Palma 2と同様にオレンジ色の優しい光に設定できるのは大きなメリットです。輝度のムラも少なく、最小輝度まで絞れば、真っ暗な部屋でも目が冴えてしまうことなく読書に没頭できました。屋外の直射日光下ではライトを完全にオフにすることで、紙と全く同じように反射のないクリアな画面で文字を追うことができます。
リフレッシュ技術:xRapidの実力と残像感
操作性に関しては、Bigme独自の「xRapidリフレッシュアルゴリズム」と「SSS(Super Squeeze Speed)」技術が光ります。Webブラウジング時に「高速モード(Extreme)」に設定すると、秒間約21フレームでの描画が可能となり、E Ink特有のカクつきを抑えて動画すら視聴可能なレベルになります。
ただし、BOOX Palma 2に搭載されている「BSR(BOOX Super Refresh)」と比較すると、高速スクロール時の残像(ゴースト)処理にはわずかな違いを感じました。Palma 2が残像を「消す」ことに長けているのに対し、HiBreak Proは描画速度を優先して残像を許容しつつ動かす印象です。とはいえ、自動ゴースト除去機能が効いているため、静止画に戻った瞬間に画面がクリアになる挙動は非常にスムーズで、実用上のストレスは感じません。
目の保護とブルーライト:長時間使用でも疲れない
E Inkの最大の魅力である目の保護性能は、Pro版でも健在です。バックライトではなくフロントライト構造のため、光が直接目に入らず、長時間のブラウジングでも眼精疲労が劇的に軽減されます。ブルーライトやフリッカー(ちらつき)がないため、就寝前のスマホいじりが「睡眠を妨げないリラックスタイム」に変わりました。これは液晶や有機ELを搭載した通常のスマホでは得られない体験です。
まとめ:ディスプレイ
- 第一印象:6.13インチのE Ink Carta 1200を採用し、マットな質感で反射が少なく、紙のような自然な視認性を実現している。
- 解像度比較:前モデル(275PPI)から300PPIへ進化し、BOOX Palma 2と同等の高精細さで文字のジャギーが解消された。
- カラー版の違い:HiBreak Pro ColorはKaleido 3を搭載し、カラー解像度が前作の約92PPIから150PPIへ向上。図表の視認性が増している。
- ライト機能:36段階の寒色・暖色調整に対応し、夜間でも目に優しい暖色ライトが利用可能になった。
- 動作速度:xRapid技術により最大21fpsの描画が可能で動画も視聴できるが、残像処理はBOOXのBSRに比べると多少の甘さがある。
- 目の保護:ブルーライトとフリッカーがゼロで、長時間の使用でも眼精疲労を感じさせない。
通信性能:Bigme HiBreak Pro 5G対応でメイン機へ昇格
ここでは、5G対応により真のスマートフォンへと進化したBigme HiBreak Proの通信周りと、NFCやIRポートなどの付加機能について、実際の使用感を交えてレビューします。
5G対応とSIMフリー:楽天モバイルも掴む快適さ
通信面での最大の進化は、なんといっても5Gへの対応です。前モデル「Bigme HiBreak」は4G LTEまでの対応でしたが、Pro版ではDimensity 1080チップセットの恩恵により、高速な5G通信(Sub-6)が可能になりました。実際にSIMフリー端末として、私が普段使用している楽天モバイルのSIMカードを挿入してみたところ、主要バンド(B3/B18/n77)に対応しているため、エリア内ですぐにアンテナが立ち、快適にデータ通信を行えました。
競合の「BOOX Palma 2」はWi-Fi専用機であり、外出先でネットを使うにはテザリングやWi-Fiスポットが必須です。それに対し、HiBreak Proは単体でどこでも繋がるという「当たり前」の自由さが、E Ink端末としては非常に新鮮で強力な武器になります。デュアルSIMスロットを搭載しているため、仕事用とプライベート用で回線を分ける運用もスムーズでした。
技適マーク取得済み:日本国内でも安心して利用可能
海外製スマートフォンを使う上で気になる「技適(技術基準適合証明)」ですが、Bigme HiBreak Proはしっかりと通過しています。総務省の電波利用ポータルなどの情報によると、型番「B651」として2025年7月に工事設計認証を受けていることが確認されています。
これにより、5G(n78など)、4G LTE(B1/B3/B8/B28など)、さらにWi-FiやBluetoothに至るまで、日本国内の電波法に適合した状態で堂々と利用できます。海外メーカーのニッチな端末では技適未取得のケースも少なくない中、Bigmeが日本市場を重視し、安心してメイン機として使える環境を整えてくれたことは高く評価できます。
通話機能:メインスマホとしての実力
「BOOX Palma 2」との決定的な違い、それは「電話ができる」ことです。HiBreak Proはスマートフォンとして設計されており、通話アプリを使っての電話はもちろん、VoLTEによるクリアな音声通話が可能でした。
実際にメイン端末として数日間運用してみましたが、耳元のスピーカーからの音声は明瞭で、こちらの声も相手にしっかりと届いていました。仕事の連絡待ちの際も、E Ink画面で資料を読みながら着信があれば即座に応答できるため、タブレットとスマホの2台持ちをする必要がなくなります。この「1台で完結する」感覚は、荷物を減らしたいミニマリストにとって大きなメリットだと感じました。
待望のNFCとIRポート:財布もリモコンもこれ一台
日常生活での使い勝手を大きく向上させるのが、全方位NFCとIR(赤外線)ポートの搭載です。特にNFCは「全方位NFC」を採用しており、タップひとつで接続性に革命をもたらすと謳われています。Pro版ではGoogle Walletに対応しており、コンビニなどでNFCを使った非接触決済がスムーズに行えました。
また、本体上部にはIRポートがあり、リモコンアプリを入れることで、エアコンやテレビの操作が可能になります。外出先で「リモコンがない!」という場面でも、スマホ一つで対応できるのは地味ながら便利なポイントでした。
GPSナビゲーション:直射日光下で見やすい地図
GPS精度についても検証を行いました。Googleマップを起動してナビゲーションを行いましたが、ジャイロスコープや電子コンパスを内蔵しているため、方向を見失うことなく正確な位置情報を追従してくれました。
注目は、屋外での視認性です。通常のスマホでは真夏の直射日光下で画面が見えにくくなりますが、HiBreak ProのE Inkディスプレイは光を反射せず、紙の地図を見ているかのようにくっきりとルートを確認できます。バイクや自転車のナビとしてホルダーに固定して使う場合、この視認性の良さは圧倒的なアドバンテージになります。BOOX Palma 2はGPSモジュールの有無が曖昧(Wi-Fi測位メイン)なため、ナビ用途なら間違いなくHiBreak Proが有利です。
Wi-FiとBluetooth:テザリングも安定動作
Wi-FiとBluetoothの接続安定性もチェックしました。Wi-Fiは2.4GHz/5GHzのデュアルバンドに対応しており、PCを接続してテザリングを行っても、通信が途切れることなく安定して利用できました。外出先でのルーター代わりとしても十分に機能します。
Bluetoothはバージョン5.2に対応しており、BOOX Palma 2(Bluetooth 5.0)よりも新しい規格を採用しています。実際にワイヤレスイヤホンやポータブルスピーカーと接続してみましたが、ペアリングは非常にスムーズでした。スピーカーと接続して離れた部屋に移動しても接続は維持され、途切れることなく安定して通信できていることを確認しました。
まとめ:通信性能
- モバイル通信:前モデルの4Gから5G対応へ進化し、楽天モバイルなどの国内キャリアでも快適に通信可能。
- 技適:日本の技適マークを取得済みであり、国内で安心して通信機能を利用できる。
- SIM機能:物理デュアルSIMスロットを搭載し、2回線の同時待受が可能(eSIMに関する明確な記述はなし)。
- 通話機能:BOOX Palma 2(Wi-Fi専用)とは異なり、VoLTE対応の通話機能を持つ完全なスマートフォンとして運用できる。
- NFC:新たにNFCを搭載し、Google Walletによる非接触決済が可能になった。
- IRポート:赤外線ポートを搭載し、家電のリモコンとしても利用可能。
- GPS:GPS、ジャイロ、コンパスを完備し、直射日光下でも見やすいナビゲーションが可能。
- Wi-Fi/Bluetooth:テザリング利用時も通信が安定しており、Bluetooth 5.2によりスピーカーやイヤホンとの接続も途切れにくい。
パフォーマンス
ここではBigme HiBreak Proのパフォーマンスについて、Antutuベンチマーク、CPU性能の比較、アプリの動作感、メモリとストレージの4つのセクションに分けて、詳しく紹介します。
Antutuベンチマーク
Bigme HiBreak Proは、プロセッサ(SoC)にMediaTek製の「Dimensity 1080」を採用しています。これはTSMCの6nmプロセスで製造されたミドルレンジ向けのチップセットで、最大2.6GHzで動作する高性能な「Cortex-A78」コアを2つと、省電力性に優れた「Cortex-A55」コアを6つ組み合わせたオクタコア(8コア)構成となっています。
GPUには「Mali-G68 MP4」を搭載しており、E Ink端末としては異例とも言える高い処理能力を持っています。省電力性能とパワーのバランスが良く、長時間のバッテリー持ちとサクサクとした動作の両立が期待できるスペックです。
Antutuベンチマーク(V9)は以下のようになっています。
例: Antutu V9.5.6 総合で「511667」、CPUで「141854」、GPUで「129228」、MEMで「101239」、UXで「139346」
※Antutu V10 換算で総合「約59万点」、CPU性能「約18万点」、GPU性能「13万点」
CPU性能を比較
Bigme HiBreak Proが搭載するMediaTek Dimensity 1080プロセッサと、他のCPUをAntutuベンチマーク(V10)で比較してみました。
<CPUランキング>
※Antutu V10総合スコアで比較したものです。
- MediaTek Dimensity 1080 (Bigme HiBreak Pro)・・・Antutu:59万
- Qualcomm Snapdragon 750G (BOOX Palma 2)・・・Antutu:44万
- Snapdragon 680 (BOOX Go 10.3)・・・29万
- Snapdragon 662 (BOOX Palm)・・・Antutu:23万
- MediaTek Helio P35 MT6765 (Bigme HiBreak)・・・17万
<比較からわかること>
この比較結果から、Bigme HiBreak Proの性能が突出していることが一目瞭然です。まず、前モデルである「Bigme HiBreak」に搭載されていたHelio P35(約17万点)と比較すると、スコアは3倍以上に跳ね上がっています。前モデルでは重いアプリの起動やマルチタスク時にもたつきを感じることがありましたが、Pro版では次元の違う快適さを体感できます。
また、強力なライバルである「BOOX Palma 2」はSnapdragon 750Gを搭載し、約44万点と健闘していますが、HiBreak Proはそれをさらに約15万点も上回る約59万点を叩き出しています。一般的なE Ink端末(BOOX Go 10.3など)が20万〜30万点台に留まる中、この数値は圧倒的です。単なる電子書籍リーダーとしてではなく、ブラウジング、SNS、ビジネスアプリをストレスなく動かせる「メインスマホ」としての実力を十分に備えていることが、このグラフからも読み取れます。
アプリの動作感:Bigme HiBreak Pro 驚きのサクサク動作と実用性
Dimensity 1080プロセッサと8GB RAMの搭載により、E Ink端末とは思えないほどの応答性を実現しており、日常的なアプリ操作でストレスを感じることはほぼありませんでした。
ブラウザとOneNote:PCライクな快適さ
Webブラウザでのスクロールは、前モデル「Bigme HiBreak」のもっさり感が嘘のようにスムーズです。HiBreakではHelio P35プロセッサの影響で画像の読み込みや描画に明らかな遅延(レイテンシ)がありましたが、Pro版では指の動きに画面がしっかりと追従します。
Microsoftの「OneNote」でテキスト入力を試みたところ、文字入力の反映も高速で、変換候補の表示も遅れることなく思考を妨げられません。BOOX Palma 2が搭載する「BSR技術」と比較しても、スクロールの滑らかさは肉薄しており、E Ink特有のカクつきを最小限に抑えた快適なブラウジングが可能です。
電子書籍:残像を感じさせない没入感
KindleやKoboアプリでの読書体験は極めて快適です。ページめくりは瞬時に行われ、テキストのゴースト(残像)も「自動ゴースト除去」機能のおかげでほとんど気になりません。Bigme独自の「xRapid」リフレッシュ技術が効いており、コミックの細かい書き文字もくっきりと表示されます。Palma 2と比較すると、Palma 2の方が残像処理がやや自然で洗練されている印象を受けますが、Pro版も「E-Ink Center」からリフレッシュモードを調整することで、好みのクリアさにカスタマイズできます。
動画再生:視聴可能だが割り切りが必要
YouTubeで動画を再生してみたところ、「ビデオモード(Extremeモード)」に設定することで、最大21fpsのリフレッシュレートによりコマ落ちすることなく視聴できました。ただし、あくまでE Ink画面であるため、鮮明な画質は期待できません。白黒テレビを見ているようなノスタルジックな感覚です。長時間再生していると、カメラ付近にほんのりとした発熱を感じましたが、持てなくなるような熱さではなく、システムの安定性は保たれています。高負荷な処理でもアプリが落ちることなく動作するのは、高性能なオクタコアCPUの恩恵でしょう。
画像編集:処理能力は高いが色確認は難題
リアカメラで撮影した書類を画像編集アプリでトリミングや補正してみました。8GB RAMのおかげで、高解像度画像の読み込みやフィルタ処理の応答性は非常に高速です。ただし、カラーモデル「HiBreak Pro Color」であっても色再現性は液晶に劣るため、写真の正確な色調整には向きません。連続して編集作業を行うと、動画再生時と同様に背面に温かさを感じましたが、処理速度が低下するようなことはありませんでした。アプリごとにコントラストやリフレッシュレートをプリセット表示モードとして保存できるため、カスタマイズ性は非常に高いと感じました。
まとめ:アプリの動作感
- 通常動作:Dimensity 1080と8GB RAMにより、前モデルとは別次元の応答性を実現している。
- Web閲覧:遅延(レイテンシ)が少なく、BOOXのBSR技術に迫る滑らかなスクロールが可能。
- 電子書籍:ページめくりが高速で、自動ゴースト除去により残像も気にならず読書に集中できる。
- 動画再生:視聴は可能だが画質は粗く、長時間の高負荷時にはわずかな発熱を感じる。
- カスタマイズ性:アプリごとに最適な表示設定を保存でき、用途に応じた使い分けが便利である。
メモリとストレージ:Bigme HiBreak Pro 大容量化と拡張性のトレードオフ
Bigme HiBreak Proは、E Inkスマートフォンとしては最高峰の8GBメモリと256GBストレージを搭載していますが、前モデルからの変更点として外部ストレージへの対応状況に注意が必要です。
8GB RAMが生む圧倒的な安定性
メモリ(RAM)に関しては、前モデルの「Bigme HiBreak」および競合の「BOOX Palma 2」がいずれも6GBであるのに対し、Pro版は8GB RAMへと増強されました。実際に複数のアプリを裏で立ち上げながら作業を行ってみましたが、アプリが強制終了することなく保持される「安定性」は抜群です。
例えば、Kindleで読書をしながらブラウザで調べ物をし、さらにSNSを行き来するようなマルチタスク運用でも、アプリの再読み込みが発生する頻度は明らかに減りました。なお、一部のAndroid端末にあるようなストレージを転用する仮想メモリ機能は本機では利用できませんが、物理メモリが8GBあればE Ink端末の用途で不足を感じることはまずありません。
256GBの大容量とmicroSD廃止の衝撃
内蔵ストレージ(ROM)は256GBを搭載しており、これは前モデルBigme HiBreakやBOOX Palma 2の128GBと比較して2倍の容量です。システム領域を除いても200GB以上が自由に使えるため、マンガなら数千冊、PDF資料なら数万ファイルをオフラインで持ち運べる「ライブラリ収納力」は圧巻です。
しかし、ここで重大な注意点があります。前モデルBigme HiBreakやBOOX Palma 2には搭載されていたmicroSDカードスロットが、HiBreak Proでは廃止されています。ハイブリッドSIMスロット仕様ですが、SIMカード2枚のみの対応となり、microSDXCカードによる最大2TB等の拡張はできません。自炊した書籍データをSDカードで管理していたユーザーにとっては、運用方法の変更を迫られる大きな違いとなります。
クラウド連携で容量不足をカバー
SDカードが利用できない分、重要になるのがクラウドストレージとの連携です。Android 14ベースであるため、Google Drive、Dropbox、OneDriveといった主要なクラウドサービスの公式アプリが問題なく動作します。実際にEvernoteやOneNoteを使用してメモのデータ同期を行いましたが、5G通信のおかげで同期はスムーズで、SDカードの物理的な抜き差しの手間がない分、スマートな運用が可能だと感じました。大量のデータはクラウドに逃がし、閲覧頻度の高いものだけを256GBの内蔵ストレージに保存するという使い分けが、本機を使いこなす鍵となります。
まとめ:メモリとストレージ
- 搭載メモリ:8GB RAMを搭載し、前モデルやBOOX Palma 2(6GB)よりもマルチタスク時の安定性が向上している。
- 内蔵ストレージ:256GB ROMを搭載。競合機の倍の容量があり、単体でのライブラリ収納力は非常に高い。
- 拡張性:microSDカードスロットは廃止されており、ストレージの物理的な拡張はできない(前モデルやPalma 2は対応)。
- クラウド連携:Google DriveやOneNoteなどのアプリでデータ同期が可能。SDカード非対応の弱点を5G通信とクラウドで補える。
カメラ性能:Bigme HiBreak Pro 進化した20MPと実用的なOCR機能
ここでは、前モデルから大幅に解像度が向上したカメラ性能と、E Ink端末ならではの実用的なドキュメントスキャン機能について、実際の使用感を交えてレビューします。
カメラの構成・仕様:フロントカメラ搭載が大きな強み
まずハードウェアのスペックを確認すると、リアカメラは20MP(2000万画素)、フロントカメラは5MP(500万画素)を搭載しています。前モデルの「Bigme HiBreak」がリア13MPだったことを考えると、解像度は大きく向上しました。
競合機である「BOOX Palma 2」(リア:16MP)と比較して決定的に優れている点は、フロントカメラの有無です。Palma 2はリアカメラ(16MP)のみでフロントカメラを搭載していないため、顔認証や自撮り、ビデオ通話ができません。対してHiBreak Proはフロントカメラを備えており、ZoomやGoogle Meetなどのアプリで顔を見ながらビデオ通話できるため、ビジネスツールとしての汎用性は一歩リードしています。動画撮影も最大4K解像度に対応しており、スペック上は現代的な水準に達しています。
静止画の撮影:白黒ファインダーでの撮影体験
実際にリアカメラで風景や小物を撮影してみました。明るい照明の下であれば、20MPの高解像度を活かした、記録用としては十分まともな画質の写真が撮れます。LEDフラッシュも搭載されているため、薄暗い場所でも撮影は可能です。
ただし、撮影体験は独特です。ファインダー(画面)がグレースケール(白黒)であるため、被写体の「色」を確認できません。料理の写真を撮ってみたところ、画面上では美味しそうに見えているのか判断がつかず、後でカラー液晶のPCに転送して初めて「ちゃんと撮れていた」と安堵する場面がありました。また、OIS(光学式手ぶれ補正)が搭載されていないため、暗所での撮影は手ブレに注意が必要です。
ドキュメントスキャン・OCR機能:仕事で使える「メモ」代わり
このカメラの真価は、風景写真よりも「ドキュメントスキャン」で発揮されます。会議中に配布された資料やホワイトボードを撮影し、プリインストールのOCR機能を使ってテキスト化してみましたが、このプロセスは非常にスムーズでした。
20MPの高解像度のおかげで細かい文字も潰れずに認識され、撮影後にドキュメントを再編集したり、テキストデータとして即座に共有したりできます。写真のテキスト認識機能に最適化されたデュアルHDカメラという触れ込み通り、アナログな情報をデジタル化するツールとしては、下手なスキャナアプリよりも手軽で実用的だと感じました。
注意点:電子ペーパー特有の表示遅延
カメラを使用する上で避けられないのが、E Inkディスプレイ特有の表示遅延です。カメラを動かして構図を決めようとすると、画面の追従がワンテンポ遅れ、残像(ゴースト)が発生します。Eink Centerでリフレッシュモードを「Extreme」などの高速モードに変更すればある程度改善されますが、液晶スマホのような滑らかなプレビューは期待できません。
また、4K動画の撮影は可能ですが、撮影中の画面はカクつき、再生時もE Ink上では滑らかに表示されません。動画はあくまで「記録用」として割り切り、再生や鑑賞は別のデバイスで行うのが正解でしょう。
まとめ:カメラ性能
- リアカメラ:前モデル(13MP)から20MPへ進化し、ドキュメントスキャン等の記録用途には十分な解像度を確保している。
- フロントカメラ:5MPカメラを搭載しており、フロントカメラ非搭載のBOOX Palma 2とは異なりビデオ通話や自撮りが可能。
- 動画撮影:4K解像度での録画に対応しているが、OIS(光学手ぶれ補正)は非搭載。
- 撮影体験:プレビュー画面が白黒かつ低フレームレートであるため、色味やピントの確認には慣れが必要。
- OCR機能:高解像度カメラとOCR機能の相性が良く、紙資料のデジタル化やテキスト再編集がスムーズに行える。
オーディオ性能:Bigme HiBreak Pro 進化したステレオサウンドと実用的な音声機能
Bigme HiBreak Proは、E Ink端末でありながらオーディオ機能にも力が入れられています。ここでは、スピーカーの音質から、ビジネスに役立つ録音・文字起こし機能、そしてワイヤレスリスニング体験まで、実際の使用感をレビューします。
スピーカーの構成と音質:ステレオ化で広がる音場
前モデル「Bigme HiBreak」がモノラルスピーカーだったのに対し、Pro版では上部と下部にスピーカーを配置したステレオ構成(デュアルスピーカー)へと進化しました。実際にSpotifyでアコースティックな楽曲を再生してみると、予想以上にダイナミックな音色が響きます。
ボーカルなどの中音域はクリアで聞き取りやすく、ポッドキャストやラジオを流し聴きする分には十分なクオリティです。ただし、筐体のサイズ制限もあり、重低音(ディープベース)の迫力や音の深みには欠ける印象です。映画館のような臨場感までは期待できませんが、静かな部屋でBGMとして音楽を流す「音楽プレイヤー的な使い方」であれば、十分に実用的だと感じました。BOOX Palma 2と比較しても、通話用スピーカーを兼ねている分、人の声の帯域が聞き取りやすいチューニングになっていると感じます。
オーディオブックとテキスト読み上げ:読書の新体験
本機は「読む」だけでなく「聴く」読書体験も優秀です。まずはAmazon Audibleで小説を聴いてみましたが、ステレオ効果のおかげでナレーターの声が立体的になり、物語の世界に没入できました。長時間聴いていても耳が疲れにくい音質です。
さらに、無料の組み込みTTS(テキスト読み上げ)機能も試してみました。今回は「青空朗読」アプリを使用して、芥川龍之介の作品を読み上げさせてみました。以前のE Ink端末では機械的な音声に違和感がありましたが、HiBreak ProのTTSはイントネーションが比較的自然で、クリアな音声に変換してくれます。画面を見ずに、通勤中の満員電車で「耳読書」をするスタイルが、私の新しい日課になりました。
マイクと録音:デュアルマイクで会議もクリアに
マイク性能についても触れておきます。HiBreak Proはデュアルマイクアレイを搭載しており、画面下部と上部にマイクが配置されています。これにより、ノイズを抑えたクリアな録音が可能になっています。
実際にICレコーダー代わりに、少人数の会議を録音してみました。再生してみると、発言者の声がはっきりと分離して録音されており、議事録作成の補助として十分に使えるレベルでした。ふと思いついたアイディアをボイスメモに残す際も、スマホを口元に近づけすぎなくてもしっかりと声を拾ってくれるため、メモ帳を取り出すよりもスピーディーに記録できます。
音声認識・文字起こし機能:無料で使える強力なツール
ビジネス用途で強力なのが、無料の音声テキスト変換(文字起こし)機能です。録音した音声をスマートに文字起こしし、さらにBigmeクラウド経由でデバイス間で同期することができます。
側面のファンクションキーにこの機能を割り当てておけば、ボタン一つで即座に文字起こしモードに入れます。実際にインタビューの練習で使ってみましたが、変換精度は実用的で、あとでテキストを修正する手間が大幅に省けました。BOOX Palma 2にはないマイクを活用したこの機能は、ライターや学生にとって大きなメリットとなるでしょう。
Bluetoothオーディオ:LDAC対応でハイレゾ級の音質へ
イヤホンジャックは非搭載ですが、Bluetooth 5.2に対応しており、SBCやAACだけでなく、高音質コーデックの「LDAC」もサポートしています。
Sony製のワイヤレスイヤホンを接続してハイレゾ音源を聴いてみたところ、スピーカー再生時とは別次元の繊細な音が楽しめました。楽器の細かいニュアンスやボーカルの息遣いまで再現され、E Ink画面で静かに読書をしながら、耳では最高品質の音楽に浸るという、贅沢な時間を過ごせます。有線イヤホン派には残念な点かもしれませんが、ワイヤレス環境での音質に関しては妥協がありません。
まとめ:オーディオ性能
- スピーカー構成:前モデルのモノラルからデュアルスピーカー(ステレオ)へ進化し、音の広がりが向上した。
- 音質傾向:中音域やボーカルがクリアで聞き取りやすい一方、重低音の迫力はサイズなりで少し物足りない。
- テキスト読み上げ:組み込みTTS機能が優秀で、「青空朗読」などのアプリでも自然でクリアな音声読み上げが可能。
- マイク性能:デュアルマイクアレイを搭載し、会議やボイスメモでもクリアな録音ができる。
- 文字起こし:無料の音声テキスト変換機能があり、録音から文字起こしまでをスムーズに行える点がビジネスに強い。
- Bluetooth音質:LDACコーデックに対応しており、ワイヤレスイヤホンを使用すればハイレゾ相当の高音質で音楽を楽しめる。
バッテリー持ちと充電:Bigme HiBreak Pro スタミナ増強と18W充電の進化
ここでは、E Inkスマートフォンとして最大級のバッテリー容量を搭載したBigme HiBreak Proのスタミナ性能と、充電周りの仕様について、実測値や競合比較を交えてレビューします。
バッテリー容量とベンチマークテストの結果
Bigme HiBreak Proは、4500mAhという大容量バッテリーを搭載しています。これは前モデル「Bigme HiBreak」の3300mAh から大幅に増量されただけでなく、ライバル機である「BOOX Palma 2」の3950mAh をも上回る数値です。5G通信や高性能なDimensity 1080プロセッサを動かすための電力ですが、省電力なE Inkディスプレイとの組み合わせにより、公式では「超長時間バッテリー駆動」を謳っています。
客観的な指標として、スマホのバッテリー性能を計測する「PCMark for Android」(バッテリーテスト)を実行したところ、連続駆動時間は約10時間という結果が出ました。これは画面を常時点灯させ、ブラウジングや画像編集などの処理を連続して行った場合の数値です。一般的な液晶スマホと比較しても遜色ない数字ですが、静止画表示で電力を消費しないE Inkの特性を活かせば、実際の待機時間はさらに伸びることが期待できます。
実際の体験談:読書と5G通信のバランス
実際にメイン端末として一日中持ち歩いてみました。朝、満充電の状態で家を出て、通勤電車での往復2時間の読書、昼休みのWebブラウジング、そして断続的なLINEやメールのやり取りを行いましたが、帰宅時のバッテリー残量はまだ余裕がありました。特に驚いたのは、Kindleアプリで小説を読んでいる時の消費の少なさです。画面が書き換わる瞬間しか電力を使わないため、オフラインで読書に没頭している時間は、バッテリーの減りがピタリと止まったかのような感覚に陥ります。
ただし、5G通信をオンにして動画ストリーミングや大容量データのダウンロードを行うと、それなりに減りは早くなります。それでも、前モデルを使用していた時のような「夕方には充電切れを心配する」というストレスからは完全に解放されました。BOOX Palma 2はWi-Fi専用機のため単純比較は難しいですが、常時ネットにつながるスマホとしてこのスタミナは頼もしい限りです。
18W急速充電とインターフェース
充電に関しては、最大18Wの急速充電に対応しています。競合の「BOOX Palma 2」は急速充電に非対応で、HiBreak Proの方が、大容量バッテリーを効率よく運用できる点で有利です。前モデルが満充電に時間を要していたことを考えると、この進化は実用性を大きく高めています。
充電ポートは両機種とも底面にUSB Type-Cポートを搭載しており、汎用性は高いです。PCと接続してデータ転送も行えますが、転送速度はUSB 2.0規格相当のようで、数百MBの動画ファイルを転送する際は少し待たされる感覚があります。なお、残念ながら両機種ともワイヤレス充電には対応していません。プラスチック筐体であるため期待していましたが、この点は有線充電のみの対応となります。
まとめ:バッテリー持ちと充電
- バッテリー容量:4500mAhの大容量バッテリーを搭載。前モデル(3300mAh) やBOOX Palma 2(3950mAh)と比較して最大容量を誇る。
- 駆動時間テスト:PCMark for Androidの実測テストでは約10時間の連続駆動を記録。
- 実使用感:5G通信利用時でも1日は余裕で持ち、読書メインの使用であれば数日間充電なしで運用できるスタミナがある。
- 充電速度:最大18Wの急速充電に対応。前モデルよりも充電速度が向上している。
- 充電方式:底面のUSB Type-Cポートを使用。ワイヤレス充電には非対応。
AI機能:Bigme HiBreak Pro 無料で使えるBigmeGPT 4.0の実力
Bigme HiBreak Proには、独自のAIアシスタント「BigmeGPT 4.0」が標準搭載されており、これが予想以上に実用的でした。ここでは、他機種にはないこのAI機能の魅力と、実際の活用シーンについてレビューします。
無料のBigmeGPT 4.0:BOOX Palma 2との決定的な違い
最大のアドバンテージは、「BigmeGPT 4.0」が完全無料で利用できる点です。競合の「BOOX Palma 2」や一般的なAndroid端末では、ChatGPTなどのAIアプリを個別にインストールし、場合によってはサブスクリプション契約が必要ですが、HiBreak Proなら買ったその日から高度なAI機能が使い放題です。
前モデル「Bigme HiBreak」にもAIアシスタント機能はありましたが、Pro版ではハードウェア性能(Dimensity 1080プロセッサと8GB RAM)が向上しているため、AIの応答速度や生成処理が格段にスムーズになっています。アプリを立ち上げる手間なく、システムレベルで統合されたAIを指先ひとつで呼び出せるのは、Bigmeならではの強みです。
スマートチャット:日本語でのレスポンスも快適
実際に「スマートチャット」機能を使い、日本語で「おすすめの有酸素運動を教えて」と質問してみました。5G通信の速さも相まって、回答が生成されるまでの待ち時間はわずか数秒です。日本語の精度も高く、自然な文章で的確なアドバイスが返ってきました。
E Ink画面でチャットを行うと、まるで紙に文字が浮かび上がってくるような不思議な感覚を覚えます。液晶画面のように光らないため、長時間チャットを続けても目が疲れません。ちょっとした調べ物や、暇つぶしの話し相手として、このスマートチャットは非常に優秀なパートナーになります。
クリエイティブライティング:執筆の強力なサポーター
仕事でメールの返信に悩んだ際、「クリエイティブライティング」機能を活用してみました。「取引先への丁寧な謝罪メールを作成して」と入力すると、TPOに合わせた適切なビジネスメールの文面があっという間に生成されました。
これまではPCを開いて考えていた作業が、片手のスマホ操作だけで完結するのは感動的です。ブログ記事のアイデア出しや、構成案の作成にも使ってみましたが、自分では思いつかない視点を提示してくれるため、執筆の効率が大幅に上がりました。E Ink端末の「書く・読む」に特化した特性と、文章生成AIの相性は抜群です。
インテリジェントな描画:言葉から画像を生成
「インテリジェントな描画」機能では、テキストから画像を生成することができます。試しに「未来都市の風景」と入力してみたところ、数秒で独創的なイメージ画が生成されました。
E Inkディスプレイ特有のモノクロ表示(カラー版の場合は淡いカラー)となるため、生成された画像の細部や鮮やかな色味を確認するには限界がありますが、アイデアのラフスケッチやイメージボードとして使う分には十分楽しめます。描画生成のような重い処理でもアプリが落ちることなく動作するのは、8GBの大容量メモリのおかげでしょう。
まとめ:AI機能
- 機能の有無:無料で使える「BigmeGPT 4.0」を標準搭載しており、追加費用なしで高度なAI機能を利用できる。
- 比較優位性:AI機能がシステムに統合されていないBOOX Palma 2に対し、アプリ導入の手間なく即座に使える点が大きなメリット。
- スマートチャット:日本語での対話もスムーズで、Dimensity 1080による高速処理によりレスポンスも快適である。
- クリエイティブライティング:メール作成やアイデア出しに実用的で、E Inkの目に優しい環境で執筆作業が捗る。
- インテリジェントな描画:テキストから画像を生成可能。E Ink表示の制限はあるものの、発想の補助ツールとして楽しめる。
OSとソフトウェア:Bigme HiBreak Pro Android 14搭載の安心感と独自機能
ここでは、最新のAndroid 14を搭載し、長期的なアプリ運用が可能になったOS周りと、E Ink端末ならではの工夫が凝らされた独自UIやリーダーアプリについて、実機での体験を交えてレビューします。
OSとUIデザイン:Android 14搭載で競合を一歩リード
Bigme HiBreak Proの大きな強みは、OSに最新に近い「Android 14」を搭載している点です。前モデル「Bigme HiBreak」がAndroid 11、競合の「BOOX Palma 2」がAndroid 13であることを考えると、セキュリティやアプリの互換性において最も有利な立場にあります。Google Playストアも標準搭載されており、普段使っているアプリを特別な手順なしにインストールできるのは大きな安心感につながります。
UIデザインは、E Inkディスプレイでの視認性を最優先した独自のシェルが採用されています。ホーム画面のアイコンはシンプルな線画や高コントラストなデザインに調整されており、カラー表示ができない(または淡い)画面でも機能が判別しやすいよう工夫されています。また、画面上に常駐できる「フローティングボタン(ナビボール)」が非常に便利で、ホームに戻る、戻る、リフレッシュといった操作を親指一つで完結できるため、片手操作時の快適性が格段に向上しました。日本語対応については、一部の翻訳が不自然な箇所も見受けられますが、実用上の支障はありませんでした。
アップデート:ユーザーの声に応える改善体制
Android OS自体のメジャーアップデートは頻繁には行われない傾向にありますが、Bigmeはファームウェアの修正アップデートを比較的こまめに提供してくれるメーカーです。
実際に私が手にした初期段階では、日本語キーボードがうまく表示されないという不具合に遭遇しましたが、システムアップデートを2回ほど実施したところ無事に解消され、快適に日本語入力ができるようになりました。このように、発売後の不具合に対しても放置せず、しっかりと修正パッチを配布してくれる体制は信頼に値します。Android 14ベースであるため、アプリ側のサポート切れを心配することなく、数年単位で長く愛用できるデバイスだと感じました。
xReaderアプリの翻訳機能:洋書読書のハードルを下げる
標準搭載されている読書アプリ「xReader」には、強力な翻訳機能が備わっています。私は英語の技術書を読む際にこの機能を多用していますが、分からない単語や文章を長押しするだけで、Google翻訳などのエンジンを利用したテキスト翻訳が即座に表示されます。
わざわざ別の翻訳アプリを立ち上げてコピペする必要がないため、読書のリズムを崩すことなく読み進められます。翻訳精度も高く、海外のニュース記事や論文をE Inkの目に優しい画面で読み込みたいというニーズに完璧に応えてくれます。
xReaderアプリのハイライト・注釈:学習ツールとしての実力
「xReader」は、学習用途にも最適化されています。重要な箇所にハイライトを引いたり、気になった部分に注釈(メモ)を残したりする操作が非常にスムーズです。
実際に資格試験の勉強に使ってみましたが、ハイライトした箇所を後から一覧で確認できるため、復習が効率的に進みました。また、フォントサイズや行間、余白の調整といったレイアウト設定も柔軟に変更でき、自分にとって最も読みやすい表示にカスタマイズすることで、長時間の学習でも集中力が途切れにくいと感じました。
まとめ:OSとソフトウェア
- 搭載OS:最新のAndroid 14を採用し、前モデル(Android 11)やBOOX Palma 2(Android 13)と比較してセキュリティやアプリ互換性で有利。
- アプリストア:Google Playストアを標準搭載し、ほぼすべてのAndroidアプリをシームレスにインストール可能。
- UIデザイン:E Inkに最適化された高コントラストな線画アイコンや、片手操作を補助するフローティングボタンを採用。
- アップデート:ファームウェア更新により、日本語入力の不具合などが修正されるなど、サポート体制が整っている。
- xReader(翻訳):アプリ内で完結する翻訳機能を備え、洋書や海外記事のリーディングを強力にサポート。
- xReader(注釈):ハイライトや注釈機能が使いやすく、柔軟なレイアウト設定と合わせて学習用途にも最適。
検証してわかったBigme HiBreak Proのメリット・デメリット
Bigme HiBreak Proを実際にメイン端末として運用し、前モデルの「Bigme HiBreak」やライバル機「BOOX Palma 2」と比較検証を行いました。E Ink端末としては破格のスペックを持つ一方で、構造上のトレードオフも見えてきました。ここでは、実際に使ってみて感じた「強み」と「弱点」を包み隠さず紹介します。
メリット(長所、利点)
メリット1:5G通信と音声通話に対応(BOOX Palma 2はWi-Fi専用)
最大のメリットは、単体で5G通信と音声通話ができる点です。競合の「BOOX Palma 2」はWi-Fi専用機であり、外出先ではテザリングが必須で電話番号による通話もできません。対してHiBreak Proは、楽天モバイルなどのSIMカードを挿せば、どこでもネットに繋がり、VoLTEによるクリアな通話が可能です。スマホとタブレットの2台持ちから解放される「これ一台で完結する自由」は、何物にも代えがたい魅力でした。
メリット2:Android 14と圧倒的な処理性能(旧モデル比3倍以上のスコア)
OSと処理性能の進化は劇的です。最新に近いAndroid 14を搭載し、Dimensity 1080プロセッサによりAntutuスコアは約59万点を記録しました。これは前モデル(Helio P35、約17万点)の3倍以上、BOOX Palma 2(Snapdragon 750G、約44万点)と比較しても頭一つ抜けています。アプリの起動や切り替えがサクサクで、E Ink端末にありがちな「もっさり感」を感じさせない快適さは感動的です。
メリット3:フロントカメラ搭載でビデオ通話が可能(BOOX Palma 2は非搭載)
仕事で使う上で大きかったのがフロントカメラ(5MP)の存在です。BOOX Palma 2にはリアカメラしかなく、顔を見ながらのビデオ通話や自撮りができません。HiBreak Proなら、ZoomやMeetで急な会議が入ってもそのまま対応できます。リアカメラも20MPに強化されており、OCR機能を使ったドキュメントスキャンも高精細に行えるため、ビジネスツールとしての完成度はPro版が圧倒的に上です。
メリット4:18W急速充電に対応(BOOX Palma 2は非対応)
バッテリー周りでも明確な優位性があります。4500mAhの大容量バッテリーを搭載しているだけでなく、最大18Wの急速充電に対応しています。BOOX Palma 2は急速充電に対応していないため、充電速度には差が出ます。大容量バッテリーをサッと充電して長時間使えるスタミナ性能は、毎日持ち歩くデバイスとして非常に頼もしく感じました。
メリット5:全方位NFCとIRポートを完備(生活を変える付加機能)
地味ながら生活を変えてくれたのが、NFCとIR(赤外線)ポートです。Google Wallet対応によりコンビニでのタッチ決済が可能になり、IRポートでエアコンなどの家電操作も行えます。これらの機能は前モデルにはなく、また電子書籍リーダー専用機にはまず搭載されない機能です。「スマホとして使う」ことを本気で考えた仕様だと感じました。
メリット6:カラー版とモノクロ版を選択可能
ユーザーの好みに応じて、最新のカラー電子ペーパー技術「Kaleido 3」を搭載したカラー版「HiBreak Pro Color」と、コントラストと解像度を重視したモノクロ版(Carta 1200)の2モデルから選べるのも大きな魅力です。雑誌やWebサイトを色付きで見たいならカラー版、小説やドキュメントの読みやすさを最優先するならモノクロ版といったように、自分の用途に最適な一台を選べます。
デメリット(短所、欠点)
デメリット1:microSDカードスロット廃止(旧モデル・BOOX Palma 2は対応)
検証して最も残念だったのが、microSDカードスロットの廃止です。前モデル「HiBreak」やライバルの「BOOX Palma 2」はmicroSDに対応しており、安価に容量を増やせました。Pro版は内蔵ストレージが256GBと大容量ですが、TB単位で自炊データを持ち歩きたいユーザーにとっては、物理的な拡張手段がないことは痛手となるでしょう。クラウドストレージの活用が必須となります。
デメリット2:重量増とサイズ感(BOOX Palma 2より重い)
高機能化の代償として、重量は約182gとなりました。これは「BOOX Palma 2」や前モデル(約170g)と比較すると、手に持った時にずっしりとした密度を感じます。6.13インチへのサイズアップに伴い横幅も広がっているため、手の小さい方は片手操作時に少し持ちにくさを感じるかもしれません。
デメリット3:スピーカーの低音不足と防水非対応
オーディオ機能はステレオスピーカーになりましたが、音質は中音域寄りであり、音楽鑑賞時の低音の迫力は不足しています。また、防水・防塵性能(IP等級)に関する記載がなく、水回りでの使用には不安が残ります。この点は、アウトドアやお風呂での読書を想定しているユーザーには注意が必要です。
デメリット4:筆圧対応スタイラスペンには非対応
AIによる画像生成機能はありますが、Galaxy Noteシリーズや一部のE Inkタブレットのような「筆圧感知対応のスタイラスペン」による手書き入力には対応していません。手書きでメモを取ったり、イラストを描いたりしたいと考えている場合は、別途専用の電子ノート端末が必要になります。
まとめ:メリット・デメリット
Bigme HiBreak Proは、単なる電子書籍リーダーの枠を超え、メインのスマートフォンとして十分に通用する性能を備えていることがわかりました。特に5G通信、Android 14、急速充電、そしてフロントカメラの搭載は、競合であるBOOX Palma 2に対する明確なアドバンテージです。
一方で、microSDカードスロットの廃止は、大量のローカルデータを扱うユーザーにとっては無視できないデメリットと言えます。総じて、E Ink端末に「軽快な動作」と「常時接続の利便性」を求める人にとっては、現状でこれ以上の選択肢はない最強のデバイスと言えるでしょう。
Bigme HiBreak Proのスペック(仕様)
- ディスプレイ: 6.13インチ HD Epaper B/W ディスプレイ (824×1648) 300PPI、フリッカー・ブルーライトなし
- フロントライト: 調整可能な36レベル 暖色・寒色フロントライト
- プロセッサ: MediaTek Dimensity 1080、オクタコア、2.4GHz
- GPU: ARM Mali-G68 MC4
- RAM(メモリ): 8GB
- ストレージ: 256GB
- バッテリー: 4500mAh
- 充電: Type-C ポート、18W急速充電対応
- 背面カメラ: 20MP、写真テキスト認識 (OCR) 機能
- 前面カメラ: 5MP
- ワイヤレス通信: 2.4G/5G WIFI、Bluetooth 5.2
- GPS: サポート、高精度ナビゲーション
- NFC: サポート、Omnidirectional NFC
- インターフェース: Type-C 充電ポート、IR(赤外線)ポート
- センサー: ジャイロスコープ、重力センサー、コンパス
- ボタン: 指紋認証ボタン、音量ボタン、リフレッシュボタン(カスタマイズ可能)
- 機能: Bigme “SSS”Super Refresh (高速、クリーン、スムーズな表示) と xRapid refresh algorithm による 21 F/S のリフレッシュレート、Auto Ghosting removal / Mininum Ghosting (自動ゴースト除去)、写真テキスト認識 (OCR)、音声テキスト変換 (無料)、BigmeGPT 4.0 (無料)、テキスト翻訳 (xReaderアプリ)、テキスト読み上げ (TTS) (無料内蔵)、ハイライトと注釈、柔軟なレイアウト設定、指紋認証によるロック解除、Omnidirectional NFC
- 防水防塵: 非対応
- ゴースト除去: Auto Ghosting removal、Mininum Ghosting
- 生体認証: 指紋認証、顔認証
- OS: Android 14、Google Play Storeプリインストール
- サイズ: 159.8×80.9×8.9mm
- 重量: 約182g
- カラー: Black、White
- 付属品: シリコンケース、USB Type-Cケーブル、SIMピン、マニュアル
- モバイル通信: 5G、4G対応、Dual SIM Dual standby
- SIMカード: 5G Dual SIM、デュアルSIMデュアルスタンバイ
対応バンド:Bigme HiBreak Pro
Bigme HiBreak Proは5G通信に対応しています。
基本的には本体にSIMカードを入れて、APN設定を済ませると、通信できます。
SIMはNanoSIMに対応しています。
対応バンドは以下の通りです。
- 5G NR: NSA:N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/40/41/66/77/78、SA:N1/2/3/5/7/8/20/25/28/38/41/77/78
- 4G LTE: LTE-FDD :B1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/25/26/28/66、LTE-FDD :B34/B39/B38/B40/B41
対応バンドの詳細
ドコモ:
- 5G: n78に対応。ドコモの主要バンドであるn79には対応していませんが、n78も広く使われています。また、4Gからの転用バンドであるn28にも対応しています。
- 4G: B1, B3, B19 (プラチナバンド), B28に対応。主要なLTEバンドとプラチナバンドに対応しているため、広いエリアで通信可能です。
- プラチナバンド: B19に対応。
ドコモ回線ならahamoがおすすめ! → ahamoについての記事を読む
au:
- 5G: n77, n78に対応。auの主要な5Gバンドをカバーしています。転用バンドn28にも対応しています。
- 4G: B1, B3, B18/B26 (プラチナバンド), B28, B41に対応。主要なLTEバンドとプラチナバンドに対応しています。
- プラチナバンド: B18/B26に対応。
au回線ならpovoがおすすめ! → povoについての記事を読む
ソフトバンク:
- 5G: n77に対応。ソフトバンクの主要な5Gバンドです。転用バンドn3, n28にも対応しています。
- 4G: B1, B3, B8 (プラチナバンド), B28, B41に対応。主要なLTEバンドとプラチナバンドに対応しています。
- プラチナバンド: B8に対応。
ソフトバンク回線ならLINEMOがおすすめ! → LINEMOについての記事を読む
楽天モバイル:
- 5G: n77に対応。楽天モバイルの5Gバンドです。
- 4G: B3 (自社回線), B18/B26 (パートナー回線) に対応。楽天モバイルの自社回線エリア、およびパートナー(au)回線エリアの両方で通信可能です。また、楽天モバイルが今後展開するプラチナバンドB28にも対応しています。
- プラチナバンド: パートナー回線のB18/B26に対応。自社のB28にも対応。
楽天モバイル回線についてはこちらで紹介! → 楽天モバイルについての記事を読む
結論
この端末は、
- ドコモ: 5Gのn79に非対応な点を除けば、主要な4G/5Gバンドおよびプラチナバンドに対応しており、ほとんどのエリアで問題なく利用できると考えられます。
- au: 主要な4G/5Gバンド、プラチナバンドに幅広く対応しており、快適に利用できる可能性が高いです。
- ソフトバンク: 主要な4G/5Gバンド、プラチナバンドに幅広く対応しており、快適に利用できる可能性が高いです。
- 楽天モバイル: 自社回線、パートナー回線、そして将来的なプラチナバンドにも対応しており、問題なく利用できると考えられます。
総合的に見て、この端末は日本の4キャリアすべてにおいて、主要な通信バンドをカバーしており、多くのエリアで快適に利用できる可能性が高いと言えます。ただし、各キャリアが今後導入する可能性のある新しいバンドや、ミリ波(n257など)には対応していない点にご注意ください。
なお、モバイル通信を利用するには、自分のSIMがスマホ側のバンドに対応している必要があります。
こちらのページで対応しているかどうかを確認できます。
ドコモ、ソフトバンク、au、楽天モバイル回線の「対応バンド」を詳細にチェック!
Bigme HiBreak Proの評価
10の評価基準で「Bigme HiBreak Pro」を5段階で評価してみました。
【項目別評価】
ディスプレイの見やすさ: ★★★★★
6.13インチ、300PPIの高解像度に進化したことで、文字のジャギーがなくなり、暖色ライト対応で夜間の読書も非常に快適です。
ペンでの描画性能: ★☆☆☆☆
スタイラスペンによる手書き入力には対応していません(AIによる画像生成機能「インテリジェントな描画」は搭載しています)。
パフォーマンス: ★★★★★
Antutu約59万点のDimensity 1080と8GBメモリを搭載し、E Ink端末としては最高峰のサクサクとした動作を実現しています。
機能: ★★★★★
指紋・顔認証、フロントカメラ、NFC、IRポート、AI機能(BigmeGPT)など、メインスマホとして使える機能が全て揃っています。
通信性能: ★★★★★
5G通信に対応し、物理デュアルSIMで通話も可能。Wi-Fi専用機とは一線を画す「どこでも繋がる」利便性があります。
バッテリー: ★★★★★
4500mAhの大容量バッテリーと18W急速充電に対応。読書メインなら数日間充電不要で、スマホとしてのスタミナも十分です。
デザイン: ★★★★☆
背面カメラがフラットで実用的ですが、プラスチック筐体のため高級感はそこそこ。重量が約182gと少し重めです。
オーディオ: ★★★☆☆
ステレオスピーカーに進化したものの、低音は弱めです。ただし、TTS(読み上げ)や通話音声はクリアに聞こえます。
価格: ★★★★☆
約62,500円という価格は安くはありませんが、5Gスマホとしての性能とE Inkの希少性を考えれば納得できる設定です。
使いやすさ: ★★★★☆
Android 14搭載でアプリ互換性が高く、物理ボタンのカスタムも便利ですが、microSD非対応な点が運用を少し難しくしています。
【総評】最強のE Inkスマホへ進化:★★★★☆(4.5)
前モデル「Bigme HiBreak」からの劇的な進化
Bigme HiBreak Proは、前モデルからあらゆる面で飛躍的な進化を遂げています。処理性能はCPUがHelio P35からDimensity 1080に変更されたことで、Antutuスコアが約17万点から約59万点へと3倍以上に向上しました。これにより、ブラウジングやアプリの切り替えでもたつくストレスが解消されています。
また、画面サイズが5.84インチ(275PPI)から6.13インチ(300PPI)へ拡大・高精細化し、フロントライトも寒色のみから「暖色・寒色調整」が可能になったことで、読書体験の質が格段に上がりました。通信面でも4Gから5Gへ、バッテリーも3300mAhから4500mAhへと増強され、まさに「Pro」の名に恥じないスペックアップを果たしています。
BOOX Palma 2との違いとデメリット
ライバル機「BOOX Palma 2」と比較した際の最大の強みは、「単体で通信・通話ができるスマートフォンである」点です。Palma 2はWi-Fi専用機でフロントカメラやNFCも非搭載ですが、HiBreak Proは5G通信、音声通話、ビデオ会議、NFC決済までこれ1台で完結します。
しかし、購入前に注意すべきデメリットとして「microSDカードスロットの廃止」が挙げられます。Palma 2や前モデルはSDカードで容量を拡張できましたが、Pro版は内蔵256GBのみです。大量の自炊データを物理メディアで管理したいユーザーには痛手となるでしょう。また、重量も約182gとPalma 2(約170g)より重く、防水性能の記載がない点もアウトドア利用には不安が残ります。そのほかにも筆圧ペンに非対応でスムーズな手書きが利用できない点も注意が必要です。
最適なユーザーとおすすめの理由
このデバイスは、「スマホの便利さ」と「目に優しい画面」を両立させたいユーザーに最適です。特に、Wi-Fiルーターを持ち歩くのが面倒な人や、仕事の連絡(通話・メール・ビデオ会議)もE Ink端末で済ませたいミニマリストには、現状で唯一無二の選択肢となります。
読書専用機としてならBOOX Palma 2も優秀ですが、生活のすべてを目に優しい画面で完結させたいなら、間違いなくBigme HiBreak Proがおすすめです。メインスマホをこれに置き換えることで、目の疲れから解放され、通知に追われない穏やかなデジタルライフを手に入れられるでしょう。
Bigme HiBreak Pro携帯電話 スマートフォン本体 6.13 インチ 8+256GB Android 14 OS,GPS, 5GデュアルSIM
Bigme HiBreak Proの価格・購入先
※価格は2025/12/07に調査したものです。価格は変動します。
Bigme公式ストア
$439(日本円で約68,210円)で販売されています。
Bigme公式ストアで「Bigme HiBreak Pro」をチェックする
ECサイト
- Amazonで62,799円(税込)、
- 楽天市場で74,458円(送料無料)、
- AliExpressで62,204円、
で販売されています。
Amazonで「Bigme HiBreak Pro」をチェックする
楽天市場で「Bigme」をチェックする
ヤフーショッピングで「Bigme」をチェックする
AliExpressで「Bigme HiBreak Pro」をチェックする
米国 Amazon.comで「Bigme HiBreak Pro」をチェックする
※AliExpressでの購入方法・支払い方法はこちらのページで紹介しています。
AliExpressで激安ガジェットをお得に購入する方法を徹底 解説

おすすめのライバル機種と価格を比較
「Bigme HiBreak Pro」に似た性能をもつE-inkタブレット(電子ペーパータブレット)も販売されています。価格の比較もできるので、ぜひ参考にしてみてください。
BOOX Palma 2 Pro
Onyx から発売された6.13インチのカラーE inkタブレットです(2025年11月 発売)。
Android 15、Kaleido 3 カラー電子ペーパー(カラー150ppi/モノクロ300ppi)、オクタコアCPU(Snapdragon 750G)、8GBメモリ、128GBストレージ、3950mAhバッテリー、フロントライトを搭載しています。
また、専用スタイラスペン「InkSense Plus」(別売・筆圧4096段階)、データ通信、SIMカード(※eSIMは非対応)、「EinkWise」機能、メモアプリ「Notes」、AI機能、「スマートボタン」、撥水設計、マグネット式2-in-1ケース(別売)に対応。
カメラのスキャン機能(OCR機能・「DocScan」アプリ)、指紋認証センサー、自動回転用Gセンサー、デュアルスピーカー、BSR技術、Google Playストア、サードパーティのアプリ、3年間のアップデート保証、Type-C(OTG)、microSDカード(最大2TB)、Nano SIM(5G対応)、Wi-Fi、Bluetooth 5.1に対応しています。
価格は、Amazonで69,800円(税込)、楽天市場で69,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで69,800円、米国 Amazon.comで$399.99、です。
関連記事:BOOX Palma 2 Pro徹底レビュー!先代からの進化点とBigme比較
Amazonで「BOOX Palma 2 Pro」をチェックする
BOOX Palma 2
Onyx から発売されたスマートフォン風デザインの6.13型E-inkタブレットです(2024年10月24日 発売)。
Android 13、オクタコア プロセッサ、6GB LPDDR4X メモリ、18:9のCarta1200フラットスクリーン、128GB UFS2.1 ストレージ、3950 mAhバッテリー、16MPのスキャンカメラを搭載しています。
指紋認証、スマートボタン(AIアシスタントの起動を含む)、デュアルスピーカー、デュアルマイク、専用フリップフォールドケース(別売)、2色フロントライト、明るさ自動調整、
最大2TBまでのストレージ拡張、10GBのOnyxクラウドストレージ(無料)、防滴、カスタムウィジェット、BOOX スーパーリフレッシュ、Gセンサー(自動回転)、USB-C (OTGサポート)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0に対応しています。
価格は、Amazonで39,999円(税込)、楽天市場で47,800円(中古・送料無料)、ヤフーショッピングで52,800円(送料無料)、です。
関連記事:高速化した「BOOX Palma 2」とBOOX Palmaの違いをレビュー
Amazonで「BOOX Palma 2」をチェックする
BOOX Palma
Onyxから発売された6.13インチのE inkタブレットです(2023年9月19日に発売)。
Android 11、Qualcomm 8コアプロセッサ、4GB LPDDR4Xメモリ、18:9のCarta1200フラットスクリーン、3950mAhバッテリー、128GB UFS2.1ストレージ、Gセンサー、スピーカー、マイク、microSDカードスロットを搭載しています。
また、16MPカメラ(LEDフラッシュ付)、ページめくりボタン、ファンクションボタン、カスタムウィジェット、防滴、BOOX Super Refresh、最大2TBまでのストレージ拡張、2色フロントライト、OTAアップデート、Google Playストア、専用ソフトケース(別売)、USB-C (OTG)、Wi-Fi 5のデュアルバンド、Bluetooth 5.0に対応しています。
価格は、Amazonで39,800円 (税込)、楽天市場で46,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで43,874円、です。
関連記事:スマホサイズ「BOOX Palma」のできること、機能、評価を解説
Amazonで「BOOX Palma」をチェックする
BOOX Go 6
Onyxから発売された6インチのE inkタブレットです(2024年8月26日発売)。Android 12、Qualcomm 2.0GHz オクタコア プロセッサ、2GB LPDDR4X メモリ、HD Carta 1300 ガラス スクリーン、32GB eMMC ストレージ、1500 mAhバッテリー、microSDカードスロット、マイク搭載で、
ストレージ拡張、マグネットカバー(別売)、2色フロントライト、Google Playストア(サードパーティ製アプリの追加)、10GBのOnyxクラウドストレージ(無料)、USB Type-C (OTG/オーディオ ジャックとして使用可)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0に対応しています。
価格は、Amazonで27,800円、楽天市場で27,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで27,800円です。
関連記事:「BOOX Go 6」とPoke5、Page、Go Colorの違いを解説
Amazonで「BOOX Go 6」をチェックする
Meebook M6
Boyueから発売されたAndroid 11の6.0型 E inkタブレットです(2023年4月発売)。300ppiのHD E Inkスクリーン、クアッドコア 1.8GHzプロセッサ、3GBメモリ、32GBストレージ、2200 mAhバッテリー搭載で、
最大1TBまでストレージ拡張、2色フロントライト(24段階・暖色と寒色)、Google Playストア(電子書籍アプリおよびサードパーティ製アプリの追加)辞書(翻訳)、読書モード(ダーク色)、ZReaderアプリ、オリジナルレザーケース(付属)、USB Type-C (OTG)、Wi-Fiデュアルバンド、Bluetooth 5.0に対応しています。
価格は、AliExpressで21,808円、です。
関連記事:最大1TBの「Meebook M6」と6型E inkタブレットを比較
Amazonで「Meebook M6」をチェックする
その他のおすすめE inkタブレットは?
その他のおすすめEinkタブレット(電子ペーパータブレット)は以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
Einkタブレットに新モデル続々 最新 機種 ラインナップを比較
Eink液晶を搭載したタブレットをまとめて紹介しています。
BOOXのE-inkタブレット 全機種を比較! 最新のカラー、超大型あり
他のBOOXタブレットをまとめて紹介しています。
Meebook (LIKEBOOK) E-ink タブレットの最新モデルと選び方を紹介!
MeebookのE inkタブレットをまとめて紹介しています。
今買うべき電子書籍リーダーはKindleか? 最新モデル ラインナップ 一覧
Amazon Kindleシリーズをまとめて紹介しています。
楽天Koboが予想外に大ヒット! 電子書籍リーダー ラインナップ 機種 まとめ
楽天の電子書籍リーダーをまとめて紹介しています。