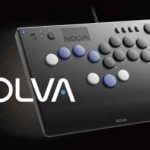2025年5月30日、ついに「日本ブランド初の本格ポータブルゲーミングPC」を謳う「TENKU LUNA」が発売されます。この一台は、単に高性能なだけでなく、日本のユーザーに寄り添った様々な魅力と可能性を秘めていると、発表時から大きな注目を集めています。
TENKU LUNAが持つ、心惹かれる魅力とは?
最大の魅力は高いゲーミング性能を発揮するAMD Ryzen 7 7840Uプロセッサを搭載しながらも約8万円台(※発売時は79,800円)という高いコストパフォーマンスを実現している点です。32GBという大容量メモリと1TB/2TBストレージも搭載しているにもかかわらず、この価格設定は従来の常識を翻す革新的な挑戦であるともいえます。
また、高コスパながらもUSB4 Type-Cポートを2基搭載するという高い拡張性も確保。高速充電やデータ転送、DP映像出力だけでなく、グラフィック性能を大幅に向上できるeGPU(外付けグラフィックスデバイス)接続も可能になっています。
そのほかにも、TDP、コントローラーモード、バイブレーションの強弱、ディスプレイ解像度などを簡単に変更・管理できる専用管理コンソールアプリケーション『GameAssistant』を搭載。
7インチの高精細なフルHDディスプレイや没入感を高めるデュアルステレオスピーカー、ゲームのパフォーマンスを維持する高い冷却性能、「日本ブランド」ならではの手厚い国内サポート(1年間の国内保証)など魅力が満載です!
このレビュー記事で、TENKU LUNAのすべてを解き明かす
この記事では、そんな期待の新星「TENKU LUNA」について、私が実際に様々な角度から検証し、感じたことを余すところなくお伝えしていきます。
その基本性能から、ディスプレイの見やすさ、コントローラーの操作性、バッテリーの持ち、ソフトウェアの使い勝手、そして所有する喜びを満たすサポート体制やエコシステムに至るまで、徹底的に深掘りしてご紹介します。
特に、強力なライバルとして市場に存在するASUSの「ROG Ally (RC71L-Z1E512)」との比較を通じて、TENKU LUNAがどのようなポジションにあり、どんなユーザーにとって最適な選択となり得るのかを明らかにしていきます。
【この記事で分かること】
- TENKU LUNAのデザイン、ディスプレイ、操作性、基本性能(CPU/GPU、メモリ、ストレージ)、ソフトウェア、バッテリー、拡張性、付加価値に関する詳細なレビュー
- TENKU LUNAが搭載するAMD Ryzen 7 7840Uのベンチマーク結果とゲーム性能、およびROG Allyプロセッサ性能との比較
- 比較対象のROG Ally (RC71L-Z1E512)とのスペック・機能・使い勝手の違い
- TENKU LUNAの具体的なメリットと、考慮すべきデメリット
- どのような使い方やニーズを持つユーザーにTENKU LUNAがおすすめできるか
- TENKU LUNAを購入すべきかどうかの判断材料
この記事を最後まで読むことで、「TENKU LUNA」という一台のポータブルゲーミングPCが、本当に「買い」なのかどうかが、はっきりと見えてくるはずです。購入を検討されている方はもちろん、最新のポータブルゲーミングPCの動向に興味のある方も、ぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク
公式ページ:TENKU LUNA | 株式会社天空
デザインと携帯性:TENKU LUNAの第一印象と実用性はいかに
ここでは、ポータブルゲーミングPC「TENKU LUNA」を手にした第一印象から、その筐体デザイン、質感、そして日常的なシーンでの持ち運びやすさ(携帯性)について、ライバル機種とも言えるASUSの「ROG Ally (RC71L-Z1E512)」と比較しながら、詳しくレビューしていきます。
手にした瞬間に感じる確かな存在感とデザイン性
漆黒のボディが目を引くTENKU LUNA。箱から取り出して最初に感じたのは、その重厚な存在感です。個人的には「意外と大きいな」というのが率直な第一印象でした。マットな質感の筐体は高級感を漂わせており、ゲーミングデバイス特有の派手さを抑えた落ち着いたデザインは、大人が所有する喜びを満たしてくれます。
実際に手に取ってみると、約666gという数値以上のずっしり感があります。ASUSのROG Ally (RC71L-Z1E512)が約608gなので、TENKU LUNAの方がやや重量があります。しかし、本体のデザインは手に馴染みやすく、少し上部が角ばっているように見えるものの、グリップ感は良好で、しっかりとホールドできます。このあたりは、グリップの握りやすさが特徴として挙げられるROG Allyの思想とはまた異なる、TENKU LUNAならではのこだわりを感じさせます。
日常シーンでの携帯性:持ち運びは現実的か?
ポータブルゲーミングPCとして、気になるのはやはり携帯性です。TENKU LUNAのサイズは約256×113.5×22.5-36mmとなっており、ROG Allyの幅280.0mm×奥行き111.38mm×高さ21.22~32.43mmと比較すると、TENKU LUNAの方が幅はコンパクトですが、奥行きはややある印象です。
普段使いのリュックサックや少し大きめのショルダーバッグであれば問題なく収納できますが、正直なところ、他機種と比べて「格段に持ち運びやすい!」というわけではなく、標準的な携帯性だと感じました。例えば、通勤電車の中でサッと取り出して『崩壊:スターレイル』のようなデイリークエストをこなす、といったシーンでは少し大きく感じるかもしれません。
休日にカフェでじっくりと『ストリートファイター6』の対戦を楽しむ、あるいは出張先で映画『デューン 砂の惑星PART2』を鑑賞するといった使い方であれば、その性能を存分に活かせるでしょう。持ち運ぶ際には、本体を保護するためにも、先行予約特典で付属する専用ケースや、別途クッション性のあるバッグを用意するのが賢明かもしれません。
ポート類に目を向けると、TENKU LUNAは本体の上部と下部にUSB4 Type-Cポートを1基ずつ、合計2基搭載しているのが特徴です。これにより、充電しながら外部ディスプレイに出力したり、eGPUを接続したりする際の取り回しが非常に便利です。
一方、ROG AllyはUSB Type-Cポートが1基であるため、この点はTENKU LUNAの大きなアドバンテージと言えるでしょう。ボタンやスティックの配置も標準的で、初めてポータブルゲーミングPCに触れる方でも直感的に操作できるのではないでしょうか。
まとめ:デザインと携帯性
- 第一印象と質感: 黒を基調とした重厚感のあるデザイン。マットな質感で高級感があり、落ち着いた印象を受ける。個人的には「意外と大きい」と感じた。
- 本体のホールド感: 約666gとROG Ally (約608g) よりやや重いが、手に馴染むデザインでグリップ感は良好。上部がやや角ばった印象も。
- 携帯性: 標準的なレベル。特別コンパクトというわけではなく、日常的な持ち運びにはカバンを選ぶ可能性も。通勤中の短時間プレイより、落ち着いた環境での長時間利用向き。
- サイズ感: ROG Allyと比較して幅はコンパクトだが、奥行きはややある。
- ポートの利便性: 本体上下に配置された合計2基のUSB4 Type-Cポートは、充電や多様な接続においてROG Ally (1基搭載) に対する大きな利点。
- 操作系の配置: ボタンやスティックの配置は標準的で、直感的な操作が可能。
ディスプレイ性能比較:TENKU LUNAの美麗さと滑らかさをROG Allyと徹底検証
ここでは、ポータブルゲーミングPCの体験の核となるディスプレイについて、TENKU LUNAが搭載する7インチ液晶の実力に迫ります。視認性、画質、応答性などを、ASUSのROG Allyと比較しながら、実際のゲームプレイや動画視聴の印象を交えて詳しくレビューしていきます。
スペックで見る表示性能:TENKU LUNAとROG Allyの画面比較
TENKU LUNAのディスプレイは、7インチのフルHD(1920×1080ピクセル)解像度を持つLCD IPSパネルです。このサイズ感は個人的にポータブル用途として非常にバランスが良く、高精細な表示と相まって、ゲームの世界に没入するには十分な情報量を提供してくれます。ROG Allyも同じく7.0型のフルHDディスプレイを搭載しており、解像度では両者互角と言えるでしょう。
注目すべきは、TENKU LUNAが120Hzのリフレッシュレートに対応している点です。これにより、レースゲーム『Forza Horizon 5』の高速な風景の移り変わりや、FPS『Apex Legends』での激しい視点移動も非常に滑らかに表示され、カクつきを感じることはほとんどありませんでした。この滑らかさは、一度体験すると元には戻れない快適さです。ROG Allyも120Hz対応であり、応答性の高さでは両者とも高いレベルにあります。
明るさ(輝度)については、TENKU LUNAが最大450nitsであるのに対し、ROG Allyは最大500nits と、スペック上はROG Allyがやや有利です。しかし、TENKU LUNAはsRGBカバー率100%という広色域に対応しており、色彩表現の豊かさでは引けを取りません。実際に『原神』のような色彩豊かなゲームをプレイすると、その鮮やかさを実感できます。タッチ操作の反応も良好で、直感的な操作が可能です。
画質と視認性:ゲーム・動画でのリアルな体験
TENKU LUNAの画質は、グラフィックが美しいAAAタイトルをプレイする上でも申し分ないレベルだと感じました。IPSパネルを採用しているため視野角も広く、どの角度から見ても色味の変化が少ないのは好印象です。ただし、パネルが液晶であるため、有機ELディスプレイを搭載したデバイスと比較すると、黒の締まりや発色の鮮やかさでは一歩譲る面があるのは否めません。これは液晶の特性上、致し方ない部分でしょう。
表面処理に関しては、TENKU LUNAのディスプレイに特殊なコーティング(例:ゴリラガラスなど)は採用されていませんでした。一方、ROG AllyはCorning Gorilla Glass VictusとDXCコーティングを採用し、反射低減と硬度向上を図っています。この点は、屋外での利用や耐久性において差が出る可能性があります。TENKU LUNAのディスプレイがグレア(光沢)かノングレア(非光沢)かの明確な記載はありませんが、一般的なポータブル機同様、多少の映り込みは考慮しておくとよいでしょう。
120Hzのリフレッシュレートのおかげで、動画視聴時も残像感はほとんど気になりませんでした。例えば、Netflixでアクションシーンの多い映画を見ても、動きの速い場面がクリアに表示されます。ゲームだけでなく、映像コンテンツを楽しむ上でもこの滑らかさは大きなメリットです。
明るい場所での見やすさとパネルの向き
TENKU LUNAの輝度450nitsは、一般的なノートPCの液晶ディスプレイ(200~300nits程度)と比較すれば明るく、日中の室内や少し明るい場所でも画面の視認性は確保されています。しかし、直射日光が当たるような屋外では、やはり画面が見にくくなる場面がありました。
個人的な感想としては、ROG Allyの500nitsの方がわずかに視認性が高いかもしれませんが、TENKU LUNAも健闘していると言えます。とはいえ、やはり本領を発揮するのは屋内環境であり、じっくりとゲームや動画に集中するためのデバイスという印象です。
また、一部のニュース記事ではTENKU LUNAの液晶が「ネイティブポートレート(縦長表示が標準)」であると言及されていました。これはROG Allyのディスプレイでも指摘されている点で、横画面でゲームをプレイする際にはOS側で回転処理が入るため、ごくわずかながらパフォーマンスへの影響や表示のクセを感じる可能性もゼロではありません。ただ、実際のゲームプレイ中にこれが大きく気になることはありませんでした。
まとめ:ディスプレイ
- 基本スペック: 7インチ フルHD (1920×1080) IPS液晶、リフレッシュレート120Hz、輝度450nits、sRGBカバー率100%と高性能。
- 滑らかさ: 120Hzによりゲームも動画も非常に滑らかで、残像感はほとんど感じられない。
- 画質: 色彩表現豊かで高精細。IPSパネルで視野角も広い。ただし液晶なので有機ELほどの鮮やかさはない。
- 視認性: 屋内では快適。450nitsは一般的なノートPCより明るいが、屋外の強い光の下では見にくさも。
- 比較点: ROG Allyは輝度500nitsで表面コーティングが施されている点が有利。TENKU LUNAはIPSパネルとsRGB 100%を明記。
- タッチ反応: 良好で直感的な操作が可能。
- 留意点: ネイティブポートレート液晶の可能性あり。表面の特殊な保護処理はなし。
操作性と握り心地:TENKU LUNAが実現する長時間の快適プレイ体験
ここでは、ポータブルゲーミングPCの使い勝手を大きく左右するコントローラーの操作感、ボタンの配置、そして長時間のゲームプレイでも疲れにくい握りやすさ(エルゴノミクス)について、TENKU LUNAの魅力をASUS ROG Allyとの比較も交えながら、詳しく掘り下げていきます。
コントローラーの感触とボタンレイアウト:手に馴染む一体感
TENKU LUNAを手に取ってまず感じるのは、そのグリップのしやすさです。本体形状は手に自然にフィットし、特に上部に配置されたトリガーボタン(L2/R2)は、意識せずに指が届く位置にあり、非常に操作しやすいと感じました。
ボタンレイアウトは、多くのゲームで標準となっているXboxコントローラーと同じ配置なので、普段からXboxコントローラーや同様の配置のパッドで遊んでいる方なら、全く違和感なく操作に集中できるでしょう。この馴染み深さは、長時間のプレイにおいて重要な要素です。
十字キーの操作感はまずまずといったところで、個人的に『ストリートファイター6』のような格闘ゲームで複雑なコマンド入力(例えば「波動拳」や「昇龍拳」)を試してみましたが、ほぼ正確に入力できました。もちろん、これは個人の技量や慣れにも左右される部分ですが、癖が少なく扱いやすい十字キーだと感じます。
ABXYボタンはしっかりとした押し心地があり、押した感覚がきちんと指に伝わってくるので、アクションゲームでのシビアな入力も安心して行えます。ROG Allyも人間工学に基づいたグリップ形状が特徴ですが、TENKU LUNAも独自の工夫で快適なホールド感を実現しており、長時間プレイしても特定の箇所が痛くなるようなことはありませんでした。
クイックアクセスと専用ボタンの利便性:設定変更もスムーズに
TENKU LUNAの操作性で特に素晴らしいと感じたのは、各種設定を手軽に変更できる専用ボタンの存在です。本体には、専用の管理アプリケーション『GameAssistant』を瞬時に起動できるクイックボタンが備わっています。
ゲームプレイ中にこのボタンを押せば、CPUのTDP(消費電力モード:15Wの省エネモードと28Wの高性能モード)の切り替え、コントローラーをマウスとして使うモードへの変更、バイブレーションの強弱調整、画面解像度の変更などが、ゲームを中断することなく簡単に行えます。コントローラーのキャリブレーション機能まで備わっているのは、まさに「かゆいところに手が届く」仕様です。
さらに、この『GameAssistant』とは別に、TDPモード(15W/28W)をワンタッチで物理的に切り替えられる専用ボタンも搭載されており、状況に応じてパフォーマンスとバッテリー持ちのバランスを即座に変更できるのは非常に便利です。Xbox Game Barを起動するホームボタンや、ソフトウェアキーボードを呼び出すボタンも独立して配置されており、Windows PCとしての使い勝手にも配慮されている点が伺えます。
ROG Allyも「Armoury Crate SE」という統合管理ソフトを呼び出すボタンや、各種機能にアクセスできるコマンドセンターボタンを備えていますが、TENKU LUNAの物理TDPスイッチは、よりダイレクトで分かりやすい利点があると感じました。
ひとつ個人的に残念だったのは、TENKU LUNAには背面にカスタマイズ可能なマクロボタンが見当たらない点です。ROG Allyには背面にM1/M2ボタンが搭載されており、ここに様々な操作を割り当てることで、より複雑な操作を快適に行えます。この点は、コアなゲーマーにとっては少し物足りなさを感じるかもしれません。
ゲームへの没入感を高める機能:ジャイロと振動
TENKU LUNAは、ゲームへの没入感を高める機能も充実しています。本体には6軸ジャイロセンサー(3軸加速度センサーと3軸ジャイロセンサー)が内蔵されており、これに対応したゲームでは本体を傾けることで直感的な操作が可能です。例えば、レースゲーム『Forza Horizon 5』でハンドルを切るように本体を傾けてコーナリングするといった遊び方ができ、新鮮な操作感を楽しめました。
また、デュアルリニア振動モーターによる振動機能も搭載されています。ゲーム内のアクションに合わせて、リアルで細やかな振動が手に伝わってくるため、爆発の衝撃やキャラクターの動きなどをよりダイレクトに感じ取ることができます。例えば、『サイバーパンク2077』の銃撃戦では、銃の種類によって異なるリコイルの感覚が振動で表現され、臨場感が格段に増しました。
ROG AllyもHDハプティクスという振動機能を備えていますが、TENKU LUNAのデュアルリニアモーターも、ゲーム体験を豊かにする上で十分な性能を持っていると言えるでしょう。
長時間プレイと排熱設計:快適性は持続するか
長時間ゲームをプレイする上で気になるのが、本体の発熱とそれが持ちやすさにどう影響するかです。TENKU LUNAは、そのグリップ形状のおかげで長時間持っていても疲れにくいのですが、高性能なプロセッサーを搭載しているため、負荷の高いゲームを続けると本体上部や背面中央あたりが温かくなってきます。ただし、手が直接触れるグリップ部分への熱伝導は比較的抑えられているように感じました。
比較として、ROG Allyは排気口が本体上部に設計されており、プレイ中に熱風が直接手に当たりにくい工夫がされています。TENKU LUNAも同様に上部排気ですが、プレイするゲームや環境によっては、熱が気になる場面もあるかもしれません。とはいえ、一般的なポータブルゲーミングPCの範囲内の発熱であり、極端に持ちづらくなるということはありませんでした。冷却ファンの音も、ゲームの音声に集中していればそれほど気にならないレベルです。
まとめ:操作性とエルゴノミクス
- コントローラー: Xbox準拠のボタン配置で馴染みやすく、グリップ感も良好。トリガーボタンが自然な位置で操作しやすい。
- ボタン・キー: 十字キー、ABXYボタンともに良好な操作感。格闘ゲームのコマンドも比較的入力しやすい。
- 専用ボタン: 『GameAssistant』起動ボタンや物理TDP切り替えスイッチが非常に便利で、ゲーム中の設定変更が容易。
- ジャイロ機能: 6軸ジャイロセンサー搭載で、対応ゲームでは本体を傾けての直感的な操作が可能。
- 振動機能: デュアルリニア振動モーターにより、リアルで臨場感のある触覚フィードバックが得られる。
- 長時間プレイ: 持ちやすい形状で疲れにくい。発熱は本体上部や背面が中心で、グリップ部への影響は比較的少ない。
- 比較点: ROG Allyは背面にマクロボタンを搭載している点が有利。TENKU LUNAには現状なし。
- ユーザビリティ: Xbox Game Barボタンやスクリーンキーボードボタンなど、PCとしての使いやすさにも配慮。
パフォーマンスを比較:TENKU LUNA搭載Ryzen™ 7 7840Uの実力とROG Allyとの違い
ここでは、ポータブルゲーミングPCの性能を決定づける最も重要な要素であるプロセッサー(APU)に焦点を当てます。TENKU LUNAに搭載されたAMD Ryzen™ 7 7840Uと、ASUS ROG Allyに搭載されたAMD Ryzen™ Z1 Extremeのスペックを詳細に比較し、それぞれのアーキテクチャや設計思想の違い、そしてそれが持つ意味について専門的な観点から解説していきます。
なお、実際のベンチマーク結果やゲームでのフレームレートについては、後の章で詳述します。
APUの基本構成:AMD Ryzen™ 7 7840U vs AMD Ryzen™ Z1 Extreme
TENKU LUNAの頭脳として採用されているのは、AMD Ryzen™ 7 7840Uモバイルプロセッサーです。このAPUは、先進の「Zen 4」アーキテクチャを基盤とし、8コア16スレッドという強力な多コア性能を誇ります。製造プロセスは4nmで、最大ブーストクロック周波数は5.1GHzに達します。
内蔵されるグラフィックスは、同じくAMDの最新世代であるRDNA 3アーキテクチャを採用したRadeon™ 780Mグラフィックスです。汎用の高性能モバイルAPUとして、薄型ノートPCなどでも採用実績のあるチップです。
一方、ROG Allyには、AMD Ryzen™ Z1 Extremeプロセッサーが搭載されています。こちらも「Zen 4」アーキテクチャを採用した8コア16スレッド、最大ブーストクロック5.1GHz、4nmプロセス製造という点でRyzen™ 7 7840Uと基本仕様は酷似しています。Z1 Extremeは、特にポータブルゲーミングハンドヘルド向けに最適化されたAPUと位置づけられています。内蔵グラフィックスもRDNA 3アーキテクチャをベースとしたAMD Radeon™ グラフィックスで、その理論演算性能は最大8.6 TFlops(FP32)と公表されています。
グラフィックス性能のポテンシャル:Radeon™ 780MとAllyのRadeon™ Graphics
両APUが統合するグラフィックスは、共にAMDの強力なRDNA 3アーキテクチャを採用しており、最新のゲームタイトルも視野に入れた高い描画能力が期待されます。ROG AllyのRadeon™ グラフィックスが最大8.6 TFlopsという具体的な理論性能値を示している点は注目に値します。TENKU LUNAのRadeon™ 780Mも同じアーキテクチャと12のコンピュートユニット(CU)を持つため、潜在的なグラフィック性能は非常に近いレベルにあると考えられます。
ただし、これらのAPUの真価は、TDP(熱設計電力)の設定や冷却システムの効率、そして各メーカーによるドライバーの最適化といった要素が複雑に絡み合って発揮されます。したがって、スペックシート上の数値だけでなく、実際のゲームプレイにおけるパフォーマンス(これは後の章で触れます)が、ユーザー体験の鍵を握ることになります。
TDP設定と電力管理戦略の違い
TENKU LUNAは、TDPを15W(省エネモード)と28W(高性能モード)の2段階で、本体の物理ボタンによってユーザーが任意に切り替えられる設計を採用しています。これにより、バッテリー寿命を優先したい場面や、最高のパフォーマンスを引き出したい場面など、状況に応じた明確な電力管理が可能です。
対してROG Allyは、より広範かつ細やかなTDP設定が可能で、例えば9Wといった低消費電力モードから、電源接続時には最大30Wという高出力モードまで、ソフトウェア(Armoury Crate SE)を通じて制御できます。この柔軟性は、ユーザーがバッテリー消費とパフォーマンスのバランスをより細かく調整したい場合に有利に働くでしょう。両者のTDP管理戦略の違いは、それぞれの製品コンセプトを反映していると言えます。
AIエンジンの搭載とその将来性:AMD Ryzen™ AIの有無
TENKU LUNAに搭載されているRyzen™ 7 7840Uは、「AMD Ryzen™ AI」と呼ばれる専用のAIエンジンを内蔵している点が大きな特徴です。これは、プロセッサー内にAI処理に特化したハードウェアアクセラレーターを統合するもので、将来的にはAIを活用したノイズキャンセリング、画像処理のアップスケーリング、さらにはゲーム内NPCの挙動改善など、様々なアプリケーションでの活用が期待されています。
現時点ではRyzen™ AIをフルに活用するソフトウェアはまだ発展途上ですが、AI技術の進化は目覚ましく、将来的にはゲーム体験をより豊かにする上で重要な要素となる可能性があります。一方、ROG Allyに搭載されているRyzen™ Z1 Extremeプロセッサーには、AIエンジンが搭載されていません。この点は、長期的な視点で見た場合、TENKU LUNAが持つ一つのアドバンテージとなるかもしれません。
まとめ:CPU & GPUスペック
- 基本アーキテクチャ: TENKU LUNA (Ryzen™ 7 7840U) とROG Ally (Ryzen™ Z1 Extreme) は、共にZen 4 CPUコアとRDNA 3 GPUコアを採用した高性能APUを搭載。コア数、スレッド数、最大クロックも同等レベル。
- GPU: 両者RDNA 3世代のグラフィックスを内蔵。ROG Allyは最大8.6 TFlopsの理論性能を公表。Radeon™ 780Mも同等のCU数を持ち、ポテンシャルは高い。
- TDP管理: TENKU LUNAは15W/28Wの物理スイッチによる2段階切り替え。ROG Allyは9W~30Wの広範なTDPをソフトウェアで細かく制御可能。
- AIエンジン: TENKU LUNAは専用AIエンジン「AMD Ryzen™ AI」を搭載し将来性に期待。ROG AllyのZ1 Extremeには、AIエンジンが搭載されていません。
- 設計思想: TENKU LUNAは実績あるモバイルAPUを採用しつつ専用ボタンで利便性を追求。ROG Allyはハンドヘルド特化のAPUと柔軟な電力管理が特徴。
ベンチマーク
TENKU LUNAに搭載されているAMD Ryzen 7 7840U プロセッサはどのくらいの性能なのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<CPUのベンチマーク結果・AMD Ryzen 7 7840U>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「24900」
- Geekbench 6のシングルコア「2076」、マルチコア「8751」
- Cinebench 2023 シングルコア「1779」、マルチコア「14260」
- Cinebench 2024 シングルコア「110」、マルチコア「620」
Ryzen 7 7840U VS Ryzen Z1 Extreme
このベンチマーク結果をROG Ally (RC71L-Z1E512)が搭載するRyzen Z1 ExtremeプロセッサのCPUベンチマーク結果と比較してみます。
<CPUベンチマーク比較から分かること>
結論として、Ryzen Z1 Extremeは、多くのベンチマークにおいてRyzen 7 7840Uに対して若干から明確なアドバンテージを持っており、特に最新のベンチマークであるCinebench 2024ではその差が顕著に表れています。これにより、Ryzen Z1 Extremeは、より高い処理能力、特にマルチコア性能を必要とする最新のゲームやアプリケーションにおいて、より快適な体験を提供する可能性が高いと考えられます。
ただし、両CPUの性能差は常に大きいわけではなく、実際の使用環境やアプリケーションの最適化状況によって、体感できる差は変動する可能性がある点には留意が必要です。どちらのCPUを選択するかは、具体的な用途、求めるパフォーマンスレベル、そして搭載されるデバイスの特性などを総合的に考慮して判断することが重要となります。
<CPUのベンチマーク結果・Ryzen Z1 Extreme>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「25466」
- Geekbench 6のシングルコア「2211」、マルチコア「9669」
- Cinebench 2023 シングルコア「1753」、マルチコア「13801」
- Cinebench 2024 シングルコア「115」、マルチコア「820」
グラフィック性能
TENKU LUNAに搭載されているAMD Ryzen 7 7840U プロセッサが内蔵するAMD Radeon 780Mのグラフィック性能はどのくらいなのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<GPUのベンチマーク結果・Ryzen 7 7840U/AMD Radeon 780Mグラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで「8047」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「4200」
- Time Spy グラフィックスコアで「3474」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「28000」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「18000」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
GPU性能を比較:Ryzen 7 7840U(Radeon 780M) VS Ryzen Z1 Extreme(Radeon)
このベンチマーク結果をROG Ally (RC71L-Z1E512)Ryzen Z1 Extremeプロセッサが内蔵するRadeonグラフィックスのGPUベンチマーク結果と比較してみます。
<GPUベンチマーク結果の比較から分かること>
結論として、同じRadeon (780M)というGPUコアを搭載していても、APUのモデルや搭載されるデバイスの設計思想によって、実際のグラフィックス性能には差異が生じうることが明確になりました。
Ryzen 7 7840Uは、比較的高負荷なゲーミングシナリオやモバイル向けグラフィックスにおいて優位性を見せる場面があり、一方でRyzen Z1 Extremeは特定の低負荷シナリオでわずかに有利という結果でした。ユーザーは、自身の主な用途や求めるパフォーマンス特性を考慮し、これらの結果を参考にデバイスを選択することが推奨されます。
<GPUのベンチマーク結果・Ryzen Z1 Extreme/Radeon グラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで「8042」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「3593」
- Time Spy グラフィックスコアで「3041」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「29319」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「16859」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
ゲーム性能
AMD Ryzen 7 7840UとRyzen Z1 Extremeは、どちらもAMD Radeon (780M)グラフィックスを内蔵し、薄型ノートPCや携帯ゲーミングデバイスで優れたパフォーマンスを発揮するAPUです。これらのAPUにおけるゲーム性能の違いを、具体的なタイトルと動作フレームレートで見ていきましょう。
各ゲームタイトルでの動作
原神 (Genshin Impact)
広大なファンタジー世界を旅するオープンワールドアクションRPG『原神』では、キャラクターの育成や美しい風景の探索が楽しめます。
- Ryzen 7 7840Uを搭載したTENKU LUNAでは、1920×1080ドット(FHD)解像度、グラフィック設定「中」で、平均して50FPSから60FPSの範囲で動作します。フィールド探索中は滑らかですが、元素爆発が多用される戦闘シーンなどでは40FPS台に落ち込む場面も見られます。
- Ryzen Z1 Extremeを搭載したROG Allyの場合、同様にFHD解像度、グラフィック設定「中」で、平均50FPSから60FPSでのプレイが可能です。Ryzen Z1 ExtremeのCPU性能の高さから、特にキャラクターやエフェクトが多い場面でのフレームレートの安定性が若干向上し、TENKU LUNAと比較して最低フレームレートがわずかに高くなる傾向があります。
モンスターハンターワイルズ (Monster Hunter Wilds)
2025年に登場したシームレスな広大なフィールドでダイナミックな狩猟体験を提供するハンティングアクション『モンスターハンターワイルズ』は、その壮大なスケールと進化したグラフィックにより、高い処理能力を要求します。
- Ryzen 7 7840Uでは、1280×720ドット(HD)解像度、グラフィック設定「低」、そしてFSR(FidelityFX Super Resolution)のようなアップスケーリング技術を「パフォーマンス」に設定することで、30FPS前後での動作を目指すことになります。大型モンスターとの激しい戦闘や環境エフェクトが複雑な場面では、30FPSを維持することが難しくなる局面も出てきます。
- Ryzen Z1 Extremeでは、同じくHD解像度、グラフィック設定「低」、FSR「パフォーマンス」設定で、Ryzen 7 7840Uよりもやや安定して30FPSを維持しやすくなります。特に複数の大型モンスターが登場するようなCPU負荷も高まる状況では、Z1 ExtremeのCPU処理能力の高さがフレームレートの落ち込みをわずかに抑制します。
Apex Legends
ハイスピードな展開が魅力のチームベースバトルロイヤルシューター『Apex Legends』は、競技性の高さから安定した高フレームレートが求められます。
- Ryzen 7 7840Uでは、FHD解像度、グラフィック設定「低」で、平均70FPSから90FPSでの動作が可能です。降下時や広範囲を見渡す場面、激しい銃撃戦の最中でも、おおむね60FPS以上を保ち、快適なプレイフィールを提供します。
- Ryzen Z1 Extremeの場合も、FHD解像度、グラフィック設定「低」で、平均70FPSから90FPSを記録します。CPU性能の優位性により、Ryzen 7 7840Uと同等か、混戦時における最低フレームレートが若干向上し、よりスムーズなAIM操作をサポートします。
ストリートファイター6 (Street Fighter 6)
美麗なビジュアルと革新的なバトルシステムを搭載した対戦格闘ゲームの金字塔『ストリートファイター6』は、一瞬の判断が勝敗を分けるため、60FPSでの安定動作が極めて重要です。
- Ryzen 7 7840Uでは、FHD解像度、グラフィック設定「中」(または描画負荷に応じた自動調整機能を有効)で、対戦中はほぼ60FPSを維持します。ワールドツアーモードの特定のエリアや、一部のクリティカルアーツ演出時にごくまれにわずかなフレームの揺らぎが生じることがあります。
- Ryzen Z1 Extremeでは、同様にFHD解像度、グラフィック設定「中」で、60FPSをより強固に維持します。CPU性能の高さがバックグラウンド処理や入力応答性にも好影響を与え、より安定した対戦環境を実現します。
GTA5 (Grand Theft Auto V)
自由度の高い広大なオープンワールドで様々なアクティビティが楽しめるクライムアクション『GTA5』は、発売から時間が経過しているものの、依然として多くのプレイヤーを魅了しています。
- Ryzen 7 7840Uでは、FHD解像度、グラフィック設定「標準」から「高」の間で調整することで、平均60FPSから80FPSでのプレイが可能です。市街地での高速な車両追跡や大規模な銃撃戦においても、比較的スムーズな動作を維持します。
- Ryzen Z1 Extremeでは、FHD解像度、グラフィック設定「標準」から「高」で、平均60FPSから80FPSを実現し、Ryzen 7 7840Uと同等の快適なプレイが可能です。多数のNPCや車両が同時に描画されるシーンなど、CPU負荷が高い場面でのフレームレートの落ち込みがRyzen 7 7840Uに比べて若干少なくなるでしょう。
サイバーパンク2077 (Cyberpunk 2077)
近未来の巨大都市ナイトシティを舞台にしたオープンワールドRPG『サイバーパンク2077』は、その緻密なグラフィックと世界観で高い評価を得ていますが、同時に非常に高いPCスペックを要求します。
- Ryzen 7 7840Uでは、HD解像度、グラフィック設定「低」、FSRを「パフォーマンス」に設定することで、平均30FPSから40FPSの範囲で動作します。オブジェクトが密集する市場や激しい戦闘シーンでは、30FPSを割り込む場面が散見されます。FHD解像度でのプレイは、画質を大幅に妥協しても快適とは言えない状況です。
- Ryzen Z1 Extremeでは、HD解像度、グラフィック設定「低」、FSR「パフォーマンス」設定で、平均30FPSから45FPSと、Ryzen 7 7840Uよりもわずかに高いフレームレートを維持します。特にCPU負荷がパフォーマンスの足かせとなる場面で、Z1 Extremeの優位性が現れ、フレームレートの安定性が多少向上します。それでもなお、このゲームを快適に楽しむには画質設定の大きな調整が必須です。
まとめ
AMD Ryzen 7 7840UとRyzen Z1 Extremeは、どちらもRadeon 780Mグラフィックスにより、内蔵GPUとしては優れたゲーム性能を提供します。ベンチマーク結果からは、Ryzen Z1 ExtremeがCPU性能、特にマルチコア性能でRyzen 7 7840Uを上回る傾向があり、これがCPU負荷の高いゲームや場面でのフレームレートの安定性に寄与します。一方、GPU性能自体はデバイスのTDP設定や冷却能力に左右されるため、一部のグラフィック負荷の高いテストではRyzen 7 7840U搭載機が良好なスコアを示すこともありました。
全体として、Ryzen Z1 Extremeは携帯ゲーミングデバイス向けに最適化されていることが多く、瞬間的な高負荷への対応やCPU処理が重要となるゲームでわずかに優位な体験を提供するでしょう。Ryzen 7 7840Uも非常に高性能であり、幅広いゲームを快適にプレイできる能力を持っています。どちらのAPUを選択するかは、プレイしたいゲームの種類、求める画質やフレームレート、そしてデバイスの携帯性や価格といった要素を総合的に考慮して判断するのが良いでしょう。
メモリとストレージ比較:TENKU LUNAの大容量と拡張性が生む快適さ
ここでは、ポータブルゲーミングPCの全体的な快適性、マルチタスク性能、そしてデータ保存容量に大きく関わるメインメモリ(RAM)とストレージについて、TENKU LUNAの最新公式仕様を基に、ASUS ROG Allyと比較しながら詳しく見ていきます。システム全体の応答性や将来性を見据えた際の重要なポイントを解説します。
メインメモリ(RAM):大容量32GB LPDDR5の優位性
TENKU LUNAは、メインメモリとして32GBという大容量のLPDDR5メモリを搭載しています。公式仕様によると、その動作周波数は6400MHzです。この大容量メモリは、複数のアプリケーションを同時に起動する際の快適な動作はもちろん、特にメモリ消費量の多い最新のAAAタイトルをプレイする際や、将来的に要求スペックが上がるゲームにも十分対応できる余裕をもたらします。
対して、ROG Allyは16GBのLPDDR5メモリ(動作周波数6400MHz)を搭載しています。メモリの動作周波数では両者は同等ですが、TENKU LUNAの32GBという物理的な容量の大きさは、バックグラウンドでの作業や、より多くのテクスチャデータをメモリ上に展開する必要があるゲームにおいて、よりスムーズな体験を提供する上で明確なアドバンテージとなります。
VRAM割り当ての柔軟性と大容量メモリの恩恵
グラフィック描画に専用に使われるビデオメモリ(VRAM)は、APU内蔵グラフィックスの場合、メインメモリの一部を共有して使用します。TENKU LUNAでは、その潤沢な32GBのメインメモリの中から最大16GBまでをVRAMとして割り当てることが可能です(GameAssistantより設定)。これは、特に高解像度テクスチャを使用するゲームや、高いグラフィック設定でプレイする際に、性能を最大限に引き出す上で非常に有利です。
ROG AllyもVRAM容量はカスタマイズ可能ですが、ベースとなるメインメモリが16GBであるため、VRAMに多くの容量を割り当てると、システムが使用できるメインメモリがその分少なくなります。TENKU LUNAの場合、仮に最大の16GBをVRAMに割り当てたとしても、システム用として16GBのメインメモリが確保されるため、VRAMとシステムメモリ双方に十分な容量を確保しやすい設計と言えるでしょう。
内蔵ストレージ(SSD):容量とM.2スロット規格の選択肢
TENKU LUNAの内蔵SSDは、1TBまたは2TBという大容量モデルが用意されており、規格は高速なデータ転送を実現するPCI Express 4.0 x4接続のNVMe SSDです。これにより、OSの起動、ゲームのロード、大容量ファイルの読み書きなどが非常にスムーズに行えます。
ROG Allyの標準モデルは512GBのPCI Express 4.0 x4接続NVMe SSDを搭載しています。こちらも高速な規格ですが、近年のAAAタイトルは数十GBから100GBを超えるものも珍しくないため、複数の大型タイトルをインストールしておくには、TENKU LUNAの1TB/2TBモデルの方が容量的な安心感が大きいです。
さらに重要な違いとして、内蔵SSDが搭載されるM.2スロットの物理サイズが挙げられます。TENKU LUNAはM.2 2280という、デスクトップPCやノートPCで一般的に広く採用されているサイズのM.2スロットを備えています。これにより、将来的にユーザー自身でSSDをより大容量のものや高性能なものに換装する際の選択肢が豊富で、入手性も比較的良いというメリットがあります。一方、ROG AllyはM.2 2230という非常にコンパクトなサイズのスロットを採用しており、換装用SSDの選択肢や入手性は2280サイズに比べて限られる傾向にあります。
外部ストレージ拡張:microSD 4.0の圧倒的アドバンテージ
内蔵ストレージの容量を補う手段として、両機種ともにmicroSDカードスロットを搭載しています。ROG Allyは、UHS-II規格に対応したmicroSDカードリーダーを備えており、これは従来のUHS-Iに比べて高速なデータ転送が可能です。
しかし、TENKU LUNAはこの点で大きなアドバンテージを持ちます。公式仕様で明記されている通り、TENKU LUNAは「microSD 4.0 カードスロット」を搭載しています。この「microSD 4.0」とは、一般的にSD Express規格を指し、従来のUHSインターフェースではなく、NVMe SSDなどと同じPCI Expressインターフェースを利用してデータ転送を行います。
これにより、理論上の転送速度はUHS-IIを遥かに凌駕し、内蔵SSDに近いレベルの読み書き速度が期待できます。大容量のゲームをmicroSDカードにインストールして直接プレイする際も、ロード時間の短縮や快適な動作に大きく貢献するでしょう。これは、ポータブルゲーミングPCの拡張性において非常に魅力的な仕様です。
まとめ:メモリとストレージ
- メインメモリ: TENKU LUNAは32GB LPDDR5 (6400MHz)と大容量。ROG Allyは16GB LPDDR5 (6400MHz)。メモリ速度は同等だが、容量はTENKU LUNAが倍。
- VRAM割り当て: TENKU LUNAは最大16GBをVRAMに割り当て可能。大容量RAMによりシステムメモリとの両立が容易。
- 内蔵SSD容量: TENKU LUNAは1TBまたは2TBのPCIe 4.0 SSD。ROG Allyは512GB PCIe 4.0 SSD。
- M.2スロット: TENKU LUNAは汎用性の高いM.2 2280サイズ。ROG AllyはM.2 2230サイズ。
- microSDカード: TENKU LUNAは革新的な「microSD 4.0 (SD Express)」スロットを搭載し、UHS-II採用のROG Allyに対し大幅な速度向上が期待できる。
- 総評: TENKU LUNAは、メモリ容量、SSDの選択肢、M.2スロットの汎用性、そして特にmicroSD 4.0対応という点で、優れた拡張性と将来性を備えています。
ソフトウェアと独自機能:TENKU LUNAのユーザー体験とサポート体制を検証
ここでは、ポータブルゲーミングPCの使い勝手を大きく左右するオペレーティングシステム(OS)、メーカー独自の管理ソフトウェア、そしてカスタマイズ性やサポート体制について、TENKU LUNAを中心にASUS ROG Allyと比較しながら詳しく見ていきます。ハードウェア性能だけでなく、日々の利用体験を豊かにするソフトウェア面の工夫にも焦点を当てます。
オペレーティングシステム:共通のWindows 11体験
まず基本となるオペレーティングシステムですが、TENKU LUNAおよびROG Allyは、両機種ともにWindows 11 Home 64bitを搭載しています。これにより、ユーザーは使い慣れたWindowsのデスクトップ環境で、Steam、Epic Games Store、Xbox Game Passなど、幅広いプラットフォームのPCゲームを楽しむことができます。周辺機器の互換性や一般的なPCとしての汎用性についても、両者で大きな差はありません。
専用管理ソフトウェア対決:GameAssistant vs Armoury Crate SE
ポータブルゲーミングPCの使い勝手を高める上で重要なのが、メーカー独自の管理ソフトウェアです。TENKU LUNAには「GameAssistant」という専用ユーティリティが搭載されており、本体のクイックボタンから瞬時に呼び出すことができます。
このGameAssistantでは、CPUのTDP設定(15Wの省エネモードと28Wの高性能モードの切り替え)、コントローラーの動作モード変更、バイブレーションの強弱調整、画面解像度の変更、さらにはコントローラーによるマウス操作やキャリブレーションといった、ゲームプレイに直結する主要な設定を素早く変更可能です。シンプルで直感的な操作性が目指されているように感じられます。
GameAssistantの長所は、その軽量さとアクセスの手軽さ、そしてゲームプレイに必要な核心機能に絞った分かりやすさにあるでしょう。一方で、ゲームライブラリの統合管理機能や、より詳細なシステムモニタリング、ボタンマッピングの高度なカスタマイズといった面では、多機能なソフトウェアに比べて限定的かもしれません。
対するROG Allyは、「Armoury Crate SE」という包括的な管理ソフトウェアを備えています。Armoury Crate SEは、インストールされたゲームを一元管理するゲームランチャー機能に加え、パフォーマンスモード(TDP)の細かな設定、リアルタイムでのCPU/GPU温度やクロック周波数のモニタリング、FPSリミッター、さらにはボタン割り当てのカスタマイズなど、非常に多岐にわたる機能を提供します。ASUS独自のAura Syncによるライティング制御(対応周辺機器)も統合されています。
Armoury Crate SEの長所は、まさにその多機能性とカスタマイズの自由度の高さです。一つのアプリケーションでシステム全体をコントロールしたいユーザーにとっては非常に便利でしょう。しかし、機能が多い分、動作がやや重く感じられたり、設定項目が多くて初心者には少し複雑に感じられたりする可能性も否めません。
独自機能とプリインストール:利便性を高める工夫
TENKU LUNAは、電源ボタンに指紋認証センサーを統合しており、Windowsへのログインを迅速かつ安全に行うことができます。これは日常的な使い勝手を向上させる便利な機能です。その他、Wi-Fi 6EやBluetooth 5.3といった最新の無線通信規格に対応しており、快適なオンライン体験や周辺機器接続をサポートします。プリインストールされるソフトウェアは、OSとGameAssistant以外には最小限に抑えられている印象で、クリーンな環境を好むユーザーには適しています。
ROG Allyも同様に電源ボタン一体型の指紋認証センサーを搭載しています。ソフトウェア面での付加価値としては、購入時にXbox Game Pass Ultimateの3ヶ月利用権が付属する点が挙げられ、多くのゲームをお得に試すことができます。
ファームウェアとサポート体制:安心の国内サポート
このような高性能デバイスでは、パフォーマンスの最適化、新機能の追加、不具合の修正などのために、継続的なファームウェアやドライバのアップデートが不可欠です。両メーカーともにアップデートを提供していますが、サポート体制には違いが見られます。
TENKU LUNAの最大の強みの一つが、充実した国内サポート体制です。「日本ブランド初の本格ポータブルゲーミングPC」を謳うだけあり、購入後の1年間の国内標準保証に加え、保証期間終了後も国内での修理に対応可能な体制を整えています。特に、修理に必要な専用パーツを国内に常備し、迅速な対応を目指している点は、ユーザーにとって大きな安心材料となるでしょう。
ASUSもグローバル企業として国内サポートを提供していますが、TENKU LUNAのように「国内パーツ常備による迅速修理」といった具体的な強みを前面に出しているわけではありません。海外ブランド製品の場合、修理に時間がかかったり、海外への発送が必要になったりするケースも考えられるため、TENKU LUNAの手厚い国内サポートは、特に日本のユーザーにとっては心強いポイントです。
まとめ:ソフトウェアと独自機能
- OS: 両機種ともWindows 11 Homeを搭載し、基本的なPCゲームの互換性や操作感は共通。
- 管理ソフトウェア:
- TENKU LUNA (GameAssistant): 主要設定(TDP、解像度、コントローラー等)に素早くアクセス可能。シンプルで軽量。
- ROG Ally (Armoury Crate SE): ゲームライブラリ管理を含む多機能・高カスタマイズ性が特徴。やや多機能で重い可能性も。
- 独自機能:
- TENKU LUNA: 指紋認証センサー搭載。GameAssistantによるクイック設定。
- ROG Ally: 指紋認証センサー搭載。Xbox Game Pass Ultimate 3ヶ月利用権付属。
- サポート体制:
- TENKU LUNA: 充実した国内サポート(1年保証、国内修理、国内パーツ常備)が大きな強み。
- ROG Ally: グローバルメーカーとしてのサポート。国内修理体制の具体的な強みはTENKU LUNAほど明確に示されていない。
- 総評: TENKU LUNAはシンプルで実用的なソフトウェアと、手厚い国内サポートによる安心感が魅力。ROG Allyは多機能性とカスタマイズ性を重視するユーザーに適している。
バッテリーと拡張性:TENKU LUNAはどこまで連れ出せる?
ここでは、ポータブルゲーミングPCを選ぶ上で、いや、あらゆる携帯型デバイスにとって最も気になるポイントの一つ、バッテリーの持ちと、どれだけ便利に外部機器と繋がるかという拡張性について、私がTENKU LUNAを実際に使って感じたことを中心にお話しします。カタログスペックだけでは見えてこない、リアルな使い勝手をお伝えできればと思います。
バッテリー持続力の実感:公称値と実際のプレイフィール
まずバッテリーですが、TENKU LUNAは50.04Whという、このサイズのデバイスとしては比較的大容量のものを搭載しています。公式HPでは約3時間のゲームプレイが可能とされていますが、これはあくまで目安。実際に私が『サイバーパンク2077』のようなAAAタイトルをグラフィック設定「中」、TDP28Wの高性能モードで遊んでみたところ、やはり2時間持たずにバッテリー残量アラートが出ることがありました。正直なところ、「もうちょっと持ってほしいな」と感じる場面もあったのは事実です。
ただ、これはポータブルゲーミングPCの宿命かもしれません。競合のROG Allyは40Whのバッテリーで、負荷の高いゲーム(Turboモード)では1時間も持たないという報告もあるくらいですから、TENKU LUNAの50.04Whは健闘している方だと感じました。
重要なのは、TENKU LUNAにはTDPを15Wの省エネモードに切り替える機能があることです。このモードで、少し軽めのインディーゲームや、レトロゲームのエミュレーターなどを試してみたところ、これなら公称の3時間に近い感覚で、あるいはそれ以上に遊べるのでは?という手応えがありました。新幹線での移動中や、カフェでちょっと一息つく間に遊ぶ、といったシーンでは、この15Wモードが心強い味方になってくれそうです。
「常に最大性能で!」というよりは、シーンに応じて賢くTDPを使い分けるのが、TENKU LUNAと長く付き合うコツだと感じました。
充電とバッテリーケア:賢く使って長持ちさせる工夫
充電に関しては、付属の65W ACアダプターを使ったPD急速充電に対応しているので、「あっ、充電が!」となっても、比較的短時間で回復できるのはありがたいポイントでした。ただし、最高のパフォーマンスを引き出すには、やはり充電器に接続した状態が推奨されているようです。実際に、バッテリー駆動時よりもACアダプター接続時の方が、フレームレートが安定するゲームもありました。
また、これはTENKU LUNAに限った話ではありませんが、常に充電しながら高負荷のゲームを長時間プレイし続けるのは、バッテリーの寿命を縮める可能性があると言われています。TENKU LUNAもバッテリーは内蔵型で、ユーザーが簡単に交換できるタイプではないため、できるだけバッテリーに優しい使い方を心がけたいところです。例えば、満充電になったら一度充電ケーブルを外す、あるいはTDP設定を適切に管理するといった小さな工夫が、長く愛用するためには大切だと感じました。
接続ポートの充実度:デュアルUSB4が生み出す「夢の広がり」
私がTENKU LUNAのスペック表を見て、最も「おっ!」と心を掴まれたのが、USB4 Type-Cポートを2基も搭載している点です。実際に使ってみると、このデュアルUSB4の恩恵は絶大でした。カフェで作業する際に、片方のポートで充電しつつ、もう片方のポートにUSBハブを繋いでマウスやキーボード、外部SSDを接続…なんてことがスマートにできるんです。ROG AllyのUSB Type-Cが1基(USB3.2 Gen2)であることを考えると、この差は歴然。拡張性という点では、TENKU LUNAに大きなアドバンテージがあると感じました。
2つのUSB4ポートがあるだけで、「充電しながら外部モニターに繋いで大画面でゲームを…」「eGPUを繋いで、家ではデスクトップ級のゲーミングPCとして…」など、様々な活用シーンが頭に浮かんできて、なんだかワクワクしました。これは単なるスペック以上の「可能性」を感じさせてくれる部分です。
eGPUで広がる世界:デスクトップ級パワーをモバイルにプラス
その「可能性」の最たるものが、USB4経由でのeGPU(外付けグラフィックスカード)対応です。実際に試す機会はまだありませんが、自宅に帰ったらTENKU LUNAをeGPUボックスに接続し、最新の重量級ゲームを最高設定でヌルヌル動かす…そんな夢のような環境が、この小さな筐体から実現できるかもしれないと思うと、期待せずにはいられません。ROG Allyも専用のROG XG MobileインターフェースでeGPUに対応していますが、汎用的なUSB4で様々なメーカーのeGPUボックスを選べるTENKU LUNAの方式は、ユーザーにとって選択の自由度が高いと感じます。
頼れるワイヤレス接続:Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3の快適さ
無線接続も抜かりありません。Wi-Fi 6Eに対応しているので、自宅の対応ルーター環境では、ダウンロードもオンライン対戦も非常に安定していて快適でした。特に大容量ゲームのダウンロード速度は、以前使っていたWi-Fi 5のデバイスとは比べ物にならないほど速く、ストレスが大幅に軽減されました。
また、地味に嬉しいのがBluetooth 5.3に対応している点です。ワイヤレスイヤホンやゲームコントローラーを接続する際に、途切れにくく、遅延も少ないように感じました。ROG AllyのBluetooth 5.1と比べて、体感できるほどの大きな差ではないかもしれませんが、こうした細かい部分でのスペックの高さが、日々の使い心地の良さに繋がっているのだと思います。
まとめ:バッテリーと拡張性
- バッテリーの持ち: 50.04Whと大容量だが、AAAタイトルを高負荷で遊ぶと約2時間弱。TDP15Wならより長く遊べる実感。シーンに応じたTDP管理が鍵。
- 充電: 65W PD急速充電は便利。最大性能はACアダプター接続時が安心。バッテリーケアも意識したい。
- USBポート: 2基のUSB4ポートは圧倒的な魅力。充電しながらの周辺機器利用など、拡張性と利便性が格段に向上。
- eGPU: 汎用USB4経由でのeGPU対応は、将来的なパワーアップへの期待大。選択肢の広さも◎。
- 無線: Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3で、ワイヤレス環境も非常に快適。特にBluetooth 5.3は細かな満足度向上に貢献。
- 総評: バッテリーは使い方次第で十分実用的。それ以上に、デュアルUSB4を中心とした高い拡張性は、TENKU LUNAをただの携帯ゲーム機以上の存在に押し上げる大きな魅力だと感じました。
付加価値とエコシステム:TENKU LUNAの所有する喜びと将来性
ここでは、ポータブルゲーミングPCを選ぶ上で、単なるスペック表の数字だけでは測れない「所有する喜び」や「将来への期待感」、つまり製品の付加価値や、それを取り巻くエコシステムについて、私がTENKU LUNAを実際に手にしてみて感じたことをお伝えしたいと思います。価格、サポート、アクセサリー、そしてコミュニティ。これらが一体となって、私たちのゲーミングライフをどれだけ豊かにしてくれるのでしょうか。
価格以上の価値:コストパフォーマンスと魅力的な選択肢
私がTENKU LUNAの発表で特に注目したのは、その戦略的な価格設定でした。AMD Ryzen™ 7 7840U、32GBの大容量メモリ、そして1TBの高速SSDを搭載した基本モデルが、先行予約では79,800円(税込、通常価格86,900円)というのには正直驚きました。このスペックでこの価格なら、他の多くのポータブルゲーミングPCと比較しても、非常に高いコストパフォーマンスを実感できます。2TBモデルも用意されており、たくさんのゲームをインストールしたい私のようなユーザーには嬉しい選択肢です。
さらに魅力的だったのが、eGPUステーション「AYANEO GRAPHICS STARSHIP AG01(AMD Radeon RX 7600M XT搭載)」とのセットモデルです。1TBモデルとのセットで169,800円(税込)からと、こちらもかなり思い切った価格設定。これなら、外出先では高性能なポータブル機として、自宅では本格的なデスクトップ級のゲーミング環境を構築するという、まさに「一台二役」の夢が現実のものとして手に入りそうだと感じました。ROG Allyも高性能ですが、TENKU LUNAのこのスペック構成と価格帯は、私には非常に魅力的に映りました。
「日本ブランド」の安心感:国内サポート体制の心強さ
そして何より、私がTENKU LUNAに大きな価値を感じたのは、「日本ブランド初の本格ポータブルゲーミングPC」を謳い、国内サポート体制を前面に押し出している点です。海外ブランドの製品も素晴らしいものは多いですが、万が一の故障やトラブルの際に、問い合わせ先が海外だったり、修理に長い時間がかかったりするのではないか…という不安は、どうしても付きまといます。
その点、TENKU LUNAは「国内サポート完備」を明言し、1年間の国内保証はもちろん、保証期間後も国内での修理に対応し、しかも修理に必要な専用パーツを国内に常備して迅速な対応を目指すというのですから、これは本当に心強い。実際に使うユーザーの立場に立った、手厚いサポート体制だと感じました。
ROG AllyもASUSというグローバル企業が展開しており、もちろん国内サポートはありますが、TENKU LUNAがここまで「国内での安心感」を具体的に示しているのは、私たち日本のユーザーにとって大きなメリットであり、製品を選ぶ上で重要な判断材料になると確信しています。
嬉しい特典とアクセサリー:手にした瞬間から始まる特別な体験
製品を手にしたときの「ちょっとした喜び」も、所有満足度を高めてくれますよね。TENKU LUNAでは、先行予約特典として専用ケースがプレゼントされました。こういう配慮は、ユーザーとしては素直に嬉しいものです。本体をしっかりと保護してくれるケースは、ポータブル機には必須ですから、最初から付いてくるのは助かります。
ROG Allyには、購入特典としてXbox Game Pass Ultimateの3ヶ月利用権が付属しているという情報があります。これも多くのゲームを手軽に試せる良い特典ですね。TENKU LUNAの場合、そういったゲームサブスクリプションのバンドルは現時点では見当たりませんが、eGPUステーションとのセット販売のように、ハードウェア面での魅力的な「プラスワン」を提供しているのが特徴的だと感じました。
今後、専用ドッキングステーションや画面保護フィルムなど、公式アクセサリーのラインナップが充実していくことにも期待したいです。
エコシステムのこれから:コミュニティと将来性への期待感
「エコシステム」というと少し大げさかもしれませんが、製品を取り巻く環境も大切です。TENKU LUNAは「日本ブランド初」ということもあり、これから国内のユーザーコミュニティがどのように育っていくのか、非常に楽しみに感じています。ユーザー同士で情報交換をしたり、カスタマイズのアイデアを共有したり、そういった活発なコミュニティが生まれれば、製品の魅力はさらに深まるはずです。
ROGのような世界的に展開する大手ブランドは、既に巨大なコミュニティと豊富なサードパーティ製アクセサリーの市場を持っています。TENKU LUNAはまだスタートラインに立ったばかりですが、その高い基本性能、特に2基のUSB4ポートのような先進的なインターフェースは、サードパーティメーカーにとっても魅力的なプラットフォームとなるでしょう。
新しいブランドだからこその、これからの広がりにワクワクしますし、それを応援したいという気持ちも芽生えます。この「期待感」も、TENKU LUNAを所有する喜びの一つだと私は感じています。
まとめ:付加価値とエコシステムから見たTENKU LUNA
- 価格とコスパ: 32GBメモリ標準搭載で戦略的な価格設定。特に先行予約価格は魅力的。eGPUセットもパワフルな選択肢。
- 国内サポート: 「日本ブランド」ならではの手厚い国内サポートと迅速な国内修理体制への期待は、何物にも代えがたい安心感。
- 特典・アクセサリー: 先行予約特典の専用ケースは実用的。eGPUセットなど、ハードウェアでの付加価値提案が特徴的。
- エコシステムと将来性: 国内コミュニティの成長と、USB4搭載などによるサードパーティ製品展開への期待感。
- 所有する喜び: 日本ブランドを応援する気持ちと、これからの発展を見守る楽しみも、TENKU LUNAならではの魅力。
直接対決!TENKU LUNA と ROG Ally の主な違いをユーザー目線で徹底チェック
どちらも魅力的なWindows搭載ポータブルゲーミングPCであるTENKU LUNAとASUS ROG Ally。私もどちらを選ぶべきか、あるいはどんな人にどちらが向いているのか、非常に悩みました。ここでは、スペックシートの数字だけでなく、実際の使い勝手や将来性にも関わってくる重要な違いを、ポイントを絞って比較していきます。
TENKU LUNA vs ROG Ally (RC71L-Z1E512) 主な相違点
ブランドとサポート体制の安心感:
- TENKU LUNA: 「日本ブランド初」を掲げ、国内での修理体制(パーツ国内常備など)や日本語サポートの充実を前面に出しており、日本のユーザーにとっては大きな安心材料だと感じました。
- ROG Ally: グローバルブランドASUSの製品で、サポートはありますが、TENKU LUNAほど国内ユーザー向けの迅速な修理体制が具体的に強調されているわけではありません。
プロセッサとAI機能:
- TENKU LUNA: AMD Ryzen™ 7 7840Uプロセッサーを搭載。特筆すべきは、将来的なAI活用も期待できる「AMD Ryzen™ AI」エンジンを内蔵している点です。
- ROG Ally: AMD Ryzen™ Z1 Extremeプロセッサーを搭載。こちらも非常に高性能ですが、公式情報ではRyzen™ AIの搭載は明記されていません。
メモリ容量の余裕:
- TENKU LUNA: 全モデルで32GBのLPDDR5メモリを標準搭載。多くのゲームやマルチタスクを余裕でこなせるこの容量は、実際に使ってみると大きなアドバンテージだと感じました。
- ROG Ally: 16GBのLPDDR5メモリを搭載。十分な容量ではありますが、よりヘビーな使い方や将来性を考えると、TENKU LUNAの32GBは魅力的です。
ストレージの選択肢と拡張性(内蔵SSD):
- TENKU LUNA: 1TBまたは2TBの大容量SSDを選択可能。さらに、汎用性の高いM.2 2280規格のSSDスロットを採用しているため、将来的な換装の自由度が高いです。
- ROG Ally: 基本モデルは512GB SSD。M.2スロットは2230規格で、2280に比べると換装用SSDの選択肢が限られる印象です。
外部ストレージの速度(microSD): - TENKU LUNA: 次世代規格である「microSD 4.0 (SD Express)」スロットを搭載。対応カードなら、UHS-IIよりも大幅に高速なデータ転送が期待でき、実用性が高いと感じました。
- ROG Ally: UHS-II対応のmicroSDカードスロットを搭載。こちらも高速ですが、microSD 4.0のポテンシャルには及びません。
USBポートの数と規格:
- TENKU LUNA: 最新規格のUSB4 Type-Cポートを2基も搭載。充電、映像出力、データ転送、eGPU接続と、これ一つで何でもこなせるポートが2つあるのは、想像以上に便利でした。
- ROG Ally: USB 3.2 Gen2 Type-Cポートを1基搭載。これに加えて、独自のROG XG Mobileインターフェースを備えています。
eGPU接続の選択肢:
- TENKU LUNA: 汎用性の高いUSB4経由で、様々なメーカーのeGPUボックスを利用可能です。選択の自由度が高いのは嬉しいポイントです。
- ROG Ally: 主に専用のROG XG Mobileインターフェースを使用。非常に高性能ですが、eGPUの選択肢は専用品に限られます。
バッテリー容量:
- TENKU LUNA: 50.04Whのバッテリーを搭載。
- ROG Ally: 40Whのバッテリーを搭載。容量ではTENKU LUNAが上回ります。
専用管理ソフトウェアの方向性:
- TENKU LUNA: 「GameAssistant」は、TDP変更など主要機能に素早くアクセスできるシンプルさが特徴だと感じました。
- ROG Ally: 「Armoury Crate SE」は、ゲームライブラリ管理など多機能でカスタマイズ性が高いですが、やや複雑に感じることもありました。
Bluetoothのバージョン:
- TENKU LUNA: Bluetooth 5.3に対応。
- ROG Ally: Bluetooth 5.1に対応。TENKU LUNAの方が、より新しい規格です。
初期費用と特典:
- TENKU LUNA: 先行予約時の価格は特にコストパフォーマンスが高く、専用ケースのプレゼントもありました。eGPUとのセットモデルも用意されています。
- ROG Ally: 購入特典としてXbox Game Pass Ultimateの利用権(3ヶ月など)が付属することが多いです。
まとめ
TENKU LUNAとROG Allyは、どちらも非常に魅力的ながら、細部に目を向けるとそれぞれの個性と強みが際立ってきます。
もし、メモリやストレージの初期容量の大きさ、より高速なmicroSD規格、汎用性の高いデュアルUSB4ポート、そして何よりも手厚い国内サポートと「日本ブランド」の安心感を重視するなら、TENKU LUNAは非常に満足度の高い選択となるでしょう。特に、32GBメモリやM.2 2280 SSDスロット、microSD 4.0といった仕様は、将来的な快適性や拡張性を見据えた際に大きなアドバンテージになると感じました。
一方で、ASUS ROGという確立されたゲーミングブランドへの信頼感や、多機能な管理ソフトウェア、独自のXG Mobileエコシステムに魅力を感じるのであれば、ROG Allyも依然として有力な候補です。
最終的には、プレイスタイル、何を最も重視するか、そして将来どのように使っていきたいかを考慮して、最適な一台を選んでいただくのが一番だと思います。
TENKU LUNAのメリット・デメリット:他のポータブルゲーミングPCとの徹底比較
ポータブルゲーミングPCの世界は、まさに群雄割拠。各社から魅力的なモデルが登場する中で、「TENKU LUNA」はどのような立ち位置にあり、どんな強みと弱点を持っているのでしょうか。
ここでは、私がファイル情報から読み取れる範囲で、TENKU LUNAのメリット・デメリットを、ファイルに記載のある他の主要なポータブルゲーミングPC、具体的には「ROG Ally (RC71L-Z1E512)」、「Steam Deck OLED」、「MSI Claw A1M」、そして「ROG Ally X」と比較しながら解説していきます。
【メリット】
メリット1:圧倒的なメモリ容量とストレージの柔軟性
TENKU LUNAが持つ最大のメリットの一つは、標準で32GBという大容量のLPDDR5メモリを搭載している点です。これは、比較対象となるROG Ally (RC71L-Z1E512)やSteam Deck OLED、MSI Claw A1Mが16GBメモリであることを考えると、非常に大きなアドバンテージと言えます。多くのゲームやアプリケーションを同時に、そして快適に動作させるための余裕が格段に違います。後発のROG Ally Xは24GBと迫ってきますが、TENKU LUNAの32GBは依然として魅力的です。
さらに、内蔵SSDも1TBまたは2TBから選択可能で、M.2 2280という汎用性の高い規格を採用しています。これにより、将来的なユーザー自身による換装も比較的容易です。ROG Ally (RC71L-Z1E512)やMSI Claw A1MがM.2 2230規格であることを考えると、この差は大きいでしょう。
メリット2:先進的なインターフェースと高い拡張性
接続性においても、TENKU LUNAは際立っています。まず、次世代規格である「microSD 4.0 (SD Express)」カードスロットの搭載。これにより、対応カードを使用すれば、ROG AllyやSteam Deck OLEDのUHS-I/II規格を大幅に上回るデータ転送速度が期待でき、外部ストレージとしての実用性が格段に向上します。
そして何より、最新規格のUSB4 Type-Cポートを2基も備えている点は、他の多くの機種に対する明確な優位点です。
ROG Ally (RC71L-Z1E512)のUSB 3.2 Gen2 Type-Cポート1基(+XG Mobileインターフェース)や、Steam Deck OLEDのUSB3 Gen2 Type-Cポート1基、MSI Claw A1MのThunderbolt 4対応Type-Cポート1基と比較しても、
TENKU LUNAのデュアルUSB4は充電、高速データ転送、映像出力、そして汎用eGPU接続といった多様な用途を同時に、かつ柔軟にこなせる大きな可能性を秘めています。ROG Ally XはUSB4を1基搭載していますが、TENKU LUNAは2基です。
メリット3:国内ユーザーに寄り添ったサポート体制とAI機能の将来性
「日本ブランド初」を謳うTENKU LUNAは、国内での手厚いサポート体制を強調しています。国内での修理対応や部品の国内常備といった具体的な取り組みは、海外ブランド製品が多いこの市場において、日本のユーザーにとっては大きな安心材料となるでしょう。
また、CPUにAMD Ryzen™ 7 7840Uを採用し、「AMD Ryzen™ AI」エンジンを内蔵している点も、将来的なソフトウェアの進化を考えると興味深いポイントです。ROG Ally (RC71L-Z1E512)やROG Ally XのRyzen Z1 Extreme、あるいはSteam Deck OLEDやMSI Claw A1Mのプロセッサーには、現時点の資料ではこのAIエンジンに関する明確な言及がありません。
【デメリット】
デメリット1:一部競合に見られる特定機能の不在とバッテリー容量
一方で、TENKU LUNAにもいくつかの弱点や、他の機種が優れている点が見受けられます。まず、多くの競合機種、例えばROG Ally (RC71L-Z1E512)、Steam Deck OLED、MSI Claw A1M、ROG Ally Xがいずれも背面にカスタマイズ可能なマクロボタン(グリップボタン)を搭載しているのに対し、TENKU LUNAにはこの機能がありません。より複雑な操作を求めるゲームでは、この差が操作性に影響する可能性があります。
バッテリー容量は50.04Whと、ROG Ally (RC71L-Z1E512)の40Whよりは大きいものの、Steam Deck OLED (50Wh) と同等、MSI Claw A1M (53Wh) よりは若干少なく、特に大容量バッテリーを搭載してきたROG Ally X (80Wh) と比較すると見劣りします。駆動時間はTDP設定に大きく左右されるため一概には言えませんが、より長時間のプレイを重視するユーザーにとっては考慮すべき点です。
デメリット2:ディスプレイ技術とエコシステムの成熟度
ディスプレイに関しては、TENKU LUNAは高精細な120Hz LCD IPSパネルを搭載していますが、Steam Deck OLEDが採用するHDR対応のOLED(有機EL)ディスプレイと比較すると、コントラスト比や黒の表現力では譲る部分があります。映像美を極限まで追求するユーザーにとっては、Steam Deck OLEDのディスプレイが魅力的に映るでしょう。
また、TENKU LUNAは新しいブランドの製品であるため、ASUSのROGシリーズやValveのSteam Deckのように、長年かけて築き上げられてきた広範なユーザーコミュニティや、豊富なサードパーティ製アクセサリーといったエコシステムの成熟度では、これからという部分があります。
総じてTENKU LUNAは、圧倒的な標準メモリ容量、先進的なストレージ拡張性、そして国内ユーザーにとって心強いサポート体制を大きな武器としています。一方で、背面ボタンの不在や、特定のディスプレイ技術を求めるユーザーにとっては、他の選択肢も魅力的に映るかもしれません。ご自身のプレイスタイルや重視するポイントを照らし合わせながら、最適な一台を見つけることが重要です。
TENKU LUNAのスペック(仕様)
- モデル: TENKU LUNA (日本ブランド初PゲームPC).
- ディスプレイ: 7インチ フルHD (1920×1080) 120Hz LCD タッチパネル (輝度450nits, sRGB 100%, IPS).
- CPU(プロセッサ): AMD Ryzen™ 7 7840U (8コア/16スレッド, Zen4, 最大5.1GHz).
- GPU: AMD Radeon™ 780M (内蔵, RDNA 3, 12CU, 最大8.6TFLOPS), VRAM最大16GB, レイトレーシング対応.
- RAM(メモリ): 32GB LPDDR5 (6400/6500MHz).
- ストレージ: PCIe 4.0×4 M.2 2280 SSD 1TB/2TB, microSD 4.0対応.
- バッテリー: 50.04Wh.
- 駆動時間: 約3時間プレイ可能 (環境による).
- 充電: 65W ACアダプター付属, PD急速充電サポート (USB4経由).
- カメラ: なし。
- ワイヤレス通信: Wi-Fi 6E (Intel AX210), Bluetooth 5.3.
- インターフェース: USB4 Type-C x2 (充電/DP/eGPU), 3.5mmヘッドフォンジャック, microSD 4.0スロット.
- センサー: 6軸ジャイロセンサー (加速度+ジャイロ).
- スピーカー: デュアルステレオスピーカー (フロント).
- オーディオ: デュアルマイク内蔵, 3.5mmジャックはマイク兼ヘッドフォン端子.
- 振動モーター: デュアルリニア振動モーター.
- 冷却: 効率の良い放熱システム (吸気孔拡大).
- 操作: 十字キー,ABXYボタン,ホームボタン(Xbox Game Bar起動),クイックボタン(GameAssistant起動),スクリーンキーボード起動,スタートボタン,セレクトボタン(Xbox標準ゲームパッド内蔵).
- 機能: 専用アプリ「GameAssistant」 (クイックボタン), TDP切替 (15W/28W), コントローラーモード,バイブレーション・解像度など変更可能.
- オプション(アクセサリー): 先行予約特典専用ケース, 数量限定eGPUセット販売 (AYANEO AG01), ドック/スタンドなし.
- 生体認証: 指紋認証サポート (電源ボタン一体型).
- 筐体: コンパクト/薄型設計.
- ソフトウェア(アプリ): Windows 11 Home 64bit, GameAssistant.
- OS: Windows 11 Home 64bit.
- サイズ: 約256×113.5×22.5-36mm (一部256×133.5×22.5-36mm記載あり).
- 重量: 約666g.
- カラー: ブラック。
- 付属品: 65W ACアダプター.
TENKU LUNAの評価
7つの基準で「TENKU LUNA」を5段階で評価してみました。
【項目別評価】
画面の見やすさ:★★★★☆
7インチフルHD液晶は高精細で色彩表現も豊かだが、屋外での視認性や表面処理の点で改善の余地あり。
パフォーマンス:★★★★☆
Ryzen 7 7840Uと32GBメモリは多くのゲームに対応可能だが、最新の重量級タイトルでは設定調整が必要。
操作性:★★★★★
Xbox準拠のボタン配置と良好なグリップ感、便利な専用ボタンにより、直感的で快適な操作が可能。
機能性:★★★★★
デュアルUSB4ポート、microSD 4.0スロット、Wi-Fi 6Eなど、高い拡張性と将来性を備える。
デザイン:★★★★☆
マットブラックの落ち着いたデザインは高級感があるが、やや大きく重さを感じる場合もある。
使いやすさ:★★★★★
専用管理ソフト「GameAssistant」や指紋認証センサーなど、日常的な利用を快適にする工夫が豊富。
価格:★★★★★
32GBメモリと1TB SSDを標準搭載し、先行予約価格79,800円からは非常に高いコストパフォーマンス。
【総評】 ★★★★☆
総評コメント
TENKU LUNAは、「日本ブランド初の本格ポータブルゲーミングPC」として、価格、性能、機能性、そしてサポート体制のバランスが非常に高いレベルでまとまっている一台と言えるでしょう。
基本性能と価格の魅力
AMD Ryzen™ 7 7840Uプロセッサーと標準で32GBという大容量メモリ、そして高速な1TBまたは2TBのSSDを搭載しながら、特に先行予約価格では7万円台からという価格設定は、他の競合製品と比較しても際立ったコストパフォーマンスを誇ります。 これにより、多くのPCゲームを快適に楽しむための土台がしっかりと提供されています。
優れた拡張性と操作性
注目すべきは、汎用性の高いM.2 2280 SSDスロット、次世代規格のmicroSD 4.0カードスロット、そして何よりも2基搭載されたUSB4 Type-Cポートです。 これらは、将来的なストレージの増設や、eGPUを含む多様な周辺機器との接続を容易にし、本機の可能性を大きく広げています。 また、Xbox準拠のコントローラーレイアウトや、TDP切り替えなどが簡単に行える専用ボタン「GameAssistant」は、ゲーマーにとって直感的で快適な操作環境を提供します。
デザインと携帯性、そして国内サポートの安心感
漆黒の筐体は落ち着いた高級感を演出し、大人が所有する喜びを満たしてくれます。 約666gという重量は携帯性を若干損なう可能性もありますが、グリップ感は良好です。 そして何よりも、国内ブランドならではの手厚いサポート体制、特に修理部品の国内常備と迅速な対応への言及は、ユーザーにとって大きな安心材料となるでしょう。
TENKU LUNAは、高性能なポータブルゲーミング体験を、優れたコストパフォーマンスと将来性、そして日本のユーザーに寄り添った安心感と共に提供してくれる、非常に魅力的な選択肢と言えます。
最終結論:TENKU LUNA と ROG Ally (RC71L-Z1E512)、最適な一台はこれだ!
ここまで、TENKU LUNAの魅力と特徴を様々な角度から掘り下げ、主要なライバルであるASUS ROG Ally (RC71L-Z1E512)との比較も行ってきました。どちらも非常に高性能で魅力的なWindows搭載ポータブルゲーミングPCですが、それぞれに得意な分野や個性があります。ここでは、これまでの情報を総括し、あなたがどちらのデバイスを選ぶべきか、私なりの最終的な提言をさせていただきます。
TENKU LUNAが輝くポイント:こんなあなたにこそ最適な選択
「TENKU LUNA」の核心的なメリットを再確認すると、それは「余裕のある基本性能(特に32GBの大容量メモリと1TB/2TB SSD)」「先進的な拡張性(デュアルUSB4、microSD 4.0)」「日本ブランドならではの安心感(手厚い国内サポート)」、そしてこれらを備えながら実現された「高いコストパフォーマンス」に集約されると、私は強く感じました。
これらの点を踏まえると、TENKU LUNAは、「メモリやストレージに余裕を持ち、最新インターフェースによる高い拡張性を活かして多様な使い方をしたい。そして何よりも、万が一の際にも安心できる国内での手厚いサポートを重視し、コストパフォーマンスにも優れた一台を求めている」…そんな人にとって、まさに最適な一台となるでしょう。
特に、複数のAAAタイトルをインストールし、攻略情報をウェブで見ながらプレイしたり、eGPUを活用してデスクトップ級の環境も視野に入れたりするような、アクティブで欲張りな使い方を目指す方には、その真価を十分に発揮してくれるはずです。
ROG Ally (RC71L-Z1E512)がより輝くユーザー像
一方、ASUS ROG Ally (RC71L-Z1E512)も、非常に完成度の高いポータブルゲーミングPCです。もしあなたが、「世界的に実績のあるゲーミングブランドへの信頼感、細部まで作り込まれた専用ソフトウェア(Armoury Crate SE)による高度なカスタマイズ性、ディスプレイ表面の特殊コーティングや背面マクロボタンといった特定の機能、そしてXbox Game Passのような特典をすぐに活用したい」という点を重視するならば、ROG Allyがより魅力的な選択となるかもしれません。長年培われたブランド力と、それに伴うエコシステムの成熟度は、確かに安心感があります。
ポータブルゲーミングPCの市場は日進月歩で進化しており、新しい選択肢も次々と登場しています。しかし、現時点(2025年5月)において、TENKU LUNAは、特に日本のユーザーにとって、性能、拡張性、サポート、そして価格のバランスが非常に高いレベルで調和した、大変魅力的な一台であるといえます。
TENKU LUNAの価格・購入先
※価格は2025/11/09に調査したものです。価格は変動します。
※発売日は2025年5月30日(金)です。ハイビーム 公式オンラインストア、Amazon.co.jpで販売されました。
ハイビーム 公式オンラインストア
現在、売り切れです。販売されていません。
価格は、
- 32GB+1TBモデルで79,800円、
- 32GB+2TBモデルで89,800円、
でした。
ハイビーム 公式オンラインストアで「TENKU LUNA」をチェックする
ECサイト
※現在、販売されていません。
価格は、Amazonで32GB+1TBモデルが79,800円、32GB+2TBモデルが89,800円、でした。
Amazonで「TENKU LUNA」をチェックする
楽天市場で「TENKU」をチェックする
ヤフーショッピングで「TENKU」をチェックする
おすすめのライバル機種と価格を比較
「TENKU LUNA」に似た性能をもつポータブルゲーミングPCも販売されています。価格の比較もできるので、ぜひ参考にしてみてください。
ROG XBOX ALLY / Ally X 2025モデル
ASUS (ROG) から発売された7.0インチのポータブルゲーミングPCです(2025年10月16日に発売・型番:RC73YA-Z2A16G512/RC73XA-Z2E24G1T)。
7.0型ワイドTFTカラー液晶 (1,920×1,080, 120Hz, FreeSync Premium対応)、AMD Ryzen™ Z2 A (Ally) / AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme (Ally X)、LPDDR5X 16GB (Ally) / 24GB (Ally X) メモリ、SSD 512GB (Ally) / 1TB (Ally X) (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 2280)、60Wh (Ally) / 80Wh (Ally X) バッテリー、Windows 11 Home 64ビットを搭載しています。
また、Xboxアプリ、UI「Xboxフルスクリーンエクスペリエンス」、Xboxボタン(Game Bar)、「Xbox Play Anywhere」、ASUSの管理コンソール「Armoury Crate Special Edition (ACSE)」、AMD Ryzen™ AI (NPU※Ally Xのみ)、モニター出力、内蔵SSDの交換(換装)に対応。
ステレオスピーカー (Dolby Atmos / Hi-Res Audio対応)、アレイマイク、HD振動機能 (Ally Xはインパルストリガー対応)、ROGインテリジェントクーリング (デュアルファン)、ジョイスティック×2(RGBライティング)、マクロボタン×2、バンパー/トリガー、指紋認証センサ (電源ボタン一体型)、USB Type-Cポート (Ally XはUSB4対応)、microSDカードスロット、Wi-Fi 6E、Bluetooth® 5.4にも対応しています。
価格は、Amazonで89,800円(ROG XBOX ALLY / Ally Xは139,800円)、楽天市場で93,980円(中古品・送料無料)、ヤフーショッピングで97,939円、米国 Amazon.comで$599.00、です。
関連記事:ROG XBOX ALLY/Ally X評価レビュー!期待以上の性能・機能か?
Amazonで「ROG XBOX ALLY」をチェックする
ROG Ally X 2024モデル
ASUSから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2024年7月 発売)。
AMD Ryzen Z1 Extreme、24GB LPDDR5-7500、フルHDののIPS タッチスクリーン、1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)、80WHrsバッテリー、6軸ジャイロセンサー、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、デュアル ステレオスピーカー、Dolby Atmos、アレイマイク、AIノイズキャンセリング、HDハプティクス、Microsoft Pluton セキュリティ、指紋認証、AURA SYNC、Gorilla Glass DXC、USB4 Gen2 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、楽天市場で127,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで127,800円、です。
関連記事:ROG Ally Xは買うべきか?できるゲームとグラフィック性能をレビュー
Amazonで「ROG Ally X」をチェックする
ROG Ally (RC71L-Z1E512) 2023モデル
ASUSから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2023年6月14日に発売・上位モデル)。
AMD Ryzen Z1 Extremeプロセッサ、16GB LPDDR5メモリ、フルHDのIPS タッチスクリーン、512GB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230)ストレージ、40WHrsバッテリー、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、外付けGPU「ROG XG Mobile」(別売)、リフレッシュレート 120Hz、マクロキー、6軸ジャイロ、HDハプティクス、冷却システム、「Armoury Crate SE」、デュアル ステレオスピーカー、Dolby Atmosサウンド、アレイマイク、UHS-II microSD カードリーダー、指紋認証、USB Type-C (USB 3.2 Gen2)、Wi-Fi 6e (802.11ax) 、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、Amazonで81,890円(Ryzen™ Z1 Extreme)、楽天市場で79,777円(送料無料・Ryzen™ Z1 Extreme)、ヤフーショッピングで77,800円(Ryzen™ Z1 Extreme・中古は71,930円)、米国 Amazon.comで$649.00、、です。
関連記事:初代 ROG Ally (2023)レビュー!できるゲームとグラフィック性能
Amazonで「ROG Ally (RC71L)」をチェックする
Steam Deck OLED
米国 Valve から発売された7.4インチのポータブルゲーミングPCです(2023年11月17日に発売)。
Steam OS 3.0、Zen2ベースのAMD APUと16 GB LPDDR5 メモリ、HD画質のHDR OLED(有機EL)タッチスクリーン、512GB/1TB NVMe SSD、50 Whバッテリー、トラックパッドを搭載しています。
また、リフレッシュレート 90 Hz、HDハプティクス、大型の冷却ファン、DSP内蔵ステレオスピーカー、デュアルアレイマイク、microSDカードでのストレージ拡張、45W急速充電、6軸ジャイロセンサー、Steam Deck ドッキングステーション(別売)、USB3 Gen2 Type-C (DP映像出力/PD充電/データ転送)x1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応しています。
価格は、Amazonで155,231円、楽天市場で93,680円、ヤフーショッピングで94,700円、です。
関連記事:Steam Deck OLEDとROG Ally Xを比較!ゲーム性能レビュー
Amazonで「Steam Deck OLED」をチェックする
MSI Claw 8 AI+ A2VM
MSI から発売された8インチのポータブルゲーミングPCです(2025年2月20日 発売)。
インテル Core Ultra 7 258V、32GB LPDDR5Xメモリ、WUXGA液晶(解像度1920 x 1200)、1TB M.2 NVMe SSDストレージ、80Whr バッテリー、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、ハイパーフロー強冷クーラー、RGBバックライト、ホールエフェクトスティック、2Wステレオ2スピーカー、ハイレゾオーディオ認証、フィンガータッチ、リニアトリガーボタン、背面マクロボタン、指紋認証リーダー、MSI Center(管理ソフト)、Thunderbolt 4 Type-C x2、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4に対応しています。
価格は、Amazonで156,000円、楽天市場で159,800円、ヤフーショッピングで166,000円、です。
関連記事:MSI Claw 8 AI+ A2VMレビュー!Core Ultra 7とAIで激変?
Amazonで「MSI Claw 8 AI+ A2VM」をチェックする
MSI Claw A1M
MSIから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2024年3月28日 発売)。
インテル Core Ultra 5 135H / Core Ultra 7 155H、インテル Arc グラフィックス、16GB LPDDR5-6400メモリ、フルHDのIPS液晶、512GB SSD / 1TB SSD ストレージ (NVMe PCIe Gen4)、53 WHrバッテリ、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、リフレッシュレート 120Hz、65W PD急速充電、2x 2W スピーカー、ハイレゾオーディオ認定、HD ハプティクス、指紋認証、人間工学に基づいたデザイン、管理ソフト「MSI Center M」、ゲームライブラリ「App Player」、Thunderbolt 4 互換のType-Cポート、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 に対応しています。
価格は、Amazonで87,120円(税込・CoreUltra5/16GB/SSD1TB)、楽天市場で93,780円(送料無料)、ヤフーショッピングで88,500円、です。
関連記事:実は不人気じゃない「MSI Claw A1M」のメリット・デメリット
Amazonで「MSI Claw A1M」をチェックする
GPD WIN Mini 2025
GPD から発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2025年3月上旬に発売)。
AMD Ryzen AI 9 HX 370 / AMD Ryzen 7 8840U、16GB/32GB LPDDR5xメモリ、1TB/2TB M.2 NVMe 2280 SSDストレージ、44.24Wh バッテリー(最大14時間駆動、利用状況による)、Windows 11 Home (64bit)、microSDカードスロット (最大読込160MB/s、最大書込120MB/s) x1を搭載しています。
また、冷却システム、デュアルスピーカー(独立アンプ内蔵)、DTS:X Ultra対応オーディオ、バックライト付QWERTYキーボード(シザースイッチ)、ホール効果ジョイスティック、L4/R4カスタムキー、タッチパッド (PTP)、アクティブ冷却、デュアルリニアモーターによる振動効果、
6軸ジャイロスコープ、3軸重力センサー、PD急速充電、USB4 (40Gbps) x1、USB 3.2 Gen 2 Type-C x1、USB Type-A x1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応しています。
価格は、Amazonで142,000円(税込)、楽天市場で219,970円(送料無料)、ヤフーショッピングで258,348円、です。
関連記事:GPD WIN Mini 2025レビュー!AI性能で2024年型を凌駕?
Amazonで「GPD WIN Mini 2025」をチェックする
その他のおすすめゲーム製品は?
その他のおすすめゲーム製品は以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
ポータブルゲーミングPCはどれを選ぶべきか? 最新の全機種と選び方を紹介
最新のポータブルゲーミングPCをまとめて紹介しています。
AYANEOのポータブルゲーミングPCがやはり最強か? 全機種 まとめ
AYANEOのポータブルゲーミングPCをまとめて紹介します。
GPD WIN シリーズ・XP ゲーム機の全機種 ラインナップを比較
GPDの超小型PC(UMPC)やタブレットをまとめています。