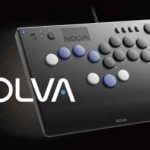ASUSが2023年に発売した「ROG Ally (RC71L)」は、Windows 11を搭載し、ポータブルゲーミングPC市場に大きな衝撃を与えた注目のデバイスです。
このレビューでは、初代ROG Ally (2023)(Ryzen Z1 ExtremeモデルとRyzen Z1モデル)で、具体的にどのようなゲームができるのか、そしてそのグラフィック性能はどの程度なのかを徹底的に深掘りします。実際のゲーム動作から、多くのユーザーが直面した弱点まで、実機使用に基づき詳しく解説します。
【先に結論からお伝えしましょう】
ROG Ally (RC71L) の長所 (Pros):
- Ryzen Z1 Extreme(上位モデル)が持つ、今なお強力なグラフィックおよびCPUパフォーマンス
- Steam、Xbox Game Pass、Epicなどプラットフォームを選ばないWindows 11搭載の圧倒的な汎用性
- 120Hzの高リフレッシュレートに対応した、明るく非常に美しいフルHDディスプレイ
- Dolby Atmos対応スピーカーによる、携帯機とは思えない迫力と臨場感のあるサウンド
- ゲーム機のような直感的操作を可能にする「Armoury Crate SE」と「コマンドセンター」の存在
ROG Ally (RC71L) の短所 (Cons):
- AAAタイトルをプレイすると1〜2時間程度しか持たない、厳しいバッテリー持続時間
- 排熱設計の問題で、microSDカードスロットが非常に故障しやすいという重大な欠点
- 汎用のUSB Type-Cポートが1基しかなく、充電しながらの拡張性に乏しい
- Windows OS起因の、スリープ復帰の不安定さや文字入力といった煩雑さが残る点
総合評価:
ROG Ally (RC71L)は、Windows PCゲームを妥協なく外に持ち出したいという夢を高いレベルで実現した一台です。バッテリー持ちやSDカードスロットの問題といった明確な弱点は抱えているものの、それを補って余りあるパフォーマンスと、120Hzディスプレイ、高音質スピーカーがもたらす高い没入感を備えています。
<この記事で分かること>
- Ryzen Z1 ExtremeとRyzen Z1モデルの詳細なベンチマークと性能比較(グラフィック性能比較)
- 『モンスターハンターワイルズ』『原神』など、人気ゲームが実際にどう動くか(実測フレームレート)
- Windows 11と専用ソフト「Armoury Crate SE」で具体的にできること(設定)
- 120HzディスプレイとDolby Atmosスピーカーの実際の品質
- TDPモード別(ターボ、パフォーマンス等)のバッテリー持続時間
- ファンの静音性やグリップ部の発熱など、冷却性能の実態
- 重大な欠点であるmicroSDカードスロットの問題と、SSD換装の必要性
- 背面ボタンやジャイロ、振動(ハプティクス)を含む操作性
- 「ROG XG Mobile」など、体験を拡張する専用アクセサリー
- 購入前に知っておくべきメリットとデメリットの総まとめ
- 専門家による5段階評価と詳しい総評
- 最新の価格(新品・中古)とお得な購入先・ライバル機種との価格比較
この記事を最後まで読むことで、あなたが今「初代 ROG Ally (RC71L)」を購入するべきかどうかがはっきりと分かるはずです。購入に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク
公式ページ:ROG Ally (2023) | #playALLYourgames | #すべてのゲームを手のひらに | ポータプルゲーム機 | ROG – Republic of Gamers | ROG 日本
ソフトウェアとできるゲーム:ROG Ally (RC71L) Windows 11が拓く無限の可能性
ここでは、初代「ROG Ally (RC71L)」がどのようなゲームをプレイできるのか、その核となるOS「Windows 11」の圧倒的な自由度と、ゲーム体験を最適化する専用ソフトウェア「Armoury Crate SE」の役割について書いていきます。
Windows 11搭載でプラットフォームの垣根はなし
ROG Ally (RC71L)の最大の強みは、OSにWindows 11 Homeを搭載している点です。これにより、特定のプラットフォームに縛られることなく、Steam、Epic Games、GOGなど、あらゆるPCゲーム配信ストアのゲームをネイティブでインストールし、遊ぶことができます。Linuxベースの携帯機で時折みられるような互換性の問題を心配する必要がなく、PCゲームのほぼすべてが動作対象となります。
この自由度は、Steam以外のゲームを遊びたい場合に真価を発揮します。例えば、独自のランチャーが必要な『原神』や、DLSiteで購入した同人ゲームなども、普通のWindows PCと同じように楽しめます。さらに、購入時には「Xbox Game Pass Ultimate」の3ヶ月無料トライアルが付属しており、『Hi-Fi Rush』や『Starfield』(※Game Pass対応タイトル例)といった数百のゲームを追加費用なしですぐにプレイ開始できるのも大きな魅力です。
クラウドゲーミングとエミュレーション
ROG Ally (RC71L)はWi-Fi 6E規格に対応しており、高速なネットワーク通信が可能です。これにより、Xbox Cloud GamingやGeForce NOWなどのクラウドゲーミングサービスも快適に利用できます。インストール容量を気にせず、ストリーミングで『Cyberpunk 2077』のようなAAAタイトルを楽しむといった使い方も現実的です。
また、Windows OSの強みを活かし、RetroArchやPPSSPPといった豊富なエミュレーターを導入することもできます。これにより、過去の懐かしいゲームをこの一台で楽しむことも可能になり、遊び方の幅はまさに無限大と言えます。
ゲーム体験の鍵を握る「Armoury Crate SE」
「Windows PCを携帯ゲーム機のように使うのは設定が面倒そうだ」と感じるかもしれませんが、その懸念を払拭するのがASUS独自の統合ソフト「Armoury Crate SE」です。このソフトウェアが強力なゲームランチャーとして機能し、インストールしたゲームをプラットフォームに関係なく一つのライブラリに自動で集約・表示してくれます。
これにより、Windowsのデスクトップ画面を介さず、コントローラー操作だけでお気に入りのゲームに素早くアクセスでき、家庭用ゲーム機に近い直感的な操作感を実現しています。また、ゲーム中でもコマンドセンターボタン を押すだけで専用メニューが開き、パフォーマンスモードの変更やFPSリミッターの設定などを瞬時に調整できるため、非常に便利です。
Windows機としての「クセ」も
ただし、あくまでもベースはWindows 11です。家庭用ゲーム機のように、スリープさせてから復帰すると、ゲーム画面がウィンドウモードになってしまうことがあったり、ゲーム起動時のIDやパスワード入力でソフトウェアキーボードの操作が必要になったりする場面も。「PCでゲームをプレイする」という意識が求められる側面もあり、PCの操作に慣れていないと、最初の設定で少し戸惑うかもしれません。
ソフトウェアとできるゲームのまとめ
- Windows 11搭載:Steam、Xbox Game Pass、Epicなど、あらゆるプラットフォームのPCゲームが動作可能。
- Armoury Crate SE:ゲームを一元管理するランチャー機能で、ゲーム機のような直感的操作をサポート。
- 高い自由度:クラウドゲーミング やエミュレーター、同人ゲームまで幅広く対応。
- PCとしての側面:スリープ復帰や文字入力などでWindows PC特有の操作が必要になる場面もあり、ある程度のPC知識があると使いこなしやすい。
パフォーマンスとゲーム性能
ここではROG Ally (RC71L)のベンチマーク結果とゲーム性能について紹介していきます。
ベンチマーク
上位モデル(RC71L-Z1E512)が搭載するのは、AMD Ryzen™ Z1 Extreme プロセッサーです。これはAMDがポータブルゲーム機向けに開発した高性能APUで、CPU部には「Zen 4」アーキテクチャを採用した8コア16スレッド、GPU部には「RDNA 3」ベースのAMD Radeon グラフィックス(Radeon 780M、12 CU)を内蔵しています。この組み合わせにより、グラフィックス性能は最大8.6TFlops(FP32)という、従来のポータブル機では考えられなかった強力なパワーを発揮します。
下位モデル(RC71L-Z1512)は、AMD Ryzen™ Z1 プロセッサーを搭載しています。こちらも同じく「Zen 4」アーキテクチャ(6コア12スレッド) と「RDNA 3」ベースのGPU(Radeon 740M、4 CU)を採用していますが、GPU性能は最大2.8TFlops(FP32)と、Z1 Extremeモデルと比較すると控えめな仕様になっています。
Ryzen Z1 Extremeのベンチマーク
<CPUのベンチマーク結果>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「25466」
- Geekbench 6のシングルコア「2211」、マルチコア「9669」
- Cinebench R23 シングルコア「1753」、マルチコア「13801」
- Cinebench 2024 シングルコア「115」、マルチコア「820」
<GPUのベンチマーク結果・グラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで「8042」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「3593」
- Time Spy グラフィックスコアで「3041」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「29319」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「16859」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
Ryzen Z1のベンチマーク
<CPUのベンチマーク結果>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「18406」
- Geekbench 6のシングルコア「2238」、マルチコア「8208」
- Cinebench R23 シングルコア「1688」、マルチコア「7180」
- Cinebench 2024 シングルコア「85」、マルチコア「510」
<GPUのベンチマーク結果・グラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで「4552」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「2200」
- Time Spy グラフィックスコアで「1807」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「20500」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「9892」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
<ベンチマーク結果の比較から分かること>
これらのベンチマーク結果から、Ryzen Z1 Extremeは、特にマルチスレッドを活用する最新のゲームや、高いグラフィックス性能を要求される場面において、Ryzen Z1よりもはるかに優れたパフォーマンスを発揮することが分かります。ASUSが公開したベンチマーク結果によると、Z1 ExtremeモデルはZ1モデルよりも1080pで平均42.8%、720pで平均32.7%高いフレームレートを示したと報告されています。
そのため、より高いフレームレートで滑らかなゲームプレイを楽しみたい、あるいは高設定で美麗なグラフィックスを体験したいユーザーにとっては、Ryzen Z1 Extremeを搭載したモデルが明確に優れた選択肢であると言えます。
グラフィック性能を比較
ROG Ally (RC71L)が搭載するRyzen Z1 Extreme、Ryzen Z1のグラフィック性能は、他のポータブルゲーミングPCと比べて、どのくらいなのでしょうか?Fire StrikeとTime Spyで比較してみました。
Fire Strikeのスコアで比較
- 9147:Ryzen AI Z2 Extreme(ROG XBOX ALLY X)
- 8042:Ryzen Z1 Extreme(ROG Ally RC71L/ROG Ally X)
- 7800:Ryzen AI 9 HX 370(GPD WIN Mini 2025)
- 5532:Ryzen 7 8840U(GPD WIN Mini 2025)
- 5015:Ryzen 5 8640U(GPD WIN Mini 2024)
- 4859:Ryzen Z2 A(ROG Xbox Ally)
- 4552:Ryzen Z1 (ROG Ally RC71L)
- 4313:AMDカスタムAPU(Steam Deck OLED)
Time Spyのスコアで比較
- 4009:Ryzen AI Z2 Extreme(ROG XBOX ALLY X)
- 3820:Ryzen AI 9 HX 370(GPD WIN Mini 2025)
- 3435:Ryzen Z1 Extreme(ROG Ally X)
- 3042:Ryzen Z1 Extreme(ROG Ally RC71L)
- 2791:Ryzen 7 8840U(GPD WIN Mini 2025)
- 2312:Ryzen 5 8640U(GPD WIN Mini 2024)
- 1929:Ryzen Z2 A(ROG Xbox Ally)
- 1807:Ryzen Z1 (ROG Ally RC71L)
- 1700:AMDカスタムAPU(Steam Deck OLED)
<比較から分かること>
これらのデータから、ROG Allyは搭載されるAPUによって明確な性能差があることが分かります。Ryzen Z1 Extreme搭載モデルは、Steam Deckを大幅に超えるトップクラスのグラフィック性能を持ち、パフォーマンスを最優先するユーザー向けの選択肢です。
一方、Ryzen Z1搭載モデルは、Steam Deckとほぼ同等の性能を持ち、価格と性能のバランスを取りたいユーザー向けの選択肢と言えます。総じて、ROG Ally (RC71L)は、そのモデルに応じて異なるターゲット層に向けた性能を提供しており、ポータブルゲーミングPC市場における競争の激しさと技術の進歩を明確に示しているデータと言えるでしょう。
ゲーム性能をレビュー!モンハンなどの人気ゲームはどう動く?
ここでは、ROG Ally (RC71L)のRyzen Z1 ExtremeプロセッサとRyzen Z1プロセッサでゲーム性能でどのくらいの差があるのか、その違いをフレームレートで検証していきます。
原神 (Genshin Impact)
まず、アニメ調の美しいグラフィックが特徴の『原神』です。Ryzen Z1 Extreme搭載モデルで試したところ、1080p解像度・高設定でも全く危なげなく、フレームレートは安定して60FPSに張り付きました。広大なテイワットの探索や、元素爆発が飛び交うエフェクトの重い戦闘シーンでも、カクつきを感じることは一切なく、非常に滑らかで快適な冒険を心の底から楽しめました。
一方、Ryzen Z1搭載モデルでも、1080p解像度で画質を中設定に調整すれば60FPSでの動作が可能です。高設定のままだと都市部などで不安定になる場面もありましたが、設定次第でZ1モデルでも十分快適にプレイできます。
モンスターハンターワイルズ (Monster Hunter Wilds)
次に、非常に高いグラフィック負荷が予想される『モンスターハンターワイルズ』です。これはベンチマークソフトでの検証になりますが、Ryzen Z1 Extreme搭載モデルであっても、1080p解像度で快適に動作させるのは非常に困難でした。解像度を720pまで落とし、グラフィックを低設定、さらにアップスケーリング技術(FSR)を併用することで、ようやく30FPS~40FPS台でのプレイが視野に入ります。
携帯機で最新の狩猟体験ができる可能性はありますが、画質・解像度ともにかなりの妥協が必要です。Ryzen Z1搭載モデルでは、解像度を720pの最低設定にしても30FPSを安定して維持することは難しく、本作をプレイするには性能的に厳しいと言わざるを得ません。
Apex Legends
スピーディーな展開が魅力の『Apex Legends』では、Ryzen Z1 Extreme搭載モデルの真価が発揮されました。1080p解像度・中設定でも、フレームレートは平均して100FPSを超える高い数値を叩き出します。ROG Allyの120Hzディスプレイと相まって、敵の動きが非常にはっきりと視認でき、精密なエイムが求められる激しい撃ち合いで、明確に有利に立てると感じました。 Ryzen Z1搭載モデルでも、1080p解像度・低設定にすることで、安定して60FPS以上を保つことができました。カジュアルにプレイする分にはまったく問題ないパフォーマンスです。
サイバーパンク2077 (Cyberpunk 2077)
極めて高いグラフィック負荷で知られる『サイバーパンク2077』にも挑戦しました。Ryzen Z1 Extreme搭載モデルでは、1080p解像度・Turboモード(低~中設定)で、アップスケーリング技術(FSR)を活用したところ、平均47.9FPSを記録しました。ナイトシティの雑踏など高負荷な場面ではフレームレートが落ち込むものの、携帯機でこの緻密な世界に没入できるという事実に大きな感動を覚えました。
Ryzen Z1搭載モデルでは、データ上でも平均25.3FPSと、そのままではプレイが困難です。解像度を720pに下げ、グラフィックを最低設定にし、FSRを最もパフォーマンス重視の設定にすることで、ようやく30FPSでの最低限のプレイラインが見えてきます。
Forza Horizon 5
最適化が素晴らしい『Forza Horizon 5』では、Ryzen Z1 Extreme搭載モデルは圧巻のパフォーマンスを見せました。1080p解像度・高設定でも平均80FPS以上を維持し、設定を中に調整すれば100FPSを超えることも可能です。滑らかに流れる美麗なメキシコの景色を感じながら、非常に爽快なドライブ体験ができました。これはRyzen Z1搭載モデルでも同様に快適で、1080p解像度・中設定で60FPSを安定して維持できます。Z1の性能でも十分に楽しめる、最適化の優れたタイトルです。
ストリートファイター6 (Street Fighter 6)
安定した60FPSでの動作が絶対条件となる『ストリートファイター6』も試しました。Ryzen Z1 Extreme搭載モデルでは、1080p解像度でグラフィック設定を最高にしても、全く問題なく常時60FPSに張り付きます。キャラクターのディテールや派手なバトルエフェクトを高品質で楽しみながら、一切の遅延を感じさせない完璧な対戦環境でした。Ryzen Z1搭載モデルでも、グラフィック設定を中、あるいは一部を低に調整することで、安定した60FPSでの対戦が可能です。画質は多少劣りますが、格闘ゲームとして最も重要なフレームレートはしっかり維持できます。
ゲーム性能のまとめ
Ryzen Z1 ExtremeとRyzen Z1の性能差は、実際のゲーム体験において明確な違いとなって現れました。Ryzen Z1 Extremeは、多くのゲームを1080p解像度で快適にプレイするためのパワーを持ち、特に『Apex Legends』のような競技性の高いゲームや、『サイバーパンク2077』のような最新AAAタイトルにおいてその真価を発揮します。
より高い画質とフレームレートを妥協したくないならば、間違いなくZ1 Extremeモデルが選択肢となります。一方のRyzen Z1は、比較的軽量なゲームや、『原神』『Forza Horizon 5』のように最適化が進んでいるタイトル、または画質設定の調整を積極的に行うユーザー向けのプロセッサーです。多くのゲームをプレイ可能ですが、重量級タイトルでは解像度や設定を大きく下げる必要がありました。
メモリとストレージ:ROG Ally (RC71L) 快適動作と拡張性の実態
ここでは、ROG Ally (RC71L)の快適な動作を支えるメモリとストレージの仕様、そして容量不足への対策として必須とも言える「SSD換装」について詳しく書いていきます。
高速LPDDR5メモリによるスムーズな動作
ROG Ally (RC71L)は、全モデル共通で16GBのLPDDR5-6400規格メモリを搭載しています。これはオンボード(基板直付け)のため、後から増設や交換はできません。しかし、この高速メモリのおかげで、Windows 11 HomeというフルスペックのOSや、ゲームの動作は非常に軽快です。
実際に、ゲームをプレイしながらバックグラウンドでDiscordを使ってボイスチャットをしたり、攻略サイトをブラウザで閲覧したりといったマルチタスクも、メモリ不足を感じることなくスムーズに行えました。16GBという容量は、ほとんどのPCゲームの推奨スペックを満たしており、安定したプレイ環境を提供してくれます。
高速SSDと、その拡張(換装)について
ストレージには、両モデルともに高速な512GBのSSD (PCI Express 4.0 x4接続) が搭載されています。このおかげで、OSの起動はもちろん、『エルデンリング』や『サイバーパンク2077』のようなAAAタイトルのロード時間も非常に短く、ストレスなくゲームを開始できます。
しかし、昨今のゲームは1本で100GBを超えることも珍しくなく、512GBの容量ではすぐに手狭になってしまいます。そこで重要になるのがストレージの拡張です。
注意:microSDカードスロットの問題点
ROG Ally (RC71L)にはUHS-II対応のmicroSDカードスロットが搭載されていますが、このスロットには排熱設計上の問題が広く指摘されています。本体の高負荷時に発生する熱がスロット周辺に集中しやすく、挿入したmicroSDカードや、スロット自体が物理的に故障するトラブルが多数報告されています。そのため、メインのストレージ拡張手段としてmicroSDカードを頼りにするのは、残念ながら現実的ではありません。
現実的な解決策:M.2 2230 SSDへの換装
この問題を回避し、根本的に容量を増やす最も確実な方法が、内蔵SSDの換装です。ROG Allyは「M.2 2230」というコンパクトな規格のSSDを採用しており、これをユーザー自身で交換することが可能です。
実際に多くのユーザーが、より大容量の1TBや2TBのSSDに換装して快適なゲーム環境を構築しています。ただし、本体の分解を伴うため、この作業を行うとメーカーの保証対象外となるリスクがあります。保証を失う覚悟は必要ですが、SDカードスロットが実質的に使えない以上、大容量のゲームを多数持ち運びたいユーザーにとって、SSD換装はほぼ必須のカスタムと言えるでしょう。
メモリとストレージのまとめ
- メモリ:16GBの高速LPDDR5-6400メモリをオンボードで搭載し、OSやゲームの動作はスムーズ。
- 内蔵SSD:512GBのPCIe 4.0 SSDを搭載し、ゲームのロード時間は非常に高速。
- microSDの問題:排熱設計の影響でSDカードスロットおよびカードが故障する不具合が多数報告されており、拡張手段として信頼できない。
- SSD換装:M.2 2230規格のSSDに換装可能。保証対象外のリスクはあるが、容量を増やす最も確実な手段となっている。
デザインと携帯性:ROG Ally (RC71L) の外観と接続ポート
ここでは、ポータブルゲーミングPC「ROG Ally (RC71L)」の外観デザイン、携帯性、そして搭載されている接続ポートについて書いていきます。
白を基調とした洗練されたフォルムと携帯性
ROG Allyの筐体は、多くのゲーミングデバイスとは一線を画す清潔感のある白いボディカラーが特徴です。表面はマットな質感で指紋がつきにくく、実用性も兼ね備えています。
注目すべきはその薄型軽量デザインです。重量は約608g、厚さは最も薄い部分で21.22mm とスリムに抑えられています。実際に手に取ると数値以上に軽快さを感じます。競合機の一つである「Steam Deck」(約669g)と比較しても軽量であり、カバンにもすんなり収まるため、通勤中やカフェなどでPCゲームを楽しむといった携帯性にも優れています。
人間工学に基づいたグリップ形状
実際にROG Allyを手に取ってみると、そのグリップの形状が非常によく考えられていることに気づかされます。両手で包み込むように持つと、背面のカーブが手のひらに自然にフィットします。この絶妙なバランスのおかげで、約608gという軽さと相まって、本体をしっかりとホールドできます。
機能美と遊び心が融合したディテール
細部に目を向けると、機能性と遊び心が見事に融合していることがわかります。例えば、スピーカーのメッシュ部分や背面のROGロゴをかたどった通気口は、効率的な冷却性能を確保しつつも未来的な印象を与えます。
また、左右スティックの根本にはRGBライティング「Aura Sync」が搭載されており、ゲーミングデバイスとしてのアイデンティティを主張します。電源ボタンには指紋認証センサーがスマートに統合されており、実用性とデザイン性を両立させている点も評価できます。
接続ポート(インターフェース)
接続ポート類は、すべて本体上部に集中して配置されています。内容は、3.5mmのヘッドホンジャック、UHS-II対応のmicroSDカードスロット、そしてASUS独自の「ROG XG Mobileインターフェース」です。
汎用ポートとしては、このROG XG Mobileインターフェースと一体型になったUSB 3.2 (Type-C/Gen2) ポートが1基のみ搭載されています。このポートはデータ転送、DisplayPort 1.4による映像出力(モニター出力)、そして本体への給電(充電)をすべて兼任します。そのため、充電しながら他のUSB機器(有線コントローラーやマウス、キーボードなど)を接続したい場合は、別途ドッキングステーションやUSBハブが必須となります。
デザインと携帯性のまとめ
- 清潔感のある白いボディカラーと、指紋がつきにくいマットな質感が特徴。
- 重量約608g、厚さ約21.22mmからの薄型軽量デザインで携帯性に優れる。
- 人間工学に基づいたグリップ形状で、手に自然にフィットする。
- Aura Sync対応のRGBライティングや、指紋認証センサーなど、機能とデザインが両立されている。
- 接続ポートは本体上部に集中。
- 汎用ポートは給電・映像出力を兼ねるUSB Type-Cが1基のみで、拡張にはハブが必須。
ディスプレイとオーディオ:ROG Ally (RC71L) 鮮やかな映像と迫力の音響
ここでは、ROG Ally (RC71L)のディスプレイとオーディオがもたらす没入感について、詳細なスペックや実際の使用感を交えながら書いていきます。この二つの要素は、ゲームプレイはもちろん、動画視聴においても格別な体験を提供してくれました。
明るく色鮮やかな7インチ フルHDディスプレイ
ROG Allyの電源を入れると、まず7インチのフルHD(1920×1080ドット)ディスプレイの鮮やかさが目に飛び込んできます。輝度500nitsというスペックは非常に明るく、さらにsRGBカバー率100%という広色域により、色彩豊かなゲームの世界が忠実に再現されます。例えば『原神』のようなゲームでは、美しい風景のグラデーションがくっきりと表示されました。
また、ディスプレイ表面にはCorning社のGorilla Glass DXCが採用されており、反射を抑えつつ透過率を高めているため、日中の明るい部屋や屋外でも画面が見やすいのは嬉しいポイントです。もちろんタッチ操作にも対応しており、Windowsの操作や対応ゲームでの直感的な入力も可能です。
120Hzリフレッシュレートが織りなす究極の滑らかさ
このディスプレイの真価は、120Hzという高いリフレッシュレートにあります。一般的な60Hzのディスプレイと比較して2倍のコマ数を表示できるため、映像が格段に滑らかになります。特に『Apex Legends』のような動きの速いFPSゲームでは、敵の動きがはっきりと視認でき、エイムの精度向上にも繋がるのを実感しました。
さらに、AMD FreeSync Premiumテクノロジーにも対応しているため、ゲーム中のカクつき(スタッタリング)や表示ズレ(ティアリング)が効果的に抑制されます。反応時間も7msと高速で、シビアなタイミングが要求されるアクションゲームでもストレスフリーなプレイを約束してくれます。
携帯機とは思えない迫力のオーディオ体験
映像体験だけでなく、オーディオ性能も並外れています。Dolby Atmosに対応したデュアルSmart Ampスピーカーは、この小さな筐体から出ているとは思えないほど高音質でパワフルなサウンドを響かせます。歪みなく音量を上げることができ、ヘッドホンなしでもゲームへの没入感が非常に高いです。
また、双方向AIノイズキャンセリング機能も搭載されています。これにより、オンラインゲームでのボイスチャット時に、こちらのマイクに入る環境音と、相手から聞こえるノイズの両方をフィルタリングしてくれます。これにより、ゲームサウンドを妨げられることなく、クリアな音声でのコミュニケーションが可能でした。
ディスプレイとオーディオのまとめ
- ディスプレイ:7インチ フルHD (1920×1080)、輝度500nits、sRGB 100%で明るく色鮮やか。
- 滑らかさ:120Hzの高リフレッシュレートとAMD FreeSync Premiumにより、カクつきや残像感のない滑らかな映像を実現。
- 視認性:Gorilla Glass DXC採用で、屋外での視認性が高く反射も抑制。
- オーディオ:Dolby Atmos対応のデュアルスピーカーを搭載し、携帯機とは思えない高音質と迫力を実現。
- ノイズキャンセル:双方向AIノイズキャンセリング機能により、クリアなボイスチャットが可能。
操作性:ROG Ally (RC71L) 直感的で快適なゲームコントロール体験
ここでは、ポータブルゲーミングPC「ROG Ally (RC71L)」が提供する優れた操作性と、それがどのように快適なゲームプレイ体験に繋がるのかを、具体的な機能や実際の使用感を交えながら書いていきます。
馴染みやすく高精度な基本コントロール
ROG Ally (RC71L)のコントローラーレイアウトは、多くのPCゲーマーに親しまれているXbox準拠の配置を採用しています。そのため、箱から出してすぐに直感的な操作が可能です。A/B/X/Yボタンは適度なクリック感があり、アナログスティックの精度も高く、FPS/TPSでのスムーズなエイム操作も行えました。
スティックの感触はややバネの抵抗が少なめ(柔らかめ)に感じられるかもしれませんが、慣れれば問題ない範囲です。一方、十字キーは一部の格闘ゲームなどで複雑なコマンド入力を正確に行うには少しコツが必要かもしれません。
プレイスタイルを拡張するカスタマイズ性
ROG Ally (RC71L)の操作性の魅力は、基本コントロールの質の高さだけではありません。本体背面にはカスタマイズ可能な2つのマクロボタン(M1, M2)が搭載されており、ここに頻繁に使用するアクションやショートカットを割り当てられます。
これらのカスタマイズは、専用ソフトウェア「Armoury Crate SE」から簡単に行えます。ボタンマッピングだけでなく、スティックの感度調整やデッドゾーンの設定、振動の強度まで、自分のプレイスタイルに合わせて細かく調整できるのは非常に嬉しいポイントです。
没入感を高める独自機能(ハプティクス・ジャイロ)
ゲームへの没入感を深める機能も充実しています。HDハプティクス(振動機能)は非常に優秀で、単なる振動ではなく、ゲーム内の状況に応じた多彩でリアルな振動が手に伝わります。爆発の衝撃や銃の発射反動などがよりダイレクトに感じられ、臨場感が格段に向上しました。
また、本体には6軸ジャイロセンサーも搭載されています。これにより、対応しているゲームでは本体の傾きを利用した直感的なエイム操作が可能です。ただし、標準ではジャイロ機能が有効にならないゲームもあり、その場合はサードパーティ製のソフトウェアを導入するなどの工夫が必要になる場面もありました。
操作性のまとめ
- レイアウト:多くのゲーマーに馴染みやすいXbox準拠のボタン・スティック配置を採用。
- カスタマイズ性:背面に2つのマクロボタンを搭載し、Armoury Crate SEで詳細なキー割り当てや感度調整が可能。
- 振動機能:HDハプティクスによるリアルな振動フィードバックで、ゲームの没入感が向上。
- ジャイロ機能:6軸ジャイロセンサーを搭載し、対応ゲームでは直感的なエイム操作が可能。
- スティックとボタン:スティックの精度は高いが感触は柔らかめ。ボタンは1,000万回の耐久テストをクリアしている。
バッテリーと冷却:ROG Ally (RC71L) の持続時間と安定性
ここでは、ROG Ally (RC71L)のポータブル機としての生命線である「バッテリー持続時間」と、パフォーマンスを維持するための「発熱および冷却性能」について、詳しく書いていきます。
バッテリー持続時間の実態
ROG Ally (RC71L)の最大の弱点とも言えるのが、バッテリー持続時間です。40Whのリチウムポリマーバッテリーを搭載しており、公式の数値ではヘビーゲームのプレイで最大約2時間、動画視聴で最大約6.8時間とされています。
実際に試してみたところ、この数値は設定(TDP)とプレイするゲームに大きく左右されます。例えば、TDPを最大にするターボモードで『サイバーパンク2077』のようなAAAタイトルをプレイすると、1時間持たない(約45分)こともありました。一方で、TDPを抑えるサイレントモードでノベルゲームや2Dゲームを遊ぶ場合は、2時間半から3時間程度は持つ印象です。多くの3Dゲームを快適に遊ぶにはパフォーマンスモード以上が必要で、その場合の現実的な駆動時間は1時間半から2時間程度と考えておくのが妥当です。
充電機能と拡張アクセサリー
心強いのは、付属のType-C/65W ACアダプターによる急速充電機能です。公式の情報では、わずか30分でバッテリー残量を0%から約50%まで回復できるとされています。この65Wという電力はターボモード(30W)を安定して動作させるためにも重要で、低出力のアダプターでは電力不足の警告が出ることがあります。
ただし、汎用ポートはUSB Type-Cが1基のみで、充電にポートが占有されてしまうのが難点です。この問題を解決し、充電しながら大画面プレイやPCとしての利用を可能にするのが、別売の専用アクセサリーです。「ROG Gaming Charger Dock」は、ACアダプターとUSBハブが一体化した製品で、本体へのPD 3.0規格による急速充電、HDMI 2.0での映像出力、そして外部コントローラーなどを接続できるUSB Type-Aポートを同時に利用できます。
発熱と優れた冷却性能
これだけのパフォーマンスをこの薄型筐体で実現しているため、高負荷時の発熱は相応にあります。特に本体上部の排気口付近はかなりの熱を持ちますが、注目すべきは、その熱がプレイヤーの手にほとんど伝わらないように設計されている点です。
その秘密は、ASUS独自の「ROG Intelligent Cooling」システムにあります。本体の向きに影響されないアンチグラビティヒートパイプと、2つのファンを搭載したデュアルファン設計により、効率的に熱を排出します。このファンは非常に静音性が高く、ターボモード時でも最大30dB程度と、ゲーミングノートPCと比べても静かです。高負荷時でもファンの音がゲーム音を妨げることは少なく、快適にプレイを続けられました。
バッテリーと冷却のまとめ
- バッテリー持続時間:AAAタイトルのTurboモードでのプレイは1時間半から2時間が目安。
- Silentモードや動画視聴:軽量ゲームでは3時間以上、動画視聴では最大約6.8時間と、より長く使用可能。
- 急速充電:付属の65Wアダプターにより、30分で約50%まで急速充電が可能。
- 充電アクセサリー:充電と映像出力を両立する「ROG Gaming Charger Dock」などが別売で用意されている。
- 冷却性能:デュアルファンとヒートパイプによる「ROG Intelligent Cooling」を搭載し、冷却性能は高い。
- 発熱と静音性:高負荷時は本体上部が熱くなるが、グリップ部には熱が伝わりにくい設計。ファンは非常に静音性が高い。
独自機能とカスタマイズ性:ROG Ally (RC71L) のゲーム体験を最適化
ここでは、ROG Ally (RC71L)がゲームプレイを快適にするために搭載している、ソフトウェアによる直感的な操作体系と、没入感を高めるハードウェアの独自機能について書いていきます。
直感操作を実現するコマンドセンターと高度なカスタマイズ性
ゲームプレイ中の快適性を格段に向上させてくれるのが、「コマンドセンター」機能です。これは専用ボタン一つで呼び出せるオーバーレイメニューで、パフォーマンスモードの切り替え(サイレント: 9W、パフォーマンス: 15W、ターボ: 25W、ACアダプター接続時は最大30W)、画面の明るさや音量調整、リアルタイムのシステム情報表示、FPSリミッターの設定などを、ゲームを中断することなく素早く行えます。
バッテリー残量を気にしながら静かにプレイしたい時はサイレントモード、最高のパフォーマンスを引き出したい時はターボモードといった使い分けが瞬時にできるのは、ポータブルデバイスとして非常に大きな利点です。
「Armoury Crate SE」では、操作性のカスタマイズも自由自在です。各ボタンの割り当て変更はもちろん、本体背面に搭載された2つのマクロボタン(M1、M2)には、よく使うキーコンビネーションなどを登録できます。例えば、『モンスターハンターライズ』でアイテムショートカットを割り当てたところ、狩りの効率が格段に上がりました。また、スティック周りのRGBライティング「Aura Sync」の発光パターンや色を自分好みに設定できるのも、ゲーミングデバイスならではの楽しみの一つです。
独自機能とカスタマイズ性のまとめ
- コマンドセンター:ゲームを中断せず、パフォーマンスモード(TDP)やFPSリミッターなどに即時アクセス可能。
- Armoury Crate SE:背面マクロボタンを含むキー割り当てや、Aura Syncライティングを自由にカスタマイズできる。
アクセサリー:ROG Ally (RC71L) 体験を拡張する周辺機器
ここでは、ROG Ally (RC71L)のポテンシャルをさらに引き出し、デスクトップPC化したり、大画面で楽しんだりするための専用アクセサリーや周辺機器について書いていきます。
真価を発揮させる専用オプション:ROG XG Mobile
ROG Ally (RC71L)のポテンシャルを最大限に引き出すための切り札とも言えるのが、ASUS独自の外部グラフィックスデバイス「ROG XG Mobile」です。これは専用のインターフェースを介してROG Allyに接続することで、NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop GPUといったデスクトップPCクラスの圧倒的なグラフィック処理能力を付加します。
これにより、ROG Ally単体では設定を妥協せざるを得なかった最新のAAAタイトルも、高解像度・高フレームレートで快適にプレイ可能になり、レイトレーシングを駆使した美麗な映像世界も存分に楽しめます。ROG XG Mobile自体に豊富なI/Oポート(USB、HDMI、有線LANなど)も備わっているため、まさにROG Allyを高性能ゲーミングデスクトップへと変貌させるドッキングステーションと言えるでしょう。
手軽な大画面出力とPC利用:ROG Gaming Charger Dock
より手軽にデスクトップライクな体験や、リビングでの大画面プレイを実現したい場合には、「ROG Gaming Charger Dock」が便利です。これはACアダプターとUSBハブが一体化した製品で、ROG Allyを充電しながらHDMI 2.0経由でテレビやモニターに映像を出力できます。さらにUSB Type-Aポートも備えているため、外部コントローラーやキーボード・マウスを接続して、据え置きゲーム機のようにソファでくつろぎながら遊んだり、PCとして作業したりする際に役立ちます。
携帯性と保護、そしてさらなる周辺機器
ROG Ally (RC71L)を外出先へ安全に持ち運ぶためには、専用ケース「ROG Ally Travel Case」が用意されています。これは撥水加工が施された生地で作られており、本体を保護するだけでなく、小物類を収納するスペースや簡易スタンド機能も備わっています。
さらに、ASUSはROGブランドの高性能な周辺機器も展開しています。例えば、低遅延接続とノイズキャンセリング機能を備えたワイヤレスイヤホン「ROG Cetra True Wireless」や、OLEDディスプレイを搭載し多彩なカスタマイズが可能なコントローラー「ROG Raikiri Pro」などがあり、これらを組み合わせることで、より質の高いゲーミング環境を構築できます。もちろん、Windows PCであるため、市販のUSB Type-CハブやBluetooth接続の周辺機器も幅広く利用可能です。
アクセサリーのまとめ
- ROG XG Mobile:RTX 4090 Laptop GPUを接続可能にし、豊富なポートも備えた究極のドッキングステーション。
- ROG Gaming Charger Dock:充電とHDMI出力、USBポートを兼ね備え、手軽に大画面プレイを実現。
- ROG Ally Travel Case:撥水加工とスタンド機能を備えた、持ち運びに便利な専用ケース。
- その他:ROG Raikiri ProコントローラーやROG Cetraイヤホンなど、体験を向上させる多彩なオプションが用意されている。
ROG Ally (RC71L)のメリット・デメリット:購入前に知っておきたいポイント
ASUSが投入したポータブルゲーミングPC「ROG Ally (RC71L)」は、その高い性能とWindows 11搭載による汎用性で多くのゲーマーから注目を集めています。しかし、実際に購入を検討する際には、魅力的な点だけでなく、注意しておきたいポイントも理解しておくことが重要です。ここでは、ROG Allyが持つ主なメリットとデメリットを、具体的な側面から解説していきます。
メリット
メリット1:パワフルなパフォーマンスと美麗なディスプレイ
ROG Ally (RC71L)の最大の魅力の一つは、AMD Ryzen Z1 Extremeプロセッサ(上位モデル)がもたらす卓越した処理性能です。これにより、多くのPCゲームを携帯機でありながら快適にプレイすることが可能です。加えて、リフレッシュレート120Hzに対応したフルHD解像度の7インチIPSディスプレイは、非常に滑らかで美しい映像を描写します。輝度も高く、sRGBカバー率100%の色再現性により、ゲームの世界観を鮮やかに映し出し、没入感を高めてくれます。
メリット2:Windows 11搭載による圧倒的な汎用性とゲーム互換性
オペレーティングシステムにWindows 11 Homeを搭載している点は、ROG Ally (RC71L)の汎用性を飛躍的に高めています。Steam、Xbox Game Pass、Epic Games Storeなど、主要なPCゲームプラットフォームのほぼ全てのゲームをプレイできる互換性の高さは、専用OSを搭載する一部の携帯ゲーム機に対する大きなアドバンテージです。また、ゲーム以外の一般的なWindowsアプリケーションも利用できるため、動画視聴やブラウジング、簡単なドキュメント作業など、一台で多岐にわたる用途に対応できます。
メリット3:快適な操作性と便利な独自機能
Xboxコントローラーに準じたボタン配置は多くのゲーマーにとって馴染みやすく、直感的な操作を可能にしています。ホール効果を採用したアナログトリガーや、カスタマイズ可能な背面の追加ボタン(マクロキー)も、より快適で高度なゲームプレイをサポートします。ASUS独自の統合管理ソフト「Armoury Crate SE」は、ゲームライブラリの一元管理やパフォーマンスモードの簡単な切り替え、各種設定のカスタマイズなどをスムーズに行えるように設計されており、Windows機でありながらゲーム専用機に近い手軽さを提供しています。
メリット4:高い拡張性と優れたオーディオ体験
ROG Ally (RC71L)は、別売りの外付けGPUユニット「ROG XG Mobile」を接続することで、デスクトップのハイエンドゲーミングPCに匹敵するグラフィック性能を発揮できるという、他に類を見ない拡張性を秘めています。また、Dolby Atmosに対応したデュアルスピーカーは、携帯機とは思えないほどクリアで迫力のあるサウンドを実現し、ゲーム体験の質を一層高めます。Wi-Fi 6Eへの対応や、UHS-II対応のmicroSDカードスロットなど、通信速度やストレージ拡張の面でも配慮されています。
デメリット
デメリット1:バッテリー駆動時間と携帯時の注意点
高性能なプロセッサとディスプレイを搭載しているため、特に負荷の高いゲームをプレイする際のバッテリー駆動時間は、多くのユーザーが懸念するポイントです。公称値では長時間の利用が可能とされていますが、AAAタイトルを快適な設定で遊ぶ場合、1.5時間から2時間程度でバッテリー残量が厳しくなることもあります。外出先で長時間プレイしたい場合は、65Wの急速充電に対応しているとはいえ、モバイルバッテリーの携行や電源を確保できる場所の確認が推奨されます。
デメリット2:Windows OS特有の操作感とインターフェースの制約
Windows 11は汎用性が高い一方で、タッチ操作やコントローラー操作がメインとなるポータブルデバイスにおいては、マウスやキーボードを前提とした操作感が残る場面もあります。「Armoury Crate SE」によってゲーム中心の操作性は向上していますが、OSレベルでの細かな設定変更やトラブルシューティング時には、Windows特有の知識や一手間が必要になることがあります。また、USB Type-Cポートが1基のみであるため、充電しながら複数の有線周辺機器を利用したい場合には、別途USBハブやドックが必要となる点は注意が必要です。
デメリット3:ストレージ容量とオプション製品の価格
上位モデルでも内蔵SSDは512GBであり、近年の大容量化が進むAAAタイトルを複数インストールするには、やや心許ない容量と言えます。microSDカードでの拡張は可能ですが、ロード速度や安定性の面では内蔵SSDに劣る場合があります。さらに、本機のポテンシャルを最大限に引き出すROG XG Mobileのような専用オプション製品は非常に高価であり、全てのユーザーが気軽に導入できるものではないという側面も考慮に入れるべきでしょう。
ROG Ally (RC71L)のスペック(仕様)
- モデル: RC71L-Z1E512 (Ryzen Z1 Extreme搭載) / RC71L-Z1512 (Ryzen Z1搭載)
- ディスプレイ: 7.0型ワイドTFTカラー液晶、1,920×1,080ドット (FHD/16:9)、グレア、タッチパネル搭載 (10点マルチタッチ)、輝度 500nit、sRGB 100%、Corning Gorilla Glass Victus、Corning Gorilla Glass DXC、AMD FreeSync Premium対応
- リフレッシュレート: 120Hz
- 応答時間: 7ms
- プロセッサ: AMD Ryzen™ Z1 Extreme プロセッサー (Zen 4 / 4nm / 8コア / 16スレッド / 最大5.10 GHz)
(下位モデル): AMD Ryzen™ Z1 プロセッサー (Zen 4 / 4nm / 6コア / 12スレッド / 最大4.90 GHz) - GPU: AMD Radeon™ グラフィックス (AMD RDNA™ 3アーキテクチャ、CPU内蔵) (Z1 Extreme: 最大8.6TFlops FP32 / Z1: 最大2.8TFlops FP32)
- RAM(メモリ): 16GB LPDDR5-6400 (デュアルチャネル・オンボード)
- ストレージ: 512GB PCIe 4.0 NVMe™ M.2 SSD (2230) (※日本国内モデルは512GB)
- バッテリー: 40WHrs、4セル リチウムポリマーバッテリー
- 駆動時間: 約10.2時間 (※資料内にはヘビーゲームで最大約2時間、動画再生で最大約6.8時間との記載もあり)
- 充電: Type-C、65W ACアダプター (出力: 20V DC、3.25A、65W、入力: 100~240V AC 50/60Hz ユニバーサル)
- ワイヤレス通信: Wi-Fi 6E (IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax)、Bluetooth 5.4
- インターフェース: ROG XG Mobileインターフェース ×1 (USB Type-C 3.2 Gen2と兼用、DisplayPort 1.4および給電サポート)、UHS-II microSD カードスロット ×1 (microSD/microSDHC/microSDXC対応)、3.5mm マイクロホン/ヘッドホン/ヘッドセット・コンボジャック ×1
- スピーカー: デュアル ステレオスピーカー (スマートアンプテクノロジー採用)
- マイク: 内蔵アレイマイク
- オーディオ: 双方向AIノイズキャンセリング、ハイレゾ認定、Dolby Atmos
- センサー: 加速度センサー、ジャイロセンサー搭載 (6軸IMU)
- 振動: HDハプティクス (レビュー情報に基づく)
- 操作: アナログ スティック x 2、A B X Y ボタン、方向ボタン (十字キー)、L&R アナログトリガー、左右バンパー、割り当て可能なマクロボタン x 2 (背面)、Armoury Crate ボタン、表示ボタン、メニューボタン、コマンドセンターボタン
- 生体認証: 指紋認証 (電源ボタン一体型)
- アプリ: ROG Armoury Crate SE (ゲームライブラリ、キーマップカスタマイズ、Aura Sync調整など)
- OS: Windows 11 Home 64ビット
- サイズ: 幅280.0mm × 奥行き111.38mm × 高さ21.22~32.43mm
- 重量: 約608g
- カラー: ホワイト
ROG Ally (RC71L) 再評価(2025年5月版):熟成されたWindowsポータブルゲーミングPCの実力
ASUSから登場し、ポータブルゲーミングPC市場に大きなインパクトを与えた「ROG Ally (RC71L)」。発売から時間が経過した現在(2025年5月)、その評価はどのように変化したのでしょうか。当時の興奮を振り返りつつ、現在の市場環境と照らし合わせながら、ROG Allyの各項目と総合的な実力について改めて評価していきます。
各項目評価(2025年5月時点)
スペック:★★★★★
Ryzen Z1 Extremeプロセッサ(上位モデル)が提供する処理能力は、発売から約2年が経過した2025年現在においても依然として高く、多くのPCゲームを快適に楽しむことができます。特に、120Hzの高リフレッシュレートに対応したフルHDディスプレイは、滑らかで美しい映像を提供し続け、視覚的な満足度は非常に高いレベルを維持しています。最新世代のAPU搭載機と比較すれば見劣りする場面もありますが、総合的なパフォーマンスバランスは優れています。
通信:★★★★☆
Wi-Fi 6Eに対応している点は、現在でも十分に高速で安定した無線通信環境を提供します。オンラインゲームや大容量データのダウンロードも快適に行えるでしょう。ただ、市場にはさらに新しいWi-Fi 7規格に対応したデバイスも登場し始めているため、絶対的な最先端とは言えなくなりました。とはいえ、実用上ほとんどのユーザーにとっては十分以上の性能です。
機能:★★★★★
専用ソフトウェア「Armoury Crate SE」によるゲームランチャー機能やパフォーマンス管理、カスタマイズ可能なボタン設定、そして独自のRGBライティングなど、ゲーミング体験を豊かにする機能は非常に充実しています。特に、別売りの外付けGPUユニット「ROG XG Mobile」との連携によるグラフィック性能の大幅な向上は、本機ならではのユニークな拡張性であり、その価値は依然として高いと言えます。
デザイン:★★★★☆
人間工学に基づいて設計されたグリップ形状やボタン配置は、長時間のプレイでも疲れにくい快適な持ちやすさを提供します。約608gという重量は、現在の視点で見ると標準的か、やや重めと感じるかもしれません。より軽量なポータブルゲーミングPCも登場しているため、携帯性を最重視するユーザーにとっては比較検討のポイントとなり得ます。
使いやすさ:★★★★☆
Windows 11を搭載しているため、幅広いPCゲームやアプリケーションが動作する汎用性の高さは大きな魅力です。「Armoury Crate SE」によってゲーム機ライクな操作感も提供されていますが、OSの基本的な部分はWindowsであるため、時折PC的な操作や設定の知識が求められる場面もあります。専用OSを搭載した一部の携帯ゲーム機と比較すると、手軽さの面で一歩譲る部分は否めません。
価格:★★★★☆
発売当初、その高性能に対する価格設定は市場に衝撃を与えましたが、2025年現在では後継機種の噂や多数の競合製品が登場し、新品価格の魅力は相対的に落ち着いてきました。しかし、中古市場やセール時においては、依然として高いコストパフォーマンスを発揮する有力な選択肢の一つです。トータルバランスを考えれば、十分納得できる価格帯にあると言えるでしょう。
総評(2025年版)★★★★☆
市場を切り開いた先駆者、色褪せぬ基本性能
ROG Ally (RC71L)は、Windows搭載ポータブルゲーミングPCというカテゴリーを一般のゲームユーザーに広く認知させた立役者の一つと言えるでしょう。発売から時間が経過した2025年5月現在でも、その中心的な魅力であるRyzen Z1 Extremeプロセッサのパワフルな性能と、120Hzの美麗なディスプレイは健在で、多くのゲームを快適に楽しむための実力を十分に有しています。この基本性能の高さが、今なお多くのユーザーに支持される理由の一つです。
独自ソフトウェアと拡張性が光る
ASUS独自の「Armoury Crate SE」は、Windowsマシンでありながらゲームコンソールに近い操作感を提供し、使い勝手の向上に貢献しています。ゲームライブラリの一元管理やパフォーマンス設定の容易さは特筆すべき点です。また、「ROG XG Mobile」によるグラフィック性能の拡張というユニークな特徴は、本機を単なる携帯ゲーム機以上の存在たらしめています。ただし、このXG Mobileは依然として高価であり、誰もが気軽に利用できるオプションとは言えません。
携帯性とOS:ユーザーの工夫が求められる点
一方で、バッテリー駆動時間に関しては、高性能なハードウェアを搭載している以上、特にAAAタイトルを高設定でプレイする際には、依然としてユーザーの工夫(設定調整やモバイルバッテリーの活用など)が求められます。また、Windows OSの汎用性はメリットであると同時に、ポータブル機としての手軽さや最適化の面では、専用OSを搭載した競合機に比べてユーザーを選ぶ部分があることも事実です。ある程度のPC知識があった方が、本機のポテンシャルをより引き出しやすいでしょう。
2025年現在の選択肢としての魅力と推奨ユーザー
2025年現在、市場には最新世代のAPUを搭載した新しいポータブルゲーミングPCが多数登場し、ROG Ally (RC71L)も選択肢の一つとして相対的に評価されるようになりました。しかし、完成度の高いハードウェア、豊富な機能、そしてWindowsの自由度といった要素は色褪せておらず、特に中古市場やセール価格で手に入れられるならば、依然として非常に魅力的な一台です。PCゲームを手軽に持ち出して遊びたい、かつWindows環境の恩恵も受けたいと考えるユーザーにとって、ROG Allyは引き続き有力な候補となるでしょう。
ROG Ally (RC71L)の価格・購入先
※価格は2025/11/09に調査したものです。価格は変動します。
ASUSストア
RC71L-Z1E512(Ryzen™ Z1 Extreme)
109,800円で販売されています。
ASUSストアで「ROG Ally (RC71L)」をチェックする
ECサイト
- Amazonで81,890円(Ryzen™ Z1 Extreme)、
- 楽天市場で79,777円(送料無料・Ryzen™ Z1 Extreme)、
- ヤフーショッピングで77,800円(Ryzen™ Z1 Extreme・中古は71,930円)、
- 米国 Amazon.comで$649.00、
で販売されています。
Amazonで「ROG Ally (RC71L)」をチェックする
楽天市場で「ROG Ally (RC71L)」をチェックする
ヤフーショッピングで「ROG Ally (RC71L)」をチェックする
AliExpressで「ROG ALLY」をチェックする
米国 Amazon.comで「ROG ALLY」をチェックする
おすすめのライバル機種と価格を比較
「ROG Ally (RC71L)」に似た性能をもつポータブルゲーミングPCも販売されています。価格の比較もできるので、ぜひ参考にしてみてください。
ROG XBOX ALLY / Ally X
ASUS (ROG) から発売された7.0インチのポータブルゲーミングPCです(2025年10月16日に発売・型番:RC73YA-Z2A16G512/RC73XA-Z2E24G1T)。
7.0型ワイドTFTカラー液晶 (1,920×1,080, 120Hz, FreeSync Premium対応)、AMD Ryzen™ Z2 A (Ally) / AMD Ryzen™ AI Z2 Extreme (Ally X)、LPDDR5X 16GB (Ally) / 24GB (Ally X) メモリ、SSD 512GB (Ally) / 1TB (Ally X) (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2 2280)、60Wh (Ally) / 80Wh (Ally X) バッテリー、Windows 11 Home 64ビットを搭載しています。
また、Xboxアプリ、UI「Xboxフルスクリーンエクスペリエンス」、Xboxボタン(Game Bar)、「Xbox Play Anywhere」、ASUSの管理コンソール「Armoury Crate Special Edition (ACSE)」、AMD Ryzen™ AI (NPU※Ally Xのみ)、モニター出力、内蔵SSDの交換(換装)に対応。
ステレオスピーカー (Dolby Atmos / Hi-Res Audio対応)、アレイマイク、HD振動機能 (Ally Xはインパルストリガー対応)、ROGインテリジェントクーリング (デュアルファン)、ジョイスティック×2(RGBライティング)、マクロボタン×2、バンパー/トリガー、指紋認証センサ (電源ボタン一体型)、USB Type-Cポート (Ally XはUSB4対応)、microSDカードスロット、Wi-Fi 6E、Bluetooth® 5.4にも対応しています。
価格は、Amazonで89,800円(ROG XBOX ALLY / Ally Xは139,800円)、楽天市場で93,980円(中古品・送料無料)、ヤフーショッピングで97,939円、米国 Amazon.comで$599.00、です。
関連記事:ROG XBOX ALLY/Ally X評価レビュー!期待以上の性能・機能か?
Amazonで「ROG XBOX ALLY」をチェックする
ROG Ally X
ASUSから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2024年7月 発売)。
AMD Ryzen Z1 Extreme、24GB LPDDR5-7500、フルHDののIPS タッチスクリーン、1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2280)、80WHrsバッテリー、6軸ジャイロセンサー、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、デュアル ステレオスピーカー、Dolby Atmos、アレイマイク、AIノイズキャンセリング、HDハプティクス、Microsoft Pluton セキュリティ、指紋認証、AURA SYNC、Gorilla Glass DXC、USB4 Gen2 Type-C x1、USB 3.2 Gen2 Type-C x1、Wi-Fi 6e、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、楽天市場で127,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで127,800円、です。
関連記事:ROG Ally Xは買うべきか?できるゲームとグラフィック性能をレビュー
Amazonで「ROG Ally X」をチェックする
TENKU LUNA
TENKUから発売される7インチのポータブルゲーミングPCです(2025年5月30日に発売)。
AMD Ryzen 7 7840U、AMD Radeon™ 780M GPU グラフィックス(内蔵, RDNA 3, 12CU, 最大8.6TFLOPS)、32GB LPDDR5(6400/6500MHz)メモリ、7インチ フルHD (1920×1080) LCD IPSディスプレイ(タッチ対応・輝度450nits, sRGB 100%)、PCIe 4.0×4 M.2 2280 SSD 1TB/2TBストレージ、50.04Wh バッテリー、Windows 11 Home 64bitを搭載しています。
また、専用アプリ「GameAssistant」、TDP切替 (15W/28W)、クイックボタン(GameAssistant起動)、ホームボタン(Xbox Game Bar起動)リフレッシュレート120Hz、PD急速充電(65W ACアダプター付属・USB4経由)に対応。
デュアルステレオスピーカー (フロント)、デュアルマイク、6軸ジャイロセンサー、デュアルリニア振動モーター、効率の良い放熱システム (吸気孔拡大)、microSD 4.0、指紋認証 (電源ボタン一体型)、専用ケース(付属・先行予約特典)、国内サポート(一年間の保証付き)、USB4 Type-C x2 (充電/DP/eGPU接続)、Wi-Fi 6E (Intel AX210)、Bluetooth 5.3にも対応しています。
※現在、販売されていません。
関連記事:TENKU LUNA徹底レビュー!驚きのコスパ性能とROG Allyとの違い
Amazonで「TENKU LUNA」をチェックする
Steam Deck OLED
米国 Valve から発売された7.4インチのポータブルゲーミングPCです(2023年11月17日に発売)。
Steam OS 3.0、Zen2ベースのAMD APUと16 GB LPDDR5 メモリ、HD画質のHDR OLED(有機EL)タッチスクリーン、512GB/1TB NVMe SSD、50 Whバッテリー、トラックパッドを搭載しています。
また、リフレッシュレート 90 Hz、HDハプティクス、大型の冷却ファン、DSP内蔵ステレオスピーカー、デュアルアレイマイク、microSDカードでのストレージ拡張、45W急速充電、6軸ジャイロセンサー、Steam Deck ドッキングステーション(別売)、USB3 Gen2 Type-C (DP映像出力/PD充電/データ転送)x1、Wi-Fi 6E、Bluetooth 5.3に対応しています。
価格は、Amazonで155,231円、楽天市場で93,680円、ヤフーショッピングで94,700円、です。
関連記事:Steam Deck OLEDとROG Ally Xを比較!ゲーム性能レビュー
Amazonで「Steam Deck OLED」をチェックする
MSI Claw A1M
MSIから発売された7インチのポータブルゲーミングPCです(2024年3月28日 発売)。
インテル Core Ultra 5 135H / Core Ultra 7 155H、インテル Arc グラフィックス、16GB LPDDR5-6400メモリ、フルHDのIPS液晶、512GB SSD / 1TB SSD ストレージ (NVMe PCIe Gen4)、53 WHrバッテリ、Windows 11 Homeを搭載しています。
また、リフレッシュレート 120Hz、65W PD急速充電、2x 2W スピーカー、ハイレゾオーディオ認定、HD ハプティクス、指紋認証、人間工学に基づいたデザイン、管理ソフト「MSI Center M」、ゲームライブラリ「App Player」、Thunderbolt 4 互換のType-Cポート、Wi-Fi 7、Bluetooth 5.4 に対応しています。
価格は、Amazonで87,120円(税込・CoreUltra5/16GB/SSD1TB)、楽天市場で93,780円(送料無料)、ヤフーショッピングで88,500円、です。
関連記事:実は不人気じゃない「MSI Claw A1M」のメリット・デメリット
Amazonで「MSI Claw A1M」をチェックする
その他のおすすめゲーム製品は?
その他のおすすめゲーム製品は以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
ポータブルゲーミングPCはどれを選ぶべきか? 最新の全機種と選び方を紹介
最新のポータブルゲーミングPCをまとめて紹介しています。
AYANEOのポータブルゲーミングPCがやはり最強か? 全機種 まとめ
AYANEOのポータブルゲーミングPCをまとめて紹介します。
GPD WIN シリーズ・XP ゲーム機の全機種 ラインナップを比較
GPDの超小型PC(UMPC)やタブレットをまとめています。