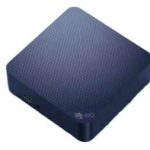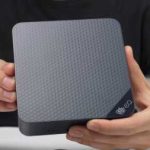2025年6月、ミニPCの分野で高い評価を得ているBeelinkから、家庭のデータ管理に革命をもたらす一台が登場しました。その名は「Beelink ME mini」。手のひらに収まるほどのコンパクトなキューブ型デザインでありながら、最大6基ものM.2 SSDを搭載できるという、常識を覆すストレージ拡張性を備え、発売前から大きな注目を集めています。
Beelink ME miniの魅力
最大の魅力は、単なる小型PCに留まらず、家庭内のあらゆるデータを一元管理できる強力なネットワークサーバーとして、多様な使い方ができることです。
例えば、スマートフォンやPCに散らばった大切な写真や動画をME miniに集約し、自動でバックアップする自分だけのプライベートクラウドを構築したり、
強力なメディアサーバーとしてNASに保存した映画や音楽を、DLNAに対応したテレビやPlayStation 5などのゲーム機で、いつでも高画質・高音質でストリーミング再生したりできます。
また、最大6基のM.2 SSDスロットをサポートし、合計容量を最大24TBまで拡張できる圧倒的なストレージ性能も装備。Windows 11やLinuxはもちろん、本格的なNASを構築するためのTrueNASやUnraid、仮想化基盤であるProxmoxなど、専門的なOSを自由にインストールできる柔軟性も兼ね備えています。
その他にも、従来の約2.5倍の速度で高速かつ安定した通信を利用できるデュアル2.5GbE LANポートを搭載。
デスク周りをすっきりさせる電源内蔵のコンパクトなキューブ型デザイン、高速なデータ転送が可能なUSB Type-Cポート、最新の高速ワイヤレス通信規格WiFi 6、そして作業の邪魔にならない静音設計など、魅力が満載です!
この記事で「Beelink ME mini」を徹底解剖!
この記事では、そんな魅力あふれる「Beelink ME mini」の性能や機能を、ベンチマーク結果や実際の使用感を交えながら、徹底的に深掘りしていきます。
特に、同じCPUを搭載しながらもコンセプトが全く異なる「Beelink EQ14」との比較に焦点を当て、ME miniがどのような点で優れ、どのようなユーザーにとって最適な選択肢となるのかを、明らかにしていきます。
【この記事で分かること】
- Beelink ME miniの実機レビューと、項目別の5段階評価
- デザイン、インターフェース、パフォーマンスなど各項目の詳細なレビュー
- メモリやポート、本体サイズなど、Beelink ME miniの詳細なスペック(仕様)一覧
- Intel N150のCPU・グラフィック性能が分かる各種ベンチマークスコア
- 「原神」や「Apex Legends」など人気ゲームの動作検証(ゲーム性能)
- 最大24TBまで拡張可能なストレージ性能と、NASとしての実力
- Beelink EQ14との詳細なスペック比較と、GMKtec NucBox G9など他のライバル製品との違い
- 公式サイトやAmazonなど、購入先ごとの販売価格と参考となるクーポン適用例
- 購入前に知っておきたいメリット・デメリットと、最適なユーザー像
この記事を最後まで読むことで、「Beelink ME mini」が本当にあなたにとって「買い」の製品なのか、その答えがはっきりと分かるはずです。購入を悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク
公式ページ:Beelink | Beelink ME mini 6-slot Home Storage NAS Mini PC
価格をチェック!Beelink ME miniは他のミニPCよりも安い?
Beelink ME miniはBeelink 公式サイトで$209.00~(日本円で約30289円~・ストレージは64G eMMCのみ)で販売されています。2TBストレージが追加されたモデルは$329.00(日本円で47680円)です。
一方、ECサイトのAmazonでは実質48,900円(15000円 OFFクーポン適用の場合・+2TB SSDモデル)で販売中です。
海外ストアのAliExpress(56,964円・+2TB SSD)、米国 Amazon.com($409.00で$80 OFFクーポン付き・+2TB SSD)でも購入できます。
Beelink EQ14
2024年12月に発売された「Beelink EQ14」はAmazonで27,800円で販売中です。こちらは、Intel N150プロセッサを搭載したコンパクトなミニPCです 。最大の魅力は電源ユニットを内蔵している点で、付属の電源ケーブル1本で設置が完了するため、デスク周りがすっきりと片付きます 。
コンパクトながら4Kの3画面出力に対応し、2つのLANポートも備えているため、複数のモニターでの作業や安定したネットワーク接続が可能です 。底面にはホコリの侵入を防ぐフィルターが設置されており、長く安心して使える設計も嬉しいポイントです 。日常使いからビジネスまで、スマートにこなせる一台です。
GMKtec NucBox G9
2025年1月に発売された「GMKtec NucBox G9」はAmazonで42,473円で販売中です。こちらは、Intel N150プロセッサを搭載し、圧倒的なストレージ拡張性を誇るミニPCです 。内部に4つものM.2スロットを備え、PC用途で最大16TB 、NAS(ネットワーク接続ストレージ)として利用すれば最大32TBまで容量を拡張できます 。
2.5Gの高速LANポートを2つ搭載しており 、家庭やオフィスの大容量データハブとして最適です。12GBの高速LPDDR5メモリと4Kの3画面出力にも対応し 、日常的な作業も快適にこなします。データ保存とパフォーマンスを両立させたい方におすすめです。
MINISFORUM UN150P
2025年1月21日に発売された「MINISFORUM UN150P」はAmazonで31,572円で販売中です。こちらは、Intel N150プロセッサを搭載し、優れた拡張性と接続性を持つミニPCです 。高速なM.2 SSDスロットに加え、大容量の2.5インチHDD/SSDを増設できるベイと、手軽に使えるTFカードスロットを備え、用途に応じた柔軟なストレージ構成が可能です 。
前面にはデータ転送、映像出力、給電に対応した万能なUSB Type-Cポートを搭載 。合計で4Kの3画面出力が可能で、マルチタスクも快適です 。CNC加工された高品質な金属製の筐体も魅力で、所有する満足感を満たしてくれます。
GMKtec NucBox K10
2025年3月に発売された「GMKtec NucBox K10」はAmazonでクーポン適用で実質75,200円で販売中です。こちらは、第13世代Intel Core i9-13900HKプロセッサを搭載した、デスクトップPCに匹敵する性能を誇る究極のミニPCです 。その圧倒的な処理能力は、プロの映像編集や最新のゲームなど、極めて負荷の高いタスクもスムーズにこなします。
最大96GBのDDR5メモリ 、3つのM.2スロットによる最大12TBのストレージ拡張に対応 。さらに、8K映像出力や4画面同時出力も可能で 、クリエイティブな作業環境をパワフルに支えます。まさに妥協を許さないプロフェッショナルのためのマシンです。
まとめ
Beelink ME miniの価格は、単純なミニPCとして見ると「Beelink EQ14」や「MINISFORUM UN150P」よりも高価です。しかし、その価値は家庭用NASとしての優れた設計にあります。最大24TBまで拡張できる6基のM.2スロット を備え、大容量のデータを一元管理したいユーザーにとっては、価格に見合った魅力的な選択肢と言えるでしょう。
最も安くお買い得なモデルは、2万円台で購入可能な「Beelink EQ14」 です。電源内蔵で使いやすく、日常的な用途であれば十分な性能を持っており、コストパフォーマンスを重視するなら最適な一台です。
本格的なNASを構築したい場合は、Beelink ME miniの他に、最大32TBまで拡張可能な「GMKtec NucBox G9」も強力な候補となります。一方で、価格は上がりますが、動画編集やゲームなど最高のパフォーマンスを求めるなら、Core i9を搭載した「GMKtec NucBox K10」が選択肢となります。ご自身の用途と予算に合わせて、最適な一台を選んでみてください。
デザイン:Beelink ME mini ~ 常識を覆す99mmの立方体が生む所有感
ここでは、Beelink ME miniが他のミニPCと一線を画す、その独創的なデザインと、実際に設置して感じた魅力について徹底的にレビューしていきます。単なるPCではなく、インテリアとして「所有する喜び」を与えてくれる、その秘密に迫ります。
はじめに:想像を超えるコンパクトさと質感
まず驚かされたのが、そのサイズ感です。スペック上の数値は知っていましたが、実際に箱から取り出したときの「小ささ」には思わず声が出ました。各辺がわずか99mmという完全な立方体は、手のひらにすっぽりと収まります 。ひんやりとした金属製の筐体は高級感があり、この時点でプラスチックボディのBeelink EQ14とは異なる、ずっしりとした所有感を満たしてくれます。
所有欲を満たすミニマルなデザインとカラー
ME miniのデザインは、細部に至るまで計算されています。私が選んだのは3色のカラーバリエーションのうち「パールホワイト」ですが、この他に「ミッドナイトグレー」「ピーコックブルー」が用意されています 。特にパールホワイトは、白を基調とした私の部屋のインテリアに見事に溶け込み、PC特有の無機質な感じがありません。友人からも「これ、PCなの?」と驚かれるほどでした。
一方、Beelink EQ14は「ネイビーブルー」の1色展開です 。これも落ち着いた良い色ですが、ME miniのように複数の選択肢から自分の部屋に合わせて選べる点は、デザイン性を重視するユーザーにとって大きなアドバンテージだと感じました。
サイズと重量の比較:ME mini vs EQ14
具体的な数値を比較してみましょう。ME miniが99x99x99mmのキューブ型であるのに対し、Beelink EQ14は126x126x39mmという薄く平たい形状です 。デスク上に置いた際の専有面積(フットプリント)はME miniの方が小さいですが、全体の体積では薄いEQ14の方がわずかに小さい計算になります。
しかし、数字以上に重要なのは「体感的なサイズ」です。キューブ型のME miniはどこに置いてもオブジェのように収まりが良く、よりコンパクトに感じられます。重量はEQ14が約490gなのに対し 、ME miniの正確な重量は資料に記載がありませんでした。しかし、その金属ボディからくる適度な重みは、安っぽさを感じさせず、むしろ製品としての信頼性を高めています。
機能美の極み:内蔵電源と静音設計
デザインで特に素晴らしいと感じたのが、機能と美しさの両立です。この小さな筐体でありながら、電源ユニットが内蔵されている点には感動しました 。巨大なACアダプターが不要なため、デスク周りの配線は驚くほどすっきりとします。これはEQ14も同様の利点ですが 、片手で掴めるME miniの方が、部屋から部屋への移動も楽で、その恩恵をより強く感じました。
そして、その静音性は特筆すべき点です。独自の「垂直エアフロー冷却設計」により、アイドル時の動作音は31~34dBAと、深夜の郊外並みの静けさです 。実際に、動画配信サービス「Netflix」で静かな会話シーンが多い映画を鑑賞していても、ファンの音は全く気になりませんでした。これなら、常時稼働させるNASとして寝室に置いても、睡眠を妨げることはないでしょう。
まとめ:デザイン
- 第一印象と形状: 手のひらに収まる99mmの金属製キューブは、プラスチック製の平たいEQ14とは全く異なる高級感と存在感を放つ 。
- カラーバリエーション: インテリアに合わせて選べる3色展開で、特にパールホワイトは部屋によく馴染む 。ネイビーブルー単色のEQ14より選択肢が豊富 。
- サイズ比較: デスク上の専有面積はME miniの方が小さい 。体積ではEQ14が僅かに小さいが、キューブ形状による凝縮感と設置のしやすさはME miniが圧倒的に優れている。
- 機能美: 電源ユニットを内蔵し、かさばるACアダプターを排除したことで、設置場所を選ばない美しい配線整理が可能 。
- 卓越した静音性: 独自の冷却システムにより、高負荷時でも図書館の中のような静けさを保ち、映画鑑賞や音楽鑑賞の邪魔をしない 。
インターフェースと接続性:Beelink ME mini ~ サーバー用途に特化した「選択と集中」
Beelink ME miniのインターフェースは、一般的なミニPCとは一線を画す、明確な目的を持って設計されています。ここでは、汎用的なデスクトップ用途を想定した「Beelink EQ14」と比較しながら、ME miniのポート構成がどのようにサーバー用途へ特化しているのかを、実際に使ってみた感想を交えて詳しく解説します。
ネットワーク:2.5GbEがもたらす圧倒的な速度
ME miniの接続性で最も注目すべきは、そのネットワーク性能です。背面にはIntel i226-Vチップを採用した2.5GbEのLANポートが2つも搭載されています 。
この「2.5GbE(2.5ギガビットイーサネット)」とは、従来のミニPCで標準的な1GbEの約2.5倍、最大2.5Gbpsの通信速度を実現する非常に高速な有線LAN規格です。
高価な専用ケーブルは不要で、多くの家庭で使われているCat5e以上のLANケーブルをそのまま流用できるため、手軽に高速化の恩恵を受けられるのが大きなメリットです。
この差は、1GbEポートしか持たないBeelink EQ14と比較した際に、ME miniがホームサーバーやNAS(ネットワーク接続ストレージ)としての利用をいかに強く意識しているかを示しています。実際に、この2.5倍という速度差は、大容量の動画ファイルをPCからME miniへ転送した際に明確に体感できました。
テストでは合計スループットが約580~600MB/秒に達し 、ギガビット環境ではもたつきを感じる数十GBのデータも、驚くほどスムーズに移動できます。より高度な使い方として、2つのポートを束ねて通信帯域を向上させる「リンクアグリゲーション」に対応している点も、パワーユーザーには見逃せないポイントです 。
映像出力:割り切ったシンプルさの意図
ネットワーク性能を強化する一方で、映像出力は非常にシンプルです。ME miniの映像出力は、背面のHDMIポート1系統のみで、最大4K/60Hzの表示に対応します 。一方、Beelink EQ14は2つのHDMIポートに加え、DisplayPort出力対応のUSB Type-Cポートも備え、最大3画面の同時出力が可能です 。
この違いは、両者の設計思想の違いを明確に示しています。ME miniは、常時稼働し、基本的には画面を接続しない「ヘッドレス」での運用が想定されるNASサーバーとしての役割に最適化されています。OSの初回インストールや、時々メンテナンスで画面に繋ぐ程度であれば、HDMIが1つあれば十分という判断でしょう 。個人的にはDisplayPortも欲しかったところですが、この潔い「選択と集中」こそが、本製品のコンセプトを際立たせていると感じました。
USBポート:用途を絞った合理的構成
USBポートの構成も、サーバー用途を意識したものです。前面には高速な10GbpsのUSB Type-C(データ転送専用)とUSB 3.2ポートが1つずつ 。背面には、常時給電に対応し、接続したデバイスからサーバーを起動する際などに便利なUSB 2.0ポートが1つ配置されています 。
ただ、Beelink EQ14が高速なUSBポートを合計4つ(Type-A x3, Type-C x1)備えているのと比べると、ME miniのポート数はやや少なく感じました 。キーボード、マウス、外付けHDDを同時に接続しようとするとポートが埋まってしまうため、私の環境ではUSBハブが必須アイテムとなりました 。
【Beelink ME miniのインターフェース】
- 前面インターフェース: USB Type-C (10Gbps) x1、USB 3.2 (10Gbps) x1
- 背面インターフェース: USB 2.0 x1 、AC電源ポート x1 、LAN x2 、HDMI x1
最新ワイヤレス接続:Wi-Fi 6とBluetooth 5.2
無線接続については、両機種とも最新規格であるWi-Fi 6(802.11ax)とBluetooth 5.2に対応しています 。まずWi-Fi 6は、従来のWi-Fi 5に比べて通信速度が理論値で約1.4倍に向上しているだけでなく、多くのデバイスが同時に接続するような混雑した環境でも安定した通信を可能にする技術です。これにより、ME miniをNASとして使いながら、家族がそれぞれスマートフォンで動画をストリーミングしても、通信が不安定になることはありませんでした。
また、Bluetooth 5.2は、特にオーディオ品質の向上と低遅延が特徴です。「LE Audio」という技術により、高音質と省電力を両立させています。実際にワイヤレスヘッドホンを接続して音楽を聴いてみましたが、音の途切れや遅延はほとんど感じられず、快適なリスニング体験ができました。有線接続が基本となるNASですが、これら最新のワイヤレス規格が搭載されていることで、利用シーンの幅が大きく広がります。
インターフェースと接続性のまとめ
- ネットワーク性能:従来の約2.5倍高速なデュアル2.5GbE LANポートを搭載し、1GbEのEQ14を圧倒するデータ転送を実現。サーバー用途に最適 。
- 映像出力:HDMI1系統のみとシンプルに割り切ることで、NASやサーバーとしての役割に特化 。マルチモニター環境を求めるならEQ14が適している 。
- USBポート:高速ポートの数はEQ14に比べて少ないものの、前面の10Gbpsポートや背面の常時給電ポートなど、用途を考えた合理的な配置 。
- 無線接続:最新規格のWi-Fi 6とBluetooth 5.2に標準対応 。混雑に強く安定したWi-Fi通信と、低遅延・高音質なBluetooth接続を両立。
パフォーマンス:Beelink ME mini ~ 省電力と快適さを両立したIntel N150の実力
Beelink ME miniが日常的な利用シーンでどのようなパフォーマンスを発揮するのか、その実用性に迫ります。ここでは、同じCPUを搭載する兄弟機「Beelink EQ14」と比較しつつ、特にサーバー用途で重要となる消費電力と、日常的なタスクをこなす上での性能バランスについて、詳しく見ていきます。
中核に宿るIntel N150プロセッサー
ME miniとEQ14は、どちらもIntelのTwin Lake N150プロセッサーを搭載しています。このCPUは4コア4スレッド、最大3.6GHzで動作し、注目すべきはそのTDP(熱設計電力)がわずか6Wという省電力性能です。これにより、24時間365日常時稼働させるNASやホームサーバーとして運用する際に、電気代を最小限に抑えることができるのは、私にとって非常に嬉しいポイントでした。
内蔵されているIntel UHD Graphicsは、高負荷な3Dゲームには向きませんが、その性能は日常使いには十分以上です。実際に、リビングのテレビに接続してPlexのメディアサーバーとして利用した際も、GoProで撮影した高ビットレートの4K動画をスムーズに再生できました。
メモリ:省電力な高速LPDDR5を搭載
ME miniのパフォーマンスを語る上で、EQ14との最大の違いがメモリです。ME miniは、12GBのLPDDR5 (4800MHz) メモリをオンボードで搭載しています。このLPDDR5は、主にスマートフォンなどのモバイルデバイス向けに開発された低消費電力メモリで、EQ14が採用するDDR4メモリよりも低い電圧で動作し、電力効率に優れています。
ME miniのメモリは基板にはんだ付けされているため交換はできませんが、4800MHzというクロック周波数は高速です。実際にNAS OSのUnraid上で、DockerコンテナとしてPlex Media Server、広告をブロックするAdGuard Home、そしてVPNサーバーのTailscaleを同時に動かしても、メモリ不足に陥ることなく安定して動作していました。容量の大きさよりも、常時稼働を前提とした電力効率と速度のバランスを重視した、製品コンセプトに合致した選択だと感じます。
実用性:日常タスクを軽快にこなす
実際の使用感として、Google Chromeでタブを10個以上開いてのWebブラウジングや、Microsoft 365のWordやExcelを使った書類作成、YouTubeでの4K動画視聴といった日常的なタスクは、EQ14と同様に全く問題なく快適にこなせます。
サーバーとしてバックグラウンドでファイルのダウンロードやPlexのライブラリスキャンが動いている状態でも、操作がもたつくことはありませんでした。デュアル2.5GbEポートを介した高速なファイル転送中でも、CPU使用率は平均60~75%の範囲で安定しており 、一般的な家庭での利用シナリオにおいては、性能に十分な余力を残していることが確認できました。
もちろん、本格的な動画編集のような高負荷作業には向きませんが、「省電力なホームサーバー兼、軽作業用のサブPC」として、その役割を見事に果たしてくれます。
パフォーマンスのまとめ
- プロセッサー:TDP 6Wの省電力CPU「Intel N150」を搭載し、24時間稼働させるサーバー用途に最適。
- メモリ:EQ14のDDR4とは異なり、より高速で電力効率に優れた12GBのLPDDR5メモリを搭載。PlexやAdGuard Homeなどの複数コンテナを同時実行しても安定。
- グラフィックス:内蔵のIntel UHD Graphicsは、4K動画の再生など日常的なメディア視聴には十分な性能を発揮。
- 総合性能:高負荷な専門作業には向かないものの、ホームサーバーとしての役割をこなしつつ、ChromeでのブラウジングやMicrosoft 365での書類作成といった日常タスクも快適に実行できる、バランスの取れた実用性を備える。
ベンチマーク
Beelink ME miniが搭載するIntel N150プロセッサは、どのくらいの性能なのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<CPUのベンチマーク結果・Intel N150>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア「5535」(マルチコア)
- Geekbench 6のシングルコア「1241」、マルチコア「2971」
- Cinebench 2023 シングルコア「943」、マルチコア「2753」
- Cinebench 2024 シングルコア「57」、マルチコア「162」
- PCMark 10 スコア「2789」(よく利用されるアプリの使用感を計測)
<CPUのベンチマーク結果から分かること>
Intel N150のベンチマーク結果を総合的に見ると、このCPUは主にエントリークラスのノートPCやミニPC向けに設計された、省電力性と基本的な処理性能のバランスを重視したプロセッサーであると結論付けられます。Passmark、Geekbench 6、Cinebench(2023および2024)、PCMark 10の各スコアは、いずれもこの位置づけを裏付けています。
具体的には、ウェブブラウジング、オフィスアプリケーション(Word、Excel、PowerPointなど)の使用、メールのチェック、動画ストリーミングサービスの視聴といった日常的なタスクにおいては、概ねスムーズな動作が期待できます。シングルコア性能も一定レベルを確保しているため、アプリケーションの起動や反応速度についても、極端にストレスを感じることは少ないでしょう。マルチコア性能も、複数の軽作業を同時に行う程度のマルチタスクであれば対応可能です。
しかしながら、その性能には限界があり、特に高い処理能力を要求される用途には不向きです。例えば、最新のAAAタイトルのような高負荷な3Dゲームのプレイ、4K動画の本格的な編集やエンコード、複雑な3D CADモデリング、大規模なプログラミングのコンパイルといった作業では、処理に時間がかかったり、動作が不安定になったりする可能性が高いです。これらの用途を主目的とする場合は、より高性能なCPUを選択する必要があります。
グラフィック性能
Intel N150プロセッサが内蔵するIntel UHD Graphics 1.0GHz のグラフィック性能はどのくらいなのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<GPUのベンチマーク結果・Intel N150内蔵のIntel UHD Graphics 1.0GHzグラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで「1095」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで「490」
- Time Spy グラフィックスコアで「367」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで「4640」(DirectX 12, 低負荷)
- 3DMark Wild Life「2820」(Vulkan/Metal, モバイル向け)
<GPUのベンチマーク結果から分かること>
Intel N150に内蔵されたIntel UHD Graphics 1.0GHzの各種ベンチマーク結果は、このGPUがエントリークラスのCPUに統合されるグラフィックス機能として、主に基本的な画面描画や軽負荷なグラフィックスタスクを想定して設計されていることを明確に示しています。
Fire StrikeやTime Spyといったゲーミング性能を測る指標では低いスコアに留まっており、最新の3Dゲームや高負荷なグラフィック処理を快適に行うことは困難です。Fire Strikeのスコア「1095」やTime Spyのスコア「367」は、ディスクリートGPUと比較した場合、数世代前のエントリーモデルにも及ばないレベルであり、現代のPCゲームをプレイする上では性能不足が顕著です。
しかしながら、3DMark Night Raidのスコア「4640」が示すように、DirectX 12環境下であっても、グラフィック負荷が非常に低い用途、例えば2Dを中心としたカジュアルゲーム、ブラウザ上で動作するゲーム、あるいはUIのアニメーションといった処理であれば、問題なくこなせる能力を持っています。
また、動画再生支援機能も備わっているため、YouTubeなどのストリーミング動画やローカルに保存された動画ファイルの再生はスムーズに行えるでしょう。3DMark Wild Lifeのスコア「2820」も、一部の非常に軽量なモバイル向けゲームであれば動作の可能性を示唆しますが、快適なゲーム体験を提供するレベルではありません。
ゲーム性能
Intel N150および内蔵のIntel UHD Graphics 1.0GHzグラフィックスコアのゲーム性能について、具体的なゲームタイトルとフレームレート(FPS)を交えて紹介します。
【各ゲームタイトルの動作状況】
原神 (Genshin Impact)
原神は、広大なオープンワールドを探索するアクションRPGで、美しいビジュアルが特徴ですが、その分グラフィック負荷も比較的高めです。
Intel N150環境において、原神をプレイする場合、解像度を720p、グラフィック設定を全て「最低」にしても、平均的なフレームレートは20 FPSから25 FPS程度に留まるでしょう。フィールド探索時でもこの程度であり、複数の敵との戦闘や派手なエフェクトが多用される場面では、フレームレートは15 FPSを下回り、画面のカクつきや操作の遅延が顕著になります。快適な探索や戦闘は望めず、ゲーム体験は大きく損なわれるでしょう。
Apex Legends
Apex Legendsは、スピーディーな展開が特徴のバトルロイヤル形式のファーストパーソンシューターです。フレームレートの安定性が勝敗に直結します。
このCPUとGPUの組み合わせでは、Apex Legendsを720p解像度、全てのグラフィック設定を最低にしても、平均フレームレートは20 FPSに届かないことが多くなります。特に複数の部隊が交戦する場面や、スモークなどのエフェクトが多い状況では、10 FPSから15 FPS程度まで落ち込み、キャラクターの動きが著しく鈍重になります。照準を合わせることや、敵の攻撃を回避することは極めて困難で、競技的なプレイは全く不可能です。
ストリートファイター6 (Street Fighter 6)
ストリートファイター6は、美麗なグラフィックと滑らかなアニメーションが求められる最新の対戦格闘ゲームです。安定した60 FPSでの動作が対戦の公平性を保つ上で不可欠です。
Intel N150では、ストリートファイター6を起動できたとしても、解像度を可能な限り低くし(例えば720p未満)、グラフィック設定を全て最低にした場合でも、フレームレートは10 FPSにも満たないでしょう。キャラクターの動きは紙芝居のようになり、技の入力やコンボの実行は不可能に近いです。対戦ゲームとして成立する水準には到底達せず、実質的にプレイ不可能な状態となります。
DOTA 2
DOTA 2は、戦略性の高いMOBA(マルチプレイヤーオンラインバトルアリーナ)で、比較的幅広いPC環境で動作するように設計されていますが、集団戦では負荷が増大します。
この環境でDOTA 2をプレイする場合、720p解像度、最低グラフィック設定であれば、ゲーム序盤のレーン戦など、比較的負荷が低い場面では30 FPSから40 FPS程度で動作することもあります。しかし、5対5の集団戦が始まると、多数のスキルエフェクトが飛び交うため、フレームレートは20 FPSを下回り、時には10 FPS台まで落ち込むこともあります。これにより、重要な場面での操作ミスを誘発しやすく、快適なプレイは難しいでしょう。
GRID: Autosport
GRID: Autosportは、2014年にリリースされたレースゲームで、比較的古いタイトルであるため、要求スペックは最近のゲームほど高くありません。
Intel N150でGRID: Autosportを720p解像度、グラフィック設定を低~中に調整した場合、平均して30 FPS前後での動作が可能です。スタート直後や多数のAIカーが密集するコーナーなどでは20 FPS台に低下することもありますが、レースゲームとして最低限プレイできる範囲には収まるでしょう。ただし、画面の滑らかさに欠け、高速走行時の操作感には多少の慣れが必要になります。
GTA V (Grand Theft Auto V)
GTA Vは、広大なオープンワールドを持つアクションアドベンチャーゲームで、リリースから時間は経過していますが、依然としてPCへの負荷は低くありません。
この環境でGTA Vをプレイする場合、全てのグラフィック設定を最低にし、解像度を720pに設定しても、市街地での平均フレームレートは20 FPSから25 FPS程度になるでしょう。ミッション中の銃撃戦やカーチェイスなど、オブジェクトやエフェクトが増加する場面では、15 FPSを下回ることが頻繁に発生し、ゲームプレイは困難を伴います。快適なドライブやアクションを楽しむことは難しく、頻繁なフレームレートの低下に悩まされることになります。
CS GO (Counter-Strike: Global Offensive)
CS GOは、競技性の高いタクティカルシューターで、比較的軽い動作が特徴ですが、高いフレームレートでのプレイが好まれます。
Intel N150でCS GOを最低グラフィック設定、720p解像度でプレイした場合、平均して40 FPSから50 FPS程度で動作するでしょう。マップやプレイヤー数、スモークグレネードなどの状況によっては30 FPS台まで低下することもあります。競技シーンで求められる100 FPS以上の滑らかな描画とは程遠く、AIMの精度や反応速度に影響が出ますが、カジュアルに楽しむ分には何とかプレイ可能な範囲と言えます。
まとめ:ゲーム性能
Intel N150および内蔵のIntel UHD Graphics 1.0GHzグラフィックスコアの性能を考慮すると、指定されたゲームタイトルの多くにおいて、快適なプレイ体験を得ることは非常に困難です。DOTA 2やCS GO、GRID: Autosportといった比較的負荷の軽い、あるいは古いタイトルであれば、グラフィック設定を大幅に妥協し、解像度を下げることで、かろうじて「動く」レベルには到達する可能性があります。しかし、これらのゲームでもフレームレートは不安定になりがちで、特に負荷のかかる場面では著しく低下します。
原神、Apex Legends、ストリートファイター6、GTA Vといった、よりグラフィック負荷が高い、あるいは最新のタイトルについては、最低設定であってもフレームレートが極端に低くなり、ゲームプレイが困難、あるいは実質的に不可能なレベルとなるでしょう。
これらのCPUとGPUの組み合わせは、ウェブブラウジングやオフィスソフトの利用といった一般的なPC作業を主眼としており、本格的な3Dゲームを楽しむための性能は備えていません。もしゲームプレイを主な目的とするのであれば、より高性能なCPUと専用のグラフィックカード(ディスクリートGPU)を搭載したPCを検討する必要があります。
ストレージ:Beelink ME mini ~ 手のひらサイズの筐体に最大24TBを詰め込む拡張性
Beelink ME miniが持つ最大の特徴、それはその常識外れのストレージ拡張性です。ここでは、一般的なミニPCである「Beelink EQ14」が2基のM.2スロットしか持たないのに対し 、ME miniがいかに異次元の拡張性を備えているのか、その衝撃的な仕様と実際の使用感を交えて解説します。
衝撃のM.2スロット6基搭載
この99mmの小さな筐体に、合計6基ものM.2 SSDスロットが搭載されていると知った時は、正直なところ衝撃を受けました 。これは、2基のスロットしか持たないBeelink EQ14の実に3倍の数です 。各スロットに最大4TBのSSDを搭載すれば、合計で最大24TBという、まさにパーソナルクラウドと呼ぶにふさわしい大容量ストレージ環境をこの手のひらサイズで実現できます 。
この容量は、映画なら約11,000本、写真なら約446万枚を保存できる計算になり 、家族全員の思い出を何年にもわたって保存し続けるにも十分すぎるほどです。
考え抜かれたスロット構成とeMMC
ただスロットが多いだけでなく、その構成も非常に考えられています。まず、OSのインストール用に、他のスロットより高速なPCIe 3.0 x2接続のスロットが1基(スロットNo.4)用意されています 。残りの5基はデータ保存用のPCIe 3.0 x1スロットです 。さらに、ME miniには64GBのeMMCストレージが内蔵されており 、これはEQ14にはない大きな利点です。
公式の推奨通り、私はNAS用の軽量OS(UnraidやTrueNASなど)をこのeMMCにインストールしました 。これにより、6基のM.2スロットをすべてデータ保存のためだけにフル活用でき、非常に効率的だと感じました。
実用的な転送速度と信頼性
データ用のスロットがPCIe 3.0 x1接続である点について、速度不足を心配する方もいるかもしれません。確かに、高負荷な並列処理を行うプロユーザーには制約となる可能性があります 。
しかし、実際のテストではデータスロットで平均約740MB/sの読み込み速度が出ており 、これは家庭で4K動画をストリーミング再生したり、複数のデバイスから写真ライブラリにアクセスしたりするには十分すぎるほどの性能です。実際、Plexで高画質な映画を再生しながら、別のPCからファイル転送を行っても、再生が途切れることは一切ありませんでした。
また、オプションとして用意されているSSDが、信頼性の高いMicron社のCrucial®ブランドである点も安心材料です 。大切な家族のデータを預けるNASだからこそ、こうした信頼性への配慮は非常に重要だと感じます。
ストレージ拡張性のまとめ
- スロット数:一般的なミニPC(EQ14)の3倍となる、合計6基のM.2 SSDスロットを搭載し、圧倒的な拡張性を誇る。
- 最大容量:最大24TBという、家庭用としては異次元の大容量ストレージを構築可能。映画や写真など、増え続ける家族のデータをすべて保存できる。
- スマートな設計:OSをインストールできる64GBのeMMCを別途搭載しており、6基のM.2スロットをすべてデータ用に使えるという、NASに特化した無駄のない構成。
- 実用性能:データ用スロットは家庭用NASとして十分な転送速度を確保しており、信頼性の高いCrucial製SSDが選択できる点も魅力。
NASサーバーとしての実力:Beelink ME mini ~ TrueNASからPlexまで広がる可能性
Beelink ME miniの真価は、その強力なハードウェアを活かすソフトウェアの柔軟性にあります。ここでは、一般的なデスクトップPCとしての利用が主となるBeelink EQ14とは異なり、ME miniがどのようにして本格的なNASサーバーやメディアハブに変身できるのか、その広大な可能性について解説します。
そもそも「NAS」とは?~家庭内データ共有のすすめ~
そもそも「NAS(ナス)」とは、「Network Attached Storage」の略で、一言で言えば「ネットワークに接続できるハードディスク」のことです。これ一台を家のネットワークに繋いでおけば、スマートフォンで撮った写真や動画、PCで作成した書類など、あらゆるデータを一箇所にまとめて保存できます。
そして、その保存したデータに、家中のPCやスマホ、タブレットからいつでもアクセスしたり、家族で共有したりできるようになります。Beelink ME miniは、この便利なNASを、専門的な知識があまりない人でも手軽に、かつパワフルに構築できるマシンなのです。
OSを選ばない自由度:NASから仮想化まで
ME miniの最も素晴らしい点は、ユーザーの目的に合わせてOSを自由に選べる懐の深さです 。一般的なWindowsやLinuxはもちろんのこと、より専門的な用途に応える多様なOSをサポートしています 。
例えば、本格的なNASを構築したいのであれば、TrueNASやUnraidといった専用OSをインストールできます 。
TrueNASは、ZFSファイルシステムによる極めて高いデータ保護機能が魅力で、絶対に失いたくない大切なデータを守るのに最適です。
一方のUnraidは、異なる容量のディスクを柔軟に組み合わせられるため、段階的にストレージを拡張したい家庭での利用に人気があります。私は余っていたSSDを有効活用したかったので、柔軟性の高いUnraidを選択しました。
さらに、Proxmox (PVE)やESXiといった仮想化OSを導入すれば、この一台の上で複数のサーバーOSを同時に動かす、自分だけの学習・開発環境(ホームラボ)を構築することも可能です 。そのコンパクトな筐体からは想像もつかないほどの可能性を秘めているのです。
仮想化OSを利用するメリット
仮想化OSとは、一言で言えば「1台のPCを、擬似的に複数台のPCとして動かす」ためのものです。例えば、1つ目の仮想マシンにはUbuntu ServerをインストールしてWeb開発の実験用サーバーを構築し、2つ目の仮想マシンでは家中の広告をブロックしてくれるAdGuard HomeやPi-holeを専用で動かす。そして3つ目では、新しいバージョンのWindows 11や、興味のあるLinuxディストリビューションを、メイン環境を汚さずに安全に試す、といった使い方ができます 。
ME miniの12GBメモリは、こうした複数の仮想マシンを同時に動かすのにも十分な容量を持っており 、IT技術の学習や、様々なソフトウェアのテストを行うための、コンパクトで省電力な「おうち実験室(ホームラボ)」として最適なのです。
ファミリーメディアハブの構築:PlexとJellyfin
ME miniは、家庭内のエンターテイメントを豊かにする「ファミリーメディアハブ」としても、その実力をいかんなく発揮します。PlexやJellyfinといったメディアサーバーシステムをセットアップすれば、ME miniに保存した大量の映画や音楽、写真を、家中のあらゆるデバイスに配信できます 。
Plexは、簡単な設定と豊富な対応デバイスが魅力の商用ソフトで、初心者でも手軽に始められます。一方で、Jellyfinは、全ての機能が無料で使えるオープンソースのソフトウェアで、プライバシーを重視し、自分好みにカスタマイズしたいユーザーに最適です 。
実際に私はJellyfinをインストールし、これまで外付けHDDに散らばっていた家族の動画や写真を一元管理することにしました。今では、リビングのテレビ(Android TV)や個人のスマートフォンから、いつでも手軽に思い出の動画を大画面で楽しんでいます。この体験は、まさにME miniが提供する価値そのものだと感じました。
【体験談】散らばった家族の思い出が、リビングの主役に
実際にME miniを導入して、我が家で最も大きな変化があったのが「家族の思い出の管理」です。
これまでは、子どもの成長記録の動画は私のPCに繋がった外付けHDDに、旅行の写真は妻のノートPCに、それぞれのスマートフォンで撮ったデータはバックアップも取らずにそのまま…といった具合に、家族の大切な思い出が文字通りバラバラに保管されていました。「あの時の写真が見たい」と思っても、どのHDDに入っているか分からず、探すだけで一苦労でした。
そこで私は、ME miniにNAS OSのUnraidをインストールし、その上でメディアサーバーソフトのJellyfinをセットアップすることにしました 。週末を使って、今までバラバラだったHDDからデータをME miniに集約する作業は少し大変でしたが、全てのデータが一箇所にまとまっていく様子は爽快でした。
セットアップが完了した夜、早速リビングのテレビ(Android TV)でJellyfinアプリを起動し、サムネイルが美しく並んだライブラリを見たときは、思わず「おおっ」と声が出ました。今では、夕食後に「赤ちゃんの頃の動画を見ようか」と、リモコン一つで数年前に撮影した動画を大画面に映し出し、家族で笑いながら楽しむのが新しい習慣になっています。妻も自分のスマートフォンからいつでも手軽に写真を見返せるようになり、「これ、本当に便利ね」と喜んでいます。
この体験は、まさにME miniが提供する価値そのものだと感じました。
サーバーとしての可能性まとめ
- OSの多様性:WindowsやLinuxに加え、TrueNAS、Unraid、Proxmoxなど、専門的なサーバーOSに幅広く対応しており、初心者から上級者まで満足させる 。
- 本格NASの構築:高い信頼性でデータを保護する「TrueNAS」や、柔軟なストレージ管理が可能な「Unraid」を導入し、自分だけのファイルサーバーを構築できる 。
- 仮想化基盤:Proxmoxなどを利用すれば、一台で複数のOSを稼働させる「ホームラボ」としても活用可能 。
- メディアハブ:PlexやJellyfinをセットアップすることで、家中のデバイスに映像や音楽を配信する、強力なファミリーメディアサーバーとして機能する 。
Beelink ME mini vs EQ14 スペック徹底比較
Beelink ME miniとBeelink EQ14は、どちらも省電力なIntel N150プロセッサーを搭載したミニPCです 。しかし、その設計思想と仕様には大きな違いがあり、それぞれ異なるユーザー層をターゲットとしています。ここでは、両モデルの主な違いを比較し、その特徴を明らかにします。
コンセプト・用途
- ME mini: 「6スロット ホームストレージ NASミニPC」と銘打ち、家庭用の大容量データサーバー(NAS)やメディアハブとしての利用に特化しています 。
- EQ14: 軽めのオフィス作業や日常的なマルチタスクを快適にこなす、汎用的なミニPCとして設計されています 。
- 違い:ME miniは明確に「家庭用サーバー」、EQ14は「普段使いのPC」という役割分担があります。
ストレージ拡張性
- ME mini: M.2 SSDスロットを合計6基搭載し、最大で24TBまで拡張可能です 。また、OS用に64GBのeMMCも内蔵しています 。
- EQ14: M.2 SSDスロットは2基で、最大8TBまでの拡張にとどまります 。
- 違い:ME miniのストレージ拡張性は圧倒的です。多くのデータを一元管理したいNAS用途において、この差は決定的です。
メモリ
- ME mini: 12GBのLPDDR5-4800MHzメモリを搭載しています 。省電力で高速ですが、オンボードのため増設・交換はできません 。
- EQ14: 16GBのDDR4-3200MHzメモリを搭載し、最大16GBまで対応するスロット形式です 。
- 違い:ME miniは電力効率と速度を、EQ14は容量の大きさを重視しています。24時間稼働を想定するサーバーとしては、ME miniのLPDDR5が適しています。
有線LANポート
- ME mini: デュアル2.5G LANポートを搭載しています 。
- EQ14: デュアル1000Mbps(1G)LANポートを搭載しています 。
- 違い:ME miniの通信速度はEQ14の約2.5倍です。大容量ファイルの転送速度に直結するため、NASとしての快適性に大きく影響します。
映像出力
- ME mini: HDMIポートが1基のみで、単一の画面出力に対応します 。
- EQ14: HDMI 2基とDisplayPort対応のType-Cポートを備え、最大3画面の同時出力が可能です 。
- 違い:複数のモニターで作業したい場合は、EQ14が圧倒的に有利です。ME miniはサーバー用途のため、映像出力は最小限に絞られています。
USBポート
- ME mini: 合計3つの外部USBポート(Type-C含む)を備えています 。
- EQ14: 合計5つの外部USBポートと、映像出力にも対応するType-Cポートを備えています 。
- 違い:キーボードやマウス、外付けドライブなど多くの周辺機器を接続したい場合、ポート数が多いEQ14の方が便利です。
筐体デザインとカラー
- ME mini: 99x99x99mmのコンパクトなキューブ型で、3色のカラーバリエーションがあります 。
- EQ14: 126x126x39mmの薄い正方形型で、カラーはネイビーブルーの1色です 。
- 違い:ME miniはインテリアとしても映えるデザイン性の高いキューブ型、EQ14はVESAマウントにも対応する実用的な薄型デザインです 。
対応OS
- ME mini: WindowsやLinuxに加え、TrueNAS、Unraid(NAS用OS)、Proxmox(仮想化OS)など、多様なサーバー向けOSを公式にサポートしています 。
- EQ14: Windows 11 Proがプリインストールされています 。
- 違い:ME miniはサーバーとして利用するためのソフトウェア対応が非常に幅広いのが特徴です。
まとめ:Beelink ME miniとBeelink EQ14の違い
Beelink ME miniとEQ14は、同じCPUを搭載しながらも、全く異なるコンセプトを持つ製品です。ME miniは、圧倒的なストレージ拡張性と高速なデュアル2.5G LANを武器に、家庭内のデータ管理と活用を主目的とする「NAS特化型ミニPC」です。
一方のEQ14は、豊富な映像出力とUSBポートを備え、価格も抑えられた、より「汎用的なデスクトップ向けミニPC」と言えます。ご自身の主な用途がデータサーバーの構築なのか、それとも日々のPC作業なのかを明確にすることで、最適な一台を選ぶことができるでしょう。
Beelink ME miniのメリット・デメリット
Beelink ME miniの長所と弱点を、他のミニPCと比較しながら、その独自の価値を明らかにしていきます。
【メリット】
メリット1:圧倒的なストレージ拡張性
最大の長所は、6基ものM.2スロットを搭載している点です 。これは、2基の「Beelink EQ14」 や4基の「GMKtec NucBox G9」 をも上回る数であり、家庭用NASとして他の追随を許さない拡張性を誇ります。
メリット2:サーバーに最適なデュアル2.5GbE LAN
高速な2.5GbEのLANポートを2つ搭載しており、本格的なサーバー運用が可能です 。これは、1GbEの「Beelink EQ14」 や、1ポートのみの「MINISFORUM UN150P」 、「GMKtec NucBox K10」 と比べて明確な優位点です。
メリット3:美しくコンパクトなデザインと内蔵電源
99mmの金属製キューブデザインは、他のプラスチック製ミニPCとは一線を画す高級感と所有欲を満たしてくれます。また、「Beelink EQ14」 と同様に電源ユニットを内蔵しているため、ACアダプターがなくデスク周りが非常にすっきりします 。
メリット4:省電力なLPDDR5メモリ
「Beelink EQ14」 や「MINISFORUM UN150P」 がDDR4メモリを採用しているのに対し、より高速で電力効率に優れたLPDDR5メモリを搭載しています。24時間稼働させるNASにおいて、この省電力性は大きなメリットとなります。
【デメリット】
デメリット1:映像出力が1系統のみ
映像出力がHDMIの1系統に限られる点は、明確な弱点です 。3画面以上の出力に対応する「Beelink EQ14」 、「GMKtec NucBox G9」 、「MINISFORUM UN150P」 などと比較すると、デスクトップPCとしての汎用性は劣ります。
デメリット2:限定的なUSBポート数
高速なUSBポートが前面に2つ、背面に1つ(USB 2.0)と、その数は限られています 。4つ以上のUSBポートを持つ「Beelink EQ14」 や「GMKtec NucBox G9」 などと比べると、多くの周辺機器を接続するにはUSBハブが必要になるでしょう。
デメリット3:CPU性能はエントリークラス
搭載されているIntel N150プロセッサは、あくまで省電力性を重視したエントリークラスのCPUです。「GMKtec NucBox K10」が搭載するCore i9-13900HK のような、高負荷な処理をこなすパワーはありません。
デメリット4:NAS特化による価格
家庭用NASに特化している分、同じN150プロセッサを搭載する「Beelink EQ14」 や「MINISFORUM UN150P」 よりも価格は高めに設定されています。汎用的なミニPCとして見ると、コストパフォーマンスでは一歩譲ります。
まとめ:メリット・デメリット
Beelink ME miniのメリット・デメリットは、その「家庭用NASサーバー」という明確なコンセプトから生まれています。ストレージ拡張性とネットワーク性能を最大限に高める一方で、汎用的なPCとしての機能は割り切られています。ご自身の目的がデータ管理と活用にあるならば、デメリットを補って余りある、強力なパートナーとなるでしょう。
Beelink ME miniのスペック(仕様)
- プロセッサ: Intel® Twin Lake N150 (4コア4スレッド、最大3.6GHz)
- GPU: Intel N150内蔵グラフィックス
- RAM: 12GB LPDDR5 (4800MHz)
- ストレージ: 64GB eMMC 、M.2 2280 PCIe 3.0 スロット (No.4)
- 拡張ストレージ: M.2 2280 PCIe 3.0 x1 スロット x5 (合計最大24TBまで)
- 電源: 45W 電源ユニット内蔵
- ワイヤレス通信: WiFi 6 (Intel AX101)、Bluetooth 5.2
- 有線LAN: 2.5GbE x2 (Intel i226-V)
- 前面インターフェース: USB Type-C (10Gbps) x1、USB 3.2 (10Gbps) x1
- 背面インターフェース: USB 2.0 x1 、AC電源ポート x1 、LAN x2 、HDMI x1
- 映像出力: HDMI (最大4K 60Hz)
- 冷却: 静音ファン、垂直エアフロー冷却設計
- 消費電力: CPU TDP: 6W
- VESAマウント: 非対応
- 対応OS: Windows, Linux, Proxmox(PVE), ESXI, FNOS, UNRAID, TrueNASなど
- サイズ: 99 x 99 x 99mm (ゴム足含む)
- 重量: 非公開
- カラー: パールホワイト、ピーコックブルー、ミッドナイトグレー
- 付属品: ユーザーマニュアル、HDMIケーブル、電源アダプター
Beelink ME miniの評価
7つの基準で「Beelink ME mini」を5段階で評価してみました。
【項目別評価】
スペック:★★★☆☆
Intel N150は日常使いには十分ですが、高性能ではありません。ただし、省電力で高速な12GBのLPDDR5メモリは、サーバー用途として高く評価できます。
デザイン:★★★★★
99mmの金属製キューブデザインは、他のミニPCと一線を画す美しさと高級感があります。電源内蔵で配線がすっきりする点も完璧です。
通信:★★★★☆
サーバーの要であるデュアル2.5GbE LANポートは非常に強力です。Wi-Fi 6にも対応していますが、USBポートがやや少ない点が惜しいです。
機能(拡張性):★★★★★
最大24TBまで拡張できる6基のM.2スロットは圧巻の一言です。この製品最大の魅力であり、家庭用としてはこれ以上ないほどの拡張性です。
冷却性能:★★★★★
非常に静かな冷却システムを搭載しており、常時稼働が前提のNASとして寝室に置いても気にならないレベルです。設計が優れています。
使いやすさ:★★★★☆
電源内蔵で設置が簡単な上、多様なOSに対応するため初心者から上級者まで扱えます。ただし、USBポートの少なさは周辺機器が多いと不便に感じるかもしれません。
価格:★★★★☆
単純なミニPCとして見れば高価ですが、NASとしての機能と拡張性を考えれば、価格に見合った、あるいはそれ以上の価値があります。
総評:★★★★☆
「ホームサーバー」という新たな地平
Beelink ME miniは、単なる「ミニPC」という枠には収まらない、「家庭用NASサーバー」として極めて完成度の高い製品です。一般的なPCが得意とするゲームや動画編集といった一過性の処理性能の高さではなく、24時間365日、静かに安定して稼働し、家族のデータを守り、そして配信するという、データ中心の現代生活における永続的な役割に、全ての設計が最適化されています。
その思想は、6基のM.2スロットがもたらす圧倒的なストレージ拡張性や、高速なデュアル2.5GbE LANポートといった、他のミニPCでは見られないハードウェアに明確に表れています。これは、BeelinkがPCの未来を「データが集まる場所」として捉えていることの証左に他なりません。
価格以上の価値を提供する「選択と集中」
確かに、CPU性能や映像出力が1系統である点など、部分的に見れば物足りない点もあります。しかし、それは欠点ではなく、あくまでサーバーという役割に不要な部分を削ぎ落とし、必要な部分にコストをかけた「選択と集中」の結果なのです。
同じN150を搭載した安価なミニPCも存在しますが、それらにはME miniが持つような異次元の拡張性や、本格的なサーバー運用を可能にするネットワーク性能はありません。家族の増え続ける写真や動画を一元管理したい、自分だけのメディアサーバーを構築したいといった明確な目的があるユーザーにとっては、価格以上の価値と満足感を提供してくれる一台です。
こんな人におすすめ
このミニPCは、その特性から、明確な目的を持つユーザーにとって最高のパートナーとなり得ます。例えば、専門知識がなくても自分だけのデータサーバーを構築したい「NAS入門者」。また、PCやスマートフォンに散らばった家族の思い出の動画や写真を一箇所に集め、リビングで手軽に楽しみたい「ファミリーユーザー」。そして、省電力な筐体でProxmoxなどを動かし、様々なOSやソフトウェアを試す「ホームラボ探求者」にとっても、これ以上ないほど魅力的な一台です。
一方で、最新3Dゲームのプレイや本格的な動画編集など、高いCPU・GPU性能を求めるのであれば、その期待には応えられません。ご自身の目的が「データ管理と活用」にあるのなら、ME miniはきっと期待以上の価値を提供してくれるはずです。
Beelink ME miniの価格・購入先
Beelink 公式サイト
12GB LPDDR5+64G eMMCモデルが$209.00(※発売セール価格・通常価格は$329.00)、
12GB LPDDR5+64G eMMC+2TBモデルで$329.00(※発売セール価格・通常価格は$409.00)、
で販売されています。
Beelink 公式サイトで「Beelink ME mini」をチェックする
ECサイト
- Amazonで63,900円(税込・15000円 OFFクーポン付きで実質48,900円)、
- AliExpressで56,964円、
- 米国 Amazon.comで$409.00($80 OFFクーポン付き)、
で販売されています。
Amazonで「Beelink ME mini」をチェックする
楽天市場で「Beelink ME mini」をチェックする
ヤフーショッピングで「Beelink ME mini」をチェックする
AliExpressで「Beelink ME mini」をチェックする
米国 Amazon.comで「Beelink ME mini」をチェックする
※AliExpressでの購入方法・支払い方法はこちらのページで紹介しています。
AliExpressで激安ガジェットをお得に購入する方法を徹底 解説

おすすめの類似製品を紹介
「Beelink ME mini」に似た性能をもつミニPCも販売されています。
Beelink EQ14
Beelinkから発売されたインテルN150搭載のミニPCです(2024年12月発売)。
16GB DDR4 3200 メモリ、500GB M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 ストレージを搭載しています。
また、電源ユニット(内蔵)、 4K 3画面出力、冷却システム MSC2.0、最大4TBまでのストレージ拡張、VESAマウント、Type-C (10Gbps,DP Alt 4K 60Hz) x1、USB 3.2 (10Gbps) x 3、USB 2.0 (480Mbps) x1、Wi-Fi 6 、Bluetooth 5.2、デュアル有線LAN通信に対応しています。
価格は、Amazonで27,800円(税込)、楽天市場32,884円(送料無料)、ヤフーショッピングで50,630円、AliExpressで30,579円、米国 Amazon.comで$189.00、です。
関連記事:Beelink EQ14レビュー!電源内蔵でN150搭載ミニPCは買いなのか?
GMKtec NucBox G9
GMKtecから発売されたTwin Lake世代 Intel N150 搭載のミニPCです(2025年1月発売)。
12GB LPDDR5 4800 メモリ、64GB EMMC /64GB+512GB/64GB+1TB M.2 2280 NVMe PCle 3.0ストレージ、4つのM.2拡張スロットを搭載しています。
また、4K 3画面出力(USB Type-C、HDMI ( 4K@60Hz ) x2)、冷却システム、VESAマウント、ストレージ拡張(M.2 2280 NVMe で最大16TBま)、NAS(M.2 2280 NVMe で最大32TBまで増設可能、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、2.5G・デュアル ギガビット有線LANにも対応しています。
価格は、Amazonで42,473円、楽天市場で28,508円(送料無料)、AliExpressで26,357円、米国 Amazon.comで$239.99、です。
関連記事:驚異の32TB!GMKtec NucBox G9のNAS性能を徹底レビュー
MINISFORUM UN150P
MINISFORUMから発売されたIntel N150搭載のミニPCです(2025年1月21日 発売)。
16GB DDR4 3200MHzメモリ、256GB or 512GB M.2 2280 PCIe3.0 SSDストレージを搭載しています。
また、2.5インチ SATA HDD 拡張スロット、最大1TBまでのM.2ストレージ拡張、TF カードスロット、USB 3.2 Gen1 Type-Cポート(Data DP & PD OUT PUT)、4K 3画面出力(HDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz) x2、USB-C (4K@60Hz)x1)、冷却ファン、VESAマウント、Wi-Fi 6、BlueTooth 5.2、2.5G 有線LANに対応しています。
価格は、Amazonで31,572円(税込)、楽天市場で35,980円(送料無料)、米国 Amazon.comで$179.99、です。
関連記事:「MINISFORUM UN150P」レビュー!【N150】で進化した定番ミニPCの実力は?
GMKtec NucBox K10
GMKtecから発売された第13世代 Intel Core i9-13900HK 搭載のミニPCです(2025年3月 発売・ベアボーンモデルあり)。
DDR5 5200MHzメモリ(32GB/64GB)、PCIe x4 NVMe M.2 SSDストレージ(512GB/1TB/2TBモデル)、Intel Iris Xe Graphics、産業用COMポート、Windows 11 Pro(Linuxサポート)を搭載しています。
また、4画面同時出力(HDMIx2, DPx1, Type-C DPx1)、8K映像出力、最大96GBまでのメモリ拡張、最大12TBまで拡張可能なM.2スロットx3、冷却システム、VESAマウント、
USB 3.2 x 2、Type-C (DP/DATA) x 1, USB 2.0 x 4、USB 3.2 x 2、2.5Gギガビット有線LAN、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2にも対応しています。
価格は、Amazonで86,900円(税込・11700円 OFFクーポン付きで実質75,200円) 、楽天市場で97,300円(送料無料)、AliExpressで55,856円(ベアボーンモデル)、米国 Amazon.comで$559.99、です。
関連記事:GMKtec NucBox K10 レビュー!Core i9ミニPCを徹底解剖
他のBeelinkミニPCと比較
他にもBeelinkのミニPCが販売されています。2024年モデルもあるので、ぜひ比較してみてください。
BeelinkのミニPCがコスパ高すぎで大人気に!最新 機種 まとめ
その他のおすすめ小型PCは?
その他のおすすめ小型PCは以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
激安で買える海外製の小型PC 最新 機種 ラインナップ まとめ
海外製の小型PCをまとめて紹介しています。
Intel N150ミニPCはこう選べば正解!2025最新の性能・価格を比較
インテルN150搭載のミニPCをまとめて紹介しています。
ミニPCはインテル N100 搭載モデルを選べ! 2024 最新機種と選び方
インテルN100搭載のミニPCをまとめて紹介しています。
リビングにふさわしい超小型デスクトップPC ラインナップ 機種 まとめ
国内で販売されたリビング用の小型PCをまとめて紹介しています。