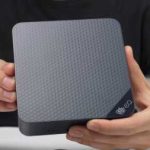2024年12月に発売されたBeelink EQ14は、その驚異的なコストパフォーマンスで、またたく間にミニPC市場の人気モデルとなりました。コンパクトなボディに十分な性能と、他の製品にはないユニークな魅力を詰め込んだ本機は、多くのユーザーから注目を集めています。
Beelink EQ14の圧倒的な魅力
最大の魅力は、なんといっても電源ユニットを本体に内蔵している点です。多くのミニPCが悩みの種としてきた、大きくて邪魔なACアダプターが不要なため、デスク周りは驚くほどスッキリします。このスマートさは、一度体験すると元には戻れないほどの快適さです。
プロセッサにはIntel N150プロセッサと16GBのDDR4メモリを搭載し、ウェブブラウジングからオフィスワークまで、日常的なタスクを快適にこなします。標準で500GBのM.2 SSDを備えつつ、内部にはデュアルM.2スロットがあり、将来的に最大8TBまでストレージを拡張できるという懐の深さも持ち合わせています。
さらに、USB 3.2 Type-Cポートや2つのギガビット有線LAN、4K@60Hzのデュアルディスプレイを可能にする2つのHDMI 2.0ポートなど、インターフェースも非常に豊富です。
これらに加え、独自のMSC 2.0冷却システムによる優れた冷却性能と驚くほどの静音性、詳細なBIOS設定、WOLによる自動電源ON対応など、語り尽くせないほどの魅力が満載です。
この記事で「Beelink EQ14」を徹底解剖!
この記事では、大きな注目を集めているBeelink EQ14の性能、機能、そして実際の使い心地を、私の体験に基づいて徹底的に深掘りしていきます。
特に、前モデルである「Beelink EQ13」から何が変わり、どこが進化したのかという点に焦点を当て、ベンチマークテストや実際の使用感を通して、その違いを明らかにしていきます。EQ14が本当に「買い」なのか、その真実に迫ります。
【この記事で分かること】
- Beelink EQ14の総合的なレビューと正直な評価
- 前モデルEQ13との詳細なスペック・性能比較
- CPU(Intel N150)と内蔵GPUのベンチマーク結果
- 人気ゲームはどのくらい動く?実際のゲーム性能を検証
- 後悔しないためのメリット・デメリット解説
- あなたに最適?EQ14がおすすめな人の特徴
- 最新の価格情報と最もお得な購入方法
この記事を最後まで読むことで、「Beelink EQ14」が本当に必要か、購入するべきかどうかが、はっきりと分かるはずです。ミニPCの購入で悩んでいる方は、ぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク / AliExpress リンク
公式サイト:Beelink | MINI PC
デザイン:Beelink EQ14 ~ACアダプター不要で叶える、究極のシンプルデスク~
ここでは、Beelink EQ14の洗練された外観と、デスク環境を劇的に変える画期的なデザインの魅力について、詳しくレビューしていきます。また、前モデルであるBeelink EQ13との比較も交えながら、その優れた設置性を掘り下げていきます。
手にした瞬間に伝わる、完成されたデザイン
Beelink EQ14を箱から取り出して最初に感じたのは、「これは前モデルのEQ13と全く同じデザインだ」ということでした 。カラーは落ち着いた「ネイビーブルー」で 、光沢のないマットな質感は指紋がつきにくく、実用性の高さを感じさせます 。筐体はプラスチック製ですが、安っぽさは一切なく、むしろ剛性感のあるしっかりとした作りです 。
天面にはさりげなく六角形のテクスチャが施され、単調ではない上品な印象を受けます 。サイズは126×126×39mmと、まさに手のひらに収まるコンパクトさ 。
私が愛用しているM4 Mac Miniと並べてみても、ほとんど同じサイズ感で、その小ささには改めて驚かされます 。このサイズと442gという実測重量 なら、普段はリビングのテレビ横に置いておき、必要な時だけ書斎に持ち運ぶといった使い方も全く苦になりません。
<サイズ・重量を比較>
- 1.「Beelink EQ14」・・・約126 x 126 x 39 mm / 約500g
- 2.「Beelink EQ13」・・・約126 × 126 × 39 mm / 約500g
- 3.「Beelink EQ12」・・・約123.9×112×38.9mm / 約506g
※箱の中には、PC本体のほかに、電源ケーブル、HDMIケーブル、ユーザーガイド、そして「Hello」と書かれたカードが入っていました。
最大の魅力「電源内蔵」がもたらす感動体験
このEQ14の設計で、私が最も感動し、声を大にして伝えたいのが「電源ユニットの内蔵」という点です 。従来のミニPCにありがちだった、本体と同じくらい大きなACアダプターがEQ14にはありません。これにより、デスク周りの配線が驚くほどスッキリします。私の作業環境では、モニターとEQ14本体から伸びる2本の電源ケーブルだけで済むようになり、足元のごちゃごちゃした配線から解放されたときの喜びは格別でした 。
必要なのはどこにでもある汎用のメガネケーブル1本だけなので 、万が一断線してもすぐに代替品が見つかりますし、設置場所に合わせて短いケーブルや、こだわりのオーディオ用ケーブルに交換するといった楽しみ方もできます 。このスマートさは、一度体験するともう後戻りはできません。
細部まで行き届いた、ユーザー本位の設計思想
デザインの魅力は見た目だけではありません。底面に目を向けると、多数の円形の通気孔と共に大きな「EQ」のロゴがデザインされています 。この底面から給気を行う効率的な冷却システムのおかげで、側面に通気口がなく、スッキリとした外観が実現できています 。
さらに感心したのはメンテナンス性の高さです。底面の四隅にあるゴム足を外してネジを4本取るだけで、誰でも簡単に分解して内部にアクセスできます 。特に嬉しかったのは、このゴム足がネジを隠すためだけのカバーで、PCを支える脚とは別パーツになっている点です 。これにより、内部のSSDを換装する際など、頻繁に開け閉めしてもゴム足が劣化する心配がありません。こうした細かな配慮に、ユーザーのことを第一に考えるBeelinkの姿勢が表れていると感じました。
まとめ:デザインと外観
- EQ13と共通の洗練されたデザイン:前モデルから外観の変更はなく、指紋がつきにくいマットなネイビーブルーの筐体は、安っぽさを感じさせないしっかりとした作りです 。
- 驚異的なコンパクトさ:126×126×39mmという手のひらサイズで、設置場所に困ることはありません 。
- 革命的な電源内蔵:巨大なACアダプターが不要で、デスク周りが劇的にスッキリするという、他のミニPCにはない最大のメリットを享受できます 。
- 優れたメンテナンス性:四隅のネジを外すだけで内部に簡単にアクセスでき、ストレージの増設や換装も容易に行えます 。
インターフェースと映像出力:Beelink EQ14 ~豊富なポートとデュアル4K対応、ただしUSB-Cには注意点も~
ここでは、Beelink EQ14が搭載する豊富なインターフェースと、実際の映像出力性能について、詳しくレビューしていきます。この小さな筐体にどれほどの拡張性が秘められているのか、前モデルのBeelink EQ13との共通点を踏まえつつ、その実力を検証します。
コンパクトさを裏切る、充実のポート類
Beelink EQ14をデスクに設置して、まず感じるのはその接続性の高さです。この価格とサイズからは想像できないほど、前面と背面に実用的なポートがぎっしりと配置されています 。これは前モデルのBeelink EQ13から受け継がれた美点であり、デザインだけでなくポート構成もほぼ同一です。
前面には、高速なUSB 3.2 Gen2のType-AとType-Cポートが1つずつ並んでおり、外付けSSDからのデータ転送もストレスなく行えます 。個人的に高速なポートが前面にあるのは、周辺機器の抜き差しが頻繁な私にとって非常に好印象でした。ただ、3.5mmオーディオジャックも前面にあるため、スピーカーを常時接続しておく場合はケーブルの取り回しに少し工夫が必要かもしれません 。
背面の充実ぶりはさらに目を見張るものがあります。2つのHDMIポートに加え、さらに2つのUSB 3.2 Gen2ポート、そして旧来の周辺機器に便利なUSB 2.0ポートが1基搭載されています 。面白いのは、高速なUSB 3.2と低速なUSB 2.0でコネクタの向きが逆になっている点で、手探りで接続する際にも間違えにくいという細やかな配慮が感じられました 。
デュアル4K出力で広がる作業領域
EQ14の映像出力は、背面に搭載された2つのHDMI 2.0ポートが担います 。実際に4Kモニターを2台接続してみたところ、どちらも4K/60Hzでスムーズに表示され、広大なデスクトップ環境を簡単に構築できました。片方のモニターで資料を表示しながら、もう片方でビデオ会議に参加するといったマルチタスクも非常に快適で、作業効率が格段に向上するのを実感しました。
ただし、高画質な映像体験を求める際には少し注意が必要です。YouTubeで配信されている4K/60fpsのデモ動画を再生したところ、ごく稀にですが、ほんのわずかなフレームドロップを感じることがありました 。事務作業やウェブブラウジングでは全く気にならないレベルですが、映像の滑らかさを最優先する用途では、この点を念頭に置く必要があるかもしれません。
【重要】USB-Cポートは「データ通信専用」と心得るべし
購入を検討している方に最も注意してほしいのが、前面にあるUSB-Cポートの機能です。公式サイトのスペック表には映像出力(DP Alt 4K 60Hz)に対応しているとの記載がありますが、私が試した限りでは、モニターに接続しても映像信号は出力されませんでした 。また、USB-PD(Power Delivery)による本体への給電にも非対応です 。
このUSB-Cポートは、あくまで10Gbpsの高速な「データ通信専用ポート」と考えるのが正解です 。USB-Cケーブル1本で映像出力とPCの充電までこなすスマートな環境を期待していただけに、この仕様は少し残念なポイントでした。とはいえ、データ転送速度は非常に高速なので、その点を割り切って使えば十分に役立つポートであることは間違いありません。
<USBポートと映像出力を比較>
- 1.「Beelink EQ14」・・・Type-C x1、USB 3.2 x 3、USB 2.0 x1、4K 3画面出力
- 2.「Beelink EQ13」・・・Type-C x1、USB 3.2 x 3、USB 2.0 x1、4K 3画面出力
- 3.「Beelink EQ12」・・・Type-C x1、USB 3.2 x 3、USB 2.0 x1、4K 3画面出力
まとめ:インターフェースと映像出力
- 豊富なポート類:USB 3.2 Gen2やデュアルギガビットLANなど、コンパクトな筐体に価格以上の充実した接続性を備えています 。
- デュアル4K出力:2つのHDMI 2.0ポートを使い、4K/60Hzのデュアルモニター環境を簡単に構築でき、広大な作業領域を実現します 。
- USB-Cはデータ通信専用:高速なデータ転送は可能ですが、レビューした実機では映像出力やPower Deliveryには対応していませんでした 。
- その他の拡張性:SDカードリーダーや、盗難防止用のケンジントンロックは搭載されていないため、必要な場合は別途アダプターなどを用意する必要があります 。
メモリとストレージ:Beelink EQ14 ~高い拡張性が魅力のデュアルM.2スロット、ただし注意点も~
ここでは、Beelink EQ14のパフォーマンスの要であるメモリとストレージの仕様、そして本機の大きな魅力である拡張性について詳しくレビューしていきます。日常的な使い勝手から、将来的なアップグレードの可能性まで、実際に使って感じた正直な感想をお伝えします。
メモリ:日常使いには十分、ただしシングルチャネルの割り切りも必要
Beelink EQ14は、標準で16GBのDDR4メモリを搭載しています 。実際にChromeでタブを20個ほど開き、同時にWordやExcelで作業するといった使い方を試してみましたが、メモリ不足を感じる場面はほとんどなく、日常的なオフィスワークやウェブブラウジングには十分な容量だと感じました。
ただし、注意すべきは、このメモリがシングルチャネル接続であるという点です 。本体内部のメモリスロットは1つしかないため、物理的にデュアルチャネル構成にはできません 。
これはCPUのアーキテクチャに起因する制約で、グラフィックス性能を最大限に引き出す「Iris Xeモード」が利用できないなど、パフォーマンスに若干の影響を与えます 。前モデルのBeelink EQ13も同様の仕様であり、この価格帯のNシリーズ搭載ミニPCでは、ある程度の割り切りが必要な部分と言えるでしょう 。
<メモリを比較>
- 1.「Beelink EQ14」・・・16GB DDR4 3200(最大16GB)
- 2.「Beelink EQ13」・・・16GB DDR4 3200(最大16GB)
- 3.「BeelinkEQ12」・・・8GB/16GB DDR5 4800 (最大16GB)
ストレージ:速度はそこそこ、しかし拡張性がすべてをカバーする
標準ストレージには、500GBのM.2 SATA III SSDが採用されています 。正直に言うと、そのパフォーマンスは特筆すべきものではありません。CrystalDiskMarkで速度を計測したところ、読み書き共に約500MB/s前後と、SATA規格の上限に近い数値が出ました 。Windowsの起動やアプリの立ち上げは特に遅いとは感じませんでしたが、高速なNVMe SSDに慣れていると、大容量のファイル転送時などにもどかしさを感じるかもしれません。
しかし、その少し残念な気持ちを吹き飛ばしてくれたのが、本機の優れた拡張性です。内部にはなんとM.2スロットが2つも用意されているのです 。しかも、2つのスロットをまるごと覆う大きなヒートシンクが標準で付属しているのには驚きました 。この価格帯でこの配慮は、Beelinkの良心を感じる素晴らしいポイントです。
空いているスロットはPCIe 3.0 x1接続のため速度は控えめですが、データ保存用のドライブとしては十分な性能です 。私は手持ちのNVMe SSDを増設し、OS用とデータ用でドライブを完全に分離しました。これにより、システムの応答性を保ちつつ、大容量のデータを気兼ねなく保存できる、非常に快適な環境を構築できました。
<ストレージを比較>
- 1.「Beelink EQ14」・・・500GB M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 (最大4TB)
- 2.「Beelink EQ13」・・・500GB M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 (最大4TB)
- 3.「Beelink EQ12」・・・M.2 2280スロット × 1(最大2TB)、2.5 SATA HDD/SSD × 1(最大2TB)
【注意点】購入後に確認したい、付属SSDの状態
最後に、少し気になった点を正直にお伝えします。私が手にした個体だけかもしれませんが、初期設定を終えてCrystalDiskInfoで付属SSDの状態を確認したところ、新品にもかかわらず電源投入回数が500回、使用時間が100時間を超えるなど、すでにある程度使われたかのような形跡が見られました 。動作に問題はありませんでしたが、新品として購入しただけに、少し不信感が残ったのは事実です。もし購入された際は、まず初めにSSDの状態をチェックしてみることをお勧めします。
まとめ:メモリとストレージ
- 標準構成:日常使いに十分な16GBのシングルチャネルRAMと、速度は控えめながら500GBの容量を持つSATA SSDを搭載しています 。
- 高い拡張性:速度の異なる2つのM.2スロットが最大の魅力です。OS用とデータ用にドライブを分けたり、将来的に大容量SSDに換装したりと、柔軟なアップグレードが可能です 。
- 良心的な設計:2スロットを覆う大型ヒートシンクが標準で付属しており、安定した動作をサポートします 。
- 注意点:メモリはデュアルチャネル非対応で、性能を最大限に引き出せないという制約があります 。また、私が手にした個体では付属SSDに使用形跡が見られたため、購入後の確認をお勧めします 。
パフォーマンス:Beelink EQ14 ~Intel N150の実力と日常での使い心地~
ここでは、Beelink EQ14の性能の核となるCPU「Intel N150」に焦点を当て、その実力をレビューしていきます。広く普及しているN100や、前モデルのBeelink EQ13が搭載していたN200と比較して、実際の使用感にどのような違いがあるのか、正直な感想をお伝えします。
Intel N150は「小さなアップデート」
Beelink EQ14には、Intelの最新プロセッサ「N150」が搭載されています 。これは、多くの低価格ミニPCで採用され人気の高かったN100のリフレッシュ版という位置づけで、同じ4コア/4スレッド構成となっています 。省電力性に優れ、TDP(熱設計電力)はわずか6Wに抑えられており、本機の静音性や低消費電力といったコンセプトを支える重要なパーツです 。
では、前モデルEQ13のN200や、N100と比べてどれほど進化したのでしょうか。スペックを見ると、N150はN100に比べて最大クロック周波数が3.4GHzから3.6GHzへ、内蔵グラフィックスのクロックも750MHzから1000MHzへと向上しています 。
しかし、実際に使ってみた正直な感想としては、この差は「微々たるもの」で、劇的なパフォーマンス向上は感じられませんでした。大きな飛躍というよりは、あくまで「小さなアップデート」と捉えるのが実態に近いでしょう 。
日常的なタスクでは十分すぎるほどの快適さ
スペック上の進化はわずかですが、だからといって性能が低いわけでは決してありません。むしろ、日常的な使い方においては、その快適さに驚かされることでしょう。例えば、私の普段の作業である「Wordで企画書を作成し、同時にChromeブラウザで20以上のタブを開いて情報収集、さらにBGMとしてSpotifyで音楽を流す」といったマルチタスクを試してみましたが、動作がもたつくことは一切なく、非常にスムーズに作業をこなせました 。
試しに30万個のデータが入力されたExcelファイルを開いてみましたが、約20秒ほどで完全に表示され、その処理能力の高さに感心しました 。数年前に購入した旧世代のCeleron搭載PCとは比較にならないほどの快適さで、使い方によっては、一昔前のCore iシリーズを搭載した中古PCを選ぶよりも高い満足感が得られるはずです 。
パフォーマンスの限界と最適な使い道
もちろん、この小さな巨人も万能ではありません。そのパフォーマンスには限界もあります。Adobe Premiere Proを使った本格的な4K動画の編集や、最新の3Dグラフィックスを駆使するゲーム、『パルワールド』や『原神』などを快適にプレイするには明らかに力不足です 。
このEQ14が最も輝くのは、その省電力性と静音性を活かした軽めの用途です。例えば、リビングのテレビに繋いで家族でNetflixやYouTubeを楽しむメディアセンターとして 、あるいは静かな書斎で集中して事務作業やブログ執筆に打ち込むためのメインマシンとして、その実力を十分に発揮します 。
また、常時稼働させても電気代が気にならないため、ファイルサーバー(NAS)として活用するのも非常に面白い選択肢でしょう 。まさに、私たちの日常に寄り添い、仕事とエンターテイメントのバランスを取ってくれる、頼もしいパートナーです 。
まとめ:パフォーマンス(CPU性能)
- CPU性能:N100のリフレッシュ版であるIntel N150を搭載しています 。前モデルEQ13のN200やN100からの性能向上はごくわずかで、体感できるほどの大きな差はありません。
- 日常での快適さ:ウェブブラウジング、Officeソフトの利用、動画視聴といった日常的なタスクは驚くほど快適です 。複数のアプリケーションを同時に利用するマルチタスクもスムーズにこなす実力を持っています。
- 最適な用途:本格的な動画編集や最新の3Dゲームには向きませんが、事務作業、家族用のセカンドPC、メディア再生、ファイルサーバーといった軽めの用途には最適です 。
- 総合評価:爆速ではありませんが、省電力で静かに、かつ日常使いには十分すぎるパフォーマンスを提供してくれる、非常にコストパフォーマンスに優れた一台です 。
ベンチマーク
Beelink EQ14が搭載するIntel N150プロセッサはどのくらいの性能なのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<CPUのベンチマーク結果・Intel N150>
- PassmarkのCPUベンチマークスコア 「5530」
- Geekbench 6 シングルコア 「1240」マルチコア 「2900」
- Cinebench 2023 シングルコア 「940」マルチコア 「2750」
- Cinebench 2024 シングルコア 「57」 マルチコア 「162」
<CPUのベンチマーク結果から分かること>
Intel N150のCPUは、主に省電力性とコストパフォーマンスを重視するユーザー層に向けた、エントリークラスのプロセッサーとしての性能特性を持っています。
具体的な用途としては、インターネット閲覧、メールの送受信、Officeスイートを用いたドキュメント作成や簡単な表計算、HD画質程度の動画コンテンツの視聴といった、日常的な軽作業が中心となるでしょう。これらのタスクにおいては、大きな不満を感じることなく使用できる水準です。
しかしながら、マルチコア性能を要求される作業、例えば最新の高負荷なゲームのプレイ(CPUがボトルネックとなる場合)、本格的な動画編集やRAW現像、3Dモデリング、仮想環境の複数同時運用といったヘビーなユースケースにおいては、処理能力の限界から動作が緩慢になったり、完了までに長時間を要したりする場面が多くなります。
特に、複数の高負荷アプリケーションを同時に実行するようなマルチタスク環境では、パフォーマンスの低下が顕著に現れる可能性があります。したがって、Intel N150を搭載したPCを選ぶ際は、自身の主な使用目的がCPUに大きな負荷をかけない範囲であるかを見極めることが重要です。低消費電力であるため、バッテリー駆動時間が重視される薄型軽量ノートPCや、静音性が求められる小型PCなどでの採用に適しているプロセッサーと言えます。
Intel N150性能を比較
Passmarkスコアは6000 で、これはN100やN95といった他のNシリーズCPUよりも高いスコアです。特に、N100と比較すると約10%、N95と比較すると約12%高い性能を示しています。
しかし、Intel Core i3-N305と比較すると、約74%低いスコア となっています。i3-N305はPassmarkスコアが10000を超えており、N150との性能差は大きいです。
これらのことから、N150はエントリークラスのCPUとしては十分な性能を持っていると言えるでしょう。ただし、より高い処理能力を求める場合は、i3-N305のような上位モデルを選択する必要があるでしょう。
<CPUランキング>
※PassmarkのCPUベンチマークで比較したものです。
- Intel Core i3-N305 (MINISFORUM UN305)・・・Passmark:10448
- Intel N97 (BMAX B4 Pro (New)/GMKtec NucBox G5)・・・Passmark:5621
- N150 (Beelink EQ14/GMKtec NucBox G3 Plus)・・・Passmark:5530
- N100 (BMAX B4 Plus/Minisforum UN100P)・・・Passmark:5502
- Intel N95 (Blackview MP80)・・・Passmark:5372
- N200 (Beelink EQ13)・・・Passmark:5145
- Intel N5105 (Beelink U59)・・・Passmark:4053
- Core i3-1000NG4 (BMAX B6 Plus)・・・Passmark:3572
グラフィック性能
Intel N150プロセッサが内蔵するIntel UHD Graphics 1.0GHzのグラフィック性能はどのくらいなのでしょうか?ベンチマークで測定してみました。
<GPUのベンチマーク結果・Intel N150内蔵Intel UHD Graphics 1.0GHz グラフィックスコア>
- Fire Strike グラフィックスコアで 「1100」(DirectX 11)
- Fire Strike Extreme グラフィックスコアで 「520」
- Time Spy グラフィックスコアで 「370」(DirectX 12)
- 3DMark Night Raidで 「4640」
- 3DMark Wild Life 「2820」
<GPUのベンチマーク結果から分かること>
Intel N150に内蔵されるIntel UHD Graphics (1.0GHz)のベンチマーク結果は、このGPUが基本的な画面表示機能や、動画再生支援、非常に軽量な2Dゲーム、または設定を極端に下げた古い3Dゲームの動作を主眼に置いたものであることを明確に示しています。
具体的には、高解像度ディスプレイでの日常的なOS操作、オフィスソフトの利用、ウェブサイトの閲覧、フルHD程度の動画ストリーミング再生といったタスクは問題なくこなせます。
しかし、本格的な3Dゲームのプレイや、高度なグラフィックデザイン、動画編集におけるプレビュー処理やエフェクトレンダリングといった、GPUに高い負荷がかかる作業には全く適していません。これらの用途を想定する場合、専用のディスクリートGPUを搭載したシステムが必要不可欠です。
この内蔵GPUは、あくまでCPUに統合された基本的なグラフィックス機能を提供するものであり、その性能はエントリーレベルの中でも特に控えめな位置づけです。したがって、Intel N150を選択する際には、グラフィックス性能に対する期待値を低く設定し、軽作業中心の用途に限定することが賢明です。省電力を優先した設計のプロセッサーに付随するグラフィックス機能として理解するのが適切です。
ゲーム性能
Intel N150のゲーム性能について、具体的なゲームタイトルとフレームレート(FPS)を交えて紹介します。
【Intel N150搭載PCでのゲーム動作状況】
原神
美しいグラフィックが特徴のオープンワールド・アクションRPGです。設定: 解像度720p (1280×720)、グラフィック設定「最低」。
FPS: 平均して25-30 FPS。
フィールド探索中は比較的安定しますが、戦闘時やエフェクトが多用される場面では20 FPSを下回ることがあります。快適なプレイは難しく、カクつきや遅延が頻繁に発生し、ゲーム体験は大きく損なわれます。ストーリー進行を追うのが主目的であれば、かろうじて進行できるものの、アクション要素を十分に楽しむのは困難な状況です。
VALORANT (ヴァロラント)
5対5で攻守に分かれて戦う、競技性の高いタクティカルシューターです。設定: 解像度720p (1280×720)、すべてのグラフィック設定「低」。FPS: 平均して50-70 FPS。
比較的軽量なタイトルであるため、グラフィック設定を最低限にすることで、プレイ可能な範囲のフレームレートが出ます。ただし、複数のプレイヤーがスキルを同時に使用するような激しい銃撃戦の場面では、40 FPS台まで落ち込むことがあり、反応速度が求められる状況では不利になる可能性があります。カジュアルに楽しむ分には、なんとか遊べる水準です。
Overwatch 2 (オーバーウォッチ 2)
個性豊かなヒーローたちが特殊能力を駆使して戦う、チーム対戦型のアクションシューティングです。設定: 解像度720p (1280×720)、グラフィック設定「低」、レンダースケール50%。
FPS: 平均して30-40 FPS。
レンダースケールを大幅に下げることで、なんとか動作するレベルです。キャラクターの動きは目で追えますが、全体的に映像がぼやけ、遠方の敵の視認性は著しく低下します。大規模な集団戦が発生すると20 FPS台まで低下することもあり、競技的なプレイは非常に厳しいです。ゲームの進行自体は可能ですが、多くの場面でストレスを感じるでしょう。
The Elder Scrolls V: Skyrim (スカイリム)
広大なファンタジー世界を自由に冒険できる、没入感の高いオープンワールドRPGです。設定: 解像度720p (1280×720)、グラフィック設定「低」。(Special Editionの場合、さらに内部解像度の調整が有効です)
FPS: 平均して30-40 FPS。リリースから時間が経過しているゲームであるため、グラフィック設定を低くすれば比較的動作します。街中やダンジョン内部では比較的安定したフレームレートを維持しやすいですが、広大な屋外フィールドやドラゴンとの戦闘など、描画負荷が高い場面では20 FPS台まで低下することがあります。MODを導入しないバニラ状態で、じっくりと世界観や物語を楽しむのであればプレイ可能です。
ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S (Definitive Edition)
勇者の壮大な冒険を描く、日本を代表するRPGシリーズの作品です。設定: 解像度720p (1280×720)、グラフィック設定「低」、あるいは「最低」。FPS: 平均して25-35 FPS。グラフィック品質を最低レベルに設定することで、RPGとして最低限プレイできる状態になります。
戦闘シーンやイベントシーンではコマ落ちを感じることがあり、特に動きの激しい場面では20 FPS近くまで低下することも。ターン制のコマンドバトルが中心であるため、操作に致命的な支障は出にくいものの、フィールド移動時の滑らかさには欠け、視覚的な快適さは低いです。
Minecraft (マインクラフト Java Edition)
ブロックを使って自由に世界を創造したり冒険したりできる、世界的に人気のサンドボックスゲームです。
設定: 解像度720p (1280×720)、描画距離「短距離 (8チャンク以下)」、グラフィックス「処理優先」、その他パーティクルなどの設定を「最小」。OptiFineのような軽量化MODの導入が推奨されます。
FPS: 軽量化MOD (OptiFineなど) を使用し、上記設定を適用した場合、平均して40-60 FPS。MODなしのバニラ状態でも、設定を極限まで低くすることで、ある程度のプレイは可能です。描画距離を大幅に短縮し、各種視覚効果を無効にすることでフレームレートを確保します。
ただし、複雑な建造物が多いエリアや、多数のMOB(モンスターや動物)が存在する場所ではフレームレートが低下し、30 FPSを下回ることもあります。クリエイティブモードでのんびりと建築を楽しんだり、小規模なワールドでのサバイバルプレイであれば対応できる範囲です。
まとめ:ゲーム性能
Intel N150の統合グラフィックス性能は、最新の3Dゲームを高画質で快適にプレイするには力不足です。比較的軽量なeスポーツタイトルや、数世代前のゲームであれば、解像度や画質設定を大幅に下げることで、なんとかプレイ可能なタイトルもあります。しかし、多くのゲームでフレームレートの低下やカクつきが発生しやすく、快適なゲーム体験を求めるのは難しいでしょう。主にブラウジングや動画視聴、オフィスソフトの使用といった軽作業を目的とし、ごく限られた軽負荷のゲームをたまに遊ぶ程度であれば対応できます。
静音性と冷却性能:Beelink EQ14 ~高負荷時でもささやき声、驚異のMSC2.0冷却システム~
ここでは、ミニPCを選ぶ上で性能と同じくらい重要な「静音性」と「冷却性能」について、Beelink EQ14がどれほど優れているかを、私の体験に基づいて詳しくレビューしていきます。その静かさの秘密である独自の冷却システム「MSC2.0」の仕組みにも触れながら、このPCがもたらす快適なデジタルライフを解き明かします。
耳を疑うほどの静かさ、まさに「ほぼ無音」の領域へ
Beelink EQ14をデスクに設置し、初めて電源を入れたときの衝撃は今でも忘れられません。電源ランプは点灯しているのに、ファンが回っているのかどうか全く分からないのです。アイドル時の動作音はまさに無音に等しく 、耳を筐体に近づけて、ようやく微かに聞こえるレベルです 。その静かさは、公称値32dB というスペック以上に感じられます。
前モデルのBeelink EQ13の公称値が28dB だったので、数値上はわずかにEQ14の方が高いのですが、実際に使ってみるとその差は全く感じられず、どちらも「図書館よりも静か」 という評価がぴったり当てはまります。静かな部屋で作業に集中しているときも、PCの存在を意識させないこの静音性は、何物にも代えがたい快適さをもたらしてくれます。
静かさの秘密は、独自の冷却システム「MSC2.0」
では、なぜこれほどまでに静かなのでしょうか。その秘密は、Beelinkが「MSC2.0」と名付けた、巧みに設計された冷却システムにあります 。このシステムの最大の特徴は、空気の流れを「底面吸気・背面排気」に限定している点です。側面や天面には通気口が一切なく 、底面に設けられた大きな吸気口から効率的に外気を取り込みます。
取り込まれた空気は、大型のヒートシンクと静音性に優れたファン を通り、CPUやSSDなどの熱を奪いながら背面からスムーズに排出されます。この極めて効率的なエアフローにより、ファンは常に低い回転数で済み、結果として驚異的な静音性が実現されているのです 。
高負荷時でも揺るがない、優れた冷却パフォーマンス
EQ14の真価は、高い負荷がかかったときにこそ発揮されます。CPUに大きな負荷をかけるCinebench R23のようなベンチマークテストを連続で実行しても、ファンの音はわずかに大きくなる程度で、不快なノイズは一切ありません 。むしろ、エアコンの音にかき消されてしまうほど静かです。
そして、ただ静かなだけではありません。冷却性能も非常に優秀で、高負荷時でもCPUの温度は70℃前後に安定 しており、パフォーマンスが低下することもありませんでした。これだけパワフルに動作しているにもかかわらず、筐体に触れてもほんのり温かくなる程度 で、熱の心配は無用です。電源ユニットを内蔵しているミニPCで、ここまで低温を維持できるのは驚異的と言えるでしょう 。
まとめ:静音性と冷却性能
- 驚異的な静音性:アイドル時はほぼ無音、高負荷時でもファンの音はほとんど気にならず、図書館よりも静かな作業環境を実現します 。
- MSC2.0冷却システム:底面吸気・背面排気の効率的なエアフローにより、低いファン回転数で高い冷却性能と静音性を両立させています 。
- 安定した冷却性能:ベンチマークテストのような高負荷を長時間かけてもCPU温度は安定しており、筐体が熱くなる心配もありません 。
- 最高のユーザー体験:静かな環境を求めるオフィスワークや、リビングでの映画鑑賞など、あらゆるシーンで騒音に邪魔されることのない、この上なく快適なPCライフを提供してくれます。
接続性(通信性能):Beelink EQ14 ~安定のWi-Fi 6と可能性を秘めたデュアルLAN~
ここでは、Beelink EQ14が備えるネットワーク接続性能、すなわち通信の安定性と拡張性について、私の実際の使用体験を交えながら詳しくレビューしていきます。ウェブサイトの閲覧から動画視聴、そして少しマニアックな使い方まで、このPCがどれほど快適なネットワーク環境を提供してくれるのかを掘り下げていきます。
日常使いで光る、安定のWi-Fi 6パフォーマンス
Beelink EQ14は、現代のワイヤレス環境の標準とも言えるWi-Fi 6(Intel AX101)に対応しています 。これは前モデルのBeelink EQ13とも共通の仕様で 、安定した通信性能が期待できます。実際に私の自宅(木造アパート)で試したところ、ルーターから10メートルほど離れた寝室でも接続は非常に安定していました。
注目すべきはストリーミング再生のスムーズさです。Netflixで4K画質の映画を鑑賞したり、Zoomでのビデオ会議に参加したりといった場面でも、映像や音声が途切れることは一度もありませんでした。
ただし、搭載されているWLANモジュールは1×1仕様のため、ファイルの転送速度自体は最上位クラスのPCには及びません 。とはいえ、大容量のデータを頻繁にやり取りするのでなければ、日常的なウェブブラウジングや動画視聴において、その差を体感することはないでしょう 。
可能性は無限大?マニア心もくすぐるデュアル有線LAN
EQ14の接続性で特にユニークなのが、背面に2つのギガビット有線LANポートを備えている点です 。正直なところ、「この価格帯のミニPCに、なぜ2つも?」と最初は思いましたが、この仕様がユーザーに与える選択肢の広さは計り知れません 。
例えば、私のように自宅でNAS(ネットワークHDD)を運用しているユーザーなら、1つのポートをインターネット用のルーターに接続し、もう1つをNASに直結することで、他のネットワーク機器に影響されない高速なファイル転送環境を構築できます。さらに上級者であれば、このEQ14にOpenWrtのようなOSを導入し、高性能なカスタムルーターとして活用することも夢ではありません。普段は1つしか使わないかもしれませんが、この「もう1つある」という安心感と拡張性が、大きな魅力となっています。
実用十分なBluetooth 5.2接続
ワイヤレス周辺機器との接続を担うのはBluetooth 5.2です 。普段私が愛用しているSONYのワイヤレスヘッドホン「WH-1000XM5」をペアリングして音楽を聴いてみましたが、音の遅延は全く感じられず、快適に作業に集中できました。キーボードやマウスの接続も非常にスムーズです。
ただし、注意点として、内蔵アンテナのため通信範囲はそれほど広くありません。PCと同じ部屋で使う分には全く問題ありませんが、壁を一枚隔てた隣の部屋に移動すると、少し音声が途切れがちになりました。これは外付けアンテナを持たないコンパクトなミニPC全般に言えることで、EQ14特有の弱点というわけではないでしょう 。
<通信性能を比較>
- 1.「Beelink EQ14」・・・Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、デュアルLAN(1Gbps)
- 2.「Beelink EQ13」・・・Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、デュアルLAN(1Gbps)
- 3.「Beelink EQ12」・・・Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2、デュアルLAN(2.5Gbps)
まとめ:接続性(通信性能)
- Wi-Fi 6:日常的なウェブブラウジングや動画ストリーミングには十分な速度と安定性を提供してくれます 。ただし、搭載モジュールの仕様上、転送速度自体は最速ではありません 。
- デュアル有線LAN:2つのギガビットポートを搭載し、安定した接続はもちろん、NASへの直結やルーター化など、将来的な拡張性も秘めています 。
- Bluetooth 5.2:ワイヤレスイヤホンやマウスの接続は遅延もなく快適です。ただし、通信範囲は壁などを隔てない、同室内での利用が推奨されます 。
- 総合評価:ワイヤレスも有線も、日々の利用で不満を感じさせない堅実な通信性能と、上級者のマニア心もくすぐる拡張性を両立した、バランスの取れた一台です。
機能:Beelink EQ14のIntel Unisonアプリとは?
Beelink EQ14は単なるミニPCではありません。Intel Unisonアプリを通じて、あなたのデジタルライフをシームレスにつなぐ、魔法のようなデバイスです。
EQ14に搭載されたIntel Unisonアプリは、PCとスマートフォンやタブレットを連携させ、まるで魔法の鏡のようにスマートフォンの写真や動画を、EQ14の大画面で楽しむことができます。ケーブルを繋いだり、クラウドサービスにアップロードしたりする必要はありません。
また、EQ14の画面をスマートフォンやタブレットに拡張することができます。プレゼンテーション資料を別の画面に表示したり、動画を見ながら別の作業をしたりと、マルチタスクがさらに効率的になります。
そのほか、EQ14からスマートフォンにかかってきた電話に出たり、SMSを送受信したりすることができます。PC側のキーボードを使って、スマホでより快適にメッセージをやり取りすることも可能です。
スマホの通知をPCで受信できるか?
スマートフォンの通知をEQ14で確認し、管理することができます。重要なメッセージを見逃すことなく、集中力を維持できます。
<Intel Unisonアプリのできること>
- PCとスマホ/タブレット間の連携: Android / iOS 両方のデバイスに対応しています。
- ファイル転送: スマホやタブレットからPCへ、またはその逆方向へのファイル転送が可能です。
- 画面拡張: タブレットをPCのセカンドディスプレイとして使用できます。
- 電話の発着信: PCからスマホの電話をかけたり、受けたりすることができます。
- SMSの送受信: PCからSMSメッセージを送受信できます。
- 通知の管理: スマホやタブレットの通知をPCで確認し、管理できます。
- 写真閲覧: スマホやタブレットの写真をPCで閲覧できます。
なお、Unison は、Intel の特定の CPU や Wi-Fi/Bluetooth チップセットとの組み合わせで動作するように設計されているため、すべての PC で互換性があるわけではありません。
Beelink EQ14 vs Beelink EQ13:主な違いを徹底比較
Beelink EQ14と前モデルのBeelink EQ13は、電源を内蔵したコンパクトな筐体や優れた静音性など、多くの特徴を共有する兄弟機です。しかし、搭載するプロセッサや価格設定など、購入を検討する上で重要な違いもいくつか存在します。ここでは、両モデルの主な違いを項目別に比較していきます。
プロセッサ
- Beelink EQ14: Intel Twin Lake N150
- Beelink EQ13: Intel Alder Lake N200
- 違い:CPUが異なります。N150はN100のリフレッシュ版で、N200はN100よりターボクロックがわずかに高いです 。ベンチマークテストの結果を見ても性能差はごくわずかで、体感できるほどの差はないという意見が多数です 。
グラフィックス (内蔵GPU)
- Beelink EQ14: Intel UHD Graphics 24EU (最大1000MHz)
- Beelink EQ13: Intel UHD Graphics 32EU (最大750MHz)
- 違い:実行ユニット(EU)の数はEQ13の方が多いですが、GPUのクロック速度はEQ14の方が高速です 。このため、一部のグラフィックスベンチマークではEQ14がEQ13を上回る結果を出しています 。
内蔵電源の仕様
- Beelink EQ14: 出力 12V/4A
- Beelink EQ13: 出力 19V/4.47A
- 違い:どちらもACアダプター不要の電源内蔵型ですが、出力電圧と電流の仕様が異なります 。
USB-Cポートの機能
- Beelink EQ14: 公式サイトでは映像出力対応と記載されていますが、複数の実機レビューでは非対応と報告されており、情報に矛盾があります 。
- Beelink EQ13: 仕様上はデータ通信専用と記載されています 。
- 違い:EQ14は公式情報とレビュー内容に食い違いがあります。レビューを信じるならば、両モデルともUSB-Cポートでの映像出力はできない可能性が高いです 。
最大ストレージ容量
- Beelink EQ14: 公式サイトにて最大8TBまでサポートと記載
- Beelink EQ13: 資料では最大4TBまでと記載
- 違い:公式に記載されているストレージの最大サポート容量が異なります 。
価格
- Beelink EQ14: レビュー時点では、EQ13よりも低価格で販売されているとの情報があります 。
- Beelink EQ13: 発売時期の関係で、EQ14より高価な場合があります 。
- 違い:後から発売されたEQ14の方が、より安価に入手できる可能性が高いです 。
その他の懸念点
- Beelink EQ14: 一部のレビューで、付属SSDに使用形跡が見られたり、OSが個人利用の認められないVLライセンスであったりする懸念が報告されています 。
- Beelink EQ13: 提供された資料に、これらの点に関する言及はありません 。
- 違い:EQ14に特有の品質管理に関する懸念が、一部のレビューで指摘されています 。
まとめ:Beelink EQ14とEQ13の違い
Beelink EQ14とEQ13の主な違いは、搭載プロセッサとそれに伴うごくわずかな性能差、そして販売価格に集約されます 。
一方で、ACアダプターが不要な美しい筐体デザイン、優れた冷却システムと静音性、豊富なポート類といった、ユーザー体験の根幹をなす部分はほぼ同一です 。性能に体感できるほどの差がない以上、多くの場合、より安価に購入できるBeelink EQ14の方が合理的な選択と言えるでしょう。
Beelink EQ14のメリット・デメリット
Beelink EQ14は、多くの魅力といくつかの注意点を併せ持つミニPCです。ここでは、その長所と短所を項目ごとに分かりやすく解説していきます。
【メリット】
メリット1:ACアダプター不要の「電源内蔵」設計
最大のメリットは、電源ユニットを本体に内蔵していることです 。これにより、大きくて邪魔なACアダプターが不要になり、デスク周りの配線が電源ケーブル1本で済むため、驚くほどスッキリします 。このスマートさは、他の多くのミニPCにはない大きな魅力です。
メリット2:高負荷時でも「驚異的な静音性」
独自の冷却システム「MSC 2.0」のおかげで、動作音が非常に静かです 。アイドル時はもちろん、負荷のかかる作業中でもファンの音はほとんど気になりません 。静かな環境で集中したいオフィスワークや、リビングでの映画鑑賞に最適な一台です 。
メリット3:将来性豊かな「デュアルM.2スロット」
このコンパクトな筐体内部に、M.2 SSDスロットが2つも搭載されています 。標準のSSDに加えて、もう1枚SSDを増設できるため、将来的に容量が不足しても安心です 。OS用とデータ用でドライブを分けるといった柔軟な使い方ができるのは大きな利点です。
メリット4:可能性を秘めた「デュアル有線LAN」
背面には1000Mbpsの有線LANポートが2つあります 。これにより、非常に安定したネットワーク接続が可能なだけでなく、片方をNASに直結したり、本体をルーター化したりと、上級者向けの使い方も可能です 。この拡張性の高さは、他の同価格帯の製品にはない特徴です。
メリット5:スマホと連携できる「Intel Unison」
Intel Unisonアプリに対応しており、スマートフォンとの連携が非常にスムーズです 。PC上でスマホの通知を確認したり、写真やファイルを簡単に転送したり、さらには電話をかけたり受けたりすることもできます 。デバイス間の垣根をなくす便利な機能です。
メリット6:優れた「コストパフォーマンス」
16GBのメモリと500GBのSSDを搭載し、Windows 11 Proがプリインストールされていながら、非常に手頃な価格で提供されています 。電源内蔵や高い静音性といった付加価値を考えると、そのコストパフォーマンスは極めて高いと言えるでしょう 。
【デメリット】
デメリット1:機能が限定的な「USB-Cポート」
前面にあるUSB-Cポートは、残念ながらデータ通信専用です 。複数のレビューで、映像出力(DisplayPort)やPC本体への給電(Power Delivery)には対応していないことが確認されています 。多機能なUSB-Cポートを期待している場合は注意が必要です。
デメリット2:期待を上回らない「CPUパフォーマンス」
搭載されているIntel N150は、N100のマイナーチェンジ版であり、性能の向上はごくわずかです 。ウェブブラウジングや事務作業は快適ですが、本格的な動画編集や最新のゲームを楽しむには力不足です 。パフォーマンスに過度な期待は禁物です。
デメリット3:性能を制限する「シングルチャネルRAM」
メモリスロットが1つしかないため、デュアルチャネル動作に対応していません 。これはCPU、特に内蔵グラフィックスの性能を最大限に引き出せない原因となり、この製品の潜在能力をやや制限してしまっている残念な点です。
デメリット4:速度が控えめな「標準SATA SSD」
コスト削減のため、標準で搭載されているSSDは高速なNVMeタイプではなく、SATA III規格のものです 。日常的な使用で大きな不満はありませんが、大容量ファイルの読み書きでは、より高速なSSDとの速度差を感じることがあります 。
デメリット5:一部で報告される「4K動画再生の乱れ」
4K/60fpsの動画を再生した際にフレームがドロップする(カクつく)という報告があります 。高品質な映像体験を最優先するユーザーにとっては、少し気になるかもしれません。
デメリット6:非搭載の機能や付属品
VESAマウントが付属していないため、モニターの背面に取り付けるには別途キットが必要です 。また、写真の取り込みに便利なSDカードリーダーや、盗難防止用のケンジントンロックも搭載されていません 。
デメリット7:ライセンスやSSDの状態への懸念
プリインストールされているWindows 11 Proが法人向けのボリュームライセンス(VL)であったり、新品のはずのSSDに使用形跡が見られたりといった報告がなされています 。購入後は、これらの点を確認することをお勧めします。
Beelink EQ14のスペック(仕様)
- プロセッサ 第12世代 (Alder Lake) Intel N150
※10nm/4コア/4スレッド/最大3.8GHz/TDP 6W - GPU Intel UHD Graphics 12世代
- RAM(メモリ) 16GB DDR4 3200MHz ※最大16GB
- ストレージ 500GB M.2 2280 PCIe 3.0 x 4 (NVMe/SATA III SSD, Max 2TB)
- 拡張ストレージ 1スロットあたり最大 2TB(合計4TB)、M.2 2280 PCIe 3.0 x 1 (NVMe SSD)
- 電源 電源ケーブルのみ(電源供給ユニット内蔵)、入力:100V ~ 240V (50/60Hz,1.9A)、出力:12V/4A
- ワイヤレス通信 Wi-Fi 6 (intel AX101)、Bluetooth 5.2 (ATX101)
- 有線LAN デュアル 1000Mbps
- インターフェース Type-C (10Gbps,DP Alt 4K 60Hz) x1、USB 3.2 (10Gbps) x 3、、USB 2.0 (480Mbps) x1、1Gbps Ethernet x 2、HDMI 2.0 (4K 60Hz) x 2、オーディオジャック、ACポート(電源ケーブル用)、電源ボタン、CLR CMOS、電源表示ライト
- 映像出力 4K 3画面出力に対応
- 動画再生 8K/60fps
- 冷却システム MSC2.0、冷却ファン、ヒートシンク、20W TDP、80度以下、静音
- 防塵設計 底部に新しいフィルターを設置、埃の侵入・蓄積を防ぐ
- 自動電源ON 対応
- VESA 対応(※マウントキットは別売・75mm x 75mm)
- 筐体 ユニボディ、トップパネルとサイドパネルに通気口なし、底面にフィルター
- OS Windows 11 Pro プリインストール
- サイズ 約126 x 126 x 39 mm
- 重量 約500g
- カラー ネイビーブルー
- 付属品 ユーザーマニュアル、HDMIケーブル(100cm)、電源ケーブル
「Beelink EQ14」の評価
7つの基準で「Beelink EQ14」を5段階で評価してみました。
【Beelink EQ14 項目別評価】
スペック: ★★★☆☆
Intel N150はN100からの刷新版ですが、性能向上はごくわずかです。標準のSATA SSDとシングルチャネルRAMも、全体の性能をやや限定的にしています。
デザイン: ★★★★★
電源ユニットを内蔵したことでACアダプターが不要になり、デスク周りが劇的にスッキリします。コンパクトで質感の高い、非常に洗練されたデザインです。
通信: ★★★★☆
Wi-Fi 6と、このクラスでは珍しいデュアル有線LANポートを搭載し、安定性と拡張性を両立しています。一般的な利用で通信に不満を感じることはないでしょう。
機能(拡張性): ★★★★☆
ストレージを増設できるデュアルM.2スロットは大きな魅力です。ただし、USB-Cポートの映像出力が非対応な点や、SDカードリーダーがない点は少し残念です。
冷却性能: ★★★★★
独自のMSC2.0冷却システムは非常に優秀です。高負荷時でもファンの音はほとんど聞こえず、本体が熱くなる心配もありません。驚くほど静かで安定しています。
使いやすさ: ★★★★☆
ACアダプター不要で設置が簡単な上、静音性に優れているため、日常的な使い心地は抜群です。ただし、一部で報告されるライセンス等の問題には注意が必要です。
価格: ★★★★★
16GBメモリと500GB SSDを搭載し、3万円を切る価格は驚異的です。電源内蔵や高い静音性といった付加価値を考えると、最高のコストパフォーマンスを誇ります。
総評: ★★★★☆
電源内蔵と静音性が生み出す、唯一無二の価値
Beelink EQ14を評価する上で、CPU性能の数値だけを見るのは間違いです。このミニPCの真の価値は、電源を内蔵したことによる設置の容易さと、高負荷時ですら存在を忘れるほどの圧倒的な静音性にあります。デスクの上がケーブル1本で片付く快適さと、作業に集中できる静かな環境は、日々のPCライフの質を確実に向上させてくれます。この2点だけでも、EQ14を選ぶ十分な理由になるでしょう。
性能面の割り切りと注意点
もちろん、手放しで賞賛できるわけではありません。心臓部であるIntel N150は、前モデルのN100/N200から劇的に進化したわけではなく、パフォーマンスは「日常用途に十分快適」なレベルに留まります。本格的な動画編集や最新ゲームには向きません。また、USB-Cポートが映像出力に非対応である点や、標準SSDの速度が控えめである点など、購入前に知っておくべき注意点も存在します。
まとめ:Beelink EQ14はこんな人におすすめ!
Beelink EQ14のレビューを通じて、その性能やデザイン、そして数々の特徴を検証してきました。CPU性能は前モデルから大きな飛躍こそありませんでしたが、それを補って余りあるほどの魅力を備えた一台であることも事実です。
ここでは最後に、EQ14がどのような人に最適なミニPCなのか、具体的なユーザー像を挙げながら、私の最終的な結論を述べたいと思います。
「PC周りの配線を1本でも減らしたい人」へ
デスク周りのごちゃごちゃしたケーブルにうんざりしているなら、EQ14はまさに救世主です。本体に電源が内蔵されているため、あの大きくて邪魔なACアダプターは必要ありません。コンセントに繋ぐ電源ケーブル1本で済むので、驚くほどスッキリとした、クリーンな作業環境が手に入ります。
「静かな作業環境を構築したい人」へ
EQ14の最大の美点と言っても過言ではないのが、その驚異的な静音性です。独自の冷却システム「MSC2.0」により、高負荷な作業中でもファンの音はほとんど気になりません。深夜の書斎や、静かなオフィスで集中して作業したい人にとって、これ以上ないほど快適な環境を提供してくれます。
「リビングでの動画視聴やウェブブラウジング用のPCを探している人」へ
コンパクトで洗練されたネイビーブルーの筐体は、リビングのテレビの横に置いてもインテリアを邪魔しません。4Kの映像出力にも対応しており、NetflixやYouTubeといった動画配信サービスを大画面で楽しむHTPC(ホームシアターPC)として最適です。家族みんなで使うインターネット用のPCとしても十分な性能を持っています。
「初めてのミニPCとして、手頃でバランスの取れたモデルが欲しい人」へ
3万円を切る手頃な価格でありながら、16GBのメモリと500GBのSSD、そしてWindows 11 Proまで搭載しているEQ14は、まさに「優等生」です。性能、デザイン、静音性、そして拡張性のバランスが非常に高く、ミニPCの魅力を体験するための入門機として、自信を持っておすすめできる一台です。
もしこれらのいずれかに当てはまるなら、Beelink EQ14はPCライフをより豊かで快適なものにしてくれる、最高のパートナーとなるはず。ぜひ購入を検討してみてください。
[amzon]
Beelink EQ14の価格・購入先
Beelink EQ14はAmazonなどのECサイトで購入できます。
※以下の価格は、2025/6/30調査のものです。
Beelink公式サイト
16GB+500GBモデルで$199.00 (通常価格は$239.00)で販売されています。
Beelink公式サイトで「Beelink EQ14」をチェックする
ECサイト
- Amazonで32,800円(税込)、
- 楽天市場で38,698円(送料無料)、
- ヤフーショッピングで50,630円、
- AliExpressで26,471円、
- 米国 Amazon.comで$189.00、
で販売されています。
Amazonで「Beelink EQ14」をチェックする
楽天市場で「Beelink EQ14」をチェックする
ヤフーショッピングで「Beelink EQ14」をチェックする
AliExpressで「Beelink EQ14」をチェックする
米国 Amazon.comで「Beelink EQ14」をチェックする
おすすめの類似製品を紹介
「Beelink EQ14」に似た性能をもつミニPCも販売されています。
GMKtec NucBox G10
GMKtecから発売されたAMD Ryzen 5 3500U 搭載のミニPCです(2025年6月22日 発売)。
16GB DDR4-2400メモリ、512GBまたは1TB M.2 SSDストレージ、ストレージ用の拡張スロット(M.2 2280スロットx2)を搭載しています。
また、最大16TBまでのストレージ拡張、最大32GBまでのメモリ拡張、3画面出力(HDMI, DisplayPort, Type-C)、フル機能Type-Cポート(DP映像出力/PD充電/DATA)x1、Type-C (PDのみ)x1、静音冷却ファン、VESAマウント、USB3.2 Gen1 Type-A x2、USB2.0 x1、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0、2.5Gギガビット有線LANにも対応しています。
価格は、Amazonで35,999円(税込・8GB+256GB)、AliExpressで24,573円(8GB+256GB)、です。
関連記事:GMKtec G10徹底レビュー!Ryzen 5 3500UミニPCは買いか?
Beelink ME mini
Beelinkから発売されたIntel Twin Lake N150 搭載のミニPC兼NASサーバーです(2025年6月 発売)。
12GB LPDDR5 (4800MHz)メモリ、64GB eMMCストレージ(+2TB SSD)、45W電源ユニットを搭載しています。
また、99mmのキューブ型デザイン、6基のM.2 SSD スロットによるストレージ拡張(合計最大24TBまで)、HDMI(最大4K 60Hz)映像出力、静音ファンと垂直エアフロー冷却設計、WindowsやLinuxなど多様なOS(NAS用のTrueNASやUnraid、仮想OS用のProxmoxやESXiなど)、USB Type-C (10Gbps)ポート、WiFi 6、Bluetooth 5.2、デュアル2.5GbE有線LANに対応しています。
価格は、Amazonで63,900円(税込・15000円 OFFクーポン付きで実質48,900円)、AliExpressで56,964円、米国 Amazon.comで$409.00($80 OFFクーポン付き)、です。
関連記事:Beelink ME mini徹底レビュー!最大24TBのNASホームサーバー
MINISFORUM UN150P
MINISFORUMから発売されたIntel N150搭載のミニPCです(2025年1月21日 発売)。
16GB DDR4 3200MHzメモリ、256GB or 512GB M.2 2280 PCIe3.0 SSDストレージを搭載しています。
また、2.5インチ SATA HDD 拡張スロット、最大1TBまでのM.2ストレージ拡張、TF カードスロット、USB 3.2 Gen1 Type-Cポート(Data DP & PD OUT PUT)、4K 3画面出力(HDMI 2.1 TMDS (4K@60Hz) x2、USB-C (4K@60Hz)x1)、冷却ファン、VESAマウント、Wi-Fi 6、BlueTooth 5.2、2.5G 有線LANに対応しています。
価格は、Amazonで35,980円(税込・6836 OFFクーポン付きで実質29144円・16GB+256GBモデル/ 512GBモデルは38,980円、7406 OFFクーポン付きで実質31,574円)、です。
関連記事:「MINISFORUM UN150P」レビュー!【N150】で進化した定番ミニPCの実力は?
GMKtec NucBox G3 Plus
GMKtecから発売されたインテル N150搭載のミニPCです(2024年12月 発売)。
8GB/16GB DDR4 3200 メモリ、256GB/512GB/1TB M.2 2280 NVMeストレージを搭載しています。
また、4K 2画面出力(HDMI x2)、最大32GBまでのメモリ拡張、M.2 2242 PCle SATAで最大2TBまでのストレージ拡張、冷却システム、VESAマウント、USB-A 3.2 Gen2 x4、HDMI (4K@60Hz) x2、有線LAN端子(RJ45,2.5G) x1、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2にも対応しています。
価格は、Amazonで25,999円(税込・6400円OFFクーポン付きで実質19,599円)、楽天市場で23,500円(送料無料)、ヤフーショッピングで24,168円、AliExpressで21,314円、米国 Amazon.comで$138.99 ($10 OFFクーポン付き)、です。
関連記事:N150は快適だった!ミニPC GMKtec NucBox G3 Plusを徹底レビュー!
Beelink EQ13
Beelinkから発売されたIntel N200 プロセッサ搭載のミニPCです。16GB DDR4 3200MHz メモリ、500GB M.2 2280 SATA SSD PCle 3.0 ストレージ、2つのHDMI ポート搭載で、
4K 3画面出力、冷却システム MSC2.0、埃の侵入を防ぐフィルター(底面)、最大4TBまでのストレージ拡張、Type-C (10Gbps,DP Alt 4K 60Hz) x1、USB 3.2 (10Gbps) x3、デュアル有線LAN、Wi-Fi 6 (intel AX101)、Bluetooth 5.2に対応しています。
価格は、Amazonで32,800円(税込・16GB+500GB)、楽天市場で34,070円、ヤフーショッピングで38,444円、AliExpressで29,447円 (16GB+500GB)、です。
関連記事:ミニPC「Beelink EQ13」アダプター不要のメリット・デメリット
BMAX B4 Pro (New)
BMAXから発売された第12世代 Intel N97 プロセッサ搭載のミニPCです。
Windows 11、16GB DDR4 メモリ、512GB SSD ストレージ、M.2拡張スロットを搭載しています。
また、4K 2画面出力(HDMI 2.0 x2)、ストレージ拡張(M.2 SATA 2280 x1)、Linux Ubuntuとのデュアルブート、VESAマウント、ファンレス設計、USB 3.2 x2、USB 2.0 x2、1Gbpsのギガビット有線LAN、Wi-Fi 5、Bluetooth 4.2に対応しています。
価格は、Amazonで29,999円(税込・6100 OFFクーポン付きで実質23,899円)、楽天市場で35,870円(送料無料)、米国 Amazon.comで$199.99、です。
関連記事:N97の「BMAX B4 Pro」とB4 Plus、B6 Plusを比較
Minisforum UN100P
Minisforumから発売されたIntel N100搭載のミニPCです。
16GB DDR4 3200MHzメモリ、256GB M.2 2280 PCIe3.0 SSD、TF カードスロット、2.5インチ SATA HDDスロット (SATA 3.0 6.0Gb/s)、HDMI x2、3.5mmコンボジャック搭載で、
4K 3画面出力、PD給電、冷却ファン、VESAマウント、
USB-C 3.2 x1、USB-A 3.2 (Gen2) x2、USB-A 3.2 (Gen1) x2、2.5G ギガビット有線LAN、Wi-Fi 6、BlueTooth 5.2に対応しています。
価格は、Amazonで37,980円(税込・7216円OFFクーポン付き)、楽天市場で34,980円(送料無料)、ヤフーショッピングで41,063円(送料無料)、MINISFORUM公式サイトで27,190円、米国 Amazon.comで$159.99、です。
関連記事:パワフルで安い「Minisforum UN100L」N100と低価格ミニPCを比較
他のBeelinkミニPCと比較
他にもBeelinkのミニPCが販売されています。2024年モデルもあるので、ぜひ比較してみてください。
BeelinkのミニPCがコスパ高すぎで大人気に!最新 機種 まとめ
その他のおすすめ小型PCは?
その他のおすすめ小型PCは以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
激安で買える海外製の小型PC 最新 機種 ラインナップ まとめ
海外製の小型PCをまとめて紹介しています。
Intel N150ミニPCはこう選べば正解!2025最新の性能・価格を比較
インテルN150搭載のミニPCをまとめて紹介しています。
ミニPCはインテル N100 搭載モデルを選べ! 2024 最新機種と選び方
インテルN100搭載のミニPCをまとめて紹介しています。
リビングにふさわしい超小型デスクトップPC ラインナップ 機種 まとめ
国内で販売されたリビング用の小型PCをまとめて紹介しています。