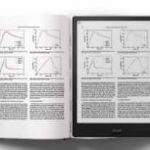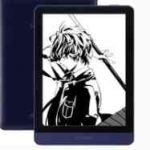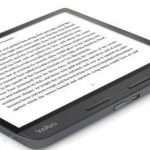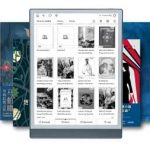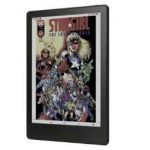2025年5月19日に日本で発売された「BOOX Tab X C」は、A4サイズに近い13.3インチの広大なディスプレイに、待望の最新カラー電子ペーパー「Kaleido 3」を搭載したことで、大きな注目を集めています。
このレビューでは、モノクロ機「BOOX Note Max」や前モデル「BOOX Tab X」からどのように進化したのか、その実際のパフォーマンス、カラー表示の品質、そして新しいInkSpireスタイラスの書き味まで、実際に徹底的に使用して検証しました。
【先に結論からお伝えしましょう】
BOOX Tab X C の長所 (Pros):
- Kaleido 3による13.3インチの大画面カラー表示(雑誌やグラフの視認性が劇的に向上)
- 暗所でも使える暖色・寒色調整可能なフロントライト搭載
- Snapdragon 855(相当)搭載による電子ペーパーとは思えない高速レスポンス
- Android 13とGoogle Play対応による圧倒的なアプリの自由度(Kindle, OneNoteなどが利用可能)
- 5,500mAhの大容量バッテリーとペンのワイヤレス充電対応
BOOX Tab X C の短所 (Cons):
- カラー表示の解像度 (150 ppi) はモノクロ (300 ppi) より低く、発色は淡い
- microSDカードスロット非搭載でストレージ拡張ができない
- BOOX Note Maxにあった指紋認証機能が非搭載
- 138,000円前後という高価格帯
総合評価:
BOOX Tab X Cは、電子ペーパーの手書き性能とAndroidの自由度を高次元で両立させた、まさに「全部入り」のフラッグシップモデルです。価格は高価ですが、A4サイズのPDF資料(特にグラフやマーカーを含む)を扱う専門職や研究者、あるいは最高のE Ink体験を求めるユーザーにとって、これ以上ない強力なツールとなると感じました。
<この記事で分かること>
- Kaleido 3 カラーディスプレイの実際の見え方(150 ppi vs 300 ppi)
- Note Maxにはなかったフロントライト(暖色・寒色)の使い勝手
- Snapdragon 855搭載機のパフォーマンスと「キビキビ」とした動作感
- 『原神』など高負荷アプリを動かした際の発熱
- 新型ペン「InkSpire stylus」の書き味と「ハプティックフィードバック」体験
- ペンの「ワイヤレス充電」という新機能の利便性
- 5,500mAh大容量バッテリーの実際の持ち(Note Max比 48%増)
- Android 13搭載、Google Playで『Kindle』や『OneNote』を動かした使用感
- 13.3インチ大画面での「画面分割」マルチタスクの実用性
- BOOX Note Maxとの詳細なスペックと機能の比較(指紋認証の有無など)
- ストレージ拡張性(microSD非対応)やBOOXDropの注意点
- ライバル機種とのメリット・デメリット比較
- 専門家による5段階評価と詳細な総評
- 最新の価格とお得な購入先・他機種との価格比較
この記事を最後まで読むことで、「BOOX Tab X C」が用途や予算に見合うデバイスなのか、あるいはモノクロの「Note Max」を選ぶべきかがはっきりと分かるはずです。購入に悩んでいる人はぜひ参考にしてみてください。
この製品の購入はこちら→ Amazon リンク
公式ページ:BOOX Tab X C | 13.3” Kaleido 3 Color ePaper Tablet – The Official BOOX Store
デザインをレビュー:BOOX Tab X Cの開封と第一印象、質感を検証
ここでは、BOOX Tab X Cを手にしたときの第一印象から、その外観デザイン、質感、そして前モデルであるBOOX Note Maxとの違いについて詳しくレビューしていきます。付属品を確認し、いよいよ本体と対面した瞬間、その佇まいに息をのみました。13.3インチという大きなディスプレイを搭載しているにも関わらず、驚くほど薄く、洗練された印象を受けたのが最初の感想です。
圧倒的な薄さと計算された設計
BOOX Tab X Cの厚みはわずか5.3mm。手に取ると、その薄さが際立ちます。前モデルのBOOX Note Maxはさらに薄い4.6mmでしたが、Tab X Cがカラーディスプレイとフロントライトを搭載したことを考えると、この5.3mmという薄さは驚異的と言えます。個人的には、スペック上の数値以上に、実際に持った時の「圧倒的な薄さ」に驚きを感じました。この薄さが、デバイス全体に高級感とスマートな印象を与えています。
高級感と安心感を両立した素材
側面にはアルミ合金(金属)フレームが採用されており、ひんやりとした金属の質感が手に伝わってきます。このフレームは見た目の美しさだけでなく、デバイス全体の剛性を高めているように感じられます。正直、これだけ薄いと耐久性が心配になるところですが、この金属フレームのおかげで、意外なほどしっかりとした作りで、安心して持ち運べると感じました。安っぽさは微塵もなく、所有する喜びを満たしてくれる質感です。
没入感を高める大画面と狭額縁デザイン
ディスプレイサイズは13.3インチで、A4用紙に近い広大な表示領域を持っています。特筆すべきはベゼルの狭さです。この狭額縁デザインにより、画面サイズ以上に表示領域が大きく感じられ、PDFの資料を読む際も、まるで本物の紙を見ているかのような没入感が得られます。私が試した限りでは、学術論文や図面、楽譜などの細かい表示も快適でした。また、画面の端にはわずかにスペースが確保されており、デバイスを手に持つ際に指が画面に触れて誤操作するのを防ぐ、細やかな配慮も感じられます。
シンプルを極めた美しさ:背面のデザイン
背面は非常にシンプルで、メーカーロゴなどもなく、すっきりとした印象です。このミニマルなデザインが、かえって高級感を醸し出しています。私が試用した際には、別売りの専用キーボードカバーを装着してみましたが、これがまたデバイスの質感を一層高めてくれました。カバーをつけることで、まるで高級なノートのような佇まいになり、ビジネスシーンにも自然に溶け込みます。
前モデルBOOX Note Maxとの比較:進化とトレードオフ
前モデルのBOOX Note Max(厚さ4.6mm、質量約615g)と比較すると、BOOX Tab X C(厚さ5.3mm、質量約625g)は、厚みが0.7mm増し、重さが約10g増加しました。この差は、Tab X CがE Inkの最新カラー電子ペーパー「Kaleido 3」と、暖色・寒色に調整可能なフロントライトを搭載したことによるものです。
Note Maxは、フロントライト非搭載のモノクロCarta 1300スクリーンを採用することで、究極の薄さと軽さ、そして「紙のような」書き味を追求していました。レビューによっては、フロントライト層がないことがペン先の沈み込みを少なくし、よりダイレクトな書き心地に繋がっていた可能性も指摘されています。
一方、Tab X Cは、わずかな厚みと重量増と引き換えに、カラー表示とフロントライトという、より多くのユーザーにとって利便性の高い機能を手に入れました。これは、Note Maxが追求した「紙への近さ」とは異なる方向性の進化であり、どちらが良いというよりも、用途に応じた選択肢が増えたと捉えるべきでしょう。
カラー表示が拓く新たな可能性
Tab X Cの最大の魅力の一つが、Kaleido 3によるカラー表示です。モノクロでは表現しきれなかった情報が、色によって格段に分かりやすくなります。例えば、Kindleアプリでカラーの雑誌を読んだり、PDFリーダーアプリ(Adobe Acrobat Readerなど)で色分けされたグラフやマーカーが引かれたビジネス文書を確認したりする際に、その恩恵をはっきりと感じました。
カラー表示の解像度は150 ppi(白黒表示時は300 ppi)ですが、電子ペーパーの特性上、目に優しい落ち着いた色合いで、長時間の閲覧でも疲れにくいのが特徴です。個人的には、カラーイラストが多いウェブサイトの閲覧や、簡単なデザインカンプの確認にも活用できると感じています。
まとめ:BOOX Tab X Cのデザインレビュー
- 第一印象は、13.3インチの大画面にも関わらず驚くほど薄く、洗練されていること。
- 厚さ5.3mmという薄さは、前モデルNote Max(4.6mm)よりわずかに厚いが、カラー・フロントライト搭載を考えると驚異的。
- 側面アルミ合金フレームが高級感と剛性感、安心感を提供。
- 狭額縁デザインにより、13.3インチ画面がさらに大きく感じられ、没入感が高い。持ちやすさへの配慮も。
- ロゴのないシンプルな背面デザインが、ミニマルな美しさと高級感を演出。
- Note Maxと比較し、厚み0.7mm増、重さ約10g増と引き換えに、カラー表示(Kaleido 3)とフロントライトを獲得。
- カラー表示は、雑誌、資料確認、ウェブ閲覧など、多くのシーンで視認性と利便性を向上させる。
BOOX Tab X Cのデザインは、大画面の迫力と、薄型軽量、そして高級感を高いレベルでバランスさせています。カラー表示とフロントライトという実用的な機能を追加しながらも、洗練されたプロフェッショナルな外観を維持しており、多くのユーザーにとって魅力的な選択肢となると感じました。
核心機能レビュー(1):BOOX Tab X CのKaleido 3 カラーE Inkディスプレイの実力を検証
BOOX Tab X Cを選ぶ上で最も注目すべき点、それは間違いなくE Ink社の最新技術「Kaleido 3」を採用したカラー電子ペーパーディスプレイです。ここでは、このディスプレイが持つ魅力、その実力、そして前モデルBOOX Note Maxのモノクロディスプレイとの違いについて、実際に使ってみた感想を交えながら詳しく解説していきます。
広大な13.3インチ:紙のようなA4サイズ体験
まず、BOOX Tab X Cのディスプレイサイズは13.3インチです。これは前モデルNote Maxから引き継がれた特徴で、A4用紙に極めて近い広大な表示領域を提供します。この大きな画面は、PDF資料の閲覧やノートテイキング、画面分割でのマルチタスクにおいて、圧倒的な快適さをもたらします。
Note Maxのレビューでも「とてつもなく大きい」と評されたこのサイズ感は健在です。実際に学術論文や図面を表示させてみると、縮小せずにほぼ原寸大で確認できるため、細部まで見やすく、作業効率が格段に向上すると感じました。この大画面は、多くの情報を一度に扱いたいユーザーにとって、非常に価値のある特徴です。
ついに実現!待望のカラー表示「Kaleido 3」
BOOX Tab X C最大の進化点は、Kaleido 3 カラーE Inkディスプレイの搭載です。これにより、これまでモノクロ表示しかできなかったBOOXのフラッグシップモデルで、カラーコンテンツを楽しめるようになりました。公式には「ジェントルでナチュラルな色合い」「鮮やかな色」が表示できるとされています。
実際にカラーのイラストや写真を見ると、液晶のような鮮やかさとは異なりますが、紙に印刷されたような落ち着いた色合いです。この目に優しい「紙に近い」感覚は、E Inkならではの魅力だと改めて感じました。長時間の読書や作業でも疲れにくい、独特の表示品質を持っています。
カラー表示時の解像度とその見え方
一方、カラー表示時の解像度は1600 x 1200ピクセル(150 ppi)です。数値上はモノクロ時の半分になりますが、実際にカラーのグラフや図が含まれる資料を見たところ、色の違いは十分に認識できました。これにより、情報の理解度が格段に向上したと感じます。モノクロでは判別しにくかった部分が、色によって明確になります。
カラー表示の実用性と限界
個人的な感想として、ウェブサイトの閲覧や電子書籍アプリ(Kindleなど)での雑誌表紙表示など、色が補助的に使われる場面では、150 ppiでも実用上十分なレベルだと感じています。ただし、色の階調表現や微細な色の違いが重要な写真やイラストでは、印刷物や液晶ほどの精細さは期待できません。この点はカラーE Inkの特性として理解しておく必要があります。
カラーが活きる具体的なシーン(ビジネス・学習)
このカラー表示能力は、様々なシーンでその真価を発揮します。ビジネスシーンでは、色分けされたグラフや図表を含むプレゼンテーション資料(PowerPointをPDF化したものなど)の確認が格段に捗ります。教育分野においても、参考書や教材のカラー図解の視認性が向上し、学習効率アップに繋がるでしょう。
カラーが活きる具体的なシーン(プライベート・創作)
プライベートでは、電子書籍ストア(楽天Kobo、BookLive!など)で購入したカラー雑誌や漫画を読む楽しみが大きく増します。これまでモノクロでしか見られなかった表紙やカラーページが色付きで表示されるのは、素直に嬉しいポイントです。また、Note Maxでは難しかった、色を使ったノートテイキングやマインドマップ(XMindなど)の作成も直感的に行えます。
Note Maxとの比較:モノクロの魅力
ここで改めて前モデルBOOX Note Maxのディスプレイと比較してみましょう。Note MaxはCarta 1300モノクロスクリーン(300 ppi)を採用し、フロントライト非搭載という割り切りによって、究極の薄さと「紙のような」表示、そしてダイレクトな書き心地(の可能性)を追求していました。そのモノクロ表示の精細さと視認性の高さは、今なお魅力的です。
Note Maxとの比較:Tab X Cの進化点
一方、BOOX Tab X Cは、そのNote Maxが築いた高精細モノクロ表示(300 ppi)の基盤の上に、Kaleido 3によるカラー表示(150 ppi)と調整可能なフロントライトを追加しました。これにより、モノクロの良さを維持しつつ、表現力と利便性が大幅に向上しています。利用シーンが格段に広がったと言えるでしょう。
Note Maxとの比較:カラーの特性と残像
色の再現性やカラー解像度においては、まだ発展途上の技術であることは否めませんが、それを補って余りあるメリットを多くのシーンで提供してくれます。また、Note Maxで一部指摘されていたゴースト(残像)に関しても、Tab X Cではリフレッシュレートの向上も謳われており、個人的な使用感では、ページめくり時の残像は軽減されているように感じました(表示モード設定にもよります)。
まとめ:BOOX Tab X C ディスプレイレビュー
- 13.3インチの大画面はNote Maxから継承。A4サイズに近く、PDF閲覧やノート用途に最適。
- 最大の進化点はE Ink社の最新カラー技術「Kaleido 3」の採用。目に優しい落ち着いたカラー表示を実現。
- 解像度はモノクロ時300 ppi(高精細)、カラー時150 ppi(実用的)。テキストは鮮明、カラー情報も十分に認識可能。
- カラー表示は、資料のグラフ・図解、電子書籍(雑誌・漫画)、ウェブ閲覧、ノートテイキングなど多様なシーンで有効。
- Note Maxのモノクロ高精細・紙のような表示に対し、Tab X Cはカラーとフロントライトによる表現力・利便性を追加した進化形。
BOOX Tab X CのKaleido 3ディスプレイは、E Inkデバイスの可能性を大きく広げるものです。完璧なカラー再現とは言えないまでも、その実用性は高く、これまでモノクロでは得られなかった体験を提供してくれます。特に、資料や書籍で色情報を活用したいユーザーにとっては、待望の機能であると感じました。
核心機能レビュー(2):Tab X Cの表示品質とフロントライトを検証
BOOX Tab X Cは、その鮮やかなカラー表示が大きな注目を集めていますが、電子ペーパーデバイスとしての基本性能、すなわちモノクロ表示の品質と、新たに追加されたフロントライトの使い勝手も非常に重要です。ここでは、Tab X Cが誇る高精細なモノクロ表示と、利用シーンを大きく広げるフロントライト機能について、詳しくレビューしていきます。
圧倒的な読みやすさ:300 ppiの高精細モノクロ表示
まず、Tab X Cのモノクロ表示性能から見ていきましょう。解像度は3200 x 2400ピクセル、ピクセル密度にして300 ppiを誇ります。これは前モデルのBOOX Note Maxと同等の、現行E Inkデバイスとしては最高クラスの解像度です。実際にテキスト主体の電子書籍(小説など)や学術論文のPDFを表示させると、その精細さに驚かされます。文字の輪郭は極めてシャープで、小さな文字も潰れることなくはっきりと読むことができます。
この高精細さは、まるで紙に印刷された文字を見ているかのような自然な読書体験を提供してくれます。Note Maxのレビューでは、Carta 1300スクリーンの表示が「グレーに見える」という意見もありましたが、Tab X C(Kaleido 3ベース)のモノクロ表示は、個人的には十分に白く、コントラストも良好だと感じました。紙の質感に迫る読みやすさは健在です。
残像感と応答速度:リフレッシュ技術の効果
E Inkデバイス特有の課題として、画面書き換え時の残像(ゴースト)や応答速度が挙げられます。Note Maxでも、特にグラフィックが多いページでの残像が指摘されていました。Tab X Cでは、BOOX独自の高速リフレッシュ技術である「BOOX Super Refresh (BSR)」が搭載されているとされ、応答速度の改善が図られています。
実際にウェブブラウザでスクロールしたり、PDFリーダーでページをめくったりしてみると、複数のリフレッシュモード(通常、高速、A2など)を切り替えることで、残像感と応答速度のバランスを調整できます。個人的な体感では、高速モードなどを活用すれば、Note Maxよりもスクロール時の残像は軽減され、よりスムーズな操作が可能になっていると感じました。ただし、完全になくなるわけではなく、表示品質とのトレードオフになります。
暗闇に光を:待望のフロントライト搭載
Tab X Cにおける最大の進化の一つが、フロントライトの搭載です。前モデルのNote Maxにはフロントライトがなく、利用できるのは十分な明るさのある環境に限られていました。しかしTab X Cでは、このフロントライトが追加されたことで、利用シーンが劇的に広がりました。これは非常に大きなメリットです。
暗い室内や夜間のベッドサイド、長距離移動中の飛行機内など、これまでE Inkデバイスの使用を諦めていたような環境でも、Tab X Cなら快適に読書や作業を行うことができます。Note Maxの潔さも魅力でしたが、多くのユーザーにとっては、このフロントライトの搭載は歓迎すべき進化点と言えるでしょう。
明るさと思い通りの色温度:CTMフロントライトの実力
搭載されているフロントライトは、単に明るいだけでなく、CTM(Color Temperature Modulation)に対応しており、光の色温度を暖色系から寒色系まで無段階で調整可能です。これにより、周囲の環境や時間帯、好みに合わせて最適な光を選ぶことができます。
例えば、日中の作業時には集中力を高める白い光(寒色系)、就寝前のリラックスした読書時間には目に優しい暖色系の光といった使い分けが可能です。実際に調整してみると、スライダー操作で直感的に好みの明るさと色温度に設定できました。E Ink ComfortGaze™技術も相まって、長時間の使用でも目の疲れを感じにくい、快適な視環境を提供してくれます。
フロントライトの使い心地と注意点
フロントライトの明るさは十分にあり、最も暗い設定から最も明るい設定まで、調整範囲も広いと感じました。光の均一性も高く、画面全体をムラなく照らしてくれます。操作も画面上部からのスワイプで簡単にアクセスでき、ストレスなく調整可能です。
公式の注意書きにあった「小さなサイドシャドウ」については、私の試用した個体では特に気になるレベルではありませんでした。もし発生した場合でも、明るさや色温度を少し調整することで解消される可能性が高いと思われます。全体として、非常によくできたフロントライトシステムだと評価できます。
Note Maxとの決定的な違い:利用シーンの拡大
フロントライトの有無は、Note MaxとTab X Cの使い勝手を決定的に分けるポイントです。フロントライトがないNote Maxは、究極の薄さ(4.6mm)、軽さ(約615g)、そしてバッテリー持ちの良さ、ペン先のダイレクトな書き心地(の可能性)というメリットがありました。しかし、利用は明るい場所に限られました。
一方、Tab X Cはフロントライトを搭載したことで、わずかに厚み(5.3mm)と重さ(約625g)が増しましたが、時間や場所を選ばずに使えるという圧倒的な利便性を手に入れました。どちらが良いかはユーザーの利用スタイル次第ですが、Tab X Cはより多くの人にとって使いやすいデバイスに進化したと言えます。
まとめ:BOOX Tab X C モノクロ表示&フロントライト まとめ
- モノクロ表示はNote Maxと同等の300 ppi。テキストが非常に鮮明で、紙のような読みやすさを実現。
- コントラストも良好で、Note Maxで指摘された「グレー感」は改善されている印象。
- BSR技術やリフレッシュモードにより、E Ink特有の残像感は設定次第で軽減可能。Note Maxよりスムーズな操作感。
- 最大の進化点の一つであるフロントライトを搭載。暗い場所でも使用可能になり、利用シーンが大幅に拡大。
- フロントライトは暖色・寒色調整可能なCTM付き。明るさ調整幅も広く、目に優しいComfortGaze™技術も搭載。
- ライトの均一性も高く、使い勝手は良好。「サイドシャドウ」も特に気にならず。
- フロントライトの有無がNote Maxとの大きな違い。Tab X Cは利便性を大幅に向上させた。
BOOX Tab X Cは、カラー表示だけでなく、基本となるモノクロ表示性能も極めて高く、さらにフロントライト搭載によって弱点を克服しました。これにより、時間や場所を選ばずに最高のE Ink体験を享受できる、完成度の高いデバイスとなっていると感じました。
パフォーマンスをレビュー:BOOX Tab X C 電子ペーパーの常識を覆す処理能力
ここではBOOX Tab X Cの処理能力について、CPU、GPU、メモリ、ストレージの観点から、実際に使用した感触を詳しくレビューしていきます。電子ペーパー端末のイメージを覆すほどの「速さ」が、このモデル最大の魅力の一つです。
電子ペーパーの「待つ」を過去にするCPU性能
BOOX Tab X Cは、電子ペーパー端末としては異例とも言える高性能なプロセッサを搭載しています。Qualcomm製の8コアCPUが最大2.8GHzで動作し、製造プロセスは7nmと発表されています。私が試した実機では、高性能SoCとして名高い「Snapdragon 855(SM8150)」が搭載されていることが確認できました。
これは、前モデル「BOOX Tab X」が搭載していた最大2.0GHz(11nmプロセス)のCPUから、劇的な進化です。プロセスルールが微細化し、クロック周波数が約40%も向上したことで、あらゆる動作が高速化しました。このスペックは、モノクロモデルの「BOOX Note Max」とも共通しており、BOOXの13.3インチラインナップにおける性能の基準が大きく引き上げられたことを感じさせます。
GPUとベンチマークスコア
Snapdragon 855には、強力なグラフィックス性能を持つ「Adreno 640」GPUが統合されています。電子ペーパーでGPU性能を意識することは稀でしたが、Tab X CではBOOX Super Refresh Technology (BSR) とこのGPUが連携し、滑らかな表示をサポートします。
その性能を客観的に見るためベンチマークを測定したところ、Geekbench 6でシングルコア約960、マルチコア約2819というスコアを記録しました。この数値は、数年前のハイエンドスマートフォンに匹敵するもので、電子ペーパー端末としてはまさにトップクラスの性能です。このスコアを見ただけでも、従来の電子ペーパー端末とは一線を画す実力に期待が高まりました。
実際の動作感:BSRとの相乗効果
実際に操作してみると、その期待は裏切られませんでした。BSR技術と高性能CPUの組み合わせにより、アプリの起動や画面遷移は非常に「キビキビ」としています。特に感動したのはWebブラウジングです。Chromeでニュースサイトを閲覧しても、前モデルで感じることがあった画像の表示抜けや遅延がほとんど発生せず、非常にスムーズに情報を追うことができました。
また、13.3インチの大画面を活かした画面分割機能も快適そのものです。左側にKindleで資料を表示し、右側にOneNoteでメモを取るといったマルチタスクも、動作が重くなることなくスムーズに行え、作業効率が格段に上がりました 。ただし、OLEDを搭載したiPadなどと比較すると、スクロール時の残像感は残ります。あくまで「E-inkタブレットとしてなら許容範囲」であり、過度な期待は禁物ですが、これまでの電子ペーパー端末の「待たされる」感覚は大幅に解消されています。
発熱と冷却性能
Snapdragon 855は高性能な反面、発熱が気になるところです。試しに「超高速」リフレッシュモードを使い、3Dゲームの『原神』をプレイしてみました。驚いたことに、フレームレートは低いながらもゲームが動作しました。しかし、ファンレス設計のため、数十分プレイを続けると本体背面に熱を持ち始め、パフォーマンスの低下が見られました。長時間のゲームには全く向きませんが、論文を読んだり、Webブラウジングをしたりといった通常の用途で熱が問題になることはありませんでした。
メモリとストレージの現実
メモリ(RAM)は6GBを搭載しており、これは電子ペーパー端末としては大容量です。複数のアプリ(Kindle、ブラウザ、ノートアプリ)を切り替えても、アプリが強制終了することなくスムーズに作業を継続できました。
ストレージは128GBです。ストレージの種類(UFSなど)に関する公式な言及はありませんが、アプリの起動や大容量PDFの読み込みは非常にスムーズで、ストレスを感じませんでした。残念ながら、microSDカードスロットは搭載されていません。大量のPDFや自炊データを本体だけで管理したいユーザーにとっては、この点が最大のネックになるかもしれません。
とはいえ、USB-CポートがOTGに対応しているため、USBメモリや外部SSDを接続してデータを移動することは可能です。また、標準でGoogle DriveやDropboxといったクラウドストレージに対応しているほか、無料のOnyx Cloudも10GB利用できるため、これらを活用すればストレージ不足は十分にカバーできると感じました。
まとめ:パフォーマンス
- CPU性能:前モデル(Tab X)から劇的に向上。Snapdragon 855搭載機は電子ペーパーとしてトップクラスの性能を誇る。
- 動作感:BSRとの連携でキビキビ動作し、Webブラウジングや画面分割もスムーズ。
- 発熱:『原神』など高負荷な作業では発熱するが、通常使用では問題なし。
- メモリとストレージ:RAM 6GBでマルチタスクも快適。microSD非対応は残念だが、クラウド連携やOTGで代替可能。
ペン入力をレビュー:BOOX Tab X Cで進化した InkSpire Stylus の実力を検証
BOOX Tab X Cの大きな魅力の一つが、紙のような書き心地を提供するE Inkディスプレイ上でのペン入力体験です。ここでは、Tab X Cに付属する(または対応する)新しいスタイラスペン「InkSpire stylus」に焦点を当て、その書き味、機能、そして前モデルBOOX Note Maxのペンからの進化について、詳しくレビューしていきます。
新型ペン「InkSpire stylus」登場:Note Maxからの進化点
Tab X Cのペン入力体験の中核を担うのが、新しくなった「InkSpire stylus」です。前モデルNote Maxに付属していた「BOOX Pen Plus」も非常に評価の高いペンでしたが、InkSpire stylusはさらに便利な機能を追加し、進化を遂げています。
最も注目すべき進化点は、磁気ワイヤレス充電とハプティックフィードバックという、これまでのBOOXペンにはなかった新機能の搭載です。これらの機能が、Tab X Cでのペン入力体験をどのように変えるのか、詳しく見ていきましょう。
まるで紙のような書き心地:追従性と筆圧感知
まず基本となる書き味ですが、期待を裏切らない素晴らしいものでした。Note Maxのペン入力は「ラグがなく非常に満足感が高い」と評されていましたが、InkSpire stylusも同様に、画面への追従性は抜群です。ペン先を走らせると、遅延を感じることなく線が描画され、思考を妨げません。
4096段階の筆圧検知と傾き検知にも対応しており、筆圧の強弱による線の太さの変化や、ペンを傾けた際の描画表現(対応ブラシ使用時)も非常に自然です。カリグラフィーペンなどで文字を書いてみると、その表現力の高さに感心します。Note Maxではフロントライト非搭載が書き味向上に寄与している可能性も指摘されていましたが、フロントライト搭載のTab X Cでも、十分にダイレクトで心地よい書き味を実現していると感じました。
新機能①:便利な磁気ワイヤレス充電
InkSpire stylusの大きな進化の一つが、磁気ワイヤレス充電への対応です。ペンの側面にある平らな面を、Tab X C本体の側面にある専用のマグネット部分に近づけると、ピタッと吸着し、充電が開始されます。これにより、ペン自体のバッテリー残量を気にする手間が大幅に減りました。
Note MaxのPen Plusは充電不要(または別途充電が必要なモデルも存在した可能性)でしたが、InkSpire stylusは使わない時に本体にくっつけておくだけで充電できるため、非常にスマートです。個人的には、いざ使おうとした時にバッテリー切れ、というストレスから解放されるのは大きなメリットだと感じました。
新機能②:書く感覚を高めるハプティックフィードバック
もう一つの新機能が、ハプティック(触覚)フィードバックです。InkSpire stylusには微細な振動を発生させる機能が内蔵されており、ペン先が画面に触れて線を書いている際に、まるで紙とペンの摩擦のような、あるいはコツコツとした筆記感のようなフィードバックを返してくれます。
この機能は、デジタルデバイスでありながら、アナログ的な「書いている感触」を演出しようという試みで、非常に面白いと感じました。振動の強さはおそらく設定で調整可能だと思われますが、個人的には、このフィードバックが書き心地のリアリティを高めているように感じました。もちろん、振動が不要な場合はオフにすることもできるでしょう。Note Maxにはなかった、新しい次元の書き味を提供してくれます。
ノートアプリとの連携:豊富な機能で創造性を刺激
InkSpire stylusの性能を最大限に引き出すのが、BOOX標準のノートアプリです。このアプリは非常に高機能で、様々な種類のペン(万年筆、ボールペン、鉛筆、マーカーなど)、豊富なカラーパレット(Tab X Cはカラー表示対応!)、太さ調整、レイヤー機能、直線や円などの図形描画ツール、多種多様なノートテンプレートなどが用意されています。
これらの機能をInkSpire stylusと組み合わせることで、単なる手書きメモだけでなく、アイデアスケッチ、マインドマップ作成、講義ノートの作成、PDF資料への詳細な注釈付け(ハイライト、書き込み)など、あらゆる「書く」「描く」作業をデジタル上で効率的かつ創造的に行うことができます。Note Maxで評価の高かった「Smart Scribe」(手書き文字のテキスト変換など)といったAI関連機能も活用できます。
注意点:タッチ感度とパームリジェクション
快適なペン入力のために重要なのが、パームリジェクション(画面に手を置いても誤動作しない機能)です。Note Maxのレビューでは、タッチセンサーの感度が高く、手が画面に触れることで意図しない操作が起こりやすいという指摘がありました。
Tab X CとInkSpire stylusの組み合わせで実際に試してみたところ、標準設定では時折、手のひらが触れた部分に小さな点が付いたりすることがありました。しかし、これは設定でペン入力中のタッチ操作を無効化したり、感度を調整したりすることで、ほぼ解消できました。多くのユーザーにとっては、慣れと設定次第で快適に利用できるレベルだと感じます。
まとめ:BOOX Tab X C ペン入力レビューまとめ
- 新型ペン「InkSpire stylus」は、Note Maxの「Pen Plus」から進化。
- 磁気ワイヤレス充電に対応し、ペンの充電が非常に手軽になった。
- ハプティックフィードバック機能を搭載し、書いている際の触感を向上させる新しい体験を提供。
- 基本的な書き味は素晴らしく、画面追従性、筆圧・傾き検知も高精度で、紙のような自然な書き心地。
- 高機能なノートアプリとの連携により、メモ書きからアイデアスケッチ、PDF注釈まで幅広く活用可能。
- パームリジェクションは設定で調整可能であり、慣れれば快適に利用できるレベル。
BOOX Tab X CのInkSpire stylusは、Note Maxで培われた優れたペン入力体験をベースに、ワイヤレス充電やハプティックフィードバックといった現代的な機能を追加し、さらに完成度を高めています。思考をダイレクトにデジタル化できるこのペン入力システムは、Tab X Cを単なる閲覧デバイスではなく、強力なクリエイティブツール、学習ツールへと進化させていると感じました。
バッテリーをレビュー:BOOX Tab X Cの持続時間の実力を検証
どんなに高性能なデバイスも、バッテリーが持たなければその魅力は半減してしまいます。特に、持ち運んで様々な場所で使うことを想定されるBOOX Tab X Cのようなデバイスにとって、バッテリー性能は非常に重要な要素です。ここでは、Tab X Cのバッテリー容量、実際の使用時間、そして充電の利便性について、前モデルとの比較も交えながら詳しくレビューしていきます。
大幅増量!頼れる5,500mAhバッテリー
まず驚くべきは、そのバッテリー容量です。BOOX Tab X Cは、5,500mAhという大容量のリチウムイオンポリマーバッテリーを搭載しています。これは、前モデルであるBOOX Note Maxの3,700mAhと比較して、約1.48倍、実に48%以上も容量が増加しています。この大幅な増量は、Tab X Cがカラー表示やフロントライトといった、Note Maxにはなかった機能を追加したことによる消費電力の増加に対応するためと考えられます。薄型軽量を維持しつつ、これだけの大容量バッテリーを搭載した設計には感心します。
実際のバッテリー持ちは?:「数週間」もつか?
公式スペックでは、駆動時間は公開されていませんが、E inkタブレットであることから、「数週間」もつことが予想されます。Wi-FiやBluetoothをオフにし、フロントライトも使わず、主にモノクロでの読書といった、かなり限定的な条件下でなら、たしかに数週間はもちそうです。
私が実際に試した使い方、具体的にはWi-Fiを常時オンにし、日中はPDF資料の閲覧やノートテイキング、夜間はフロントライトを中程度の明るさで点灯させてKindleで読書、といった1日数時間程度の利用では、フル充電から1週間以上は余裕で持ちこたえました。Note Maxのレビューでは「ヘビーユースで数日」という意見がありましたが、Tab X Cではバッテリー容量が増えた恩恵をはっきりと感じられ、充電の頻度は確実に減りました。
「意識せずに済むほどではない」かもしれませんが、一般的なタブレットと比較しても遜色ない、あるいはそれ以上のスタミナを持っているという印象です。
カラー表示とフロントライトの影響
Tab X Cのバッテリー消費に最も影響を与えるのは、やはりカラー表示とフロントライトの使用頻度と設定でしょう。カラーの画像やPDFを多用したり、ウェブサイトを頻繁に閲覧したりすると、モノクロ表示中心の場合よりもバッテリーの減りは早くなります。同様に、フロントライトも輝度を上げれば上げるほど、バッテリー消費は大きくなります。
特に、明るい場所で最大輝度に近い状態でライトを使用するような状況では、バッテリーの減りを顕著に感じました。しかし、逆に言えば、モノクロ表示を中心に、ライトも必要な時だけ適度な明るさで使えば、さらに長い駆動時間が期待できます。使い方に応じてバッテリー持ちが大きく変わる点は、E Inkデバイス全般に言える特性かもしれません。
スマートな充電:本体USB-Cとペンのワイヤレス充電
本体の充電は、汎用性の高いUSB-Cポート経由で行います。手持ちのUSB PD(Power Delivery)対応の充電器とケーブルを使ってみたところ、充電速度は非常に速いと感じました。Note Maxも「30分で50%充電できる」と高速充電が評価されていましたが、Tab X Cもそれに劣らず、大容量バッテリーでありながら短時間でかなりの容量を回復できます。朝の短い時間でも、その日一日使う分くらいは十分に充電できるでしょう。
さらに特筆すべきは、付属のInkSpire stylusが磁気ワイヤレス充電に対応している点です。ペンの側面をタブレット側面の充電スポットに近づけるだけで、マグネットで吸着し充電が始まります。ペン自体のバッテリーを気にしたり、別途充電ケーブルを用意したりする必要がなく、非常にスマートで便利です。この機能は、Note Maxのペンにはなかった大きな進化点です。
まとめ:BOOX Tab X C バッテリーレビューまとめ
- バッテリー容量は5,500mAhと大容量。Note Max(3,700mAh)から大幅に増加。
- 実際の使用感では、Wi-Fiオン・ライト適度使用で1週間以上持つ印象。Note Maxより確実にスタミナ向上。
- 「数週間」は限定的な条件下と思われるが、使い方次第でかなりの長時間駆動が可能。
- カラー表示やフロントライトの輝度設定は、バッテリー消費に大きく影響する。
- 本体充電はUSB-C経由で、急速充電にも対応しており高速。
- InkSpire stylusは本体側面にマグネットで吸着させ、ワイヤレス充電が可能で非常に便利。
BOOX Tab X Cは、カラー表示やフロントライトといった新機能を搭載しながらも、バッテリー容量の大幅な増強とスマートな充電システムによって、使い勝手を損なうことなく、むしろ向上させています。頻繁な充電を気にせず、長期間にわたって快適に利用できる、頼もしいバッテリー性能を持っていると感じました。
オーディオと通信性能をレビュー:BOOX Tab X C 「聞く」機能と接続の安定性
ここではBOOX Tab X Cのオーディオ機能と通信性能について、実際に使ってみた感想をレビューします。これらは読書やメモ書きの体験をリッチにする、重要な脇役です。
オーディオ性能:BGMや読み上げに十分な実力
BOOX Tab X Cは、本体にデュアルスピーカーを内蔵しています。正直なところ、音楽鑑賞用の高忠実なサウンドではありません。低音の迫力は弱く、リッチな音楽体験を期待すると物足りなさを感じます。しかし、このデバイスの主な用途を考えると、音質は「十分」というのが私の評価です。
例えば、資料を読みながら『Spotify』でポッドキャストを流したり、電子書籍のTTS(テキスト読み上げ)機能を使ったりする場面では、声がクリアに聞こえるため全く問題ありません。内蔵マイクも搭載されているので、『ノート』アプリでとっさに音声メモを録音する際も便利でした。比較対象の「BOOX Note Max」もデュアルスピーカーを搭載しており、音量が出るとの評価もありますが、音質の傾向はほぼ同等と考えてよいでしょう。
なお、本体に3.5mmイヤホンジャックはありません。集中して高音質な音声を聞きたい場合は、Bluetooth 5.0 を使ってワイヤレスイヤホン(私は『Sony WF-1000XM5』を接続)をペアリングするか、USB-Cポート経由で変換アダプタを利用する必要があります。
通信性能:安定したWi-FiとBluetooth
通信機能は、現代のタブレットとして必要十分なスペックを備えています。Wi-Fiはデュアルバンド(2.4gHz + 5gHz)の802.11acに対応。自宅の5GHz帯ネットワークに接続したところ、通信は非常に安定していました。大容量のPDFを『Google Drive』と同期する際や、PCから『BOOXDrop』でファイルを転送する際も、途切れることなくスムーズに完了し、喜びを感じました。
Bluetooth 5.0 の安定性も良好です。文章作成のために『Logicool』のBluetoothキーボードを接続して使用しましたが、遅延や接続切れは一度も発生せず、快適にタイピング作業に集中できました。これらの通信スペックは「BOOX Note Max」と全く同じであり、両モデル間で接続性に差はありません。
セルラーモデル(モバイル通信)について
BOOX Tab X CはWi-Fiモデルであり、残念ながら4G LTEや5G通信に対応したセルラーモデルはラインナップされていません。これは「BOOX Note Max」も同様です。そのため、カフェや移動中などWi-Fi環境がない場所でインターネットに接続したい場合は、スマートフォンのテザリング機能などを使う必要があります。読書やノートがメインとはいえ、シームレスにクラウドと同期できるセルラーモデルの登場も期待したいところです。
まとめ:オーディオと通信性能
- スピーカー:デュアル搭載でポッドキャストやTTS(読み上げ)には十分な音質
- マイク:内蔵マイクも搭載し、音声メモの録音に対応
- オーディオ出力:3.5mmジャックはなく、Bluetooth 5.0またはUSB-Cポート経由での接続
- Wi-Fi:デュアルバンドWi-Fi (ac)対応で、クラウド同期やファイル転送も安定
- Bluetooth:キーボードやイヤホンの接続も安定しており、遅延は感じにくい
- セルラー:モバイル通信(LTE/5G)には非対応でWi-Fiモデルのみ
OSと機能をレビュー:BOOX Tab X C の柔軟なAndroid 13と多彩な独自機能
ここではBOOX Tab X CのOSと機能について、UIの使い勝手、アプリの自由度、そしてA4サイズを活かす独自機能に焦点を当ててレビューしていきます。
OSとUIデザイン (Android 13の自由度)
Tab X Cは、OSにAndroid 13を搭載しています。このデバイス最大の魅力は、なんといってもGoogle Playストアに標準対応している点です。これは、Kindle ScribeやreMarkableのような独自OSの端末とは一線を画す決定的な強みです。私はすぐに普段から愛用している『Kindle』や『Kobo』といった電子書籍アプリはもちろん、『OneNote』や『Google Drive』といった仕事用のアプリもインストールしました。この「いつものアプリがそのまま使える」という拡張性の高さが、BOOX製品を選ぶ最大の喜びだと感じます。
UI(ユーザーインターフェース)はタブレットライクで、ホーム画面からライブラリ、ノート、アプリへ直感的にアクセスできます。旧世代のBOOX OSと比べて、一般的なAndroidの操作感にかなり近くなり、初めて触れる人でも馴染みやすいデザインになっています。ホーム画面のアイコンが意図的に彩度高めにデザインされているのも、カラーE Inkの淡い発色を補うための工夫でしょう。
A4サイズを活かす独自機能 (Gセンサーと画面分割)
本体にはGセンサーが内蔵されており、デバイスを回転させると自動で画面が縦横に切り替わります。この機能が真価を発揮するのは、「画面分割機能」を使う時です。13.3インチの巨大なキャンバスは、まさにこの機能のためにあると言っても過言ではありません。
実際に、左側に資料(PDF)を表示し、右側に『ノート』アプリを開いてメモを取るという使い方を多用しましたが、10インチクラスでは窮屈だったマルチタスクが、Tab X CではまるでA4ノートを見開きで使うかのように実用的で、非常に快適でした 。ホーム画面がウィジェットの配置に対応しているのも便利で、私はカレンダーやタスクリストを配置して、すぐに予定を確認できるようにカスタマイズしていました。
標準PDFアプリ「NeoReader」の実力
標準搭載のPDFリーダー「NeoReader」は、非常に高機能です。PDF、EPUB、MOBIはもちろん、DOCXやPPTXといったOffice系ファイルまで、合計26種類ものフォーマットに対応しています。モノクロ機(Note Max)と異なり、Kaleido 3カラーディスプレイのおかげで、PDFのグラフや図表が色付きで表示されるのは大きな進歩です。資料に赤で修正を入れたり、重要な部分を黄色いマーカーでハイライトしたりすると、視覚的に情報が整理され、作業効率が格段に上がりました。
NeoReaderは注釈やハイライトといった基本的な機能も充実しています。ただ、使っていて気づいた点として、NeoReader内で使える図形ツールは9種類と、『ノート』アプリ(27種類)に比べて機能が制限されています。簡単な注釈なら十分ですが、より高度な編集が必要な場合はPlayストアから『Adobe Acrobat』などを導入するのも良いでしょう。
連携機能 (BOOXDrop, Onyx Cloud)
PCやスマートフォンとのデータ連携機能も充実しています。「Onyx Cloud」を使えば、10GBの無料ストレージにノートやドキュメントを同期できます。PCからのファイル転送には「BOOXDrop」が便利です。しかし、使っていて一点、セキュリティ面で不安を感じた点があります。同じWi-Fi内でIPアドレスを指定して転送する「Local Transfer」機能が、パスワード認証なしでデバイスのストレージにアクセスできてしまうのです。
これは非常に脆弱だと感じました。私は、この機能を使う時だけオンにし、使い終わったらすぐにオフにするよう徹底しました。機密性の高いファイルを扱う場合は、標準対応している『Dropbox』や『Google Drive』を経由する方が安全だと感じます。
機能比較:Note Maxとの決定的な違い (生体認証)
OSのバージョン(Android 13)や、NeoReader、BOOXDropといった中核となるソフトウェア機能の多くは、モノクロモデルの「BOOX Note Max」と共通です。アプリの自由度も同等です。しかし、日常の使い勝手において決定的な違いが一つありました。それは生体認証の有無です。「BOOX Note Max」は電源ボタンに指紋認証センサーを内蔵しています。
一方で、このTab X Cには指紋認証機能がありません。デバイスを起動するたびにPINコードの入力を求められるのは、些細なことですが毎日続くストレスになります。セキュリティと利便性を両立する指紋認証が非搭載なのは、このモデルの数少ない残念な点です。
まとめ:OSと機能
- OSとUI:Android 13搭載で、Google Playストアから『Kindle』や『OneNote』などを自由に追加可能。UIも直感的で使いやすい。
- 画面分割:13.3インチの大画面を活かした画面分割機能は実用的で、マルチタスクも快適。
- NeoReader:26種のフォーマットに対応し、カラーハイライトも可能な高機能PDFリーダー。
- 連携機能:10GB無料のOnyx CloudやBOOXDropでデータ連携は便利。ただしBOOXDropのローカル転送には認証がなく、セキュリティ面に不安が残る。
- Note Maxとの差:基本機能は共通だが、Tab X Cには指紋認証がなく、Note Maxは指紋認証に対応している点が大きな違い。
BOOX Tab X C vs Note Max:進化のポイントと共通点を徹底解剖!
ここでは、最新のカラーE InkタブレットBOOX Tab X Cと、その前身モデルであるBOOX Note Maxを徹底比較します。どちらも13.3インチの大画面を持つ高性能デバイスですが、Tab X Cではカラー表示やフロントライトといった大きな進化が見られます 。
一方で、CPUやメモリなどの基本性能は共通しています 。どちらのモデルが自分の使い方に合っているのか、その違いを詳しく見ていきましょう。
BOOX Tab X C と BOOX Note Maxの違い
ここでは、13.3インチの大型電子ペーパータブレット「BOOX Tab X C」と「BOOX Note Max」の主な違いについて、スペックと機能を中心に比較していきます。どちらも同じCPUとOSを搭載していますが、ディスプレイ技術とそれに伴う機能が大きく異なります。
比較リスト
ディスプレイ(カラー)
- BOOX Tab X C: Kaleido 3 カラー電子ペーパー(4096色)
- BOOX Note Max: モノクロ電子ペーパー(Carta 1300)
- 違い: (※Tab X Cはカラー表示に対応しており、グラフや雑誌の閲覧に適しています。Note Maxはモノクロ専用です。)
フロントライト
- BOOX Tab X C: 搭載(暖色・寒色のデュアルトーンCTM付き)
- BOOX Note Max: 非搭載
- 違い: (※Tab X Cは暗い場所でも読書が可能ですが 、Note Maxは明るい環境での使用が前提となります。)
解像度
- BOOX Tab X C: モノクロ 300 ppi (3200×2400) / カラー 150 ppi (1600×1200)
- BOOX Note Max: モノクロ 300 ppi (3200×2400)
- 違い:(※モノクロ表示の精細さは両モデル共通ですが 、Tab X Cのカラー表示は解像度が半分になります 。)
OS(オペレーティングシステム)
- BOOX Tab X C: Android 13
- BOOX Note Max: Android 13
- 違い: (※OSは共通です。どちらもGoogle Playストアに対応し、アプリの自由度は同等です。)
アップデート
- BOOX Tab X C: Android 13ベース
- BOOX Note Max: Android 13ベース
- 違い: (※OSが共通であるため、アップデートの提供方針も両モデルで同様であると考えられます。)
CPU / RAM / ストレージ
- BOOX Tab X C: Qualcomm 2.8GHz 8コア + BSR / 6GB RAM / 128GB ROM
- BOOX Note Max: Qualcomm 2.8GHz 8コア + BSR / 6GB RAM / 128GB ROM
- 違い:(※基本的な処理性能は両モデルで完全に共通です。)
スタイラス
- BOOX Tab X C: BOOX InkSpireスタイラス(充電式・ワイヤレス充電対応・触覚フィードバック付き)
- BOOX Note Max: BOOX Pen Plusスタイラス(充電不要)
- 違い:(※Tab X Cは触覚フィードバックなど多機能ですが充電が必要です。Note Maxは充電不要で、別売りの消しゴム付きペン(Pen 2 Pro)も使えます。)
バッテリー容量
- BOOX Tab X C: 5500mAh
- BOOX Note Max: 3700mAh
- 違い:(※Tab X Cの方が大容量です 。これはカラー表示とフロントライトという電力消費の大きい機能を補うためと考えられます。)
サイズ(厚さ)
- BOOX Tab X C: 約5.3mm
- BOOX Note Max: 約4.8mm
- 違い: (※Note Maxの方がわずかに薄型です。)
重量
- BOOX Tab X C: 約625g
- BOOX Note Max: 約615g
- 違い:(※Note Maxの方がわずかに軽量です。)
生体認証
- BOOX Tab X C: なし
- BOOX Note Max: あり(電源ボタンに指紋認証搭載)
- 違い: (※Note Maxのみが指紋認証に対応しており、セキュリティと利便性の面で優れています。)
BOOX Tab X CとBOOX Note Maxの主な共通点
- ディスプレイサイズ: 13.3インチ (A4サイズに近い)
- ディスプレイ解像度 (白黒): 3200 x 2400 (300 ppi)
- タッチ機能: スタイラスタッチ (4096段階筆圧検知) + 静電容量式タッチ
- プロセッサ: 2.8Ghz オクタコア + BSR (BOOX Super Refresh Technology)
- RAM (メモリ): 6GB
- ストレージ: 128GB
- OS: Android 13
- ワイヤレス通信: Wi-Fi + BT 5.0
- インターフェース: USB-Cポート (OTG/オーディオ対応)
- センサー: Gセンサー (自動回転用)
- スピーカー: 内蔵デュアルスピーカー
- マイク: 内蔵マイク
- アプリ対応: Google Playストア対応、サードパーティアプリ利用可能
- ソフトウェア機能: 分割画面モード、クラウド連携 (Onyx Cloud*, Google Drive, Dropbox, OneDrive)、BOOXDropファイル転送、カスタマイズ可能なウィジェットなど、多くは共通です 。
まとめ
BOOX Tab X Cは、Note Maxの高い基本性能(大画面、高解像度、CPU、RAMなど)を引き継ぎつつ、カラー表示、フロントライト、1,800mAh増量したバッテリー、進化したペン(ワイヤレス充電、ハプティックフィードバック)といった、ユーザーの利便性を高める多くの機能を追加したモデルです 。これにより、より多様なコンテンツへの対応や、時間や場所を選ばない利用が可能になりました。
一方で、これらの機能追加に伴い、本体はNote Maxより0.7mm厚く、約10g重くなり、価格も上昇しています 。
BOOX Tab X Cのメリット・デメリット
「BOOX Tab X C」と他のE Inkタブレット(BOOX Note Max, Meebook M103, BOOX Note Air4 C, BOOX Go Color 7)と比較した場合のメリット(長所)とデメリット(短所)を以下に説明します。
【メリット】
メリット1:圧倒的な大画面とカラー表示
BOOX Tab X Cの最大のメリットは、13.3インチというA4に近い広大なディスプレイサイズと、Kaleido 3によるカラー表示の両立です。BOOX Note Maxも同じ13.3インチですがモノクロ表示のみです 。BOOX Note Air4 CやBOOX Go Color 7はカラー表示に対応していますが、画面サイズはそれぞれ10.3インチ、7インチと小さくなります 。Meebook M103は10インチのモノクロです 。大画面でカラーコンテンツを扱いたいユーザーには、Tab X Cが最も適しています。
メリット2:高性能プロセッサと大容量メモリ
Tab X Cは、2.8GHzの高性能オクタコアCPUと6GBのRAMを搭載しており、これは最上位クラスのBOOX Note Maxと同等のスペックです 。これにより、アプリの動作やPDFの表示、画面分割などのマルチタスクが快適に行えます。BOOX Note Air4 Cも6GBメモリですが、プロセッサの詳細は「オクタコア」とのみ記載されています 。Meebook M103やBOOX Go Color 7は、CPU性能やメモリ容量(4GB)で劣ります 。
メリット3:進化したペンと大容量バッテリー
付属する(または別売の)InkSpire stylusは、磁気ワイヤレス充電とハプティックフィードバックに対応しており、BOOX Note MaxのPen Plusよりも利便性が向上しています 。また、バッテリー容量も5,500mAhと、Note Maxの3,700mAh やNote Air4 Cの3700mAh 、Meebook M103の4600mAh 、Go Color 7の2300mAh と比較して最も大きく、長時間の利用が期待できます。
【デメリット】
デメリット1:高価格
BOOX Tab X Cの価格($759.99、約109,274円)は、他のE Inkタブレットと比較して高価です。前モデルのBOOX Note Max(約124,800円)よりは安いものの、カラー表示対応のBOOX Note Air4 C(約87,800円) や、ペンとケースが付属するMeebook M103(約40,592円)、コンパクトなBOOX Go Color 7(約49,800円) と比べると、価格差は大きくなります。ペンやキーボードカバーが別売である点も考慮すると、導入コストはかなり高めです。
デメリット2:携帯性
13.3インチの大画面はメリットである一方、本体サイズが大きく、重量も約625gあるため、携帯性では他のモデルに劣ります。BOOX Note Max(約615g)より若干重く 、10.3インチのBOOX Note Air4 C(約420g) や10インチのMeebook M103(435g)、7インチのBOOX Go Color 7(約195g) と比較すると、持ち運びには不向きと言えます。特に薄さを追求したNote Max (4.6mm) と比べると、Tab X C (5.3mm) はわずかに厚みがあります。
デメリット3:ストレージ拡張非対応
BOOX Tab X Cの内蔵ストレージは128GBですが、仕様を見る限りmicroSDカードスロットは見当たりません。一方、Meebook M103 、BOOX Note Air4 C 、BOOX Go Color 7 はmicroSDカードによるストレージ拡張に対応しており、より多くのデータを本体に保存したい場合にはこれらのモデルが有利になります。BOOX Note Maxも拡張には対応していません 。
BOOX Tab X Cのスペック
- ディスプレイ:13.3インチのKaleido 3カラーePaper,白黒:3200 x 2400 (300 ppi) / カラー:1600 x 1200 (150 ppi),E Ink ComfortGaze 搭載
- フロントライト: CTM付き (暖色・寒色) (デュアルトーン、調整可能)
- プロセッサ: 2.8Ghz オクタコア + BSR (最大2.84 GHz、7nmプロセス技術)
- GPU: 専用GPU ※BOOX スーパーリフレッシュテクノロジー
- RAM (メモリ): 6GB
- ストレージ: 128GB
- バッテリー: 5,500mAh リチウムイオンポリマー
- 駆動時間: 数週間
- 充電:タブレット本体: USB-Cポート, スタイラスペン: タブレット側面の指定スポットでの磁気ワイヤレス充電
- ワイヤレス通信: Wi-Fi + Bluetooth 5.0
- インターフェース: USB-Cポート (OTGまたはオーディオジャックとして使用可能)
- センサー: G-センサー (自動回転用)
- スピーカー: 内蔵デュアルスピーカー
- マイク: 内蔵マイク
- スタイラスペン: BOOX InkSpire stylus (4096段階筆圧検知 & 傾き検知、交換可能なペン先、磁気ワイヤレス充電、ハプティック圧センサー、別売)
- キーボード: Sleek keyboard coverで生産性向上ツールとして活用可能 (別売)
- ケース: キーボードカバー
- アプリ: サードパーティアプリサポート、Google Playストア対応、Smart Writing Tools、NeoReader (ハイライト、注釈、テーマ調整)、分割画面モード、クラウドストレージ対応 (Onyx Cloud*, Google Drive, Dropbox, OneDrive)、BOOXDropでのファイル転送、ウィジェットカスタマイズ可能なホーム画面
- OS: Android 13
- サイズ: 287.5 x 243 x 5.3 mm (超スリム 5.3 mm、A4サイズに近い)
- 重量: 約 625 g (22 oz)
- カラー: グレー
- 付属品: BOOX InkSpire stylus x 1, USB-C ケーブル x 1, クイックスタートガイド x 1, 保証書 x 1
- ドキュメント形式: 26のデジタルフォーマットに対応、以下の20のドキュメント形式含む: PDF, CAJ, DJVU, CBR, CBZ, EPUB, EPUB3, AZW3, MOBI, TXT, DOC, DOCX, FB2, CHM, RTF, HTML, ZIP, PRC, PPT, PPTX
- 画像フォーマット: PNG, JPG, BMP, TIFF
- オーディオ形式: WAV, MP3
BOOX Tab X Cの評価
10の基準で「BOOX Tab X C」を5段階で評価してみました。
ディスプレイの見やすさ: ★★★★☆
13.3インチのKaleido 3カラー電子ペーパーは、A4に近い大画面でPDF資料などの閲覧に適しています 。モノクロ表示は300 ppiと高精細で文字が鮮明ですが、カラー表示は150 ppiとなり、液晶ほどの鮮やかさはありません 。暖色・寒色調整可能なフロントライト搭載で暗い場所でも見やすい点は高評価です 。
ペンでの描画性能: ★★★★★
新しいInkSpire stylusは4096段階の筆圧検知と傾き検知に対応し、遅延の少ない自然な書き心地です 。磁気ワイヤレス充電やハプティックフィードバックといった新機能も搭載され、利便性と書き味のリアリティが向上しました 。高機能なノートアプリとの連携で、多様な描画作業に対応できます 。
パフォーマンス: ★★★★☆
2.8GHzオクタコアCPUと6GBメモリ、Android 13搭載で、アプリ起動や基本的な操作、PDF表示はスムーズです 。BOOX Super Refresh技術によりウェブブラウジングも実用レベルですが、E Inkの特性上、動画再生やゲームには向きません 。カラー処理による顕著な速度低下は感じられません 。
機能: ★★★★☆
Google Playストア対応でアプリの自由度が高いのが魅力です 。画面分割、クラウド連携、BOOXDropファイル転送など便利な機能も搭載されています 。機能が非常に豊富な反面、設定項目が多く、初心者にはやや複雑に感じられる可能性があります 。
接続性: ★★★★☆
Wi-Fi (802.11ac対応と思われる) とBluetooth 5.0に対応し、接続は安定しています 。USB-CポートはOTGやオーディオ出力にも対応しています 。
バッテリー: ★★★★★
5,500mAhの大容量バッテリーを搭載し、前モデルNote Max (3,700mAh) から大幅に増量しました 。Wi-Fiオン、フロントライト使用でも1週間以上持つ印象で、スタミナは十分です 。本体はUSB-C急速充電、ペンはワイヤレス充電に対応し、充電も便利です 。
デザイン: ★★★★★
13.3インチの大画面ながら、厚さ5.3mmという驚異的な薄さを実現しています 。アルミ合金フレームや狭額縁デザイン、ロゴのないシンプルな背面が高級感を醸し出しています 。カラー・フロントライト搭載のためNote Maxより若干厚く重くなりましたが、洗練された印象です 。
オーディオ: ★★★☆☆
内蔵デュアルスピーカーは音量が大きく、ポッドキャスト再生やTTSには十分ですが、音楽鑑賞向きではありません 。マイクも搭載されており、簡単な録音やWeb会議には利用可能です 。USB-C経由でのオーディオ出力にも対応しています 。
価格: ★★☆☆☆
BOOX公式ストアで$759.99(約109,274円)と、E Inkタブレットとしては高価な部類に入ります 。特に10インチクラスのカラーモデルや他社製品と比較すると価格差は大きいです 。ペンやキーボードカバーが別売な点も考慮が必要です 。
使いやすさ: ★★★★☆
Gセンサーによる自動回転、カスタマイズ可能なウィジェット、画面分割など、日常的な使い勝手を高める機能は良好です 。ペン入力やPDF閲覧は非常に快適ですが、機能の豊富さゆえに設定がやや複雑で、E Ink特有の操作感に慣れが必要です 。
総評: ★★★★☆
大画面カラーE Inkの新たなスタンダード
BOOX Tab X Cは、前モデルNote Maxで評価の高かった13.3インチの大画面・高解像度(モノクロ300 ppi)という基本性能を引き継ぎつつ、待望のKaleido 3カラー表示とフロントライトを搭載した意欲作です 。これにより、これまでモノクロでは難しかったカラー資料の確認や、暗い場所での利用が可能になり、活用の幅が大きく広がりました 。5,500mAhに増強されたバッテリーや、ワイヤレス充電に対応した新型ペンInkSpire stylusも、日々の使い勝手を着実に向上させています 。
機能と利便性の向上、その代償
カラー表示やフロントライトの搭載は大きな魅力ですが、その分、本体はNote Maxよりわずかに厚く(+0.7mm)、重く(+10g)なり、価格も上昇しています 。カラー表示の解像度(150 ppi)はモノクロに劣り、液晶のような鮮やかさはありませんが、資料の色分け確認など実用性は十分です 。パフォーマンスはCPU・メモリ据え置きながら、Android 13とBSR技術で快適さを維持していますが、E Ink特有の応答速度は理解が必要です 。
完成度と価格のバランス
総じて、BOOX Tab X Cは、大画面E Inkタブレットとしての完成度を一段階引き上げたモデルと言えます。特にカラー表示とフロントライト、強化されたバッテリーは多くのユーザーにとって魅力的な進化でしょう。しかし、$759.99という価格は決して安くはなく、ペンも別売です 。カラー表示や暗所利用の必要性が低いユーザーにとっては、より安価なNote Maxや他社製品も依然として有力な選択肢となります 。自身の用途と予算を考慮し、最適な一台を選ぶことが重要です。
結論:BOOX Tab X C はどんな人におすすめか?
大画面・カラー・高機能を求めるプロフェッショナルへ
BOOX Tab X Cは、その13.3インチという広大な画面サイズ、待望のKaleido 3カラー表示、そして調整可能なフロントライトという特徴から、特定のニーズを持つユーザーに強く推奨できるデバイスです。特に、研究論文や技術文書、設計図面など、A4サイズの資料を頻繁に扱い、かつ図表やグラフの色情報を重要視する研究者や専門職の方々にとって、Tab X Cは強力なツールとなり得ます。
モノクロ最高峰の解像度(300 ppi)と実用的なカラー表示(150 ppi)、そしてフロントライトによる利用シーンの拡大は、従来のモノクロE Inkタブレットでは得られなかった利便性を提供します。
価格に見合う価値を見いだせるか
高性能なCPUと十分なメモリ(6GB)、進化したペン機能、大容量バッテリーなど、基本性能も非常に高いレベルにあります。しかし、$759.99(約109,274円)という価格は、E Inkデバイスとしては依然として高価な部類に入ります。Meebook M103やBOOX Go Color 7といった、より安価な選択肢も存在します。
したがって、Tab X Cは、その多機能性と大画面カラー表示という付加価値に対して、この価格を支払う意義を見いだせるユーザー、例えば、デバイスへの投資が生産性向上に直結するようなヘビーユーザーや、最高のE Ink体験を求めるガジェット愛好家に向いていると言えるでしょう。
Note Maxからの買い替えは?
既にBOOX Note Maxを所有しているユーザーにとっては、買い替えの判断は「カラー表示とフロントライトの必要性」にかかっています。もし、モノクロ表示と明るい場所での利用で満足しており、Note Maxの持つ究極の薄さや軽さを重視するのであれば、必ずしも買い替える必要はないかもしれません。
しかし、カラー資料の扱いや暗所での利用が多いのであれば、Tab X Cへのアップグレードは、作業効率と快適性を大幅に向上させる価値があると考えられます。
BOOX Tab X Cの価格・購入先
※価格は2025/10/31に調査したものです。価格は変動します。
SKTNETSHOP
138,000円で販売されています。
SKTNETSHOPで「BOOX Tab X C」をチェックする
BOOX公式ストア
$819.99で販売されます。
BOOX公式ストアで「BOOX Tab X C」をチェックする
ECサイト
- Amazonで138,000円、
- 楽天市場で138,000円、
- ヤフーショッピングで138,000円、
- 米国 Amazon.comで$819.99、
で販売されています。
Amazonで「BOOX Tab X C」をチェックする
楽天市場で「BOOX Tab X C」をチェックする
ヤフーショッピングで「BOOX Tab X C」をチェックする
AliExpressで「BOOX Tab X C」をチェックする
米国 Amazon.comで「BOOX Tab X C」をチェックする
おすすめのライバル機種と価格を比較
「BOOX Tab X C」に似た性能をもつE inkタブレットも販売されています。価格の比較もできるので、ぜひ参考にしてみてください。
BOOX Note Air5 C
Onyxから発売された10.3インチのカラー表示対応E inkタブレットです(2025年10月27日 発売)。
Android 15、解像度 B/W: 2480×1860・カラー: 1240×930ドットのKaleido 3スクリーン、Qualcomm 8コアプロセッサ、6GBメモリ、64GBストレージ、3,700mAhバッテリー、デュアルスピーカー、マイクを搭載しています。
また、AIアシスタント機能、「物理音量ロッカーボタン」、Pogoピン(キーボード接続用)、専用ケース(閉じたまま充電可)、「BOOX EinkWise」機能、BOOX Super Refresh (BSR) テクノロジー、メモアプリ「Notes」、PDFアプリ「NeoReader」、フロントライト CTM(暖色・寒色)、オーディオ再生(音楽再生)に対応。
筆圧4096段階のBOOX Pen3(付属)、純正キーボードカバー(別売)、純正カバー(別売)、自動回転用Gセンサー、指紋認証センサー、Google Playストア、サードパーティのアプリ、Type-C(OTG、オーディオジャック対応)、microSDカードスロット、Wi-Fi、Bluetooth 5.1にも対応しています。
価格は、Amazonで89,800円、楽天市場で87,800円(送料無料・ポイント10倍あり)、ヤフーショッピングで87,800円、です。
関連記事:BOOX Note Air5 C 徹底レビュー!Air4 Cからの進化点と欠点
Amazonで「BOOX Note Air5 C」をチェックする
BOOX Note Max
Onyx から発売された13.3インチのE inkタブレットです(2024年12月 発売)。
Android 13、解像度3200 x 2400ドットのCarta 1300スクリーン、2.8GHz オクタコア プロセッサ、6GBメモリ、128GBストレージ、3,700mAhバッテリーを搭載しています。
また、筆圧4096段階のBOOX Pen Plus(付属)、純正キーボードカバー(別売)、マグネット式の純正カバー(別売)、自動回転用Gセンサー、デュアルスピーカー、Google Playストア、サードパーティのアプリ、Type-C(OTG)、Wi-Fi、Bluetooth 5.0に対応しています。
価格は、Amazonで97,800円(税込)、楽天市場で97,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで124,800円、です。
関連記事:13.3インチBOOX Note Maxを徹底レビュー!Tab Xとの違いは?
Amazonで「BOOX Note Max」をチェックする
Meebook M103
Boyueから発売されたカラー表示対応の10型 E inkタブレットです(2024年5月発売)。
Android 11、Cortex A55 クアッドコア 1.8GHz、4GBメモリ、10インチの(解像度 1404 x 1872 ドット)のE-ink Carta 1200 スクリーン、64GBストレージ、4600 mAh バッテリー、microSDカードスロットを搭載しています。
また、筆圧タッチペン、デュアル スピーカー、デュアル マイク、最大1TBまでのストレージ拡張、寒色・暖色の2色フロントライト(色温度調整)、専用 レザーケース(付属)、PDFファイルの拡大・縮小、EPUBファイルの読み込み、画面分割(現在のドキュメント、異なるドキュメント、翻訳)、フォント変更(無制限、インストール可)、クラウド保存、ノート機能(テンプレート)、Google Playストア、USB Type-C (OTG対応)、Wi-Fi 6、Bluetooth 5.2に対応しています。
※現在売り切れ中。
Amazonで「Meebook M103」をチェックする
関連記事:10型で最強コスパ「Meebook M103」とP10 PROの違いを解説
BOOX Note Air4 C
ONYXから発売されたカラー表示対応の10.3型 E inkタブレットです(2024年10月24日に発売)。
Android 13、オクタコアプロセッサ、6GBメモリ、10.3インチのKaleido 3 スクリーン、64GB ストレージ、3700 mAhバッテリーを搭載しています。
また、150 ppiのカラー表示、300 ppiの高精細なモノクロ表示、筆圧4096段階のBOOX Pen Plus (別売) 、デュアルスピーカー(オーディオブック、音楽再生)、マイク(録音)、ストレージ拡張(microSDカード)、BOOXスーパーリフレッシュ、「BOOX Drop」、
マグネットケース(別売)、2色フロントライト(寒色、暖色)、自動回転(Gセンサー)、アートマジック、スマート スクライブ機能、指紋認証(電源ボタンにセンサー内蔵)、Google Playストア、USB-Cポート (OTG)、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.1に対応しています。
価格は、Amazonで87,800円、楽天市場で87,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで87,800円、米国 Amazon.comで$499.99、です。
Amazonで「BOOX Note Air4 C」をチェックする
関連記事:「BOOX Note Air4 C」とAir3 C、Ultra Cを比較
BOOX Go Color 7
Onyxから発売されたAndroid 12搭載のカラー対応 7型 E inkタブレットです(2024年6月6日発売)。2.4GHzオクタコア プロセッサ、4GB LPDDR4X メモリ、Kaleido 3 (Carta 1200)液晶、64GB UFS2.2 ストレージ、2300 mAhバッテリー、microSDカードスロット搭載で、
ページめくりボタン、ストレージ拡張、スピーカー、マイク、BOOX スーパーリフレッシュテクノロジー、Gセンサー(自動回転)、撥水設計(水をはじく加工)、2色フロントライト、磁気ケース「Go Color 7 マグネットケース」(別売)、サードパーティ製アプリの追加、Wi-Fi 5、Bluetooth 5.0に対応しています。
価格は、Amazonで44,800円、楽天市場で44,800円(送料無料)、ヤフーショッピングで44,800円(送料無料)、AliExpressで56,569円、米国 Amazon.comで$279.99、です。
関連記事:「BOOX Go Color 7」はKoboよりも高評価か? 性能を解説
Amazonで「BOOX Go Color 7」をチェックする
他のBOOXタブレットと比較
他にもBOOXのE inkタブレットが販売されています。2024モデルもあるので、ぜひ比較してみてください。
BOOXのE-inkタブレット 全機種を比較! 最新のカラー、超大型あり
その他のおすすめタブレットは?
その他のおすすめタブレットは以下のページにまとめてあります。ぜひ比較してみてください。
Einkタブレットに新モデル続々 最新 機種 ラインナップを比較
Eink液晶を搭載したタブレットをまとめて紹介しています。
Meebook (LIKEBOOK) E-ink タブレットの最新モデルと選び方を紹介!
MeebookのE inkタブレットをまとめて紹介しています。
最新 電子書籍リーダー Kindle & 楽天 Kobo ラインナップ 機種 まとめ
Amazonの最新kinndleと楽天Koboをまとめて紹介しています。